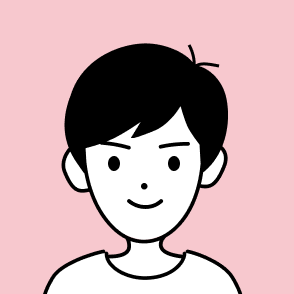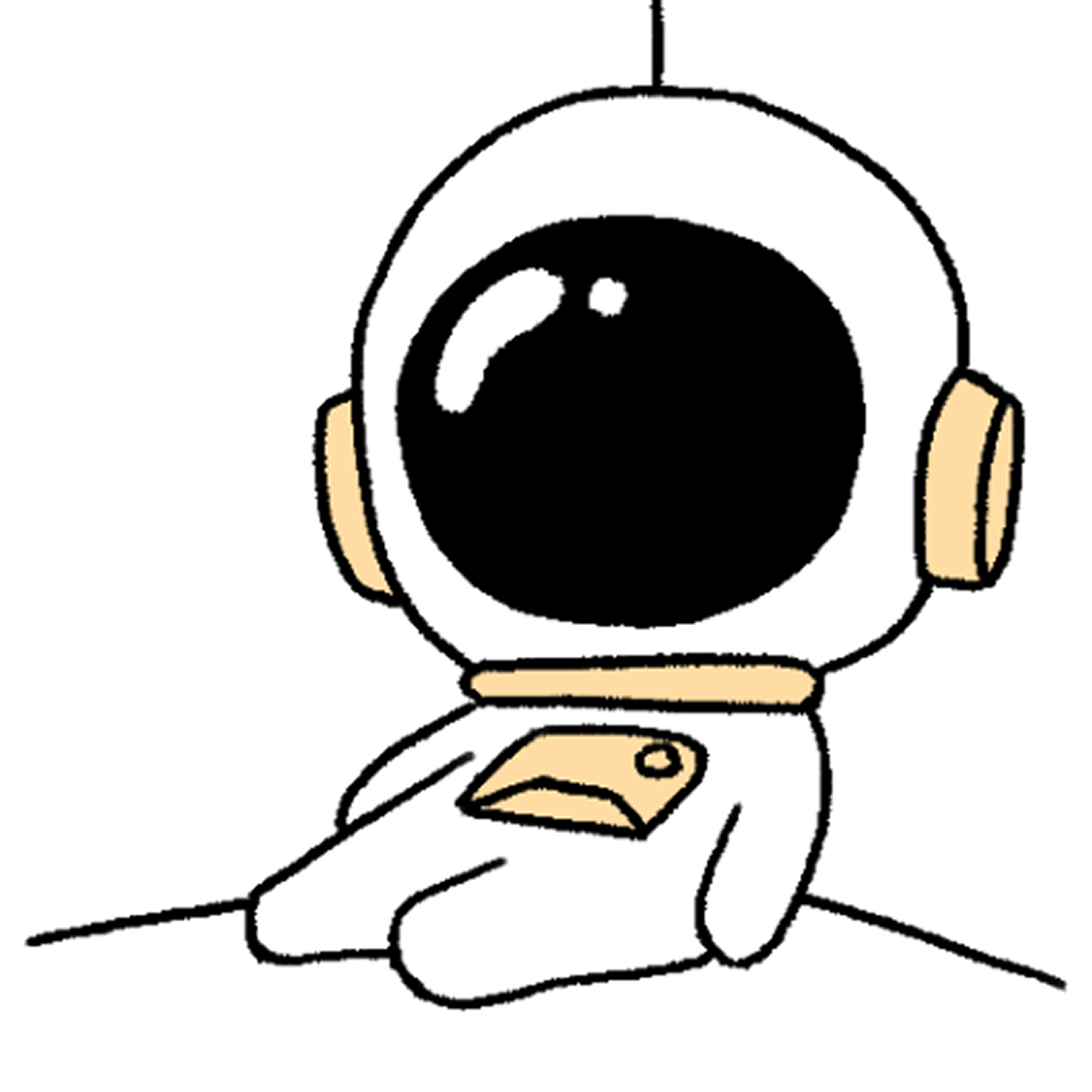夏休みの宿題といえば読書感想文…
日本の学校に通ったことのある人ならば、
きっと書いた経験をお持ちのはず。
嫌々読んでたあの本
何を書けばいいんだ?!と悩んだ学校開始前夜
感想というよりあらすじ紹介になってたあの年
結構書いたぞと思ったらまだ200字だった絶望
そんな経験もあるあるのはず…(私だけ??)
大人になって書いてみたら、
意外と1000字があっという間で、
こんな星もアリなのか?と作ってみました。
・購入記録
・積読記録
・読了記録
・もちろん読書感想文
投稿してみませんか??
搭乗条件は
・本が好き
・非公開でない
・5つ以上投稿がある
・over17
お待ちしています
アメジスト
読書記録です
高校生のための文章読本
梅田貞夫 編
ちくま学芸文庫
高校の国語の教科書や参考書に載っているような、幅広いジャンルの文章70篇がおさめられています
一篇一篇は短文なので読みやすいです
各文章について問いかけがなされており、問いかけについての解説は後半におさめられています
表現力の向上について
表現とは、一度人間の心の中をとおってきた“世界”に“かたち”を与えることである
表現でありながら文章は絵画や彫刻などの造形と違い、心象で説明されやすい
良い文章とは
①自分にしか書けないことを
②だれが読んでもわかるように書く
逆に言えば良くない文章とは
①だれにでも書けることを
②自分にしか読んでもわからないように書く
ありふれた言葉はどこにでも転がっていて手垢にまみれている。それは他人の言葉だ。私の心をいい当てるためにつくられたような言葉を見つけだそう。それはそんなにむつかしいことではないはずだ。
文章表現とは造形であるから、手垢にまみれていない作品をつくろうというのは、言うは易し行うは難しですね
普段から感じたことを、ただすごいと言うのではなくて、ちゃんとした表現が出来るかどうかですね
自由な発想をする脳力を持とうということでしょう
自分にしか書けないことというのは
ものを辞書的に説明するのではなくて
自分だけがとらえた印象を言葉にするということですね
吃音宣言(p37)
どもりはあともどりではない。前進だ。
どもりの偉大さは、反復にある。
それは、地球の回転、四季のくりかえし、人間の一生。宇宙のかたちづくる大きな生命のあらわれなのである。
#読書
#読書感想文
#文章読本
#表現
#文学

アメジスト
読書記録です
ゴシックとは何か
大聖堂の精神史
酒井健 著
ちくま学芸文庫
エドマンド・バークは『崇高と美の起源』において、美を快に、崇高さを不快あるいは不吉に結びつけました
この場合の不快あるいは不吉とは、巨大さ、無骨さ、野性味、暗さ、陰鬱さなどの要素を持った対象に覚える印象のことで、まさに本書が題材としているゴシックの大聖堂そのものです
11~12世紀のフランスにおいて
開墾が進んだことや農業生産の向上により、農民の人口が増えて、都市へ人口が流入するようになりました
都市が手狭になったことやサラセン文明からの建築技術の伝来により、建築物の高層化が進み、ゴシック建築の高層化は、こういう歴史的文脈の一環としてのものです
また、王侯貴族や高位聖職者が自分たちの権威の箔付のために大聖堂を欲していたということも重要です
一方で、都市に流入した元農民はいまだ森林への神秘的な信仰を捨てておらず、ゴシック大聖堂内部の陰鬱さ、高さ、多くの列柱、過剰装飾などが、元農民たちにとって母なる森林を思い起こさせるものだったようです
ゴシック大聖堂の巨大さ、荘厳さは
都市の住民全てを一堂に会し、神の国を演出するためのものだったようです
また、ゴシック大聖堂は、各地の土着の信仰、地母神信仰を聖母マリア信仰に昇華するための装置でもあったため、やたらと各地にノートルダム大聖堂というのがあるとのことです
異教の祭日をキリスト教の記念日にすり替えるなど、実質的に異教を包摂していったのが、カトリック文化のフォークロアチックさにもつながっており、ゴシック大聖堂もその一環であるということを感じました
#読書
#読書感想文
#ゴシック
#歴史
#ヨーロッパ

アメジスト
読書しました
睡眠の起源
金谷啓之 著
講談社現代新書
著者の生い立ちの話はとても興味深かったです。
小学生の頃からアゲハチョウについての大がかりな自由研究をされていて、高校ではプラナリアの研究、その後はヒドラと、研究一筋で不断の努力をしている生き様を応援したいと思いました。
何かの専門家になれる人ってすごいなと思います。
小学生の頃にクロアゲハの生態に興味を持って、実際に飼育して解明するというエピソードは、まさに研究者になるべくしてなる素質を幼少期から持っていたんだなという特別感を感じます。
毎日のように思考実験をする粘り強さや凡人では持ちえない好奇心の強さ。
漁師からクラゲは寝てるんだという話を聞いて、そこから研究を広げるというのは、凡人ではできないアプローチです。
科学ミステリーを帯に書いていますが、著者の頭脳がミステリーですね。
#読書
#読書感想文
#科学
#研究者
#新進気鋭

アメジスト
世界史図録を買ったんですけど、オールカラーでたくさんの図版や写真が載っていて、解説も詳しいので、読んでいて面白いです
これで定価990円はお買い得です
#読書
#読書感想文
#世界史
#図録
#オールカラー


アメジスト
読書記録です
これからの「正義」の話をしよう
今を生き延びるための哲学
マイケル・サンデル 著
鬼澤忍 著
ハヤカワ文庫
難解な内容ですが、政治や経済についての哲学的な深い考え方にじっくりと触れることができる内容となっています。
正義とは何か
同じ考え方の人が多いことがいいことなのか
つまり、多数決や最大多数の最大幸福がいいのか
選択の自由を尊重することがいいのか
つまり、自分の信じていること、自分の良心に従うのがいいのか
その上で、著者は第三の選択
アリストテレスの説く政治の目的は良き生だというものを現代的に解釈して
美徳を涵養して、共通善を論理的に考える大切さを説いています
その選択肢が理にかなっているか、全員に良い事なのか、特に立場の弱い人にとって不利になっていないかということを考えることが正義なのではないかという考察しています
功利主義、リバタリアニズム、イマヌエル・カント、ジョン・ロールズ、アリストテレスなどのそれぞれの哲学の各論についての考察はとても勉強になります
#読書
#読書感想文
#マイケル・サンデル
#正義
#哲学

アメジスト
昼間は雨が降っていなかったのでクリエイトに買い物に行きました
読書記録です
クリスマスに捧げるドイツ奇譚集
E・T・A・ホフマン編
6編のメルヘンの短編集が収録されています
冒頭に前半のあらすじが書かれているので、本編の話がすっと入ってきます
E・T・A・ホフマンの『クルミ割り人形とネズミの王様』をよみながら
チャイコフスキーのバレエ音楽『クルミ割り人形』をかけるとクリスマスのメルヘンの世界に浸れていいです
本編は、現実と幻想が入り混じる物語でまさに奇譚です
ドロッゼルマイアーおじさんも子供の味方なのか意地悪な大人なのか最後まで判然としないのも、物語に不思議な魅力を与えています
クルミ割り人形とネズミの王さまの戦いについても、現実なのか夢なのか
現実と想像、自然と超自然といったものは、自分たちには何ともしがたく互いに混じりあっているという世界観があっていいですね
K・W・ザリーツェ=コンテッサの
『剣と蛇 八章からなるメルヘン』は
中世騎士物語を思わせるような冒険譚になっているのが魅力的です
ホフマンの『見知らぬ子』では幼い兄妹に試練がふりかかるように
子供は決して素朴な存在ではなく、子供の世界は決して素朴ではないという世界観が貫かれているのが良いと思いました
#読書
#読書感想文
#メルヘン
#クルミ割り人形
#幻想

アメジスト
読書記録です
日本史のなかの神奈川県
谷口肇 編
山川出版社
地元が神奈川県なので読みました
行ったことがあるところ
有名なところ
知らないところまで
数多くの県内の歴史スポットが載っていて面白いです
地元にあたる相模川の東側の地域、旧高座郡にあたる地域は、古代の遺跡がたくさんあるんだなと改めて認識しました
地元にあたる神崎遺跡、秋葉山古墳群、相模国分寺跡の3つの国指定史跡には行ったことがあるのですが、他にもいろいろな史跡が本書で紹介されています
芹沢公園に地下壕があるのははじめて知りました
勝坂遺跡は駅から遠いので、行きようがないのですが、縄文時代中期の関東を代表する遺跡なんですね
戦国期小田原城と近世小田原城は違う場所で全く別物なのははじめて知りました
山下公園は関東大震災の瓦礫を埋め立てて造成されたそうです
山下公園の広さは甚大な被害の裏返しなんですね
川崎大師、大山、江ノ島、鎌倉、金沢八景、箱根が観光地としてブームになったのは江戸時代のことだそうです
明治時代になると、大磯、鎌倉、藤沢、鵠沼、茅ヶ崎、平塚、国府津などで海水浴場が開かれ、明治の大物政治家の別荘も建てられて
神奈川が持っているハイカラなイメージが形成されたようです
#読書
#読書感想文
#神奈川県
#歴史
#史跡

アメジスト
読書記録です
高校生のための批評入門
梅田貞夫 編
ちくま学芸文庫
高校の国語の教科書に載っているような随筆などが51編も載っているボリューミーな本となっています
ただの文章を読んで内容を理解するだけでなく、設問があり、それについて批評してみようという体裁となっています
昭和時代の文章が多く、場合によってはそれより昔の古典も載っており、難解な文章も結構あります
解説が分離しているのが、読みにくいと感じることがありますが、思考力のトレーニングはこうやるんだと勉強になりました
戦争を経験した時代に生きた人間、文学者の人生哲学の深さも感じました
ポスト・トゥルースなどという言葉が流行っている時代こそ、こういう本を読んでみる価値があると思いました
右傾化する時代にあって
国家のために馬車車のように働け
全て自助でなんとかしろ、自己責任だ
国家のお荷物は切り捨てる
美しい日本は勤勉な人間のみによって構成される
という思想を持つ人間が総理大臣に選ばれることがほぼ確実になってしまいました
富裕層とか公務員とか体制派についている人はまます豊かな生活が保障されている一方で
底辺に生きている人は生存権すら保障されなくなる時代になってしまうかもしれません
#読書
#読書感想文
#批評
#国語力
#暗黒時代へ

アメジスト
読書記録です
神秘学概論
ルドルフ・シュタイナー著
高橋巖 訳
ちくま学芸文庫
ちくま学芸文庫なので学術的な神秘学を期待して読んだのですが、想像以上に難解でした
ただ、人間の霊魂の故郷が宇宙の他の星にあるとか、本書では土星期とか言ってますが
もともと人間の霊魂は過去の記憶を持っているとかの輪廻転生的な考え方とか
東洋の世界観に似ているなという感じはしました
可視的な世界の背後には不可視的な世界があることを認めることで
世界をなんでもかんでも思い通りにしようとする人達に対してブレーキをかけられるかもしれませんし
マクロコスモス=宇宙には分かっていないことがたくさんあることを認めることで
ミクロコスモス=人間をコントロールしようとする傲慢さを抑制できるかもしれません
霊魂の存在を認めることで、人権というものはとても尊いものであると認識できるかもしれません
シュタイナーの生きた19世紀の終わりから20世紀の初めは
重化学工業が革命的に推進され、環境破壊が進み、人間に厳かな気持ちを与える源泉である自然がどんどん破壊されていったこと
社会の大衆化によって
従来の価値観が揺らぎ、何を信じて生きていけばいいのか分からなくなっていく時代でもありました
そういう行き過ぎた開発と虚無感の中で、霊的なものを見直そうと書いたのが本書だったのかもしれないと思いました
科学・技術の特に技術の面が人間精神を蝕んでしまう防波堤として、本書の意義を感じました
#読書
#読書感想文
#神秘学
#スピリチュアル
#霊

アメジスト
読書記録です
[対談]中世の再発見
網野善彦+阿部謹也 著
平凡社ライブラリー
日本中世史を専門とする網野善彦氏と西洋中世史を専門とする阿部謹也氏が化学反応を起こして、新たな歴史観の地平を開くような含蓄に富んだ内容となっています
網野氏の「無縁」という概念は興味深いです
「無縁」というのは、「世俗的な社会の権力とは無縁である」という意味で
「無縁である/無縁とされる」ということで「支配-非支配(従属)」の関係から独立した自由な存在があったそうです
これが職人やら芸能者やら商人から賤民に至るまでの人間集団の自立性の根拠になっていたそうです
日本にはあまりないけど西洋にはなぜチャリティーの文化が盛んなのか
それはキリスト教の影響だそうです
日本では何かをもらったら何かを返すというお互い様という文化なので、一方的に損をすることになる喜捨の精神は広まりませんでした
一方で西洋においては、互恵の考え方を拡大解釈して、お返しは天国でする、つまり死後の救済という考え方で普遍化しました
西洋のチャリティーの文化は死後の救済という恩恵を受けるために行なわれているそうです
キリスト教の神というのは絶対的な存在だからこそ、西洋人は「神に誓って」という言い回しをするそうです
日本との文化の違いを感じました
#読書
#読書感想文
#歴史
#比較
#文化論

もっとみる 
関連する惑星をみつける
花や植物を愛する星
1415人が搭乗中
参加
花や植物を大切に育てている方や眺めたりするのが大好きな方は、是非搭乗しませんか??皆さんの搭乗をお待ちしております。
プラモデルの星
2377人が搭乗中
参加
プラモデル、食玩なんでも🆗
農業・畑・家庭菜園
1047人が搭乗中
参加
自然豊かな星
3935人が搭乗中
参加
神社仏閣の星
3554人が搭乗中
参加
⛩🙏💚*೨̣̥◡̈⋆*⛩🙏💚*೨̣̥◡̈⋆*⛩️🙏💚
神社仏閣の星⛩️🙏✨
ご搭乗有難う御座います🙇♀️💖✨
皆様と共有し遠隔参拝や訪れるきっかけになって頂ければと思います(*ᴗˬᴗ*)❣️
どうぞ宜しくお願いしますପ(꒪ˊ꒳ˋ꒪)ଓ💞💞
なお、非アカウントの方はお断りさせていただきます(ɔ ˘⌣˘ c)
併せて宜しくお願いしますm(_ _)m
⛩🙏💚*೨̣̥◡̈⋆*⛩🙏💚*೨̣̥◡̈⋆*⛩️🙏💚
もっとみる