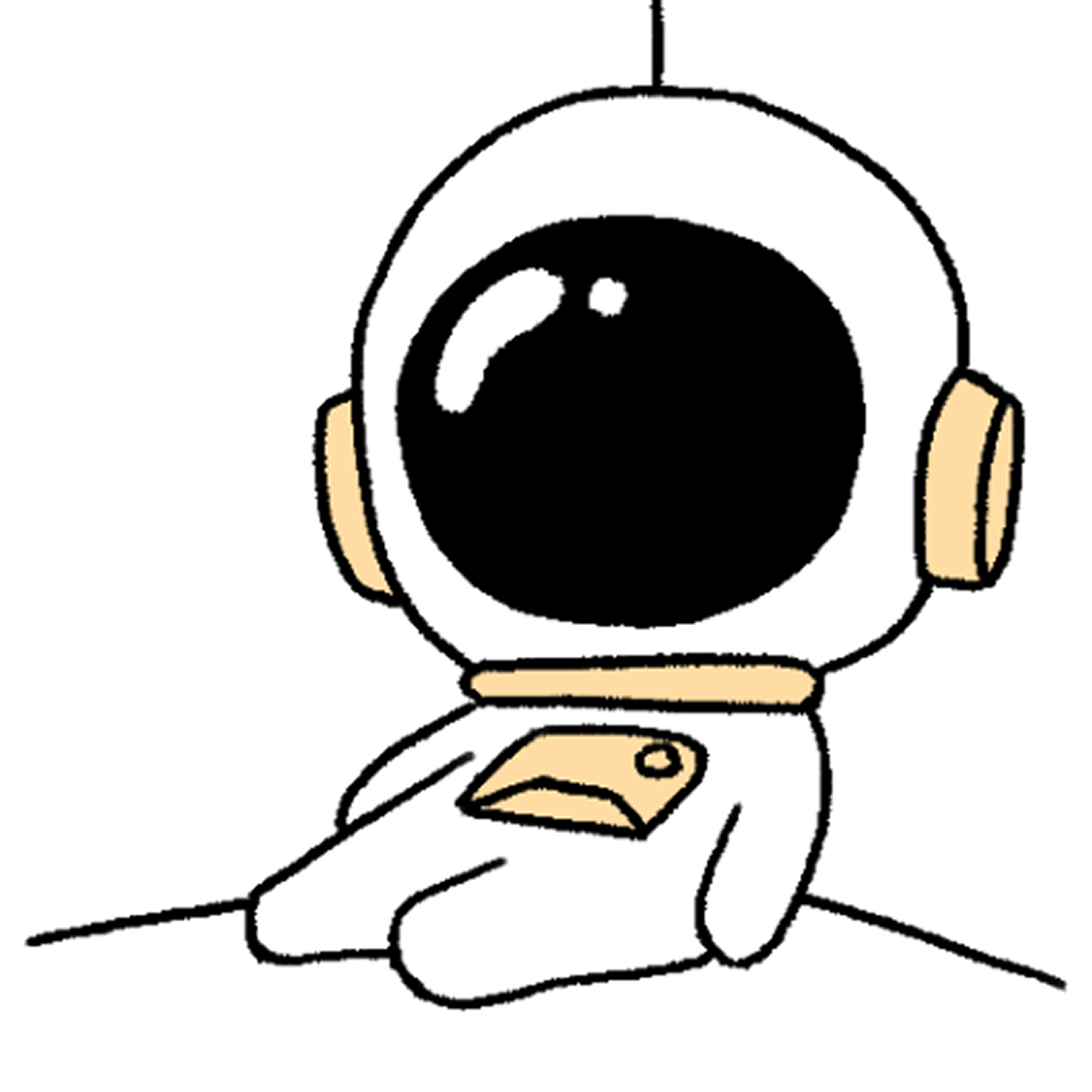夏休みの宿題といえば読書感想文…
日本の学校に通ったことのある人ならば、
きっと書いた経験をお持ちのはず。
嫌々読んでたあの本
何を書けばいいんだ?!と悩んだ学校開始前夜
感想というよりあらすじ紹介になってたあの年
結構書いたぞと思ったらまだ200字だった絶望
そんな経験もあるあるのはず…(私だけ??)
大人になって書いてみたら、
意外と1000字があっという間で、
こんな星もアリなのか?と作ってみました。
・購入記録
・積読記録
・読了記録
・もちろん読書感想文
投稿してみませんか??
搭乗条件は
・本が好き
・非公開でない
・5つ以上投稿がある
・over17
お待ちしています
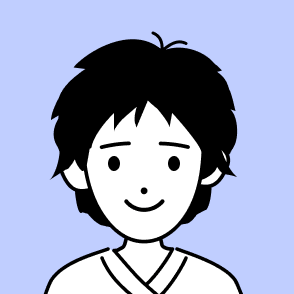
ジェントル田倉
ジェントル田倉です。
本との出会いを増やしてみたくて参加してみました。
遅読ですが、気が向いたら感想文を投稿してみます。
アメジスト
読書記録です
[対談]中世の再発見
網野善彦+阿部謹也 著
平凡社ライブラリー
日本中世史を専門とする網野善彦氏と西洋中世史を専門とする阿部謹也氏が化学反応を起こして、新たな歴史観の地平を開くような含蓄に富んだ内容となっています
網野氏の「無縁」という概念は興味深いです
「無縁」というのは、「世俗的な社会の権力とは無縁である」という意味で
「無縁である/無縁とされる」ということで「支配-非支配(従属)」の関係から独立した自由な存在があったそうです
これが職人やら芸能者やら商人から賤民に至るまでの人間集団の自立性の根拠になっていたそうです
日本にはあまりないけど西洋にはなぜチャリティーの文化が盛んなのか
それはキリスト教の影響だそうです
日本では何かをもらったら何かを返すというお互い様という文化なので、一方的に損をすることになる喜捨の精神は広まりませんでした
一方で西洋においては、互恵の考え方を拡大解釈して、お返しは天国でする、つまり死後の救済という考え方で普遍化しました
西洋のチャリティーの文化は死後の救済という恩恵を受けるために行なわれているそうです
キリスト教の神というのは絶対的な存在だからこそ、西洋人は「神に誓って」という言い回しをするそうです
日本との文化の違いを感じました
#読書
#読書感想文
#歴史
#比較
#文化論

アメジスト
読書記録です
幻影の明治
名もなき人びとの肖像
渡辺京二 著
平凡社ライブラリー
第1章で明治時代の負の側面
貧民窟や明治時代の刑事司法の強圧的で残忍であることが述べられているのが良かったです
第2章では下層民だからこその気概
あたしどもは天下国家の問題とは何の関わりもなく生きて来たし、これからもいきてみせますよという、一寸の虫の気概
そびえたつ政治や文化の構築物に対する基層の民の自立性
天下国家のレベルと関わりなく自立した生活圏に生きているのが、基層的民衆の本質なのである
ということが述べられており、痛快です
第3章
江戸時代と明治時代の最大の相違点
江戸時代においては
統治者以外の民衆はおのれの生活圏で一生を終えて、国家的大事にかかわる必要がなく、不本意にもかかわらねばならぬときは天災のごとくやりすごすだけである
幕末の日本人大衆は、馬関戦争では外国軍隊の弾丸運びに協力して、それが売国の所業だなどとはまったく考えていなかった
戊辰戦争で会津藩が官軍に攻められたとき、会津の百姓は官軍に傭われて平気の平左だった
天下国家は統治者階級の問題で、民衆の関知するところではなかったのだ
明治時代においては
国民は国家的大事にすべて有責として自覚的にかかわることが求められた
日清・日露の役で無理やり朝鮮半島を日本の支配下に置く必要があったのか
国家のために大勢の国民が犠牲になったことについて大義はあったのか
ということについて考えさせられました
第4章
士族反乱というのは
大久保利通を中心とする政府中枢の横暴のもと、何回も政変が起きて、追いやられた人々がもう一度、御一新をやり直せと立ち上がったものである
それは、農民の伝統的な支配者不信と通底していた
士族の特権回復のためという通説だけではない、官という泥棒に対して一矢報いるためという大義もあったということを感じました
#読書
#読書感想文
#明治
#日本論
#民衆

アメジスト
読書記録です
ハプスブルク帝国
地球の歩き方 歴史時代シリーズ
Gakken
今、話題の本です
これは本当に面白いです
このシリーズらしく、オールカラー図版で、ハプスブルク家にまつわる名所の写真がたくさん載っており楽しめます
特に第1章のハプスブルク家の始まりから終わりまでの歴史の解説はとても充実しており
本格的にヨーロッパの歴史が勉強できる内容となっています
歴代のハプスブルク家当主の経歴、業績も詳しくのっており、ハプスブルク帝国がいかに発展し、いかに滅んでいったのかがよく分かる内容となっています
悠久な歴史のロマンに浸れる素晴らしい本です
多民族を束ねるハプスブルク帝国という経験が、民族、国家を超えて連合し、ヨーロッパに平和をもたらすというEUの理念に繋がっていることを感じました
#読書
#読書感想文
#ハプスブルク帝国
#歴史
#ヨーロッパ

アメジスト
読書記録です
オスマン帝国の解体
文化世界と国民国家
鈴木董 著
講談社学術文庫
かつてオスマン帝国が支配していた地域では
宗教・言語・民族を異にする種々様々の人間集団が、モザイクのように入り組んで混在して存在していました
そこではイスラム教による政教一致体制を前提として、イスラム教徒の優位の体制の中で、他宗教・他民族に対する寛容な統治が敷かれていました
それを本書ではオスマンの平和=パクス・オトマニカと呼称しています
具体的には
貢納の義務と一定の行動制限を受けるかわりに
イスラム体制の規範の大枠に反しない範囲で
固有の信仰と法と慣習を守りつつ自治生活を行なうことが許されていました
あくまでもイスラム教徒優位のもとで不平等ながら他宗教の人間集団を許容するというものでしたが、このモザイク状に様々な民族・宗教が存在していた地域においては平和を担保するために有効なものでした
フランス革命以降、西洋ではグローバルな経済システムの進展と、政教分離した中央集権体制「一民族・一国家・一言語」のnation stateの理念を創出し、未曾有の西洋覇権の時代となりました
このnation stateの理念がオスマン帝国を動揺させ、各宗教・各民族が排他的なnationalismを自らの理念とするようになり、バルカン半島から中東地域は民族紛争、宗教・宗派紛争のちまたと化しました
エスニック抗争が生ずるとき
民族の平等を追求すると
支配的多数者と従属的少数者の仁義なき戦いが果てしなく続きます
オスマン帝国が衰亡していく歴史を通じて
nation stateやnationalismの排他的で暴力的な負の側面
多文化共存社会が平等の原則のもとに成立する難しさを学ぶことが出来ました
#読書
#読書感想文
#オスマン帝国
#平和
#多文化共生

アメジスト
読書記録です
いかにして超感覚的世界の認識を獲得するか
ルドルフ・シュタイナー 著
高橋巖 著
ちくま学芸文庫
オカルト好きな人にささるタイトルとなっていますが、内容はかなり難解です
ベースとしての世界観が、汎神論あるいはアニミズム的な、すべての事象に根付いている、大いなるものへの畏敬や感謝の気持ちを持つことが大切だということで、日本人に馴染みやすいなと感じました
一方で、自己においても普遍的なものが内在していることを認識すること
普遍的な自己を認識して、流動する社会情勢に対して右往左往しないこと
一方で、自分は大いなる世界の一部であることを自覚して、世界のために生きる、日常生活を大切にすることを重要視していて
オカルトは世捨て人になることではないことと釘をさしています
自己流の解釈ですけど
超感覚的世界というのは、自分の内面の中にあり、深層心理や無意識の中にこそ
自分自身を助ける指針があるのかもしれません
あるいは、東洋医学でいうところの気の流れも含んでいるようです
昔は東洋医学は非科学的だとバカにされる風潮がありましたが、今の時代はむしろ東洋医学を重視している人が増えています
ヨガのチャクラなどもそうですが、そういう概念を近代的に解釈し直したものが、シュタイナーの神秘学概念なのかなと思いました
人間は大自然の中に組み込まれた存在であるということを自覚することが大事です
今の最大の社会問題として
クマ大量虐殺問題というのがありますが
環境世界に反感で向き合い
自然を征服することを文明の目的としている日本人の未来は限りなく暗いと言わざるをえません
また、高市右翼政権は、戦争の準備を始めたくてうずうずしているようですが
そんなことでは近い将来、日本人に天罰がくだるのではないでしょうか
#読書
#読書感想文
#シュタイナー
#オカルト
#日本人論

アメジスト
読書記録です
神智学
ルドルフ・シュタイナー著
高橋巌 訳
ちくま学芸文庫
タイトルの神智学というのは、感覚的存在を超越した叡智のことだそうです
特に人間の霊的本質の核心に係わる諸問題を取り扱うのが神智学だそうです
本書によると、人間は体と魂と霊から成り立っているそうです
魂と霊の違いが今ひとつ分からなかったのですが、魂は本能的なもの、霊は理性的なものという理解でいいのでしょうか
タンパク質とか核酸などの生物の材料をいくら物理・化学反応を起こしたところで、無生物から生物は生まれません
生物と無生物の決定的な違い
それは生命力です
その生命力の実体とは何かを考えると、魂や霊の存在は決して頭ごなしに否定できるものでもないように思います
物理学者でも宗教上の神を信じる人がいるように、生命力の実体として魂や霊の存在を信じるのはおかしなことではないように思います
今までの人生で学んだことを全ては覚えていないにも関わらず、経験は積んでいるという感覚はある
脳の大きさのキャパではブルーレイに記憶を焼き付けるような仕組みでは、物理的に限界があるでしょうから、魂が体験を記憶しているという説は一理あると思います
通常の感覚的な経験ではなく、思考も魂や霊にとっては経験であるという認識もなるほどなと思いました
感じたことも考えたことも、その人にとってはリアルなことであるということだと思います
シュタイナーのオカルトは、一寸の虫にも五分の魂や輪廻転生とかの東洋的な死生観と重なるところもあるので興味深いです
#読書
#読書感想文
#シュタイナー
#神智学
#オカルト

アメジスト
読書記録です
西洋政治思想史
宇野重規 著
有斐閣アルマ
現代日本の政治家もお題目のように唱える法の支配や立憲主義というのは、中世ヨーロッパの封建社会にルーツがあるそうです
そもそも「法の支配」とは何かというと、統治される者だけでなく、統治する者もまた、より高次の法によって拘束されなければならないという考え方です
「法の支配」とは、法律をもってしても犯しえない権利があり、これらを自然法や憲法が規定していると考えるものです
このような考え方は、君主であっても決して自らの意志をすべてに貫徹させることができるわけではなく、歴史的に認められた臣下の権利を守るべきであるとした封建社会におけるコモン・ローの伝統に由来するものだそうです
中世封建社会というのは、国王と臣下の間の個人的な主従関係によって成り立っており、臣下には社会的な地位に基づく特権が認められていました
国王といえども、臣下の特権を勝手に踏みにじることは許されず、国王が古来の慣習の集積である「法」を破るとき、臣下には抵抗権が生じました
「古き良き法」を合言葉に、臣下は国王の権力を制限しようとする、支配者といえども法の下にあるという意味が見てとれる
ここに法の支配と立憲主義のルーツがあるということだそうです
臣下の同意がなければ国王は法の制定・改廃や課税を行うことができない
国王の大権と臣下の特権の間でバランスをとり、権力の濫用を防止することがはかられた
ヨーロッパにおける自由の伝統というのは、こういう歴史背景があるということが学べて良かったです
#読書
#読書感想文
#西洋
#中世
#法の支配

アメジスト
読書記録です
日本史のなかの神奈川県
谷口肇 編
山川出版社
地元が神奈川県なので読みました
行ったことがあるところ
有名なところ
知らないところまで
数多くの県内の歴史スポットが載っていて面白いです
地元にあたる相模川の東側の地域、旧高座郡にあたる地域は、古代の遺跡がたくさんあるんだなと改めて認識しました
地元にあたる神崎遺跡、秋葉山古墳群、相模国分寺跡の3つの国指定史跡には行ったことがあるのですが、他にもいろいろな史跡が本書で紹介されています
芹沢公園に地下壕があるのははじめて知りました
勝坂遺跡は駅から遠いので、行きようがないのですが、縄文時代中期の関東を代表する遺跡なんですね
戦国期小田原城と近世小田原城は違う場所で全く別物なのははじめて知りました
山下公園は関東大震災の瓦礫を埋め立てて造成されたそうです
山下公園の広さは甚大な被害の裏返しなんですね
川崎大師、大山、江ノ島、鎌倉、金沢八景、箱根が観光地としてブームになったのは江戸時代のことだそうです
明治時代になると、大磯、鎌倉、藤沢、鵠沼、茅ヶ崎、平塚、国府津などで海水浴場が開かれ、明治の大物政治家の別荘も建てられて
神奈川が持っているハイカラなイメージが形成されたようです
#読書
#読書感想文
#神奈川県
#歴史
#史跡

アメジスト
読書記録です
ハイエク入門
太子堂正称 著
ちくま新書
ハイエク思想の全体像を眺望する意欲作となっています
個人的に注目したところは
p175 『隷属への道』について
なぜ「集産主義」はダメなのか
貧困や著しい階級構造などの社会問題を解決するために、国家主導による中央集権主義的な計画経済をやろうとすることはなぜ悪手なのか
市場経済が本来持っている大勢の人々の活動による知識の再発見や再創造がなされるプロセスが、エリートによる社会の垂直的な管理によって制限され、本来、市場経済が持っているはずの発展性が阻害されるからです
一方で市場経済というのは景気変動や失業などの問題が必ず発生するため、市場システムを支える不可欠なルールの一部として、公害への対策や、貧困にあえぐ人々に対して「健康や労働能力を維持できるだけの最低限の衣食住を、社会の全成員に保障」することは必要なことです
ハイエクは日本国憲法第25条の生存権の保障については肯定しています
p313 「法の支配」について
歴史的に憲法というものは、政府の権限の肥大化のためではなく、あくまで権力をよくせいするために要請されたものです
関連して、「法の支配」というものは、国家による権力の行使が専制的にならないように法によって拘束し、人々の権利と自由を保障するための概念です
p375 保守的自由主義者としてのハイエク
ハイエクの自生的秩序論は
制度やルールを近視眼的な「設計」ではなく、時間を通じた漸進的かつ自生的な成長の産物であるとみること
ハイエクにとって保守するべき対象は「自由主義の伝統」であるという意味で
保守的自由主義者であると言えると思います
#読書
#読書感想文
#ハイエク
#社会思想
#保守的自由主義

もっとみる 
関連する惑星をみつける
ホラーの星
394人が搭乗中
参加
こんにちは😊
オカルト大好き(*^ω^*)ふれでりっくです。
オカルト全般みんなで恐怖を共有したいです、心の底からゾッとするようなあの冷たい感覚をみんなで味わいましょう、、、
見たホラー番組やYouTube、怖い体験談、怖い話し、程度の違いはあるかもだけど、気にせずどんどん投稿してくれると嬉しいです!
※グロテスクは求めていません!!!
水族館の星
1489人が搭乗中
参加
行った水族館の話、行きたい水族館の話、水族館フォトなどが集まります
生活の星
455人が搭乗中
参加
今日何食べた?
これ良かったよ
今ね〜してるよ
仕事終わったよー
家事疲れた
散歩してるよー
生活の星🌟生活と広く定義したのは 皆それぞれ
ライフスタイルが違うからこそ素晴らしい
年齢も性別も飛び越えて
交流出来たらいいな(,,>᎑<,,)♡
チャットルームもあるので良かったら💬
搭乗🌟は承認制です
買ったもの載せる
803人が搭乗中
参加
買ったお菓子、雑貨、お洋服、本などわざわざ人に言うほどではないけど誰かに共有したい気持ちのお届け場所
ことばりうむの星
944人が搭乗中
参加
ようこそ、「ことばあそびの星」へ。
ここは言葉のワンダーランド。あなたも、言葉の迷宮をさまよってみませんか?
日常のひと言や詩、ことば遊び、ふとした思索のかけらも、この星の宝物。
響きの奥に潜む、まだ名づけられていない余韻を探しにいきましょう。
あなたの音色を、聴かせてね⭐
もっとみる