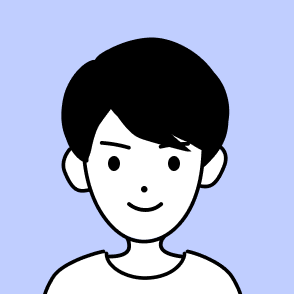
太郎さん
第九回歴程新鋭賞受賞詩人。大岡信、谷川俊太郎、高橋源一郎らから嫌われる。現在、世界俳句短歌現代詩で活躍中。2021年アラブ語圏ゴールデンプラネット賞受賞。アラブ語圏より文学博士を授与される。アルバニア、バングラデシュ、インド、アルジェ、イラク、イタリア、ギリシアなどの新聞雑誌などに詩が掲載される。世界詩人。
アニメ
マンガ
読書
散歩
音楽

太郎さん
between buildings
からうじて芒色せし蚊の飛べり
barely
a mosquito the color of silver grass
flying
木犀の雨にも匂う町の角
fragrant olive smell sweet
even in the rain
street corner
秋深し急に眠気に襲はるる
deep autumn
suddenly
I feel sleepy
秋嵐ビルの合間に咆哮す
autumn storm
roar
between buildings


太郎さん
永遠の無から生まれて永遠の無に戻ってゆく。その一時の生の認識を人生と呼ぶ。群猿の屑文化のなかで右往左往とすることは何もない。
一人の認識をこの世と呼ぶとき、この一人の認識の終わりは世界の終焉である。そして永遠の無に戻ってゆく。前世も後世も人間の妄想に過ぎない。
この世は生まれては死ぬという意味で平等である。理想主義でも現実主義でもない。苦しい人生を送ってきた者は死という幸福に恵まれ、楽しい人生を送ってきた者は死という不幸に死んでゆく。
何も持たずに生まれてきて何も持たずに死んでゆく人生に何を求めることがあるだろうか。幸せとは脳に思い描いたことが現実化するということに過ぎない。幸不幸は人生に関係がない。
脳という器官はいくつかの誤った判断を持っている。自分を観察者として他を比較することに騙される。他と常に比較し比較される。また死んでからも認識が残っていると思っている。名前を残しても死んだ当の本人には関係のないことである。最後に脳は自分の死を考えられない。なぜなら脳もバイタリティだからだ。バイタリティはバイタリティがなくなる状態を考えられないのは当然だ。これらは脳という器官のトリックでしかない。
世界ではネガティブよりポジティブに生きる方がいいというが、何を血迷っていのか。ただすることだけをすればいいだけである。もちろん幸福に感じる時も不幸に感じる時もあるというだけのことでしかない。しかし、これは実際の人生に関係ないことである。承認欲求って他者から番号振ってもらって喜ぶバカもいる。一時の人生を生きていることだけ十分だ。人生は一時の夢でしかないのだから。


太郎さん
花冷のする季節にヨーコは今日も川を凝視めた。新聞をひろげて今日も憤った。どうしてこんな酷いことが起こるのかとヨーコは起ちあがった。そうして社会の不公平を正すためにおまえはそれを言葉に変えた。ヨーコは受賞してその名は各紙に載った。おれは言った。自分だけの正義に固執するなと。しかしその言葉はますますおまえのこころに火をつける結果になった。
おまえの主人がとつぜん会社を解雇された。ヨーコは生活に貧窮した。詩集を出版する金もなくなった。世間のひとがおまえの陰口をして嘲笑う。おまえに同情する友はいてもおまえを救けだすことは困難だった。過去の栄光がおまえを追い詰める。ひとがおまえを冷ややかな目で凝視める。
春が来ても不幸ばかりがおまえを襲う。おまえの姉弟が冤罪で捕まった。ヨーコは移りゆく時代のなかで闘った。しかしどうやってこの窮地から抜けだしていいのか分からなくなっていた。おおくの友もおまえから手のひらを返すように離れた。良い結果はでなかった。ヨーコはいま橋の真中に立ち尽くし川の流れてゆくのを眺めていた。
なんども言ったじゃないか、この世ではどんなことが起こっても不思議ではないんだと。もうおまえはこの世にいない。不慮の事故でおまえは死んだと報道された。真実が明らかになることはなさそうだ。時代の不幸な詩人としてヨーコ、きっとおまえは歴史に残るだろう。しかしおまえがそれを知ることはないんだ。今日も川は流れることをやめない。花の雨が降りしきるなかを。


太郎さん
warming of water
It's too soon
to call it love


太郎さん


太郎さん
古池や蛙飛び込む水の音 芭蕉
まず「古池や」は日本の俳句で「句切れ」と言う。「句切れ」によって後の句「蛙飛び込む水の音」とシーンが変わる。ここではシーンが「古池」という焦点をはっきりさせている。「古池」というと何かどろどろとした碧を感じさせる。いかにも暑そうなムッとする感じが伝わってくる。「蛙」は夏の季語である。日本では単数の「蛙」、すなわち一匹の「蛙」を思い浮かべる。何故そうなのかは「水の音」という「清涼感」をここに見出すからである。「蛙」が複数であればむしろ暑苦しいと感じまいか。またこの句の画期的なところは「水の音」という「音」を言い表したところにある。つまり「古池」という「暑さ」に「水の音」という「清涼感」を与えている。また、「古池」という「静」に「飛び込む」という「動」を置いたこと、「水の音」という「清涼感」が耳に残る。違う角度から見れば「視覚的」であり「音声的」でもある。さらに「古池」の「碧」と「蛙」の「緑」が一体化する瞬間でもある。卓抜した技巧である。さて芭蕉のこの句の技巧は技巧にしか過ぎない。芭蕉にはどのような心理過程があったのかを推察すると「対象を向うに見るのではなく対象を自らの心の中に置いている」と思われる。対立する「静」と「動」、「暑さ」と「涼しさ」をおそらく芭蕉は芭蕉の心の中で調和させているのである。芭蕉の心ばせである。「禅」や「粋」を感じさせる。


太郎さん
詩の革命のために
革命という死語。情熱という死語。このふたつの死語の通路はまわりから、またここから人びとの歓声と熱気がともに棲むつねに太陽の屋根に通じている。森につつみこまれるしずかな巨きな公園が目印だが、今日ではとおく朽ちてしまった、空のなかに消え入りそうな積み石の残像が残っているにすぎないので、そこは何処にでもあるともいえる。おそらく何処にもないのだろう。
小鳥と栗鼠のかけめぐる森。岩を走って水の流れる音。ふるくたくましい樹樹のまわりにはいくらか人がそこに腰掛けて心地よいほどの雑草がその樹樹と同じたくましさで生きている。やわらかい草の下のあたたかな。全部嘘だ。つまり死語である大地よ。死語の凍土のきしみ砕ける音さえない時代。人びとの声が奇妙にゆがんで聞こえてくるどこまでも暗闇の通路。
時の鋼で打ちつけられた杭を指標にどこにもゆくことができない通路。この通路を破壊するためにやって来たという道化の服を着せられた英雄だと名乗る死刑囚の言葉。その何も語らずに黙っているその声にふれる。黙ったまま。とおく離されて相手が見えないところの椅子に坐って語り合った、まるで何も話さなかったかのように。そのひと言ひと言がなつかしい火薬の匂いのする言葉で。
おまえの言葉を書きうつす。この時代の冷たい紙面が一滴の墨滴がひろがる広がりかたで燃えている。消された火の情熱で燃えている。


太郎さん
spring rain
today's thoughts
go around in circles


太郎さん
『貞観政要』より
荀子は政治家の心すべき要点として
1 公正な政治を行い、国民を愛すること
2礼を尊重し、すぐれた人物に敬意を表すること
3賢者を登用し、有能な人物を抜擢すること
と説いている。


太郎さん
この異常な暑さのために花は美しく開かなかった。武器工場や科学工場が爆撃され、その塵埃は大気圏を薄くしていた。紛争は後を絶たなかった。民間人でさえも殺害されたが、他の穏やかな地域で人々は能天気に口笛を吹いて、その夜も何事もないかのようにその日を仕事に過ごした。
正しい人たちはもはや詩を書くことをやめた。歴史の頁は書かれることも読まれることももはやないと判断されたからだ。悪しき者とそれに否という者だけが尽力して紛争をつづけたが、人類が破滅へと向かっていることは否定できなかった。見えることのない破滅は花の凋落に現れていたというのに、人々は今日の個人的利権のために奮闘することしかなかった。
誰かが空が落ちてくると言っても、もうわれわれには止める術がなかった。個人的な享楽に人々は余念がなかった。人類は破滅に向かっているのに人々は目先の利益を求めて止まなかった。人々は今日も他者を足蹴にすることに始終するばかりだった。あからさまな悪意だけが人々の念頭にあった。
心の平安のために人々は慰めをカルトに求めた。カルトの主人は今日も金の算段に余念がなかった。馬も犬も猫も品種改良されてもはや予言する能力を欠いていた。歴史はあらたな頁をめくることなく、突然閉じられた。
生き延びようとする人々が門の前に押し寄せたが、門の外にいるものも内にいるものも時間は残されていなかった。門自体もこの暑さのために溶解して津波にのまれた。人類の死によって歴史の頁は閉じられ二度と開かれることはなかった。


太郎さん
cherry blossoms fall
After its dispersal
the blue leaves


太郎さん
a dream for a moment
航跡の長さ変はらず秋の海
the length of the wake
remains the same─
autumn sea
調理して流しに輝く秋の水
cook it
autumn water shining
in a sink tank
迷ひては頭のなかの糠蚊かな (夏)
when I get lost
my head is
ceratopogonidaes
何事もひとときの夢秋の月
everything is
just a dream for a moment
autumn moon


太郎さん
Seneca
who preaches that
life is sorrow
academia
as a healing for the soul


太郎さん
西洋の考え方はギリシアより、二人以上の人間のいる世界というものがあるということが前提となります。それはダイアローグから始まり社会の在り方からしいては共生という考えを導きだします。つまりどうすれば万人が平和裡に生きることができるかという考え方をします。これについてはいわゆる思想、哲学として展開されているので私が詳述するまでもないでしょう。
一方東洋的な考え方は古来より、とくに仏教では他者と兼ね合いのない認識論、一人の人間が生まれ生き死んでゆくという一個人の生き方を前提とします。この考え方は西洋的な考え方の世界伝播によりほとんど忘れられています。仏教とは頭のシステムの解明により頭では思い量ることのできない命を導きだします。命とは一個人の活き活きとした身体全体を示します。簡単に言うと脳は思いを分泌する器官であり、物事を相対に捉えます。しかし自分の命について脳は絶対として判断します。自分の命が絶対なら出会うところすべてがわが命ということになりませんか。
どちらが優れているかを考えること自体が間違っています。仏教の考え方は西洋の考え方とは違い思想についてもそれぞれに相対ではなく絶対なのですからどちらが◯でどちらが×かではなくどちらとも◯と考えてよいと思います。よくこの考えの前提に立ち戻りそれぞれの考え方の長所を個々人みずからが実践しなくてはならないと私は思います。


太郎さん
その調べは古く心は清く風格はおのずから高い。貌はかじけ骨は剛くして人は顧みることがない。口には貧乏を言うが道は貧でない。いつも襤褸を着ているが心には価値のつけようのない命という宝を蔵めているのだ。物をよく用い縁に応じて惜しむことがない。命のはたらきは身心に自在に通じている。あなたの性・智・行が整い我痴・我見・我慢・我愛から目を覚ませば命は円です。自分の物差しを捨てるということです。すべて比較、相対でしかないきみの頭の欲心に他ならないのだから生活してゆけるだけの小欲で足るのを知るしかありません。欲心にはキリがないのですよ。どこまで追っても満足することはなくそのうち寿命がきます。このことが思いのうちにきちんと分かればこころ落ち着いていられる。上士は分かればそれを生活にする。中下はよく分かってもそれを生活にすることはない。ただみずからの間違った欲心を解きなさい。誰だ、外に向かって精進を誇っているのは。誰のためのことではない。


太郎さん
信じても信じなくても自分は自分だ。間違いのない事実のみだ。あるものはある。ないものはないのだ。自分は自分を誤魔化せない。命は自分にあるのに外を探すな。まず自分が煩悩の容れ物であると知りなさい。眼耳鼻舌身意の作用はあるとかないとかいうものではなく信じても信じなくてもある。大宇宙はひとつの明珠で煩悩の比較相対の頭では様々に見える。しかし見えたとおり思ったとおりが本物ではない。みんな煩悩という煙幕の中でのことなのだ。水面の月が本当の月でないと知れば、鏡に映したみずからの影は本当の自分でない。きみが思うみずからは本当のきみではない。きみ自身は絶対なのだから。他人の評価も同じことだ。すべて測ることができないのだから何に依りかかっても仕方ない。常にひとり行き常にひとり歩く。幸不幸のない命に遊びなさい。


太郎さん
実際坐って自分の頭という塵鏡を手放しにしてみなさい。どんな思いが頭に去来するのかよく分かるはずです。欲ばかりでしょう。無念無想になりますか。生まれたことがないのですか。生まれたことがないなら生きるにあたってあれこれ思うこともないでしょう。パソコンを持ってきて問うてごらん。仏を求め功徳を施せばいつ仏になれるかと。命を持っているのにまだ何か欲しいのですか。自分だという思いをすべて放って捉まえてはならない。分別の止んだところに随って生活してごらん。何もかも常なるものはなく本当はすべてないのだ。すなわちこの世界一杯命でないものは何もないのだ。


太郎さん
すぐに坐れば、施し施され適度の欲をもち辱めを堪えることもない。命に随って、することはして、乱れることなく常にこれを生活とすればこのいのちは円だ。われわれはこのはっきりとした現実という夢を生きて、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上という六趣をさまよう。しかし覚めてみれば空くうとして大宇宙もない。罪福もなく損益もないのだ。人間は好きを握り同時に嫌いを握る頭のシステムがあるだけです。戯論、修身の話ではないのだから、自他・善悪・好悪など二つに分かれたところで探し求めて何になる。今生きているという間違いのない事実に気づきなさい。


太郎さん
身の動きはあらわれては消える浮雲。心の動きはと言えば、貪り、怒り、愚かさの泡にほかならない。頭を手放しするのだから思いは起こってもまた消えるのです。命のことが分かれば自分の思いのことなどどうでもいい。刹那に消えるこの世の地獄。どんな怖しい思いが頭に浮かんでもまた消えてしまう。わたしが嘘を言って誑かしているのなら、みずからこの舌を抜いてやろう。


太郎さん
われわれは呆ける。もっと上手いことしよう、もっといい目に遭いたいと思って呆ける。この思いを手放しにすること。それが覚めると言うことです。おれはこれだけ貰えるなんて権利はない。全くの無一物です。無一物の命は何ものにも汚されない天真爛漫です。呼吸は生きている証です。その呼吸の力はどこから来るのか。おれの思い以上の力がはたらいているのだ。困ったって頭の中で思っているだけ。すべてが大自然に生かされているのだ。宇宙一杯なのですよ。


太郎さん
手と足を閉じて坐禅すれば思いが湧き上がって来るのが分かる。これが無明の実性即仏性ということです。生命力があるから妄想煩悩が起こるのは当然です。自然の天地は否定出来ません。人権も社会的約束事にすぎない。当てにはならないということです。本来われわれの頭の中で考えるのは幻です。幻を幻と分かることが自分のみを拠り所にしていればよく分かります。


太郎さん
きみは見ないのか、すべての勉強をし終わって自己の他に何にもなく他を拠り所としない人を。作り事のないゆったりした人を。この頭では考えられない命を生きている風流の人を。妄想を除かず真を求めない人を。妄想も真実も頭に思い浮かべただけのものにすぎないのだ。頭ののぼせ上がりが消えれば何処にもない。根拠理由を考えてもどうにもならないでしょう。


太郎さん
know the strength
of a dandelion
gargling concrete
青草や春惜しむとも思はざり
green grass
they do not seem to
miss spring
橋に立つ女の髪に風ひかる
the wind shines in
the hair of a woman
standing on a bridge
初恋のハンカチ探す夏はじめ
finding
my first love handkerchief
the first of summer


太郎さん
回答数 116>>

太郎さん
It hurts me
morning nap
on the briars


太郎さん
朝とおぼしき光のなかで無用になった白銀の腕時計が碧い湖に捨てられた。腕時計は水中をゆっくりと躍るようにして水の底に落ちていった。湖底に落ちついてそれはわずかな泥けぶりをあげた。
ひとびとは咳をしたあと他者について灰色の小言に悪意をほのめかせた。勝者に媚び敗者をいたぶるひとびとの悪癖は尽きることがなかった。
他者への見えない黒い憎しみを胸にひそめてひとびとは何食わぬ顔で出かける支度をする。時間に急ぐひとびとは冷えたスープを錆びた鉄の匙でしずかにすくいあげては口に運ぶしかなかった。狂った馬のあげる青ざめた悲鳴が窓の遠くから聞こえた。
スープのなかには蜆の殻が二三個残ったまま洗われることなくその皿は白いテーブルクロスの上に残されていた。今度の無益な戦いで戦い自体が終わろうとしていた。勝利も敗北もなく地は噎びまばゆい蒼穹は冥く閉じられた。
おれたちが生き方を誤ったのかそれともおれたちの必然がそうさせたのか。誰もが無言のまま、湖底に沈んだ腕時計の歯車だけが泥土にまみれて廻りつづけた。


太郎さん
「一つの詩を終る時になると、何か最初の出発点に返って行かなければならない気がして来ます。そうでないと、何か円がまとまらないような感じがして、最初に出て来たイメエジをおしまいに又持出す形になるんですが、これでいいと思うんです。どういう駅を出発して来たか、ということが、終りになって大事になってくるんです。」
「(略)」僕、自分は少し特殊なところがあるんじゃないかと思うんです。一昨年の暮引揚げたばかりなんですし、……(略)どうも人の中にまぎれこめないような、何か押しだされたような気がしています、今だに。一寸人に説明してもわからないでしょうが、それから僕みたいな境遇にあったものは過去というものに対するノスタルジアがとても強いんです。過去をいろんな形でたてなおしてみたい気持で一杯ですね。来年をうたう事は出来ないんです。いつも過去をうたっていなければならないんです。」
「過去にこだわっているんです。しかしその事が、いま生きて行く力になっているんじゃないかとも思っています。過去というものについて、変なことを考えています、実に(笑)。過去を全部歩きなおす事ができるんじゃないかなどと。これをこの間から書こうと思っています。……(略)過去というものの意味はきまっている、しかしその意味を変える事ができるんじゃないか、観念で変えるんじゃない、実際に過去のある地点までもどって、過去をもう一回歩きなおすというようなことですが……」(『石原吉郎全集』『年譜』適宜改稿=筆者)。
よく自省すれば判ることだが、われわれもその時代じだいに翻弄され、われこそはと名乗り出て、みずからの狂気を狂気と知らぬままに演じなければならない『ドン・キホーテ』であり、『贋作ドン・キホーテ』ではないだろうか。「〈フェルナンデス〉」「しずかなくぼみは/いまもそう呼ばれる」。


太郎さん
「〈フェルナンデス〉/しかられたこどもよ/空をめぐり/墓標をめぐり終えたとき/私をそう呼べ/私はそこに立ったのだ」
「しかられたこどもよ」と石原はしずかに呼びかける。「空をめぐり/墓標をめぐり終えたとき」。ここには石原のシベリア体験による「空」ばかりの土地で、いつ死ぬかも知れない生(せい)の不確かさ、「空をめぐり/墓標をめぐり終えたとき」が見えるようだ。「私をそう呼べ/私はそこに立ったのだ」。私を「フェルナンデス」と「呼べ」。「そこに」とは石原における「贋作」の境遇、あるいは「贋作」の時代じだいのことだろうか。戦中に諜報部員になり、戦後のシベリア抑留、祖国にいながらの遠い祖国、それらの「贋作」の時代に「私はそこに立ったのだ」と石原は証言する。つまり、石原自身が「ひとりの男」であり、「くぼみ」であり、「しかられたこども」であり、「フェルナンデス」であり、エゴン・ヘッセル氏であり、遡ってはカール・バルトであったのだ。さらに言えば、表題のとおりこの詩の内容そのものが「フェルナンデス」であったのだ。これらは幾重層ものコノテーションになっている。かてて加えて、この詩の終りは始めに戻るのだ。つまり最終行「私はそこに立ったのだ」は「フェルナンデスと/呼ぶのはただしい」に戻るという円環構造になっている。
最後に石原が詩を書く動機について確認しておきたい。
一九五五年石原四十歳の八月 詩「葬式列車」(〔文章倶楽部〕)発表と共に読者代表として鼎談「作品と作者とのつながりをどうみるか」に参加。出席者 鮎川信夫、谷川俊太郎。この鼎談の発言には詩人の全詩業にかかわる興味深いものが含まれている。抜粋記載(全集未収録)。


太郎さん
「ある日やさしく壁にもたれ/男は口を 閉ざして去った」。
「ある日」(「男は」)「やさしく壁にもたれ」(その)「男は口を 閉ざして去った」のである。「ある日」とは石原が、この詩を書いた現在であり、過去であり、未来である。それは同時にこの詩を読むものの、つまりわれわれの現在であり、過去であり、未来なのだ。「男」については詳述したとおりである。「やさしく壁にもたれ」「口を 閉ざして去った」。これは石原の旧懐の念である。ある年齢に達し過去を思えば、すべての過去に「やさしく」なってくるものである。そうして「壁にもたれ」すべての過去に「口を 閉ざして去」らなければならなかったのである。「口」にできない過去、たとえそれを「口」にしてもどうしようも理解してもらうことのできない過去があるものである。ゆえに「口を 閉ざして去った」のである。
若い人には、まだわからないかも知れない。しかしわれわれ人間はそのようになってゆくものなのである。これは生理的な現象である。


太郎さん
詳細は前記の本にゆずるとして、以上のことを石原がどこまで知っていたかは不明であるが、何ヶ国語にも堪能だった石原は『贋作ドン・キホーテ』の事実を知っていたのは確かだと思ってよいだろう。
石原の『フェルナンデス』にもどる。
「寺院の壁の しずかな/くぼみをそう名づけた」。
この詩の疑問に思われる点を検閲(けみ)してみたい。「寺院の壁の しずかな/くぼみをそう名づけた」この「寺院の壁」とは『嘆きの壁』のことだろうか。石原がそこへ行った記録はないが、とうぜん『嘆きの壁』の「イメエジ」が石原の脳裏にあったはずである。その「しずかな/くぼみを」「フェルナンデス」と親しみをこめて「そう名づけた」のである。
「ひとりの男が壁にもたれ/あたたかなくぼみを/のこして去った」。石原にとっては『贋作』である歴史の経験も親しいものになっていたのではあるまいか。繰り返しになるが、この「男」は石原が洗礼を受けたというカール・バルトに直接師事したエゴン・ヘッセル氏、また石原自身のことでもある。推量はしょせん推量にしかすぎない。しかし一体どの歴史が正しいのか、石原には石原の経験した歴史があるのである。それを個人史と言うならば、われわれ個々にとって生(き)の個人史のみが確かなものである。
「〈フェルナンデス〉/しかられたこどもが/目を伏せて立つほどの/しずかなくぼみは/いまもそう呼ばれる」
「〈フェルナンデス〉」は「しかられたこども」でもある。「しかられたこどもが/目を伏せて立つほどの」。「しかられたこども」が本当に反省を促されたとき、われわれは「目を伏せて立つ」のではないか。「目を伏せて立つほどの/しずかなくぼみは/いまもそう呼ばれる」そうしてうな垂れて、「壁」に「もたれ」る。そこに「しずかなくぼみ」ができる。まず石原自身が自省して「壁にもたれ」、『ドン・キホーテ』、『贋作ドン・キホーテ』にならざるを得なかった、過去であり未来であり得る人びとに「そう呼」びかけているのだ。当然「しずかなくぼみは/いまもそう呼ばれる」「〈フェルナンデス〉」


太郎さん
『贋作ドン・キホーテ』(アベリャネーダ著 岩根圀和訳 ちくま文庫 1999年12月2日第一刷発行)についてはこの下巻「あとがき」によく纏まっていて詳しい。岩根氏の「あとがき」から一部引用する。
これはアロンソ・フェルナンデス・デ・アベリャネーダの『才智あふるる郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』(スペイン語 中略)の全訳である。世界文学の遺産ともなっている『ドン・キホーテ』の作者はスペインのセルバンテスではなかったかと思われるかも知れない。たしかに『ドン・キホーテ』前篇は一六〇五年にミゲル・デ・セルバンテスの名で出版されている。これがたちまち大評判となり、その年度末にはすでに六版を重ねてとどまることを知らぬ売れ行きであった。
騎士道小説のパロディとして書いた『ドン・キホーテ』が空前の当たりを飛ばすまでは一介のしがない作家に過ぎなかったセルバンテスは、大いに気を良くして後篇に筆を染めることにした。前篇の着想を踏襲し、さらに構想を練って『ドン・キホーテ』の後篇を書き始めたのがいつの頃であったのかはっきりしない。しかし一六一三年出版の『模範小説集』の序言で「近いうちにドン・キホーテの後篇をお目にかける」と述べているからこの時点ですでにかなりの量まで書き進んでいたと見ていいだろう。実際にセルバンテスの『ドン・キホーテ』後篇が出版されるのはそれから二年後の一六一五年である。ところがその目と鼻の先の一六一四年にアビリャネーダの『ドン・キホーテ』後篇が世に出てしまった。
当時は剽窃の意識の薄い時代のことだから先に世に出たアベリャネーダの『ドン・キホーテ』は、作者の異なる別の『ドン・キホーテ』後篇であるに過ぎないのかも知れない。アベリャネーダ自身も「ある物語が複数の著者を有することは別段真新しいことではないのですから、この後篇が別の作者の筆から生まれることにどうか驚かないで戴きたい」と序文に述べているとおりである。それを承知であえてこの作品を贋作と呼ぶなら、真作の執筆途中に贋作の出版を目の当たりにしたセルバンテスの驚きと怒りは想像するに余りある。


太郎さん
石原はインタヴューにおいても対談においても、用心深いと言っていいほど正確に言葉を選んでいるのがよく判る。石原の「声となる均衡」への留意はこの詩集の表題作『斧の思想』に表れている。「およそこの森の/深みにあって/起こってはならぬ/なにものもないと」。
このことは「人間不信」に陥った石原の第一詩集『サンチョ・パンサの帰郷』、その巻頭の詩『位置』に「しずかな肩には/声だけがならぶのではない/声よりも近く/敵がならぶのだ」と明確に「敵」と書かれている。「勇敢な男たちが目指す位置は/その右でも おそらく/そのひだりでもない」と。ところで石原は何を「敵」と見做したのか。それは石原の外界の「敵」であり、同時に石原自身という「敵」である。石原にとって外界と内面は常に同じものであったのだ。再認しておきたい。石原の外側(そと)と内側(うち)とは常に一(いつ)なるものであったのだ。言われればなるほどと思われるかも知れない。しかし石原はこのことをみずからによく承知していたのである。カール・バルトの『ローマ書講解』(小川圭治・岩波哲男訳 平凡社ライブラリー)には「神の意志は、与えられた外的状況と内的状況との真実に実現した調和において、キリスト者に可能となった正しいことへの洞察によって知られる(一二・二)。瞬間のこの認識は、人間の願いの成就が考えられる唯一の道である」とある。石原が戦後の日本においても、「声となる均衡」にどれだけ注意を払っていたことか。
旧陸軍中野学校から諜報部員として旧ソ連シベリア抑留後、この国に帰還した石原の意識はみずからの境涯を『ドン・キホーテ』に擬(なぞら)えて二重に写したのと同様、この『フェルナンデス』でもまた、『贋作ドン・キホーテ』にみずからを擬えて二重に写しているのだ。


太郎さん
『フェルナンデス』
フェルナンデスと
呼ぶのはただしい
寺院の壁の しずかな
くぼみをそう名づけた
ひとりの男が壁にもたれ
あたたかなくぼみを
のこして去った
〈フェルナンデス〉
しかられたこどもが
目を伏せて立つほどの
しずかなくぼみは
いまもそう呼ばれる
ある日やさしく壁にもたれ
男は口を 閉じて去った
〈フェルナンデス〉
しかられたこどもよ
空をめぐり
墓標をめぐり終えたとき
私をそう呼べ
私はそこに立ったのだ
「フェルナンデスと/呼ぶのはただしい」
と石原吉郎は書いた。石原の第三詩集『斧の思想』所収『フェルナンデス』の冒頭である。『石原吉郎全集』(鮎川信夫 粕谷栄市 編集委員 花神社 1980年7月20日 初版第一刷)の『年譜』によるとこの作品は、1970年、「ペリカン14」に掲載された。
「〈フェルナンデス〉」のリフレインが二度ある。この「フェルナンデス」とは誰か。もし私の推論が正しいとすれば『贋作ドン・キホーテ ラ・マンチャの男の偽者騒動』(岩根圀和著 中公新書 1997年12月20日発行)に載る偽者アロンソ・フェルナンデス・デ・アベリャネーダのことだと思われる。
石原はこの「贋作」についても知っていただろうと推測されるが、『石原吉郎全集』のなかにも、フェルナンデスについての言及はない。「男は口を 閉じて去った」のである。この「男」というのは、石原が洗礼を受けた師のエゴン・ヘッセル氏であり、石原自身でもある。
石原はインタヴューにおいても対談においても、用心深いと言っていいほど正確に言葉を選んでいるのがよく判る。石原の「声となる均衡」への留意はこの詩集の表題作『斧の思想』に表れている。「およそこの森の/深みにあって/起こってはならぬ/なにものもないと」。


太郎さん
カナコは煎ったひまわりの種子を奥歯に噛みながら、この国には詩人がいないと口ずさんだ。彼女はバルコニーの塀に肘を着いてまた溜息をついた。この高層ビルの上階から見える景色はまるで墓場だと彼女はその種子を齧った。
カナコは花瓶に活けた首垂れたひまわりから一粒の種子をとってまるで御守りのように首にかけたロケットのなかにしまいこんだ。彼女が好んだ白いシルクのシャツに銀のロケットが輝いた。彼女の近くにゆくと気流が渦を巻いたようになるのはおそらくそのせいだろう。
カナコはロケットに触れながら世界の何処に行けば詩が生まれるんだろうと呟いた。この疫病はいまに始まったことではないのよと彼女は胸のロケットに掌を当て地上を見下ろして思った。
狂った人の心を正気へと導く一粒の種子。狂ったこの世に信じられるものがあるとすればそれは一粒のひまわりの種子だけだとカナコは日記に書き残した。彼女は走り高跳びの選手さながらバルコニーの高めの塀をクリアした。
地上に叩きつけられるまでしばらくのあいだカナコは宙を漂った。彼女の首にかけられたロケットが彼女より浮きあがってその一点で空を支えた。この墓場だらけのこの世が一斉にひまわり畑になってすべてのひまわりが真実の太陽の位置を示していた。
2020/07/19


太郎さん
in silky clouds
invisible
the stars of spring
ゆく春や声出でぬまま電話切る
the going spring─
without my voice
hang up the receiver
春雨や空くらく光り路に音
spring rain─
the sky glowed darkly
noise in the street
あかつきに青葉の透けて空覆う
before dawn
through the blue leaves
cover up the sky


太郎さん
回答数 186>>

太郎さん
there is no past
the future never came
right here, right now
a Japanese bush warbler cries
the first cherry blossoms


太郎さん
spring rain
The sound is soft
piercing the earth
春昼や航跡光らす貨物船
spring noon
cargo ship shining
its wake
膝曲げて箸洗ひをり水温む
bend my knees
washing my chopsticks─
the water warms
ぼうたんの瓦解といふべき崩れ方
the peony
It should be called a collapse
the way it crumbles


太郎さん
remain unaccustomed to
the death of others─
cherry blossoms at night
橋の上あかつき青し花錦
on the bridge
dawn is blue
cherry blossom brocade
花散り終わり
Cherry blossoms have finished falling
花守が魂の篝も消えにけり
the bonfire of
the cherry blossom guard's soul
is gone
音もなく咲き散る花や大合唱
loud chorus of cherry blossoms
blooming and falling
without a sound
あをあをしみつばを奥歯に噛みあはす
bite fresh and green
Japanese chervil
into my back teeth


太郎さん
deep roots
suck nectar from the soil
in winter
when spring comes
they will be white cherry blossoms


太郎さん
when a flower blooms
it must fall
winning or losing
is a dream game
what is there to be buoyant about?


太郎さん
my life
秋の風寄り添う人もあらぬまま
autumn winds
with no one
to cuddle with
蛇笏忌や塵も積もらぬわが命
dakostu anniversary
no dust will accumulate
my life
dakostu(1885-1962)Japanese haijin
風狂の身にもしみゐる秋の風
autumn winds
that sink into
even for the insanity
秋の空馬の瞳や藁匂う
autumn sky
eyes of a horse
the scent of straw


太郎さん
人間はこの世にいる限り、人間に対して誠実に生きなければならない。
Conditions of a Poet
As long as man is in this world, he must live with integrity toward man.


太郎さん
cherry blossoms
wiping down the desk
in my late father's study


太郎さん
first cherry blossoms
embers in the depths
of my belly burn


太郎さん
the earrings sway
and the wind
temporarily glows


太郎さん
rivers run deep
the season arrives
and the cherry blossoms bud

