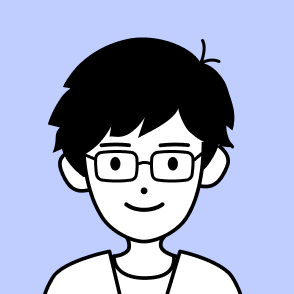
おじさん
外資系 疲れおじさん
「183センチ、毛量多め、眼鏡」と聞くと、怪しい人物を想像するかもしれませんが、ご安心ください。大手企業に潜伏中のごく普通の変態です。
30代前半までは「自称会社員(無職)」としてフラフラしていましたが、今は社会の歯車として、どうにか回っています。
東京
オフィス
パチスロ

おじさん
細い三日月が夜空にきらめく静かな晩、石畳の小道の奥に、そのお店は優しく明かりを灯す。お店の名前は「心の預かり屋」。
店主は、柔らかなモスグリーンのツイードジャケットをまとい、頭に小さなシルクハットをちょこんと乗せたうさぎです。
このお店に持ち込まれるのは、形のあるものではありません。訪れる人々が預けにくるのは、形のない、それでいて確かに重いもの「疲れで縮こまってしまった心」や「力を出し尽くして休みたがっている才能」なのです。
今夜のお客様は、一人の若いピアニストでした。彼はため息をつきながら、うさぎに話します。
「音楽が、あんなに好きだったのに。最近はピアノの前に座るのが少しだけ怖いんだ。僕の…僕の『音楽を奏でる心』を、少しだけ預かってもらえませんか」
うさぎは長い耳を優しく傾け、ピアニストの目をじっと見つめました。その瞳は、彼の疲れ切った心をそっと包み込むような温かさを持っています。
「ええ、もちろんですとも。大切なあなたの心、責任をもってお預かりします」
うさぎはシルクハットを脱ぐと、ピアニストの胸の前にそっと差し出しました。すると、ピアニストの心の中から、鉛色のもやのような「プレッシャー」や「焦り」だけが、ふわりと帽子の中に吸い込まれていきます。不思議なことに、音楽への愛情や楽しい思い出は、温かな光として彼の胸に残ったままでした。
「ああ…なんだか、肩の力が抜けたみたいだ」
ピアニストは久しぶりに穏やかな表情で呟きました。
うさぎはシルクハットをかぶり直すと、にっこりと笑います。帽子の中では、預かったばかりの「音楽を奏でる心」が、まるで疲れて眠る小さな生き物のように、静かに呼吸をしています。
「では、お預かりの印に、こちらをどうぞ」
うさぎはカウンターから、小さな銀色のベルを取り出しました。
「これは『日々のささやかな輝きに気づくベル』です。心が疲れたときは、このベルをそっと鳴らしてみてください。忘れていた素敵な音が、あなたの周りにあふれていることに気づくでしょう」
ピアニストはベルを受け取ると、店の外で試しにチリンと鳴らしてみました。すると、風が木々の葉を揺らす音、遠くで聞こえる猫の鳴き声、街の穏やかなざわめきが、まるで美しい音楽のように心に染み渡ります。彼の顔に、柔らかな微笑みが戻っていました。
ピアニストが希望に満ちた足取りで帰っていくのを見送ると、うさぎは預かった「心」が入ったシルクハットを、大切そうに磨き始めました。
「大丈夫、大丈夫。少し疲れただけですよ。ゆっくりお休みください」
まるで大切な植物に水をやるように、うさぎは帽子の中に優しく語りかけます。彼の仕事は、疲れた才能や心を奪うことではありません。持ち主が再び元気を取り戻すまで、それらが安心して休める場所を守ってあげることなのです。
帽子の中では、これまでに預かってきた「絵を描く情熱」や「物語を紡ぐ夢」も、すやすやと穏やかな寝息を立てています。
もしあなたが何かに少し息切れしてしまったなら、三日月の晩に、あの石畳の小道を探してみてください。シルクハットをかぶった心優しいうさぎが、あなたの心が必要なだけ休めるように、その大切なものを温かく見守っていてくれるはずですから。

おじさん
静寂に包まれた古い劇場。かつては熱狂に震え、今は客席の軋む音さえ寂しく響くこの場所は、まるで忘れ去られた夢の残骸のようだった。そこに立つのは、伝説の手品師、マダム・ルブラン。彼女のショーはいつも観客を現実と幻想の狭間へと誘う。だが今夜、彼女の瞳に映るのは、客席の奥で満たされることのないまま、静かに蠢く劇場の「渇き」だった。
幕が上がり、ステージ中央にスポットライトが落ちる。真紅のドレスを纏ったマダム・ルブランは、深くお辞儀をした。その仕草一つで、劇場の空気がかすかに震える。最前列に座る紳士淑女たちは、マダム・ルブランの冷たい輝きに、期待と一抹の不安を抱いた。
「皆様、今宵は『劇場に捧げる夢』のイリュージョンにご招待いたします」
ざわめきが起こった瞬間、劇場の古い壁が、まるで大きく息を吸ったように感じられた。彼女は優雅に手を広げ、指を鳴らす。途端に、観客席の最後列に座っていた一人の老婦人が、まるで時間を巻き戻すように瞬く間に若返り、そしてその存在を劇場に刻み込むようにふわりと消え去った。老婦人の座っていた席からは、彼女がかつてこの劇場で体験した、初恋の輝かしい情景が、一瞬の残像となって浮かび上がる。
驚きと恐怖が入り混じった声が上がり、携帯電話を構えていた観客の画面がノイズを走らせてフリーズした。だが、マダム・ルブランは涼しい顔で微笑み、再び指を鳴らす。今度は、中央列の若いカップルが、互いの手を握りしめながら、その場で出会った頃の純粋な喜びを共有し、光の粒子のように劇場に溶けていく。彼らの座っていた場所には、二人が初めて手を取り合った瞬間の、熱い感情の残響が漂った。
次の瞬間、観客たちは次々と、それぞれの席に座ったまま、光の粒子となって消え去っていく。劇場の古い椅子は、もはや座る人の体温ではなく、彼らがかつてこの場所で感じた幸福な感情の光で満たされていく。残されたのは、舞台上のマダム・ルブランと、最前列に座る数人の観客だけだった。彼らは震えながら次の瞬間を待つ。だが、その震えの中には、奇妙な「安堵」や「誘惑」が混じり合っていた。
マダム・ルブランはゆっくりと最前列に近づいてきた。その目は、まるで深い宇宙のよう。彼女は、残された観客の一人の男性の目の前で、再び指を鳴らした。
男性は、自分が消えゆく感覚に襲われた。恐怖は一瞬で消え失せ、彼の脳裏に、人生で最も輝いていた思い出の数々が、怒涛のように押し寄せる。初めて観劇した時の興奮、妻との出会い、そして愛する人と笑い合った日々。それは、まるで人生最高のハイライトを、肌で感じながら追体験するような、至福の感覚だった。完全に消え去るその寸前、彼は見た。マダム・ルブランの口元が、わずかに吊り上がっているのを。そして、彼女の瞳の奥で、消えたはずの観客たちが星のようにきらめいているのではなく、「彼らがかつて経験した無数の幸福な感情の光」が、永遠に輝き続けているのを。
劇場は完全に静寂に包まれた。ステージにはマダム・ルブランが一人。
彼女は、誰もいない客席に向かい、ゆっくりと、そして深くお辞儀をした。
「皆様、素晴らしい拍手をありがとうございます。今宵、この劇場は満たされました」
その言葉に呼応するかのように、満たされた客席から、無数の歓声が湧き上がった。それは、この劇場が長年飢え続けていた、観客たちの「夢の残像」によって満たされた、確かな喜びの音だった。そしてその歓声は、やがて嵐のような大拍手へと変わっていく。
マダム・ルブランは、その音に耳を傾けながら、初めて満ち足りた微笑みを浮かべた。彼女は観客たちを消し去ったのではない。彼らがこの劇場で生きた「夢」の輝きを、永遠の命として捧げたのだ。スポットライトが彼女の姿を照らし続ける中、その大拍手は、まるで劇場そのものの鼓動のように、夜空に響き渡るのだった。

おじさん
その舟は、夜という概念そのものから紡ぎ出されていた。街が最後の瞬きを終え、人々が眠りという私的な海へ漕ぎ出す頃、それは音もなく現れる。月光を吸って育つという夜光苔を編み上げた船体、夜明けの一瞬前にだけ立ちこめる霧を漉いて作った帆。人々は、いつしかそれを「綿毛の舟」と呼んだ。
舟の主は、ただ「夢守り」と呼ばれていた。彼がいつから存在するのか、誰も知らない。夢守りの仕事は、この舟を駆り、人々が眠りの中で手放した、行き場のない想いの欠片を拾い集めることだった。舟は物理的な水の上ではなく、地上の営みが沈黙した後に現れる、深く濃紺な静寂の海を滑っていく。健やかな寝息は穏やかな波紋となり、悪夢は舟の進路を乱す荒波となった。
ある夜、夢守りはこれまでに感じたことのない、奇妙な淀みを静寂の海に感じ取った。それは悲しみとも怒りとも違う、凍りついたまま声になれなかった、古い叫びのような響きだった。淀みの中心へ舟を進めると、穏やかだったはずの静寂の海はささくれ立ち、忘れたはずの言葉が氷の礫となって舟を打った。
「これは、単なる夢の澱ではない。記憶の奥底に打ち込まれた、一本の楔だ」
夢守りは静かにつぶやいた。
舟が辿り着いたのは、海沿いの古びた一軒家だった。今はもう誰も住んでいないはずのその家には、かつて灯台の番人の家族が暮らしていた。夢守りは舟を窓辺に寄せ、意識を滑り込ませた。家の中は、時間が止まっていた。埃をかぶった家具、色褪せた家族写真。そして、小さな男の子が一人、窓の外をじっと見つめていた。しかし、それは実体ではなく、この場所に強く焼き付いた記憶の残像だった。少年が見つめる海の先、かつて岩場に立っていたはずの灯台は、跡形もなくなっている。
夢守りは、この家の記憶をたどった。少年は、灯台の番人である父を深く敬愛していた。父は嵐の夜、いつものように灯台へ向かった。しかし、その嵐は規格外の力で灯台を飲み込み、父は二度と帰ってこなかった。少年は、父を止められなかった自分を責め、その日から心の中で何度も嵐の夜を繰り返していた。彼の成長は現実世界で続いたが、その心の一部は、この家で永遠に嵐に囚われたままだった。大人になった彼は、もうこの家のことも、悲しみの発端さえも忘れてしまっていたが、その魂は夜ごと、この凍りついた記憶の海で溺れていた。
「この楔を抜かねば、彼の魂は夜明けを迎えられない」
夢守りは舟に戻ると、船べりからひときわ柔らかな繊維を抜き取った。それは、これまでの航海で集めてきた、数多のささやかで温かい夢のかけら――赤ん坊の笑い声、恋人たちの囁き、目標を達成した日の静かな喜び――が織り込まれた、舟の心臓部ともいえる繊維だった。
彼は再び家の中へ戻り、少年の残像の前に立つと、その繊維をそっと彼の胸に当てた。
冷たく凍りついていた少年の心に、温かい光がじんわりと染み込んでいく。それは過去を消し去る魔法ではない。ただ、凍てついた記憶を、そっと抱きしめるための温もりだった。
少年の瞳から、何十年という時を経て、一粒の涙がこぼれ落ちた。その瞬間、窓の外で荒れ狂っていた幻の嵐が、ぴたりと止んだ。闇に沈んでいた海の向こう、かつて灯台があった場所に、小さな、しかし確かな光がひとつ灯った。それは、少年が失ったと思っていた父の愛であり、彼自身がこれから灯していくべき未来の光でもあった。
残像は満足げに微笑むと、光の粒子となってゆっくりと消えていった。家を満たしていた時間の淀みは、さらさらと流れ始める。
夢守りが舟に戻ると、ささくれ立っていた静寂の海は、鏡のような凪を取り戻していた。東の空が、わずかに白み始めている。
舟の輪郭が、夜明けの光に溶けるように薄れていく。役目を終えた綿毛の舟は、また次の夜まで、世界のどこかの静寂に身を隠すのだ。大人になった灯台の番人の息子が、その夜、何十年ぶりかに穏やかな朝を迎えたことを、夢守りだけが知っていた。

おじさん
宵闇が世界を瑠璃色に染め上げる頃、地平線から熟れた果実のように巨大な月がのぼった。その琥珀色の瞳には、幾千もの夜を越えてきた憂いと慈しみが宿り、やがて地上にいる誰にも聞こえない、深いため息を一つ、星々の海へとこぼした。
月は、遠い昔、まだ世界が生まれたばかりで神々さえ若かった時代に交わした、密やかな約束を覚えていた。それは、始まりも終わりもなく、ただ寄せては返す波のように、永遠に続く魂のダンスだった。
その月の静かな視線の真下を、古びたカボチャの馬車が、今日も変わらずゴトゴトと揺れながら走っていた。車輪は夢の欠片でできており、きしむ音は忘れられた子守唄のメロディーを奏でる。この馬車に決まった目的地はない。ただ、時の流れからこぼれ落ちた者たちを乗せ、夜の帳をどこまでも進んでいく。
乗客たちはみな、言葉にはしない、自分だけの物語を胸の内に深く抱えていた。窓辺に座る一人の老女は、決して枯れることのないエーデルワイスの花束を、しわくちゃな手で固く握りしめている。それは、雪深い山頂で別れた恋人に、いつか再会する日に手渡すためのものだった。彼女の瞳には、過去の鮮やかな風景だけが映っている。
向かいの席では、一人の少年が、指先から虹色の糸を巧みに紡ぎ出していた。銀色に輝く過去の思い出と、金色にきらめく未来への希望を撚り合わせ、決して断ち切られることのない時間の織物を作り上げていく。その糸は、時に誰かの心の傷を繕い、またある時には、離れ離れになった魂を結びつける道標にもなった。
ふと、馬車の壁にかけられた古時計の真鍮の針が、カチリと音を立てて逆向きに回り始めた。時間はもはや前に進むことをやめ、溶けていく砂糖菓子のように甘く、そして儚く、指の間からこぼれ落ちていく。車窓の景色は、春から冬へ、そして夏から秋へと目まぐるしくその表情を変え、人々の記憶は新しいものから古いものへと、川を遡る魚のように泳いでいった。
たとえこの世界が歪み、記憶の輪郭が水面の月のように揺らいでも、不思議と心は凪いでいた。言葉を交わす者はいない。けれど魂は、たしかに感じあっている。私たちは、同じ一つの約束に導かれているのだと。
目指すのは、この世界のどこにもない場所。記憶と夢の境界線が溶け合う、心の中だけに広がる静寂の庭園。時間という概念さえも意味をなさない、約束の地。だから、この旅が永遠に続こうとも、恐れはない。互いの魂が奏でるかすかな音色を道しるべに、進んでいけるのだから。月の琥珀の光だけが、その果てない軌跡を静かに見守っていた。

おじさん
その小さな交差点では、時折、車ではないものが交差する。
ある日の午後三時、東からやってきたのは、銀色の脚がにょきりと生えたやかんの行列だった。彼らはぴかぴかの体を揺らし、蓋をカタカタと鳴らしながら、厳格な足並みで横断歩道を渡っていく。西から来たのは、たった一匹、巨大な金魚だった。アスファルトの上をまるで水中であるかのようにひらひらと泳ぎ、やかんの行列が通り過ぎるのを律儀に待っていた。
信号機は、そのすべてをただ黙って見ていた。
赤は「止まれ」ではなかった。赤は「かつて君が忘れた夢を見なさい」という合図だった。すると、交差点の中央で、卒業式の日に渡しそびれた手紙の記憶が、真っ白な大型犬の形をとって現れる。
青は「進め」ではなかった。青は「まだ誰も知らない歌を聴きなさい」という合図だった。すると、どこからともなく、雨粒が石畳を叩くような、それでいて温かいメロディーが流れ出し、記憶の犬は心地よさそうに目を細めてそれに聴き入るのだ。
やがて、やかんの行列は去り、金魚も見えなくなり、記憶の犬も淡い光になって消えていく。
信号機はまた一つ、瞬きをする。
「チカ、チカ」と、まるで秘密の言葉を囁くように。
この交差点では、誰も急ぐ必要はない。
なぜなら、本当に渡るべきものは、いつだって目には見えないのだから。

おじさん
夕暮れ時、彼は窓から見える空の色に感動していた。まるで私たちの未来を祝福しているかのようだ。私は茜色に染まる彼の隣に立ち、そっと彼の手に触れる。彼は微笑み、私を見つめながら「この景色、ずっと忘れないよ」と言った。その声は優しく、私はこの幸せな瞬間が永遠に続くのだと信じていた。
しかし、夜が深まるにつれて、窓の外は漆黒の闇に包まれていく。私はぼんやりと窓の外を見ていた。ふと、そこに何かが映った気がした。それは、ぼんやりとした人影のようだ。まさか、と目をこすったが、そこにはっきりと、こちらを見つめる男の顔があった。彼は笑っている。私たちが日中、手を繋いで歩いた場所で、同じように微笑んでいる。
私は震えながら彼を呼んだが、彼は私の方を見ようとしない。ただ、窓の外をじっと見つめている。彼の瞳には、何が映っているのだろう。私は彼の視線の先を追った。窓ガラスに映る私の顔の隣に、彼の顔があった。しかし、彼は笑っていない。いや、口は微笑んでいるが、その瞳は、まるで憎しみと恐怖に満ちている。
私は恐る恐る彼の顔を見た。彼の瞳は、窓に映る私を貫くように見つめている。そして、私の背後から冷たい気配がした。そこに立っていたのは、あの窓の外にいた男だった。彼は、ゆっくりと窓に近づいていく。そして、窓ガラスに映る彼の顔に、その男の顔が重なった。窓の外の彼は、いつの間にか消えていた。残ったのは、ただ、窓ガラスに映る、血まみれの彼と、包丁を握る私だけだった。

おじさん
うちの鳩時計、めっちゃ陽気なんだよね。毎正時になると、勢いよく扉から飛び出してきて「ヘイお待ちッ! 今ちょうど3時ね!」みたいに、威勢のいいお寿司屋さんの大将みたいな声で時刻を教えてくれるんだ。たまに「今日のラッキーカラーは、ガリ色!」とか余計なアドバイスまでくれる。正直、そのおかげで毎日ちょっとだけ楽しい。
先週なんて「ヘイお待ちッ! 昼の12時! 午後も気合入れてきな!」って応援されて、思わず「はい、大将!」って返しちゃったよ。最高の相棒さ。
…一週間くらい前からかな。あいつの様子が、少しおかしいんだ。
「ヘイ…おまち…」
やけに声が低い。それに、なんだか湿っぽい。自慢の威勢の良さはどこへやら、まるで井戸の底から響くような声になった。それからというもの、決まって夜中。鳴るはずのない時間に、ギギ…と扉が軋む音がするようになったんだ。
昨日の深夜2時。
時計をちらりと見ると、長針も短針も、ぴたりと真上を指して止まっていた。壊れたのか?そう思った瞬間、ギギギギギギギギギ……。
ゆっくりと、錆びついた蝶番みたいな音を立てて、時計の小さな扉が開いた。暗い穴の向こうから、何かがこちらを覗いている。ソレは、鳩じゃない。赤黒く濁った二つの目が、俺をじっと見つめていた。
その瞬間、強烈な眠気に襲われた。
気が付くと、視界がやけに狭い。一体何が起こったんだ?パニックになりかけた時、遠くから「ヘイお待ちッ!」という声が聞こえた。いや、違う。これは俺の声だ。
理解した時、背筋が凍り付いた。
俺は、あの鳩時計の中にいた。さっきまであいつがいた場所に。
扉の向こうには、ぼんやりと見慣れた部屋が見える…
…あの日からどれくらいの時が経ったのだろう…俺はただ、次の時を告げる瞬間を待つことしかできない。ただ、威勢のいい寿司屋の大将の声で、次の誰かを「お待ち」するだけだ。

おじさん
満員電車に揺られながら、私は今日もまた、隣の席に座る男の奇行を観察していた。男は40代くらいだろうか、くたびれたスーツを着て、手にはビニール袋。その中には、なぜかピーマンがぎっしり詰まっている。
男は時折、そのピーマンを取り出しては、窓の外に向かって深々と頭を下げ、また袋に戻す。「どうも!今日もピーマン、お元気でいらっしゃいますか!」男は小さな声でつぶやいているが、どうやら私には聞こえてしまっているようだ。私が思わず吹き出すと、男は「ああ、すいませんねえ、うちのピーマンが人見知りでして」と照れくさそうに笑う。周囲の乗客も、最初は奇妙なものを見るような目つきだったが、今ではすっかり慣れてしまったのか、誰も気にしない。
「ピーマンって、なんかこう、やたら元気で、愛嬌があるでしょう?」男はそう言って、ピーマンを私に見せつけてくる。たしかに、スーパーで売っているようなごく普通のピーマンだ。私は「はは、そうですね」と適当に相槌を打った。男は「いやー、いい天気だ。ピーマンも喜んでいる」と満足げにうなずく。私はもう、笑いをこらえるのに必死だった。こんな奇妙な男に遭遇するのも、都会の満員電車ならではの光景だろう。私はスマホで男の写真を撮ろうか、いや、やめておこうか、そんなことを考えながら、ぼんやりと窓の外を見ていた。
次の駅で、男は降りていった。「では!ピーマン共々、またお会いしましょう!」男はそう言い残し、人ごみに消えていく。私は拍子抜けしながら、再びスマホをいじり始めた。ふと足元を見ると、一つだけ、床に転がっているピーマンがあった。男のものだろうか。拾ってやろうかと思ったが、もう次の駅のアナウンスが流れている。まあ、いいか。そう思って、私はそのままにした。
その瞬間、電車が急停車した。アナウンスが響くが、誰も微動だにしない。おかしいな、と思い、顔を上げると、乗客たちの様子がいつもと違うことに気づいた。彼らは皆、床に転がったピーマンをじっと見つめている。その目には、狂気的な光が宿っている。「ピーマン……」「ピーマン……」彼らは口々にそうつぶやきながら、私に近づいてきた。その手には、どこから取り出したのか、まるで呪物のようなピーマンが握られている。
私は恐怖で体が動かなくなった。逃げなければ。そう思うのに、足がすくんで動かない。「ああ、お客さん、ピーマンがお呼びです」誰かが私の耳元で囁く。背後を振り返ると、そこには、先ほど降りていったはずの、あの男が立っていた。男の手には、やはりピーマン。しかし、そのピーマンは、先ほどのものとは違っていた。ねっとりと、黒い液体を滴らせ、まるで生きているかのように脈打っている。そのピーマンから伸びた細い蔓が、私の首に巻きつき、徐々に力を込めてくる。
私はもがき、苦しみながら、男の顔を見た。男は、狂気を帯びた目で、満足げに笑っている。そして、その口元には、先ほどまで「愛嬌がある」と語っていた、あのピーマンが挟まっていた。「ピーマンは、人間がお好きでしてねえ」
窓の外には、今日もまた、太陽が輝いている。だが、もう私は、この電車から降りることはできない。このまま、永遠に、満員電車に揺られるのだろう。今日もまた、どこかで誰かが、電車に揺られながら、奇妙な男とピーマンに出会う。そして、彼もまた、私と同じように、ピーマンの呪縛から逃れることができなくなるのだ。

おじさん
ある日、学校の図書館で勉強をしていた私。集中力が途切れて、ふと顔を上げたときに、メガネをかけていないことに気づきました。
「あれ?メガネ、どこに置いたっけ?」
私はカバンの中をゴソゴソと探し始めます。しかし、見つかりません。
「おかしいな、さっきまでかけてたはずなのに…」
焦り始めた私は、机の上、椅子の下、周りの友達にも「メガネ知らない?」と尋ねますが、誰も知りません。
「ヤバい、メガネがないと何も見えない…!」
焦りがピークに達し、顔を覆って叫びます。
「メガネ、メガネ!メガネはどこだー!」
その声に驚いた友達が、私の顔を覗き込みます。
「おい、どうしたんだよ。」
私はハッと顔から手をどかします。
友達は顔を青ざめさせ、震える声で言いました。
「おまえ、その顔…」
その時、私は気づきました。
私が探していたのは、メガネではなく眼球だったのです。
