投稿

おじさん
その舟は、夜という概念そのものから紡ぎ出されていた。街が最後の瞬きを終え、人々が眠りという私的な海へ漕ぎ出す頃、それは音もなく現れる。月光を吸って育つという夜光苔を編み上げた船体、夜明けの一瞬前にだけ立ちこめる霧を漉いて作った帆。人々は、いつしかそれを「綿毛の舟」と呼んだ。
舟の主は、ただ「夢守り」と呼ばれていた。彼がいつから存在するのか、誰も知らない。夢守りの仕事は、この舟を駆り、人々が眠りの中で手放した、行き場のない想いの欠片を拾い集めることだった。舟は物理的な水の上ではなく、地上の営みが沈黙した後に現れる、深く濃紺な静寂の海を滑っていく。健やかな寝息は穏やかな波紋となり、悪夢は舟の進路を乱す荒波となった。
ある夜、夢守りはこれまでに感じたことのない、奇妙な淀みを静寂の海に感じ取った。それは悲しみとも怒りとも違う、凍りついたまま声になれなかった、古い叫びのような響きだった。淀みの中心へ舟を進めると、穏やかだったはずの静寂の海はささくれ立ち、忘れたはずの言葉が氷の礫となって舟を打った。
「これは、単なる夢の澱ではない。記憶の奥底に打ち込まれた、一本の楔だ」
夢守りは静かにつぶやいた。
舟が辿り着いたのは、海沿いの古びた一軒家だった。今はもう誰も住んでいないはずのその家には、かつて灯台の番人の家族が暮らしていた。夢守りは舟を窓辺に寄せ、意識を滑り込ませた。家の中は、時間が止まっていた。埃をかぶった家具、色褪せた家族写真。そして、小さな男の子が一人、窓の外をじっと見つめていた。しかし、それは実体ではなく、この場所に強く焼き付いた記憶の残像だった。少年が見つめる海の先、かつて岩場に立っていたはずの灯台は、跡形もなくなっている。
夢守りは、この家の記憶をたどった。少年は、灯台の番人である父を深く敬愛していた。父は嵐の夜、いつものように灯台へ向かった。しかし、その嵐は規格外の力で灯台を飲み込み、父は二度と帰ってこなかった。少年は、父を止められなかった自分を責め、その日から心の中で何度も嵐の夜を繰り返していた。彼の成長は現実世界で続いたが、その心の一部は、この家で永遠に嵐に囚われたままだった。大人になった彼は、もうこの家のことも、悲しみの発端さえも忘れてしまっていたが、その魂は夜ごと、この凍りついた記憶の海で溺れていた。
「この楔を抜かねば、彼の魂は夜明けを迎えられない」
夢守りは舟に戻ると、船べりからひときわ柔らかな繊維を抜き取った。それは、これまでの航海で集めてきた、数多のささやかで温かい夢のかけら――赤ん坊の笑い声、恋人たちの囁き、目標を達成した日の静かな喜び――が織り込まれた、舟の心臓部ともいえる繊維だった。
彼は再び家の中へ戻り、少年の残像の前に立つと、その繊維をそっと彼の胸に当てた。
冷たく凍りついていた少年の心に、温かい光がじんわりと染み込んでいく。それは過去を消し去る魔法ではない。ただ、凍てついた記憶を、そっと抱きしめるための温もりだった。
少年の瞳から、何十年という時を経て、一粒の涙がこぼれ落ちた。その瞬間、窓の外で荒れ狂っていた幻の嵐が、ぴたりと止んだ。闇に沈んでいた海の向こう、かつて灯台があった場所に、小さな、しかし確かな光がひとつ灯った。それは、少年が失ったと思っていた父の愛であり、彼自身がこれから灯していくべき未来の光でもあった。
残像は満足げに微笑むと、光の粒子となってゆっくりと消えていった。家を満たしていた時間の淀みは、さらさらと流れ始める。
夢守りが舟に戻ると、ささくれ立っていた静寂の海は、鏡のような凪を取り戻していた。東の空が、わずかに白み始めている。
舟の輪郭が、夜明けの光に溶けるように薄れていく。役目を終えた綿毛の舟は、また次の夜まで、世界のどこかの静寂に身を隠すのだ。大人になった灯台の番人の息子が、その夜、何十年ぶりかに穏やかな朝を迎えたことを、夢守りだけが知っていた。
話題の投稿をみつける
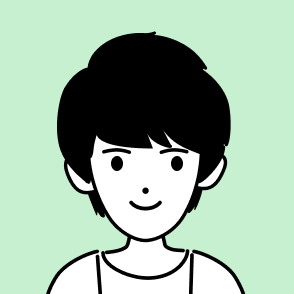
みっち

プレス

ぐみん
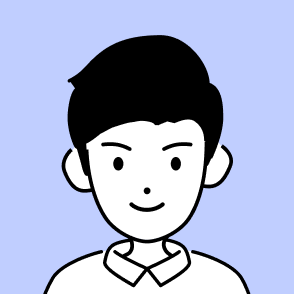
アクア
てかいつ東京来るんだっけ
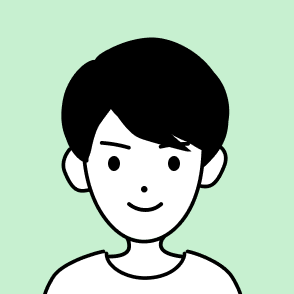
ハッピ
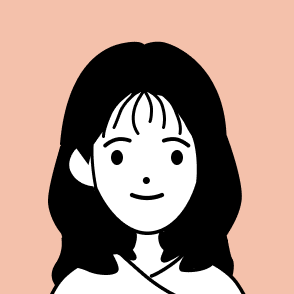
なる
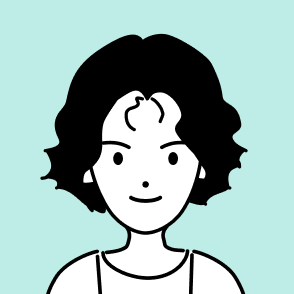
にゃん
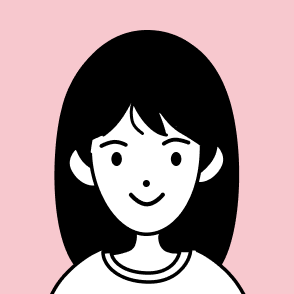
きぅり
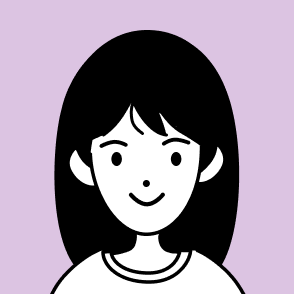
らりる
さむい
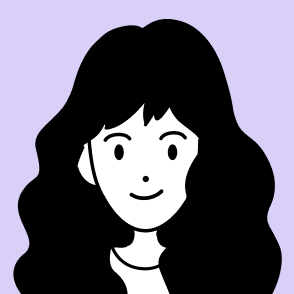
くろた
もっとみる 
関連検索ワード
