投稿

おじさん
静寂に包まれた古い劇場。かつては熱狂に震え、今は客席の軋む音さえ寂しく響くこの場所は、まるで忘れ去られた夢の残骸のようだった。そこに立つのは、伝説の手品師、マダム・ルブラン。彼女のショーはいつも観客を現実と幻想の狭間へと誘う。だが今夜、彼女の瞳に映るのは、客席の奥で満たされることのないまま、静かに蠢く劇場の「渇き」だった。
幕が上がり、ステージ中央にスポットライトが落ちる。真紅のドレスを纏ったマダム・ルブランは、深くお辞儀をした。その仕草一つで、劇場の空気がかすかに震える。最前列に座る紳士淑女たちは、マダム・ルブランの冷たい輝きに、期待と一抹の不安を抱いた。
「皆様、今宵は『劇場に捧げる夢』のイリュージョンにご招待いたします」
ざわめきが起こった瞬間、劇場の古い壁が、まるで大きく息を吸ったように感じられた。彼女は優雅に手を広げ、指を鳴らす。途端に、観客席の最後列に座っていた一人の老婦人が、まるで時間を巻き戻すように瞬く間に若返り、そしてその存在を劇場に刻み込むようにふわりと消え去った。老婦人の座っていた席からは、彼女がかつてこの劇場で体験した、初恋の輝かしい情景が、一瞬の残像となって浮かび上がる。
驚きと恐怖が入り混じった声が上がり、携帯電話を構えていた観客の画面がノイズを走らせてフリーズした。だが、マダム・ルブランは涼しい顔で微笑み、再び指を鳴らす。今度は、中央列の若いカップルが、互いの手を握りしめながら、その場で出会った頃の純粋な喜びを共有し、光の粒子のように劇場に溶けていく。彼らの座っていた場所には、二人が初めて手を取り合った瞬間の、熱い感情の残響が漂った。
次の瞬間、観客たちは次々と、それぞれの席に座ったまま、光の粒子となって消え去っていく。劇場の古い椅子は、もはや座る人の体温ではなく、彼らがかつてこの場所で感じた幸福な感情の光で満たされていく。残されたのは、舞台上のマダム・ルブランと、最前列に座る数人の観客だけだった。彼らは震えながら次の瞬間を待つ。だが、その震えの中には、奇妙な「安堵」や「誘惑」が混じり合っていた。
マダム・ルブランはゆっくりと最前列に近づいてきた。その目は、まるで深い宇宙のよう。彼女は、残された観客の一人の男性の目の前で、再び指を鳴らした。
男性は、自分が消えゆく感覚に襲われた。恐怖は一瞬で消え失せ、彼の脳裏に、人生で最も輝いていた思い出の数々が、怒涛のように押し寄せる。初めて観劇した時の興奮、妻との出会い、そして愛する人と笑い合った日々。それは、まるで人生最高のハイライトを、肌で感じながら追体験するような、至福の感覚だった。完全に消え去るその寸前、彼は見た。マダム・ルブランの口元が、わずかに吊り上がっているのを。そして、彼女の瞳の奥で、消えたはずの観客たちが星のようにきらめいているのではなく、「彼らがかつて経験した無数の幸福な感情の光」が、永遠に輝き続けているのを。
劇場は完全に静寂に包まれた。ステージにはマダム・ルブランが一人。
彼女は、誰もいない客席に向かい、ゆっくりと、そして深くお辞儀をした。
「皆様、素晴らしい拍手をありがとうございます。今宵、この劇場は満たされました」
その言葉に呼応するかのように、満たされた客席から、無数の歓声が湧き上がった。それは、この劇場が長年飢え続けていた、観客たちの「夢の残像」によって満たされた、確かな喜びの音だった。そしてその歓声は、やがて嵐のような大拍手へと変わっていく。
マダム・ルブランは、その音に耳を傾けながら、初めて満ち足りた微笑みを浮かべた。彼女は観客たちを消し去ったのではない。彼らがこの劇場で生きた「夢」の輝きを、永遠の命として捧げたのだ。スポットライトが彼女の姿を照らし続ける中、その大拍手は、まるで劇場そのものの鼓動のように、夜空に響き渡るのだった。
話題の投稿をみつける

みー💛
#ドラマDOPE
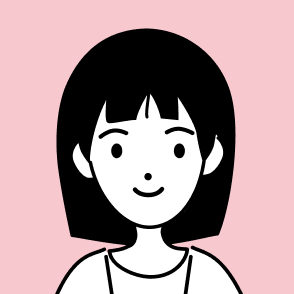
べびも

みゅう@

み~ち
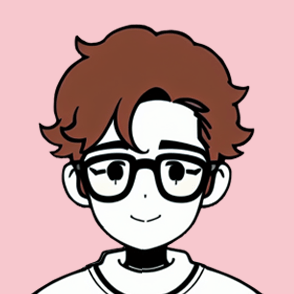
なっぽ
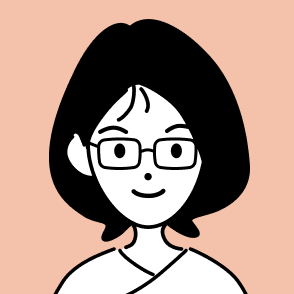
ボロ教
七月六日はいいね記念日
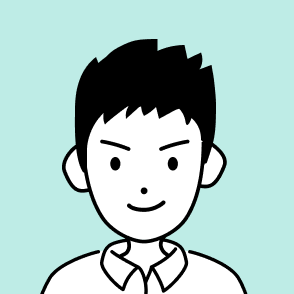
あろん
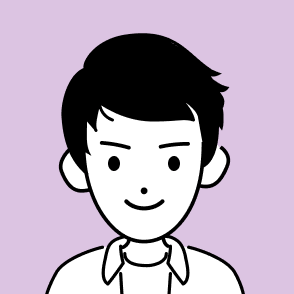
桜エビ

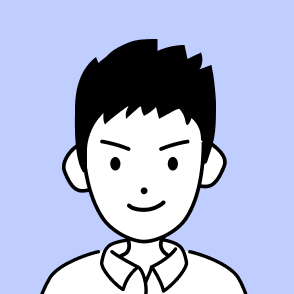
羊肉麻
連絡先知らなかったw
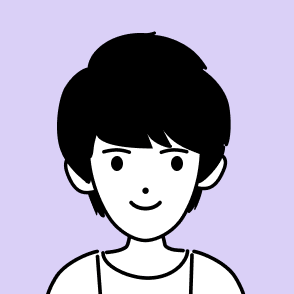
ちぇん
ふうちゃんの歌声めっちゃ好きっっ
もっとみる 
関連検索ワード
