投稿

おじさん
宵闇が世界を瑠璃色に染め上げる頃、地平線から熟れた果実のように巨大な月がのぼった。その琥珀色の瞳には、幾千もの夜を越えてきた憂いと慈しみが宿り、やがて地上にいる誰にも聞こえない、深いため息を一つ、星々の海へとこぼした。
月は、遠い昔、まだ世界が生まれたばかりで神々さえ若かった時代に交わした、密やかな約束を覚えていた。それは、始まりも終わりもなく、ただ寄せては返す波のように、永遠に続く魂のダンスだった。
その月の静かな視線の真下を、古びたカボチャの馬車が、今日も変わらずゴトゴトと揺れながら走っていた。車輪は夢の欠片でできており、きしむ音は忘れられた子守唄のメロディーを奏でる。この馬車に決まった目的地はない。ただ、時の流れからこぼれ落ちた者たちを乗せ、夜の帳をどこまでも進んでいく。
乗客たちはみな、言葉にはしない、自分だけの物語を胸の内に深く抱えていた。窓辺に座る一人の老女は、決して枯れることのないエーデルワイスの花束を、しわくちゃな手で固く握りしめている。それは、雪深い山頂で別れた恋人に、いつか再会する日に手渡すためのものだった。彼女の瞳には、過去の鮮やかな風景だけが映っている。
向かいの席では、一人の少年が、指先から虹色の糸を巧みに紡ぎ出していた。銀色に輝く過去の思い出と、金色にきらめく未来への希望を撚り合わせ、決して断ち切られることのない時間の織物を作り上げていく。その糸は、時に誰かの心の傷を繕い、またある時には、離れ離れになった魂を結びつける道標にもなった。
ふと、馬車の壁にかけられた古時計の真鍮の針が、カチリと音を立てて逆向きに回り始めた。時間はもはや前に進むことをやめ、溶けていく砂糖菓子のように甘く、そして儚く、指の間からこぼれ落ちていく。車窓の景色は、春から冬へ、そして夏から秋へと目まぐるしくその表情を変え、人々の記憶は新しいものから古いものへと、川を遡る魚のように泳いでいった。
たとえこの世界が歪み、記憶の輪郭が水面の月のように揺らいでも、不思議と心は凪いでいた。言葉を交わす者はいない。けれど魂は、たしかに感じあっている。私たちは、同じ一つの約束に導かれているのだと。
目指すのは、この世界のどこにもない場所。記憶と夢の境界線が溶け合う、心の中だけに広がる静寂の庭園。時間という概念さえも意味をなさない、約束の地。だから、この旅が永遠に続こうとも、恐れはない。互いの魂が奏でるかすかな音色を道しるべに、進んでいけるのだから。月の琥珀の光だけが、その果てない軌跡を静かに見守っていた。
話題の投稿をみつける
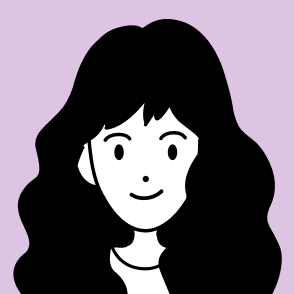
らむち
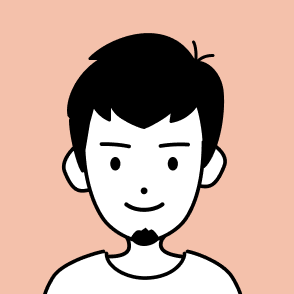
ポリぶ

きりさ

みみみ

たこう
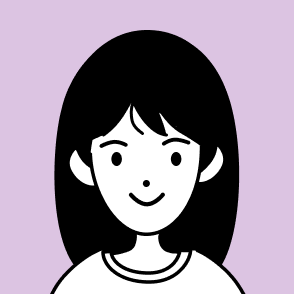
いい人

おやす
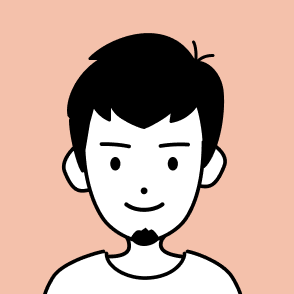
はしび
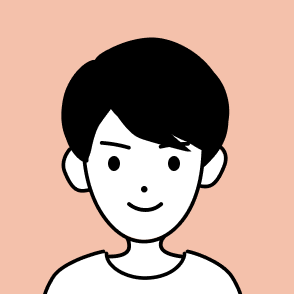
かがみ
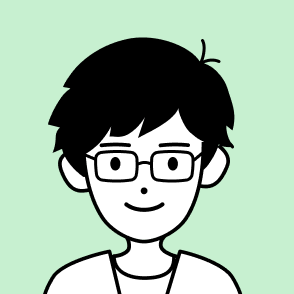
砂場 #
もっとみる 
関連検索ワード
