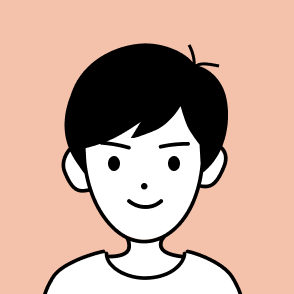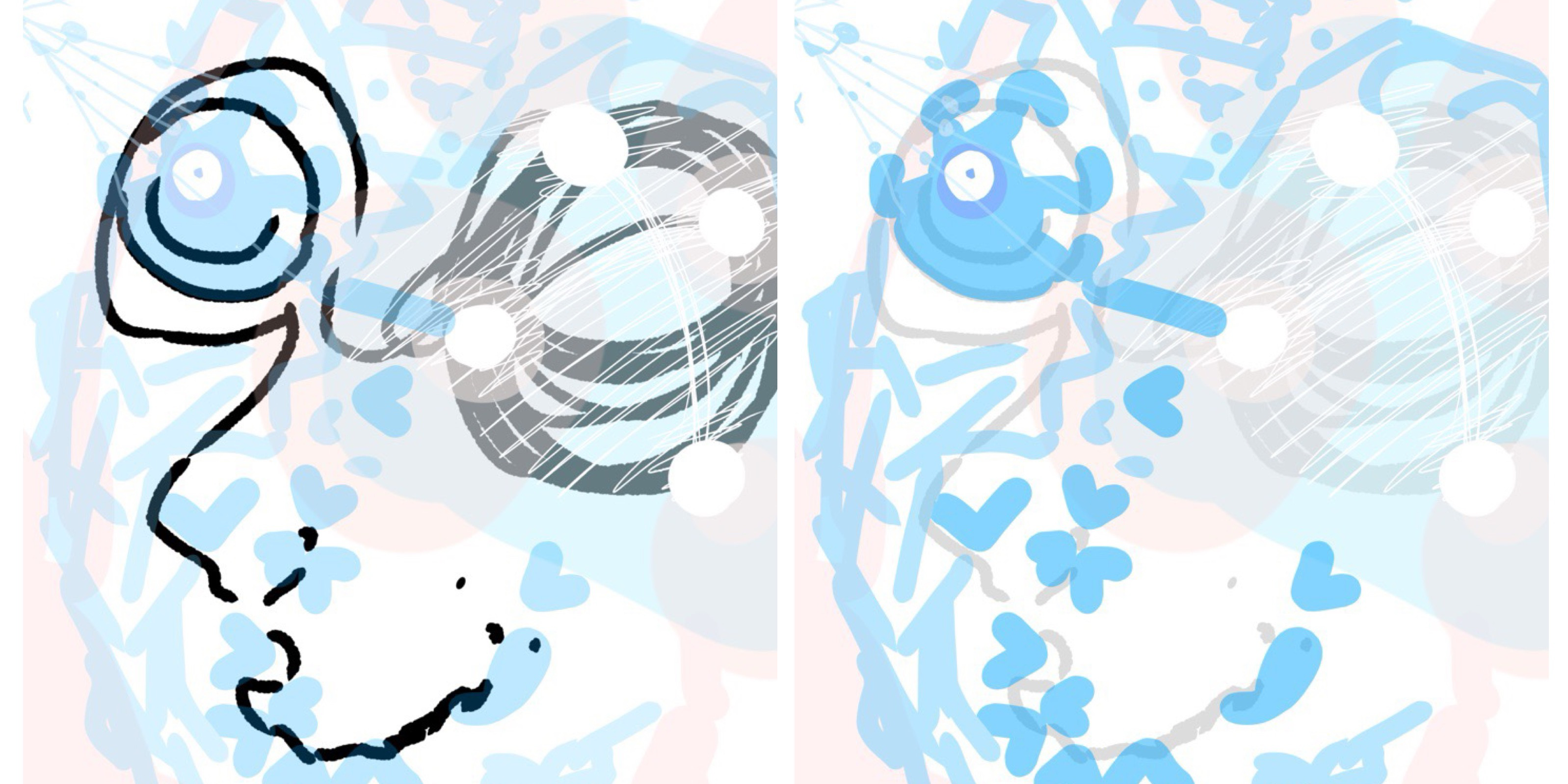

背景画像は @necco(ねこころん さんに提供いただきました😊
認知科学は、人間の「考える」「理解する」といった知的な働きを研究する学問です。心理学が人の行動や感情を扱うのに対し、認知科学は記憶や注意、言語理解など心の情報処理を探ります。認知心理学はその一部で、具体的な認知プロセスを研究します。さらに、脳波を使って脳の活動を測定し、思考やコミュニケーションの仕組みを解明することも行います。心理学、認知心理学、脳波などを組み合わせて、人間の知的活動を総合的に理解するのが認知科学です🧠
興味がある方は星に搭乗してくれると嬉しいです✨✨
#心理学
#認知心理学
#認知科学
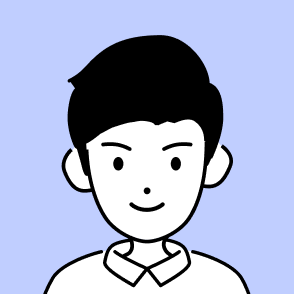
たむい
日本やアメリカの人は「〇〇するな」「最悪な人間」などネガティヴワードを聞くことが多い
ガーナやインドの農村部の人は「正しく生きよ」「良い日が来る」などのポジティブワードが混じっている
幻聴、つまり自分の内なる声は
文化に左右される
その文化が正しいと思い込むのは
もうやめたらいいのになと
声を大にして伝えたい
※1 無(最高の状態) 鈴木佑より
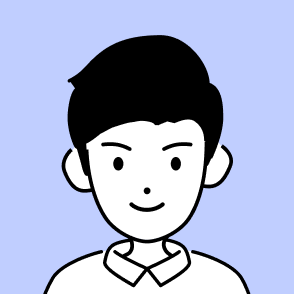
たむい
練習不要で器用に動かせると思いませんか?
身体拡張がそろそろ一般的になってほしい
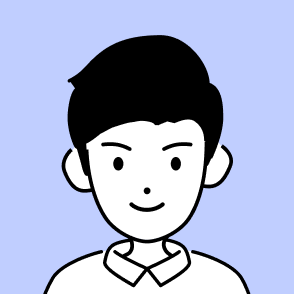
たむい
距離(長さ)、温度、音圧などがあります
これらの大きさは線形的に変化します
距離が2倍であれば、1kmは2kmとなります
これに対し、人の感覚は対数的となります
音の大きさをあらわすdB(デシベル)を例にすると、以下となります
音圧が10倍→+10db
音圧が100倍→+20db
音圧が1000倍→+30db
音圧を1000倍から1010倍にしても
人は違いをほぼ感じられないことになります
こうした単位違いを認識することで、
より人の認知を深掘りできると思います
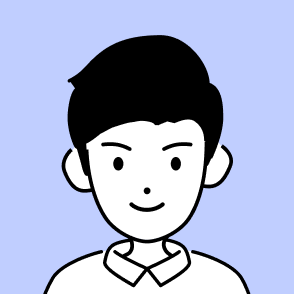
たむい
ナミビアのヒンバ族はこの画像を見た時、四角には気付かず、丸が並んでいると認識するようです。
自然には直線はないため、丸を認識しやすいようです。
ちなみに丸は横に並んだ四角と四角の間にあります。
縦線に注目すると丸を見つけやすいかも。
出典:Visual illusions reveal wide range of cross-cultural differences in visual perception
https://doi.org/10.31234/osf.io/gxzcp_v3

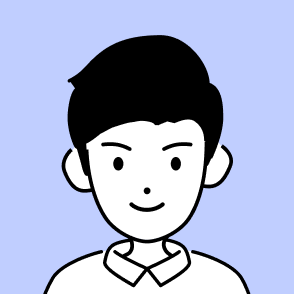
たむい
「悲しいから泣く」のではなく
「泣くから悲しい」だと感じているため
AIは感情を獲得できないと考えています
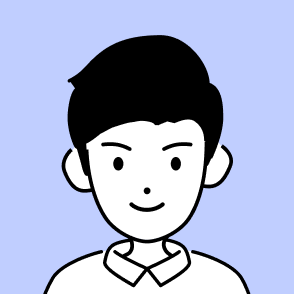
たむい
私は効率的に問題を解く方が学力向上にはいいと考えていたが、そうではないようだ。
知能向上にはまわり道が大切なんだなと自分の中では結論づけた。
子供の教育指針の参考にしよう。
子供の間はAIには頼らせず、自分で考えてもらおう。
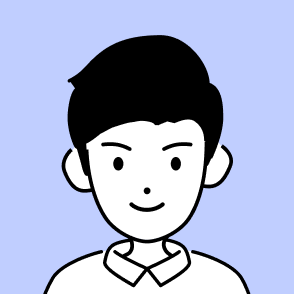
たむい
植物の葉っぱは緑色に見えます
これは光合成を行う葉緑体が緑だからです
さらに踏み込んで考えましょう
人の目は赤緑青の3色の色を感知します
葉っぱが緑に見えるのは、葉っぱから緑の光が反射しているためです
つまり、葉緑体は緑の光を吸収せずに反射していることとなります
赤や青の色を使って光合成をしていることになります
直感と逆だと思いませんでしたか
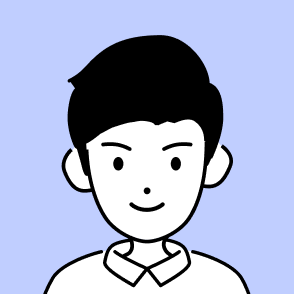
たむい
分かりやすいのが、「ん」で始まる和語はないことだ
しりとりはそのルールにより生まれた遊びである
他に知られているルールとして、ぱ行で始まる和語もほぼ存在しないというものがある
ほぼとしているのは、ある地域や一族だけでは利用している可能性は否定できず、ないことの証明はできないためである
パイナップルなどの外来語、ぱちぱちなどの擬音語は和語ではない
ぱ行の和語がない理由は別の投稿とし、ここでは割愛する
今回は日本語のルールについて、日常的に意識していないものがあるということを知ってもらう内容でした
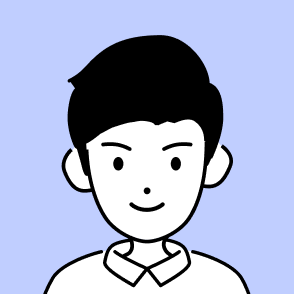
たむい
私が今までやっていたのは膝を曲げるだった。
重心の安定感が違う
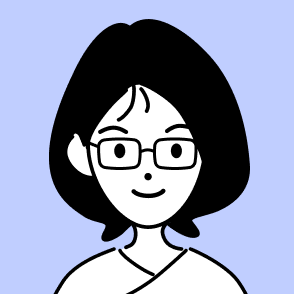
N
回答数 3>>
もっとみる 
惑星のイベントをチェックしてみよう!
終了
あなたがオススメの認知心理学の本を紹介する
参加
惑星の質問をチェックしてみよう!
干すと乾かすの違いは?
3人回答>>
2025/07/26 12:08
関連する惑星をみつける
AI研究者の星
446人が搭乗中
参加
最先端のAI研究開発などに興味のある方!
面白い研究論文やAIの最新情報を共有できる星です!
是非誰でも参加できるので、よかったら次世代の領域を切り開いていきましょう♪
哲学
7535人が搭乗中
参加
哲学-深く、より深く
日本史の星
336人が搭乗中
参加
日本史が好きな方、語りたい方どんな方でもぜひぜひ気軽に来てくださいね☺️📕✨
みんなで日本史楽しもう!!
※主は伊達政宗ガチ恋勢です。
引き継がせて頂きました!
※私は新撰組ガチ恋勢です
数学の星
1243人が搭乗中
参加
数学の星では、文系な人も、理系な人も、数学得意苦手関わらず気軽に使ってくださいね✨️
荒らしは暴言など、迷 惑発言は厳禁
MBTIの星
2619人が搭乗中
参加
⚠️【注意事項】⚠️
・16personalitiesはエンタメであり、正式なmbtiではありません。全くの別物とご理解ください。
・mbtiタイプに格差はございません。全てに同等の価値があります。
・mbtiは適性や能力を測るものではございません。
・まずはご自身の理解のためにmbtiタイプを使いましょう。
・mbtiを言い訳に利用したり、攻撃の材料にすることもおやめ下さい。
以上のことを守れる方のみ歓迎いたします。
また、以上の注意事項は日本mbti協会からの公式声明です。
守れなかった場合は惑星内の違反に該当する投稿の削除、よほどの事がない限りではありますが度重なる場合は追放ですのでよろしくお願いいたします。
もっとみる 

 めおかれん復活
めおかれん復活