人気
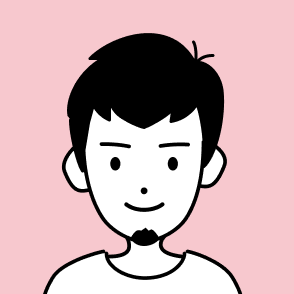
センザ
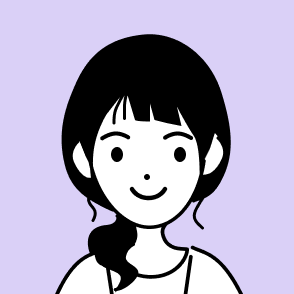
うみさ
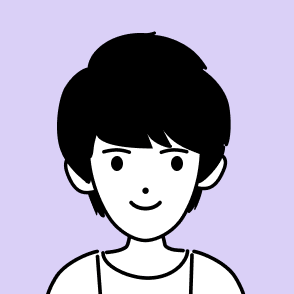
さく走
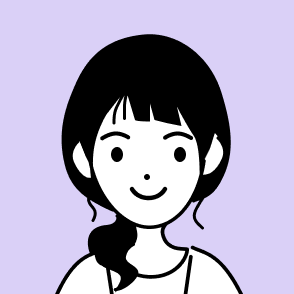
うみさ
テフヌト出ました!やったー
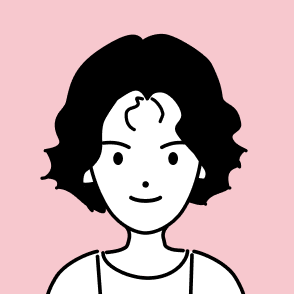
ミチタ
まあまあアリよりですな!
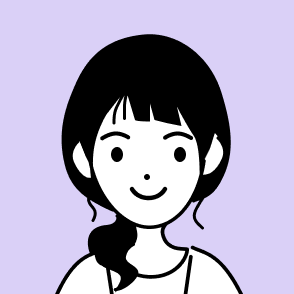
うみさ

靈龜
ジークフリート、不良ノーデンス、プルートー、テフヌトが映ってる


社畜お
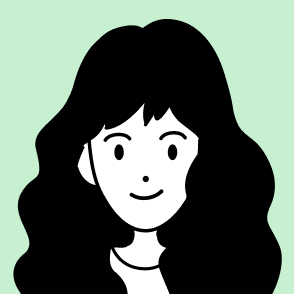
なな
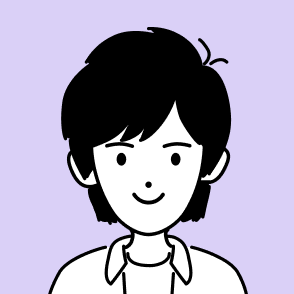
ヴィク
もっとみる 
関連検索ワード
新着

天月 兎
第三十三話 前編
最初は、壁を登って越えればいいと思っていた。
でも、乗り越えるにはあまりにも高すぎた。
空の遥か彼方まで伸びた壁は、城砦のそれよりもずっと堅固で、ずっと高かった。
だからその壁につけられるにはあまりにも小さすぎる門を通り抜けるしかなかった。
人一人が通れる程度の門だ。
けれど誰一人その門を通り抜けることは出来なかった。
その拳は全てを斬り伏せる剣であったから。
その拳は遍くを砕き伏せる槌であったから。
その拳は悉くを貫き伏せる槍であったから。
傍に転がる、自分達を殺すためだけに作られた鉄球なんて安物の包丁だ。
誰かが言った。
「あそこに行っても死ぬだけだ。迂回しよう」
けれどそんなこと、出来るわけが無かった。
あの壁は既に自分達を包囲していたから。
結局、鬼門に挑むしか道は無かった。
飛びかかる魔性の群れに拳が突き出されれば、巻き起こった風は衝撃波という刃となって他者を巻き込み、殺戮の限りを尽くしていった。
「くそ!後方援護はどうなってる!奴の動きを止めさせろ!」
群れをまとめていた者がそう言うと、側近が恐る恐る口を開く。
「あの壁が現れた際、巻き込まれて……」
全滅した、と。
ルーヴェリア達と別れ、王都から馬を飛ば…すより走った方が早かったので、クレストは文字通り走って戦線を見渡せる位置に到着した。
ヘルベ湖、ア・ヤ湖の合間を抜け、いまやもぬけの殻と化したカルシャ村から索敵魔術を行使する。
敵の進軍は発見された位置よりあまり動いていないように思えた。
陽動のための軍、そして平坦になったテフヌト族領を徒歩で進軍すると考えれば機動力はそこまで重視されなかったのだろう。
陣形は円、中心に少しばかり大きな魔力反応があることから、あれらを指揮している者は中心にいる。
だが進軍方向は前方であるが故、接敵した際を案じてか後方に支援魔術に優れた植魔と吸血鬼達を置いたらしい。
欠けてはいるが、まだ使い物になる程度の短剣を戦力として見ているあたり、魔王はそれなりに慈悲深いのかもしれない。
さて、敵の陣形等が分かれば後はやる事をやるだけだ。
クレスト「マルス団長のお力、少しばかりお借りしますぞ」
にっと笑った老騎士は、持ちうる魔力を大きく消耗させながら、敵から身を守るためではなく、敵を殺すための砦を文字通り顕現させた。
クレスト「空間把握、指定」
敵陣の後方を潰しながら、包囲できる位置に。
クレスト「存在固定、城砦概念付与」
敵がゲートを開いて逃げることも出来ないように、その存在を人間界に固定する。
そして大地に、堅牢な砦の意味を持たせた。
果てしなく高い壁、抜け出す余地など持たせない石造りの地下牢、生きながらえさせるのではなく、飼い殺すための牢獄。
出口は、自分が立つこの場所だけにして。
クレスト「建立せよ!否生の砦」
魔族らのいるヤ・クルヌ村付近の地面が大きく揺れた。
ただの地震だと思っていたが、すぐ真横に雷が落ちたのではないかと錯覚するような音が轟いたと思えば、地面が盛り上がり、高く聳える崖のように自分達を囲い込んでいた。
10万の軍勢を、囲い込んでいたのだ。
困惑した矢先、出口らしきところに人間が一人だけ立っていることに気が付いた。
その人間は肩に担いでいた鉄球を地面に転がして仁王立ちしている。
クレスト「人の言葉が通じるのならば、貴様ら魔族に教示しよう。私を倒すことだけが、この場所から抜け出す唯一の道だ」
相手はたった一人。
恐れるものなんて何もない。
1匹の魔獣が飛び出してその首に噛みつこうとした瞬間。
その魔獣は頭部から全身が弾けた。
弾けた後に、パン!という乾いた音が聞こえてくる。
自分達なら飛んで抜け出せるだろうと考えた吸血鬼が空を目指すが、どこまで飛んでも壁は目の前から途切れることはなく。
囲われているために迂回するという道も塞がれ、何故かゲートも開けない。
動揺した魔族の群れがとった行動は、一斉突撃だった。
拳が剣撃となって同胞を八つに斬り裂く。
拳が鉄槌となって仲間を千々に粉砕する。
拳が真槍となって味方を無数に刺し貫く。
たかが人間一人の繰り出す拳に、10万が圧倒されていった。
その数を半分以下に減らすことに、何分かかっただろう。
人間が到達するべきではない境地にまで磨き上げられた一撃は、ただ一度繰り出されるだけで数百、数千を虐殺した。
そうして一度退却できるところまで退却し、後方部隊は既に全滅していることを聞かされたのだ。
どうしろというのか。
武に人生を捧げて人間を辞めた悪魔のような輩相手に、自分達はなす術もなく殺される他に道はないのか。
焦燥感と屈辱に身を震わせる将に、聴き慣れた声が響いた。
それは魔界に住む者なら誰もが頭を垂れ、地に伏し、姿を見ることすら許されないような高みに座す方の声だ。
『諦念は死後に噛み締めよ。彼奴は魔力で身体能力を上げているだけに過ぎない。お前達はゲートを通れぬが、送る方は別であろう。彼奴の魔力が尽きるまで、百千萬の兵を送り続けよう。恨み言は冥土に辿り着いた彼奴の魂にでも吐いてやれ』
ああ、我が王よ。
そのお力を我らの勝利の為に振るわれるのか。
あの悪魔が倒れれば、我らが死せどもそれは勝利となるのですね。
なんと非情かつ合理的で、しかし存分に奮い立たされる言葉なのだろう。
今やこの身は焦燥感や屈辱などという小さなものに震えてなどいない。
目の前にある死という運命に武者震いしているのだ。
否、狂ってしまっただけなのかもしれないが。
そうして正気を失ったように、魔族の群れはクレストへと襲いかかった。
上空にゲートが開き、無数の魔物達が牢獄へと放り込まれる。
表すならば波。幾重にも連なり呑み込まんとする荒波のようだと人は言うだろう。
しかしクレストからしてみれば、雑魚が鯨の口に自ら飛び込むようなものでしかなかった。
群れを率いていたものでさえ、少しばかり珍しい餌に過ぎないような存在。
荒波を拳一つで堰き止めてしまった。
どれだけ高い波であろうと、どれだけ強い衝撃であろうと、その拳は全てを屍へと変貌させ、死を撒き散らして山へと変えてしまう。
イレディア「あの小童が、ここまで強くなろうとはな」
目的を果たした魔王が鏡を通してその光景を見、感嘆の言葉を漏らす。
対して横に立つ魔女は不愉快極まりなさそうな顔をしていた。
サーシャ「目的は終えたのだから、これ以上仲間を殺す必要はないんじゃないの」
鋭い声に動じることもなく、魔王は首を横に振る。
イレディア「いや、あれが死ぬまで送り続けるさ」
サーシャ「馬鹿じゃないの?死体が増えるだけでしょ。もうノクスだって死んでるのに、意味ないじゃない。なんなら私が出て殺しに行ってもいいのよ」
間髪入れず、すぐにでも殺しに行きそうな魔女を魔王は制止した。
イレディア「それでは意味がない、サーシャ。魔術は封じろ。手出しはするな」
硬い沈黙が両者に流れる間にも、魔族の血は絶えず流れ続けている。
もはや山となった死体が流れを相殺して勢いすら殺されていた。
クレストの体は敵が視界から消え去るまで延々と繰り出され続ける。
決して折れない剣、その破壊力は言うまでもない。
さて、送り出した仲間の数はいくつだったか。
とうに百万は超えているはずだが、老騎士に疲れは見えない。
時が夕刻を過ぎても、緩むことはなかった。
イレディアは一度ゲートを閉じる。
サーシャ「………どうするの、あの死体の山の後始末」
イレディア「…………とりあえず後で燃やしてやろう。あの砦は一度入れば死んでも魔界には戻れない場所だからな」
魔女の嘆息を最後に、会話は途切れた。
魔族がこれ以上出現せず、ゲートが閉じられたのを確認したクレストは、ふうと息を吐いた。
とん、という着地音を背後で聞いて振り返ると、鎧も服も破れて腹部が丸見えのルーヴェリアが立っていた。
クレスト「…師よ、私はどこに目をやれば良いのですかな?」
ルーヴェリア「こちらの台詞ですクレスト…その屍は10万どころの騒ぎではないように思えますが…」
クレストはとりあえず自分の持っていたマントを裂いてルーヴェリアの腹部に巻きながら答えた。
クレスト「マルス団長の城砦顕現を使わせていただいたところ、盗み見していた輩がゲートを開きましてな。数で押せば倒せると思ったようです。数十倍は破裂しましたかな」
流石の怪物と呼ばれたルーヴェリアも、これは青ざめものである。
ルーヴェリア「…拳で?」
クレスト「拳で」
末恐ろしい。怒らせないようにしよう。
心の中でうんうんと頷きつつ、ルーヴェリアも戦果を報告する。
ルーヴェリア「こちらはノクスとレイヴを、後、恐らく彼方側の切り札と呼べるような魔物……確か、ロストとか呼ばれていましたね。それらを討ち取ってきました」
クレスト「流石ですな」
マントを巻き終えたクレストは誇らしげに微笑んでいる。
こうしていると、昔を思い出す。
いつの日だったかはルーヴェリアの片腕が飛んでいたのをなんとか鎧で隠したり、潰れた目が周囲の人間の目に触れぬよう包帯を巻いてやったりと苦労したものだ。
下半身が丸々吹き飛んでいた時はどう誤魔化そうか頭を悩ませ、結果的に食糧を運ぶための籠に押し込めたこともあったか。
クレスト「…懐かしいですな」
ぽつりと呟くクレストに首を傾げながらもサフラニアの方面を見る。
じき夜になるが、何の伝令も飛んでこないということは、アドニスの戦線も好調なのだろう。
特に急ぐことはないと判断したクレストが、場に似つかわしくない言葉を吐いた。
クレスト「食事は摂られましたかな?」
ルーヴェリア「あ、そういえばまだでした」
砦の中で火を焚こうとし、しかし辺りは血塗れ。
乾いたものなんて見当たらず火種になるものがない。
どうしたものかと周囲を見渡していた時、ルーヴェリアのいた方から嫌な音が聞こえた。
こう、ガリガリと何かを噛むような……そう、咀嚼音だ。
クレスト「師い!?」
青ざめるクレストが見たのは、その辺に転がった何かの魔族の破片に齧り付くルーヴェリアだった。
ルーヴェリア「…この肉塊、恐らく元は吸血鬼ですね。血の味が濃い。こっちは割と筋肉質で……魔獣、ですかね?」
うむ、そのような方法で元が何の魔物だったかを当てないでいただきたい。
粉々になった魔物の肉塊で神経衰弱をしないでくだされ。
ではなく。
クレスト「せめて火を通してくだされっ!」
そも食用の魔族は出回らなくなって久しいうえ、その体に毒を宿している魔族だって存在するのだ。
不用心に口にして良いわけがない。
ルーヴェリア「確かに、火を通せばクレストも食べられますね」
あ、なんか嫌な予感がする。
クレストはすぐさま防御体制をとった。
刹那、砦内で見事な爆発音を起こしながらルーヴェリアの火炎魔術が"暴走"した。
クレスト「…元から荒野であるのに、更に焼け野原にして如何なさるおつもりで…」
やはり調理は苦手だ。
ほとんどの肉が炭になってしまった。
クレストが心労と頭痛で暫し俯いていることなど意にも介さず、ルーヴェリアはとりあえず炭を払えば食べられそうな肉片を見つけてクレストに差し出した。
ルーヴェリア「感触的に熊型の魔獣の肉です。火は間違いなく通っているので安心して食べられますよ」
そうではないのです師よ…加減というものを覚えてくだされ……何年生きていらっしゃるのか……。
クレスト「ははは…有り難く頂きましょう…」
ああ、ディゼン団長。
せめて貴方が我が師にお茶を淹れる程度の魔力に抑えられるよう鍛えてくだされば、今も残っていた自然が多かったでしょう…。
更に言えば、騎士団の厨房が爆発したり団長専用の個室が吹き飛んだりして国庫に大打撃を与え、当時の宰相が胃薬を毎日倍量飲むことも無かったでしょうな…。
苦くもあり、温かくもあり、そんな空気は魔術を通じて送り届けられた伝令の声に破られた。

天月 兎
第二十九話
玉座の間に集ったアドニス、ルーヴェリア、クレストの3名は度肝を抜かれるような報告を聞くこととなる。
帝国軍国境、旧メレンデス小国、ヴィト・リーシェ湖、エレゾルテ山脈、旧ヤ・クルヌ村、旧ラシェクス小国、それぞれにゲートの出現が確認された。
現れた魔族は各地域に分けても10万は居るという。
アドニス「包囲…されてる…」
そう。サフラニアから見ると八方向をきっちり囲い込めるよう布陣されているのだ。
国王「対するこちらの戦力は、各騎士団総員でも4万に満たない。1箇所を突破するにも数の差が大きすぎるのだ…そして奴らはこちらに向けて同時侵攻を開始している…」
国の終わりが見える。
周囲の人間誰もが絶望の表情を浮かべていた。
ただ、2人を除いては。
ルーヴェリア「策は立てられますね」
クレスト「ええ、問題ございません」
重苦しい空気を裂くように、ルーヴェリアが中空に地図を映し出した。
そして、クレストが作戦を説明する。
まず、6箇所のうち少人数でも守備が容易なのは帝国領国境、旧ラシェクス、旧ヤ・クルヌ村の3箇所です。
山脈や湖に進軍が阻まれる為、地形を利用すれば罠を仕掛けるだけで足止め程度は可能でしょう。
逆に、こちらの守備が手薄となるのは南方のケレテス山脈、ヴィト・リーシェ湖から傾れ込む敵軍です。
よって……。
クレスト「我々騎士団長を除いた全軍をこちらの守衛に回します」
国王「なっ…20万を相手に4万で太刀打ちしろと!?」
自殺行為だと驚愕を隠さない国王に、毅然とした態度で首を縦に振るクレスト。
そこで、ルーヴェリアが口を開いた。
ルーヴェリア「七将は残り2人です。吸血鬼等を従える祖翼レイヴと、死霊術を操る亜祖ノクス。翼を持つ魔族はその特性を生かして山越えや湖越えを狙うでしょう。そして私が各所に配置しておいた魔力感応の魔道具からして、指揮官クラスの魔族はこの2人だけです。頭のない魔族など、ただ前に進むことしか考えられない烏合の衆……その程度では私の鍛えた騎士団員の敵にはなり得ません」
王妃はふむ、と考えた。
その話からすれば、逆に敵指揮官が居るのは4万の騎士を置く位置になる筈だ。
電撃戦を目論むなら尚のこと。
王妃「その機動力があるからこそ、その方面から敵が来るのでは?」
ルーヴェリア「そう考えさせることこそ、奴らの目論見です」
王妃「では、指揮官らは他の箇所から来る…と?」
クレストが地図の北方を指差した。
曰く、魔族が居る南部は何もせずとも機動力で押し切れるが、ネポス山、ケレテス山脈を超えるにはそれを更に凌駕する機動力がなければ完全な包囲は出来ない。
故に、レイヴが現れているのは帝国領国境か旧ラシェクス。
そして数を理にしたいならば、ノクスの力を存分に発揮できるのも死者が多かった旧メレンデスだろう。
つまり北方付近に大きな戦力が集中している、と。
ルーヴェリア「なのであえて南方の守備を堅くしていると見せかけ、北方に集中する敵を逆に誘き寄せるのです」
国王「しかし…全軍を南方に集中させれば動けるのは…」
クレスト「ええ、我々騎士団長のみとなります」
周囲がざわめき出す。
まさか、たった3人で南方の守備が突破される前に北方に電撃戦を仕掛けて敵の頭を潰しにかかり、そのまま敵の背後を突く形で南方の援軍に回るのか。
ルーヴェリア「いいえ」
ざわめく声に首を横に振る。
ルーヴェリア「クレストは守備に特化した騎士ですから、東方から押し寄せる軍勢から守備。国の未来を考え、アドニス殿下には守備の堅い4万の騎士団の総司令官として南方で後方支援をしていただきます」
アドニス「無茶苦茶だ!師匠1人で北方の七将2人と30万の敵を潰して西方に周り、我々の援軍に回ると!?正気じゃない!」
あまりの自己犠牲精神と無茶の過ぎる作戦に、今まで黙って話を聞いていたアドニスがたまらず声をあげた。
アドニス「それにクレストだって…1人で、10万の敵を……もう私兵だって居ないのに…!」
その場に集った誰もが彼と同意見だ。
クレスト「皆さんは、ご存知ありませんからそういった考えに至るのは仕方のないことです」
何故か誇らしげに笑んでいる空気の読めない老騎士。
とうとう年齢のせいで頭がおかしくなったのかとすら思ったが、彼の口からとんでもない話が飛び出た。
クレスト「今から50年前。魔族から停戦交渉を受けた原因となったのは我が師です。あの時、我々騎士団も各国も兵力を消耗し、今のように終わりが見えた時がありました。各国にゲートが開き、各所に七将が出現したのです。我々の兵力といえば、せいぜい3千に足るか…といったところでしたか。騎士団長も私と我が師しか居なかった…そこで我が師は、私と全兵力を国の守備に回らせ、たったお一人で各所に出現した七将全てに致命傷を負わせて回ったのです。魔族側も総力戦に出ていたせいか、それは大きな痛手となったのでしょう。それが原因で停戦交渉に来たのです」
………。
驚きで息を呑む音しか聞こえない。
七将を、たった1人で、それも遠く離れた箇所に存在する者達に致命傷を負わせた。
正しく、化け物だ。
ルーヴェリア「時間もありませんのでこの作戦を決行します。よろしいですね?」
異を唱える者は誰もいない。
アドニスは何か言いたげだったが、空気がそれを許さなかった。
それでも無茶をしてほしくないなんて、言えなかった。
ルーヴェリア「王妃陛下、貴女は魔術棟を管理なさるほど優れた魔術の才をお持ちです」
王妃「え、ええ…そこまで優れているかと言われれば、貴女ほどではありませんが…」
ルーヴェリアは懐から短剣を取り出して王妃に渡した。
ルーヴェリア「これはテフヌト族領で採掘される最も希少な鉱石で造られた短剣です。が、武器ではなく魔道具です」
王妃「どう扱うものなのかしら」
ルーヴェリア「少量の魔力を込めれば、この短剣内部で潜在魔力の解放が為されます。その状態で短剣を投げつければ、開き切る前のゲートなら破壊ができます。一回きりなのが惜しいところではありますが…魔族の軍勢に太刀打ちもできないままよりは良いかと」
それは…ルーヴェリアの読みではこの攻防戦でサフラニア本国自体にゲートが開くと予想しているということだ。
ルーヴェリア「あくまでも万が一に備えて、ではありますが……常に最悪の状態を想定して戦うのが戦争というものですから」
王妃はこくりと頷いてその短剣を受け取った。
王妃「ありがとう。そうですね、貴女の言う通りです。私はいつゲートが開いてもいいよう魔術棟から監視を行います」
ルーヴェリアは頷き、両陛下に頭を下げて退室していく。
どこまで見越しているのか、そんな風に思っている視線が彼女の背中に刺さるのを遮るようにクレストが後に続いた。
アドニス「私も、行って参ります」
頭を下げるアドニスに、国王が声をかけた。
国王「お前の家は、家族はいつも此処に居る。気をつけて行っておいで、そして帰っておいで」
アドニス「…はい」
力強く頷いて退室したが、正直、複雑だった。
第一王子がいない今、次期国王になるのは自分しかいない。
だから優遇されるのもわかる。
でも、自分にだけあの言葉がかけられたのが嫌だったのだ。
自分だけじゃない。
戦いに出る騎士団の全員が、帰る場所はここなんだ。
家族がいて、恋人がいて、一人一人に居場所があって、だからこそ命をかけて守るのだから。
さて、そんな思いを抱えたまま騎士団宿舎の方へ足を運んだ。
既に全員が整列している。
鎧を纏い、武器を手にした騎士団長らが前に並べば、彼らはその身を引き締めるように背筋をぴんと伸ばした。
ルーヴェリア「命令は一つです」
静かな声が、空間に染み渡っていく。
ルーヴェリア「敵に背を向けても構いません。生きることを最優先にしてください」
騎士団にあるまじき発言に、息遣いだけで驚いたのが伝わってくる。
ルーヴェリア「自分の命も、他人の命も、一つしかありません。生きていれば再起出来ますが、死んでしまったら出来ません。大丈夫、訓練の通りに、いつもの通りに、敵を殺せば良い。殺される前に殺しなさい。それが出来ないなら背を向け、機会を伺い刺せばいい」
彼らは安堵した。
そういうことなら、確かに生きること最優先だ。
敵前逃亡ではなく戦略的撤退を選べという意味だったか、と。
ルーヴェリア「貴方達を信じています。それでは各戦線へ、進軍開始!!」
アドニス「進軍開始ー!!」
彼らは南門へ向け、歩調を揃えて歩き出した。
遥か遠方には、魔族の出現によって黒雲が立ち込めているのが見える。
だが、恐怖などない。
「この日のために、この時のために、酷い鍛錬を何度も超えてきたしな」
「何十万を相手にするより、団長1人相手にする方が骨折れるしな」
「我々が負けることなど、万に一つも無いさ」
「そうだな。俺たちには最強の騎士団長達がついてる」
そんなことを隊列の端々から漏らしながら進んでいく騎士団を見送り、ルーヴェリアはクレストを見た。
ルーヴェリア「…………」
死なないでほしい、とは思うがそれを伝えるのは彼の実力に不安があると伝えるのと変わらない。
クレスト「師よ」
ルーヴェリア「はい」
クレストは彼女の手に合うサイズの白い手袋を渡した。
ルーヴェリア「…っ…」
今までの経験からして、これは別れの挨拶だと察する。
クレスト「物理攻撃力の上昇と、速度に関する身体強化が為される術式を施した手袋です。私の魔力で組み込みました」
ルーヴェリア「………」
黙ってそれを受け取ると、クレストはにっこりと微笑んでみせた。
クレスト「この戦いの最中に、貴女の誕生日が過ぎてしまいますからな」
ルーヴェリア「はい?」
確かに、もう数えてはいないからいくつになるのかは分からないが、近く自分の誕生日がある。
クレスト「またお会いしましょう。再会の時まで、私は決して倒れはしません」
ルーヴェリアは少しだけ目を瞠ると、嬉しそうに細め、口角をあげた。
ルーヴェリア「ありがとうございます。また会いましょう」
クレストは軽く頭を下げて東門へと向かっていった。
ルーヴェリアはガントレットを外して、早速手袋を身につける。
ぴったりと馴染む手袋からは、クレストの魔力を感じた。温かなそれは、寄り添ってくれているかのようだ。
ルーヴェリア「……まったく…兄妹揃って私への贈り物が手に関するものだなんて…どう口裏を合わせたんですかね」
ガントレットを装着し直しながら呟く。
そして北方の空を睨んだ。
向こうの状況は読めないが、彼女の索敵魔術が山脈の向こう側でたむろする魔族の群れを捉える。
ルーヴェリア「さて皆さん…殲滅戦のお時間です」
誰ともなくそう言い放ち、彼女はその場から姿を消した。

天月 兎
第二十七話 前編
サフラニアが攻勢に出てから約2日後、アドニス率いる第一騎士団は帰還した。
クレストはその1日後に。
重たい音を立てて玉座の間の扉が開かれ、2人の騎士団長は国王の前に跪く。
曇天で充分な明かりが得られないせいか、室内は少し暗く、空気も重たく感じられた。
国王は2人の帰還をまず労ったが、その後すぐに眉を顰める。
国王「…アドニスの援護に向かった筈のルーヴェリアはどうした」
アドニス「…七将の襲撃に遭い、現在交戦中です」
その場に集まった者たちがひそひそと話し始める。
七将相手にたった一人置いてきたのか、王子もあの化け物に洗脳されてしまったのか、と。
国王の咳払いでそれらは口を閉じた。
国王「…まずは、第三騎士団を率いてたった1人帰還したお前の話から聞かせてもらおう」
視線を向けられたクレストは頷き、掲げていた少し大きな袋から首から上の無い人の形をした、それでも背中には虹色に輝く鱗に覆われた翼を生やしたものを転がした。
国王「それは?」
クレスト「七将が1人、祖龍セレシュバーンの死骸でございます」
クレストを除くその場の全員が息を呑んだ。
獣祖ザルヴォ、植祖シルヴェーラに続き、祖龍セレシュバーンまで。
この国は戦争と悪天候で衰退してきてはいるものの、確実に勝利へと歩んでいると、周囲の人々の目には希望という名の輝きが宿りつつあった。
クレスト「死骸を持ち帰ることは出来ませんでしたが、祖態ミュルクスの襲撃にも遭い、応戦、ゲートの破壊と共に討伐しております。その戦いにて出陣した第三騎士団の生き残りは、私一人となりました。ただ、当初より正規の騎士団ではなく、私兵を主として編成していたため、城内には未だ私の部下が一万ほど控えております」
国王はふむ、と頷いた。
私兵というのは恐らく、クレストが運営していた戦災孤児達を育てていたところだろう。
出立時、騎士団にしては少し数が少ない気がしたのはそういうことだったようだ。
何十年も前の戦いで家族を失った者達は、互いに身を寄せ合いながら、その憎悪を糧に鍛錬に励み、ついに私兵として戦場に赴いて散っていったのか。
国王「慰霊碑に、花を添えねばならないな」
クレスト「お気遣いいただき、感謝いたします。帰還道中、テフヌト族領の村々を見て参りましたが、魔獣の群れに蹂躙されたのか、家屋は崩れ去り、息のある者は誰1人として残っては居りませんでした」
脳裏に過ぎる光景は、凄惨を極めていた。
石を積み上げて造られた家屋らが、まるで道端に転がっている石ころのようにしか見えない。
その下から覗く、何かを求めるように必死に伸ばされたのであろう手や、切断された何者かの脚や頭が転がっており、それらには老いも若いも、男も女も関係なく。
ただ、そこに転がされていた。
血液が飛び散った様子がないあたりを見るに、魔獣だけの襲撃でもなく、恐らく吸血鬼あたりも絡んでいたのだろう。
死体を残しては、悪用されるだけだ。
クレストは己の力で出来うる限りの遺体をかき集め、火炎の魔術で骨にすると、今度は遺骨に鉄球を振り下ろして粉塵に変え、風に流した。
だから少し、帰還が遅れてしまったのだ。
国王「…ふむ。アドニス、お前は如何だった?」
アドニス「私は…」
彼は自分が見たものを正直に答えた。
第一王子ヴィリディスとその護衛騎士ケインが屍人となって襲ってきたこと、地面から無数の巨大な屍人が現れて騎士団を圧倒したこと、そして、ルーヴェリアが駆けつけた途端、魔族を操っていたノクスは逃げ果せ、何とか敵を凌いだことを。
だが、問題はその後だった。
降り続ける雨。空はもうじき晴れるはずなのに、天空に開いた穴はまた閉じて激しい雨を降らせた。
水溜まりが流れ、死者の血液が溶け出して血の川を成したところで、ルーヴェリアはアドニスに言ったのだ。
ルーヴェリア「この雨には、魔力が込められています。恐らく水魔を呼び寄せるつもりでしょう。そして、本来水場のない平原でそれが出来るのは、七将セラフィナだけです」
知っている。本で読んだ、あの水祖セラフィナだろう。
凄まじい魅了術と幻術、そして、全ての液体を操る力を持つ七将だと聞いた。
アドニス「すぐに防衛体制を…」
ルーヴェリア「いいえ。騎士団の中にあれの魅了術に耐えられる者は数少ないはず。私が対応しますから殿下は第一騎士団の生存者全員を引き連れご帰還を」
たった1人で七将を相手にするなんて無茶がすぎる。
まだ仲間の遺体も処理できていない中、ノクスまで戻ってきたら。
どうするのか、と問うアドニスに、ルーヴェリアはヘルム越しにふっと微笑んだ。
ルーヴェリア「ご安心を。私が死ぬことは決してありません。魅了にかかることもない。ノクスが現れたとしても同じです。私に残された魔力は、大軍を相手にするには少し足りませんが、ただそれだけです」
予め用意した小爆発を起こさせる魔道具やら何やら、色々と持ってきたから、と。
必ず敵の首を獲って帰ると言われ、アドニスは言い返すこともできず、軍を率いて帰ってきたというわけだ。
国王「……ふむ」
待つべきか、援軍を送るべきか、しかしルーヴェリアの言葉が本当ならば、果たして援軍を送ったところで足手纏いになるのではないか。
結局彼女が帰還するまで、国王や騎士団長らは待っていることしか出来なかった。

天月 兎
第二十三話 前編
雷鳴が地を這うように鳴り響く。
紫がかった黒雲が空を覆い、陽光はとっくに届かない。
アールマグ帝国と呼ばれたこの国の城は、かつての栄華など影すらも残っていない。
ひび割れた柱、床、扉、天井に至るまで飛び散らかされた血痕が染みついている。
死者の国と見間違う様相に、生者の影が4つ。
朽ち果てた玉座に腰掛けた魔王、イレディアが口を開く。
イレディア「……ザルヴォが逝ったらしい」
退屈そうに肘掛けに片肘をつき、頬杖をついて放たれた一言は落雷よりも重く鋭い。
しかし、意にも介さずといった体で水祖セラフィナが言葉を返した。
セラフィナ「想定の範囲内でしょうに」
貴女は我々をチェスの駒か何かにしか考えていないのだから、という含みを感じる。
ミュルクス「僕見てたー!」
ぴょんぴょんと、声と共に跳ねながらケタケタと笑う。
ミュルクス「首がね、ぐるん!ってなってたよ!」
お前は何故に加勢しなかったのかと周囲が嘆息をこぼす中、ひとりだけ愉快そうに笑い続けている。
無邪気とは時に恐ろしさを感じさせるが、今正にそれが体現されている。
イレディアの側近、サーシャが壁面に縫い止められた地図を眺め、肩越しに魔王を顧みた。
サーシャ「残るのは、アルゼト、サフラニア、そして……テフヌト族領」
うっそりと笑みをこぼすような琥珀の瞳は、このまま全てを根絶やしにしろと命じるのを待っているかのように煌めいている。
サーシャ「どう動くつもり?」
イレディアは数秒の沈黙の後、その問いに答えた。
イレディア「族長を失ったテフヌト族は脅威にすらならん。七将がいなくなったことで統率を失った魔獣共でも放っておけ。周辺の村々諸共勝手に根絶やしになる」
ゲートさえ開いておけばこちらがわざわざ出向き、手を加えるまでもないと言いたいそうだ。
つまらなそうに琥珀の瞳が地図に戻された。
つい、と指を動かすと焼けこげたようにテフヌト族領の地域にバツの印が刻まれる。
イレディア「ノクス、シルヴェーラ」
魔王の呼び声に応じて、2つの気配が玉座の前に現れた。
シルヴェーラ「お呼びで?」
ノクス「ここに」
無数の蔦を髪のように垂らし、花の花弁を思わせる真紅の唇を歪ませた、おおよそ女性と見て良いだろう風貌の魔物。植物系の魔物の始祖シルヴェーラと、度々戦場に茶々入れをしてきたノクスが跪く。
イレディア「当初の予定から変更する必要はない」
彼女の声に呼応するように雷鳴が轟く。
イレディア「サフラニアは最後に潰す。まずは……アルゼトを蹂躙してこい」
シルヴェーラ「仰せのままに」
ノクス「ふふ、楽しみだね? 僕の死霊たちを見て、彼らはどう反応するのかな」
三日月に歪むノクスの口元を、鋭利な稲光が照らしている。
空を裂く閃光。
かつて帝国と呼ばれたその場所には、もう人の声はない。
ただ、滅びの胎動だけが、確かに息づいていたのだった。
第三騎士団の凱旋からはや3日。
数ヶ月前まで笑顔や希望に溢れていた人々の表情は、今では不安や焦燥で溢れかえっている。
魔族に殺されるくらいなら、そう言って自ら命を絶つ者さえ現れる始末だ。
少しでも希望を与えなければ、内側から国が滅んでしまう。
宰相1「打って出るべきでは…」
宰相2「しかし、他の七将は…」
堂々巡りの議会、ある意味無駄な時間を過ごしていると言えよう。
騎士団長らのために用意された席の一つに座りながら、ルーヴェリアは考えた。
自分なら、帝国領に無理矢理乗り込んで戦うことはできる。呪いのおかげで、魔力が尽きることはあっても命が尽きることはない。
自分が行くべきではないのか、と。
一方で、彼女の隣に座るアドニスには誰の声も聞こえていない。
頭の中を巡るのは、魔族をどのようにして殺すか。心の中を占めるのは、魔族への憎しみや怒り。目を閉じれば、無惨な姿で帰ってきた侍女の姿が浮かんでくる。
夜も眠れておらず疲労困憊だが、そんなことさえどうでもいいと思えるほどには奴らを殺したくて仕方なかった。
クレストはそんなアドニスを気遣うように、度々視線を彼に送るが、気が付かれる様子はない。
宰相1「このままではいずれ我が国まで…同盟を結んだテフヌト族の族長や、ヴィリディス様も行方不明のまま。何もせずただ待てというのですか?」
宰相2「わざわざ死地に飛び込む必要はないと言っているのです。負け戦と分かっていて派兵するなど、人命軽視にも程がありますぞ」
どちらの言い分にも理がある分、どちらの味方にもつくことができない。
国王は心の中で頭を抱え、それを隠すようにぎゅっと拳を握りしめる。
どうするのが正解なのだろう。
何が正しくて、何が間違いになるのか、全くわからない。
そこへ、1人の兵士が飛び込んできた。
兵士「失礼いたします!アルゼト小国より救援要請!現在、植魔5000、食屍鬼2000と交戦中とのことです!」
ガタリ、と音を立ててテオが立ち上がった。
テオ「俺たち第四騎士団で対応します!」
有無を言わさず言い切り、返答も待たぬまま駆け出していった。
アルゼト小国は、サフラニアの第一王女シーフィが嫁いだところでもある。
約束したのだ、何かあればすぐ駆けつけると。
だから誰にも何も言わせない。
テオ(必ず助けるっすよ…!)
アドニスも立ち上がった。
アドニス「第一騎士団も行かせてください」
彼はテオと違い、返答をきちんと待った。
待ったうえで、却下された。
国王「ならぬ」
アドニス「何故ですか!」
国王「もしアルゼト小国の襲撃が陽動だったら、この国の守りが薄くなるからだ」
しかし彼は食い下がる。
アドニス「第二騎士団、第三騎士団が残っているではありませんか!」
国王「アルゼト小国で戦いが繰り広げられている中で、我が国が襲撃されるとすれば、我が国は東、西、南の三方を守らねばならぬのだぞ」
アドニス「しかし!」
王妃「アドニス」
尚も諦めないアドニスを、王妃が静かな声で制止する。
王妃「気持ちはわかります。けれど一度頭を冷やしなさい。個人の感情で冷静さを欠くことは上に立つ者として恥ずべき行為です」
アドニスはくっと歯噛みして腰を下ろした。
王妃は続ける。
王妃「このままでは堂々巡りで埒があきません。騎士団長達に無意味な時間を過ごさせるより、国防に徹していただいた方が益と思われますが?」
是非を問うように国王の方を見る。
彼は一つ頷くと、国内の問題解決を議題にあげ、後は自分達で話をするからと、騎士団長らを解放した。
廊下に出たアドニスは、暗い面持ちで俯いたままルーヴェリアに声をかける。
アドニス「…師匠」
ルーヴェリア「何でしょうか…あと、ルーヴェリアです、殿下」
アドニス「今は呼び方なんてどうでもいい、それより大事な話なんです」
おお、初めて呼び方について反論した、と第三者のクレストが見守る中、アドニスはルーヴェリアに深く頭を下げた。
アドニス「戦死した者達を、時を操る魔術で蘇生してくれませんか…!」
そうきたか。
ルーヴェリアは瞼を閉じて一呼吸数えてから答える。
ルーヴェリア「殿下は、昨今の葬送をご存知ないのですね」
彼女は何も知らないアドニスに懇切丁寧に説明した。
七将ノクスが居る限り、どんなに損壊した遺体でも、彼奴の術で操られてしまうこと。
そうすると被害が甚大になること。
被害が甚大になるとまた遺体が増え、奴等の思う壺になってしまうこと。
だから昨今の葬送は、骨も残さず焼き尽くすことだと。
無論、国内で自害した者も例外はない。
巡回兵や通報を受けて駆けつけた騎士団が遺体を回収し、誰の目にも触れぬ魔術塔で焼き払っている。
きっと彼が望むのは亡くなった侍女の蘇生だろう。
だが、もうその遺体すら無い状態では出来るわけがない。
あったとしても後述の理由で行わないが。
アドニス「じゃ、じゃあせめて、せめて…戦場では…」
ルーヴェリア「殿下、私の魔力量は常人を遥かに上回ってはいますが、無尽蔵ではありません。それに…戦場で散った勇士の蘇生は彼らへの冒涜です」
確かに、蘇生ができれば戦力差は埋められるだろう。だが、それを何度繰り返せば勝てるかは状況次第だ。
それと、死を覚悟して戦場に立つ彼らがその命を散らせた時の思いや死に様を否定するような真似は出来ないししたくもない。
これは彼女が勝手に思っていることだが、それをしてはノクスと変わらないと考えているからでもある。
よって、却下。
アドニス「でも鍛錬では蘇生してくださるじゃないですか…!」
下げていた頭を勢いよくあげて、今にもルーヴェリアに掴みかからん勢いで噛み付く。
対照的に彼女は至って冷静だ。
ルーヴェリア「鍛錬は鍛錬、戦場は戦場です。鍛錬時に戦場と思うよう言っていたのは、鍛錬だからと甘く見てほしくなかったからに過ぎません」
次に来るであろう「でも鍛錬の時、戦場と思って励むように言うではないか」という言葉を予測して先に返事をしておき、彼女は歩き出す。
ルーヴェリア「防衛態勢を整えますよ」
離れていく背中に、今はついていけない。
クレストがそっと、アドニスの背に手を添えた。
クレスト「我々も行きましょう」
今はきっと、何を言ってもアドニスの心には響かないだろうと考え、あえて慰めの言葉を飲み込み歩き出すよう促す。
アドニスは俯き、唇を噛み締めて促されるままに足を進めることしか出来なかった。

天月 兎
【おまけ】ある日の騎士団 13
これは、アドニスがまだサフラニアの歴史について知らなかった頃の話である。
彼の師であるルーヴェリアは、王命でもない限り永遠に仕事を続けるような人間だが、年に一度、必ず三日間だけ休暇をとることがあった。
不思議に思っていたアドニスは、何をしているのか気になり、彼女に許可を得てついていくことにする。
何も面白いことはないですよ、そう言いながらも同行を許可してくれた。
行ったのは、馬を使ってサフラニアから北西諸国、そして西側の山脈を抜けてテフヌト族領まで行き、山脈を帝国側に迂回してサフラニアに帰る、だけだった。
途中途中公道の端に留まり、彼女は風景を眺めて走り去っていく。
国の近場だし、ただの遠出には見えない。
野営中に聞いてみた。
アドニス「師匠」
ルーヴェリア「ルーヴェリアです、殿下」
アドニス「師匠」
ルーヴェリア「…はい」
アドニス「この旅は一体何が目的なのですか?」
するとルーヴェリアは遠い眼差しで炎を見つめながら答えてくれた。
今まで通ってきた道の全てが、かつては戦場であったこと。
今ほど運搬技術のない中で、戦死した兵士の死体を連れて帰る余裕がなかったこと。
そこで選ばれたのは、鎧ごと死体の腐食を早め、肉も、内臓も、骨も、全て土に、風に乗せて自然へ返すことだった。
ルーヴェリア「つまりこの道、或いはウェス・トリステスの大地全てが、戦死した英霊達の墓場なのです。私は停戦が結ばれたあの日から、毎年祈りを捧げにこうして遠出をしています」
アドニスは絶句するしかない。
自分たちが今、死体の上に立っているのと同じだという事実に。
故に、静かに野営の炎を見つめる彼女をただ見ていることしかできなかった。
だが彼女は表情と裏腹にある疑念を抱いている。
上手く言えない焦燥感。間違った選択をしている予感がする。
しかしそれは今考えても仕方のないことだ。
今はただ、かつての仲間のために祈りを捧げよう。

天月 兎
【おまけ】ある日の騎士団 17
サフラニア王国南東に位置する熱帯の地は、ヤヤ・テフヌト族という部族が住んでいる。
かつて魔族の襲来があった折、一時的にサフラニアと同盟を結び共に戦った部族だ。
文化の違いから相容れない者同士とのことで同盟国ではなく交易相手として長年絆を育んできた。
サフラニア王国第一王子ヴィリディスが族長の元へと訪れた時、族長は何かを悟ったようにこう言った。
族長「闇が訪れる。月も星も輝きを失った暗黒がこの地を包み込む。そこに一筋の光が差すことはなく、この地はさながら冥府のそれと化すだろう」
だが、と族長は続けた。
族長「かつての我々がそうしたように、生き抜くために抗うことは不可能ではないだろう。お前達がここへ来た理由は分かる。精霊様が教えてくれるのだ、再び手を取り合い、共に戦うべきだと」
彼が、もしくは彼らに何が見えてるのかはわからない。
未来予知のような何かだろうか。
そのおかげか、とんとん拍子で再同盟の話は進んでいった。
そしてメレンデスに到着し、魔族について語られる最中に出てきた、ナギという少年の名前を聞いて何を思っただろう。
魔族の脅威に晒され、結界を破るために尽力するも届かず。
己の無力を嘆いた。
だが、彼が最期に見た光景は、一族のために力の限りを尽くしたかつての戦士の背中だった。
魔狼に臓物を貪られる音の合間に、微かに、よく頑張ったという声が聞こえた気がした。

天月 兎
第二十一話 前編
戦場から帰国した翌日、テフヌト族と同盟を結び、族長を連れて第一王子のヴィリディスが帰城した。
テフヌト族はサフラニアの南東にその領地をもつ部族だ。自然の恵みも、災害も、全て精霊からの贈り物として尊ぶ。自然を愛し、自然と共に歩む彼らは、魔族にその全てが侵されるのを是としなかった。
かつては魔族との交戦で同盟を結んでいたこともあり、再同盟の話はスムーズに進んだ。
また、文化的に口伝にはなるが、自分達の持つ知識が何かしらの役に立てるかもしれないと、族長自ら来国してくれたらしい。
ルーヴェリアからの報告で、北西諸国も交えて魔族に対する知識の共有の場を作ることになった。
場所はアルゼト小国の西にあるメレンデス小国。
アルゼト小国同様、ゼーレース海沿いに位置する国で、サフラニア王国の現王妃の出身国でもある。
魔族に関して記述のある本は本来持ち出し厳禁の禁書だが、この際云々と言ってはいられないとルーヴェリアの言もあり、王国から多様な歴史書がメレンデス小国へと運ばれていった。
本と共に向かったのは、ヴィリディスとその護衛騎士のケイン、テフヌト族の長だ。
ルーヴェリア達も向かうべきではあったのだが、いつ魔族側が動くか分からないため、周辺を離れることが出来なかった。
彼らが出立し、静けさを取り戻した謁見の間で、国王はルーヴェリアに問うた。
国王「良いのか。あの本にはお前の名も刻まれている。……その身のことが知れたら」
折角彼女を認める者が出てきたのに、かつてのように化け物と蔑む者が現れるのではないかと案じているようだ。
ルーヴェリア「構いません。魔族の力は強大です。それは、一夜にして滅び去ったラシェクス小国が物語っています。もし、私を軽蔑し、諍いが起きたなら、この地はそれまでということです」
人間同士で争っている場合ではない時にそんなことが起きたら、確かにこの世の終わりだろう。
国王「もしそうなったら、お前は軽蔑する者としない者、どちらの側に立つ?」
は。愚問だ。何故そんなことを問うのだろう。
此奴は愚王なのか、自分がどれだけの時間をこの国で過ごしたと思っているのか。
思考回路がどうなっているのか確かめてみたいものだ。
と、少し頭に血が昇りかけたが、一呼吸おいて落ち着かせる。
ルーヴェリア「どちらがどちらだろうと関係ありません。私はこの国の騎士です。初代国王に騎士の称号を賜ってから、この命が尽きるまで。私はこの国の騎士として生きる所存です」
国王は安堵したように息を吐く。
彼女の偉大さを知るからこそ、心の片隅にあった、もし彼女が敵に回ってしまったらという不安から出てしまった問いだった。
国王「すまない、お前を愚弄してしまったな」
ルーヴェリア「謝罪は必要ありません。恐らく、誰もが一度は考えることでしょうから」
そう言って、彼女は謁見の間を出ていく。
国王はその背中をただ黙って見ていることしか出来なかった。
ルーヴェリアは自室に向かっていく。
魔術棟からの報告書や、各地の状況を宰相に纏めてもらったものを読まなくてはならない。
その時、いつもより軽装のシエラとすれ違った。
アドニス専属の侍女だが、今は侍女というより…戦場に立つ看護兵と同じような装いをしている。
シエラ「ルーヴェリア様、お疲れ様です」
ぺこりと頭を下げる彼女に、ルーヴェリアも挨拶を返した。
ルーヴェリア「……戦場に立つのですか?」
シエラはこくん、と頷く。
シエラ「アドニス様が戦場に向かわれることが多くなった今、侍女としてお世話することが出来ませんから…私なりに、考えたんです」
自分に出来ることをしたい。
国や民を守るアドニスや、騎士達のために、何か役に立ちたいと思ったそうだ。
どうやらシエラは多少ではあるが治癒術を扱えるらしい。
それを活かせると考えてのことだと。
ルーヴェリア「…そうですか……死地へ向かう覚悟はあるということですね」
シエラ「はい。いつか、ルーヴェリア様は仰いましたね。死んでは何も守れないと。だから私は死なせない立場に立つと決めたのです」
そういうことなら、否定することは出来ない。
アドニスの立場から考えれば城にいてほしいのだろうが、シエラの覚悟や思いを否定することは彼にも出来ないだろう。
ルーヴェリア「分かりました。健闘を祈ります」
シエラ「はい!」
そうして二人はそれぞれの行き先へと向かっていく。
さて、自室に着いたルーヴェリアは机に積み上がった書簡を見て早速嫌な予感を覚えた。
この量、間違いなくウェス・トリステス全域で発生した事案だ。
一つずつ中身を見ていくと、嫌な予感は的中していた。
地方全域で、農作物の不作、家畜の不審死、天候の悪化が相次いでいる。
更に、犯罪に手を染める者も増えているようだ。
ルーヴェリア(日頃の鬱憤からか、或いは何かしらの魔族が関与しているか……植魔であればただの一般人の心を操ることなど造作もないはず…)
本格的に、魔族側が動き出していることは明白。
魔術棟からの報告書には、不自然に魔力が集結する箇所も散らばっており、過去の記録のように小さな魔獣が通れるほどのゲートは頻繁に開いているともあった。
地方全域に、警戒態勢を訴えなくてはならない。
ルーヴェリアは文書をしたため始めた。
だが、その文書に対して返事が返ってくることはなかった。

天月 兎
第十九話 後編
──敵別働隊壊滅。残党はアルゼト小国軍のみで対応可能と判断。ラシェクス方面へ進軍を。
アドニスは一つ頷くと騎士団に指示を出す。
アドニス「このままラシェクス小国軍を襲撃している魔族を討つ!行くぞ!」
待機させていた馬に乗り、即刻走らせる。
山岳内に待機中の魔導部隊、弓兵らには伝言を走らせた。
到着と同時に合図を送るため、速攻で魔導と弓により強襲をかけろ、とのことだ。
アルゼト兵(お、俺ら、行く意味あるかなこれ…)
食屍鬼1体に3人がかりがやっとの自分達は、騎士団の強さに圧倒されてしまい、彼らの背を見送ることしかできない。
それでも。
アルゼト将軍「我々は友好国の援護に向かうのだ!各位残党を処理しつつ、前進!!」
号令がかかり、騎士団に続いて進軍を開始した。
ラシェクス防衛戦線、マイアコス大海端小国側。
ラシェクス防衛隊長「魔導兵、弓兵、構え!」
号令に合わせて詠唱が始まる。
ラシェクス防衛隊長「放てええ!」
無数の矢、数多の光矢が前進してくる小物達を射止めていく。
渡川に苦労するような小型の魔獣は、泳いでいる間にそれで沈められていく。
しかし中型の魔獣は、矢を受けようがお構いなしに突っ込んできて渡川を始めた。
向こう岸では、盾を構えた歩兵達が槍を片手に待ち構えている。
ラシェクス防衛隊長「魔獣は首を落とすか心臓を狙え!一撃で沈めてやれ!」
兵士達が固唾を飲んで覚悟を決めた時、敵陣後方から爆炎が上がった。
アドニスが声の限りを尽くしてラシェクス防衛隊に伝える。
アドニス「サフラニア王国第一騎士団!!これより援護を開始する!!!」
いつぞやの鍛錬で魔獣とはこんなものだとルーヴェリアが幻影を見せてくれたおかげで、初対面でもそんなに印象が強いとは感じない。
確かに体は大きく、爪も牙も強靭ではあるが、防衛隊の攻撃で弱っている今は、アドニスでなくとも首を取ることは容易だ。
突出して切り込んでいくアドニスに続く騎兵隊が残党を悉く皆殺しにしていく。
そして中心部に辿り着いたアドニスが剣を高く掲げ、剣先から閃光を放った。
合図を確認したケレテス山脈に待機中の魔導部隊、弓兵は、魔法円を展開し各々の矢を放つ。
閃光の意図を汲んだ騎士達も、先ほどと同じように防衛魔術を行使して味方を守る。
あれだけいた魔族達が、彼らの登場であっという間にいなくなってしまった。
アルゼト小国の援護に入ってから交戦終了に至るまで、僅か1時間足らずで勝利を得た。
ルーヴェリアからも報告が入る。
──戦闘終了、犠牲者0。引き続き周囲の警戒を行います。
アドニスはふう、と息をつきながら剣を納める。
アドニス「みんなお疲れ様!敵増援部隊は無し、戦闘終了!僕らの勝利だ!」
初めて魔族と戦うにしては、中々良い結果であるだろう。
まあそれもそのはずだ、魔族なんて比にならない化け物を相手してきたのだから。
後から合流したアルゼト小国軍の将は、自分たちが到着した時にはすでに戦闘終了していたため、騎士団の圧倒的なまでの強さに言葉を失う。
将軍(初交戦…のはずだよな…)
と、そこへアドニスがやってきた。
アドニス「防衛戦及び援軍の派兵、お疲れ様です」
将軍「我々は大したことは…むしろ助けていただき感謝する」
二人は握手を交わすと、ラシェクス小国防衛隊が用意した舟で渡川し、彼らの陣へと招かれた。
防衛隊長「お二人とも、応援に来てくださり大変ありがとうございます。とても助かりました」
彼らは陣幕の中で軽く自己紹介をした後、今回の襲撃について話を聞くことになる。
ゲートの出現位置は未確認。
帝国領側から魔族の侵攻を偵察兵が確認をしたため、即座に防衛線を張ったとのことだった。
アドニス「ということは、我々サフラニアが懸念している通り、すでに帝国は魔族の手に落ちている可能性が高いですね」
将軍「数ヶ月前の魔族出現を確認した時からか、それよりもっと前なのか…少なくとも、防衛一方となるよりは、戦力のあるうちに攻め込むのも手かとは思われるがな…」
これに対して、防衛隊長は首を横に振る。
防衛隊長「帝国領に滞在する魔族の種類や、以前共有いただいた七将の動向が不明な以上、リスクを犯す必要もないかと。今は各国提携し、防衛に徹する方がいいかもしれません」
アドニス「そうだね。それに攻め込むとしたら、北西諸国は陸路になるけど、ラシェクス小国はマイアコス大海を抜ける必要がある。
荒れやすい上に水棲の魔族がいたら、流石に苦戦を強いられてしまいますから」
それもそうだ、と将軍は納得した。
アドニス「これから七日間ほど、帝国領前に駐屯し様子を見るつもりです。もし襲撃があった際は、ネポス山に駐屯している第二騎士団も駆けつける手筈ですので、ご安心ください」
防衛隊長は力強く頷いた。
防衛隊長「貴重な騎士団を二団派兵してくださるとは、大変有り難いことです。是非とも、よろしくお願いします」
将軍「こちらも出来うる限りの援護は行う。交戦になったら存分に暴れてくれたまえ」
こうして、第一騎士団はアルゼト小国とラシェクス小国の中間、帝国領前に陣幕を構えることとなった。
後方に控える魔導兵、弓兵はそのままケレテス山脈に駐屯。
先行していたルーヴェリアの部隊も彼女と合流を果たし、交代で巡回、魔族側の動向を逐一確認している。
ルーヴェリア「我々の位置は敵に探られぬよう、火など光の出るものの使用は控えるように。私は一度帰城し、陛下に戦況報告を行います。何かあれば魔道具を通じて私へ報告を」
騎士「承知しました」
背を伸ばして返事をする騎士を背に、山を駆け降りたところで空間移動の魔術を行使、玉座の間の扉前に現れると、警備兵に声をかける。
ルーヴェリア「第二騎士団長ルーヴェリア。戦況報告のため一時帰城しました。陛下に謁見願います」
兵士1「し、承知しました。少々お待ちください」
兵士2(今この人空間の割れ目みたいなところから出てこなかったか…?)
兵士1「陛下の了承を得られましたので、どうぞ中へ」
ルーヴェリア「ありがとうございます」
彼女は玉座の間へと消えていった。
兵士2「ルーヴェリア様さ、どこから出てきたように見えた…?」
兵士1「多分聞いたら首が飛ぶやつだ。空から降ってきたくらいにしとけ」
兵士2「…室内だけどな、ここ」
兵士1「…何も言うな…」
ルーヴェリアは宰相2人に囲まれた国王と王妃の前に跪く。
ルーヴェリア「第一騎士団長ルーヴェリア。戦線報告のため一時帰城いたしました」
国王「うむ、ご苦労である。戦果は」
ルーヴェリア「第一騎士団にて魔族の別働隊に襲撃されていたアルゼト小国軍を救援、そのままラシェクス小国防衛線へと進軍、勝利。犠牲者は居りません」
緊張した面持ちの4人の顔がぱっと晴れる。
王妃「初戦にしては上出来の戦果ですね。さすが、貴女が鍛えただけのことはあるわ」
宰相1「この状態が続くのが良いのですがな」
宰相2「縁起が悪いですぞ。攻勢に転じることができれば別ですがな」
やりとりを聞いたルーヴェリアが口を開く。
ルーヴェリア「襲撃はやはり帝国領側より行われており、帝国領での交戦跡は確認できなかったことから、恐らく魔族は帝国領に本拠地を置いているでしょう。攻め込むには地形が不利なうえ、どの程度の戦力が相手側に集っているのか不明な以上、現状維持が妥当かと」
そう、七将も数ヶ月前に遭遇したノクスだけとは限らない。
もし他の奴らも揃っているとしたら、攻め込んだ瞬間返り討ちに遭って無駄死にするだけだろう。
国王「では引き続き帝国領の動きを観察し、逐一報告を入れてほしい。こちらはヤヤ・テフヌト族領にヴィリディスとケインを派遣し、再同盟の交渉を行わせている。戦力はあればあるほど良いからな」
ルーヴェリア「承知しました。お任せください。報告は以上です」
駐屯地に戻ります、と背を向けて歩き出す背に、王妃が声をかけた。
王妃「くれぐれも無茶はしてはいけませんからね。動向を探るにしても、週に一度は休息として帰城するのですよ」
ルーヴェリア「……場合によりますが、善処します。では」
玉座の間から出、彼女は目の前にあった窓を開き、背後の見張り兵に
ルーヴェリア「閉めるのは任せました」
と言って飛び降りていった。
兵士1「あ、ちょ、ここ3階……ああ…」
兵士2「しかももう居ねえ…」
ぱたりと窓を閉め、鍵をかけてまた配置につく。
兵士1「あれじゃ人間か疑われても仕方ないよな」
兵士2「だな…でも、すごく頼りになる良い人だと思う。行動はまあ、、あれだけど」
兵士1「激しく同意だ」
時刻は間も無く夕暮れ時。
夜が訪れれば魔族が活性化する時間だ。
警戒は怠れない。
現地に戻ったルーヴェリアは、地図を片手に遠見の魔術で帝国領方面の監視を始めるのだった。
一方で、黒雲垂れ込める帝国領中央都の城内でも戦況報告が行われていた。
帝国にはもう人間の生き残りは1人もいないため、完全に支配下に置かれているようだ。
というより、拠点化、あるいは魔界化していると言っても過言ではない。
雷鳴が度々轟く中、魔王側近の魔女が口を開いた。
サーシャ「戦況はどう?」
傾げた首の動きに合わせ、長い黒髪が揺蕩う。
優雅な見た目とは裏腹に、琥珀の双眸は同僚を射抜くような眼差しで見つめていた。
ノクス「小手調べ程度だったが、ありゃもう別次元だね。数ヶ月前の雑魚から僕たちの脅威にまで成長してやがったよ。まあ僕からすれば死体が増えて大満足って感じだけど」
サーシャは軽く腕組みをしながら続きを促した。
サーシャ「交戦開始からどの程度で全滅に至ったのかしら」
ノクス「大体1時間くらい。多分もうちょっと早かったんじゃないかな」
そんなにも人間の方は力をつけていたのか、と素直に感嘆する。
ノクス「まあでも人数はそんなにいなかったかな。アルゼトの方とラシェクスの方は。多分あっち側から潰していったほうが早そうだ」
するとそこへ、今まで静観していた者が口を開いた。
白く透き通った柔肌に、水色を帯びた銀の長髪。頬には淡い虹色に輝く鱗のような模様が浮かび上がっている。
これが七将が1人、祖龍セレシュバーンだ。
セレシュバーン「なら私が行こう。殲滅は早いうちに行ってしまった方が戦線が少なくなって戦いやすくなる。死体が増えればノクス、お前も嬉しいだろう?」
サーシャ「具体的にはどうするつもり?」
セレシュバーン「ラシェクスを背後と大海側から潰す。案ずるな、セラフィナが居なくても海竜が居るからな。水中深くに潜ませ、開戦後街を襲わせる算段だ」
ノクスはにやりと笑った。
ノクス「じゃーその間の引きつけ役は僕が任されたよ。今回よりちょっと大きめの規模で中央から攻めれば、騎士団はそっちの戦闘で忙しくなるだろう?その間にセレシュがラシェクスを潰せば……」
全てがうまくいくだろう。
雷光が七将二人と魔王側近の顔を一瞬だけ照らし出す。
その笑みは美しくもあり、醜悪でもあった。
もっとみる 
