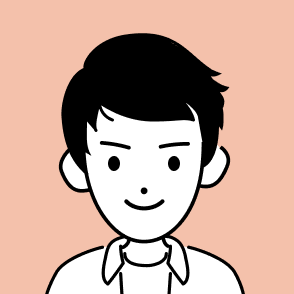
bg
欺かれぬものは彷徨う。
音楽
映画
話を聞くのが好き
写真撮影
読書
アート
ランニング
カフェ巡り
東京
IT・Web
ジャズ
ドラマ
サイクリング
サッカー
クラシック
エレクトロニック
ボサノバ
テクノ
ディスコ

bg
本作はアパート「メゾン・アフリカ」の住人たちが織りなす群像劇で、結婚式の日に婚約者が逮捕され好奇の目にさらされることになった杉立八重子(鈴木京香)、8年前に八重子にプロポーズするも別れた過去を持つ木村礼太郎(佐藤浩市)、礼太郎のいまの彼女である女優の卵の相沢有香(松雪泰子)、惣菜屋「おかずの丸ちゃん」のおかみさん丸山みづほ(室井滋)など個性的なキャラが登場する。
話は八重子と礼太郎、有香の三角関係になるかと思いきやさにあらず。みづほが逃亡中の殺人犯「亀田伸枝」ではないかという疑惑が持ち上がると、物語は時効間近の事件を中心に息詰まる展開をみせる。
「いつでも、誰の前にも、道はひらかれている」とは礼太郎の言葉で、このドラマの重要なテーマだ。過去に傷を負った八重子やみづほがどうやって進むべき「道」を見つけるのか。8年前のプロポーズを振り返り、八重子と礼太郎はどんな未来を思い描くのか。
放送から27年もたったことに驚きを隠せないけど、ひとがどうやって幸せを掴むのか、失敗から立ち直るのかは普遍的な問題であり、21世紀も4分の1を過ぎたいま現在でも十分見応えがあるドラマだ。
過去を含め自らと正対しない限り、前には進めないし、幸せにはなれないということ。そして、進もうとする「道」は、自ら選べるということ。そういう前向きなメッセージをもらえる、隠れた名作である。


bg
戦国の世で一国を統治してきた一文字秀虎(仲代達矢)が家督を譲って隠居すると口にした途端、権力に目が眩んだ息子たちが骨肉の争いを始め、ついには自分の命を狙いに城を攻められ火を放たれる。当時なら秀虎が自害して終わるところを「あんまり酷いことされてアタマ狂っちゃった」と生き延びてしまい、ますます惨めな思いを味わう。
長男の太郎孝虎(寺尾聰)の奥方だった楓の方(原田美枝子)は、かつて秀虎に家族を殺されており、打倒・一文字家に燃える鬼として腑抜けな息子どもを操る。次男の次郎正虎(根津甚八)側によって太郎孝虎が殺されると次男に擦り寄り、さらにその正室だった末の方(宮崎美子)の首を取れとの狂人ぶりを発揮。末の方も、その弟で秀虎に目を潰された鶴丸(野村武司、後の野村萬斎)も、秀虎の蛮行の犠牲者である。
秀虎だって、自分の行いへの自覚はあった。いつも悲しい顔をしていた末の方には、彼女の家族を城もろとも焼いたのは自分なんだ、恨みを込めて睨んでくれ、といたたまれない心情を吐露している。秀虎も、戦乱の世を生き抜くために処世してきた意味で時代の犠牲者である。
本当は誰が酷いのか、狂ってるのか、それとも正しいのか、まったく分からない。こうした混沌とした状態が「人間の愚かさ」とも言えるし「人間のおかしさ」とも捉えられる。実際、狂阿弥(ピーター)のトリックスターぶりはその悲喜劇を体現している。時に茶化し、時に嘆き、映画の場面ごとにキャラを変えながら、観るものに俯瞰的なメッセージを届けている。
40年以上前の映画だが、まったく色褪せていない。人間も馬も城も炎もリアルという生々しさ。落ちぶれた狂人大殿を名演した仲代達矢をはじめとする役者の一挙手一投足に、武満徹の迫真の音楽がいっそうの息吹を与え、ワダ・エミの絢爛豪華な衣装が画面を美しく彩る。こんな手間、そして巨費をかけた作品はもう二度とできないだろう。黒澤明という存在の大きさを思い知る。


bg
スネークマンショーのブラックなギャグの合間に突如流れる幸宏色全開の『今日、恋が』。フランスかぶれが嫌味じゃないのが彼らしさ。


今日、恋が (2021 Remastering For Grand Espoir)

bg
2017年の大回顧展「DAVID BOWIE is」の最後のセクションで大画面に映し出された、"Rock ‘n’ Roll Suicide"を歌うボウイの「Oh no love! you're not alone!」という言葉に、あれだけ感動するとは思ってもみなかった。
若い頃も素敵だけど、2000年代初頭、リアリティ・ツアー中の50代の"おじさまボウイ"みたいになりたい、という密かな夢がある。ぜんぜんなれてないけど。


Rock 'N' Roll Suicide (Live on 3rd July 1973)

bg
魔女伝説のドキュメンタリー映画を撮る、という3人の学生の軽薄な思いつきで始まった撮影は、伝説の森での奇怪な出来事に翻弄されサイコスリラーの様相を呈する。
夜になると感じるひとの気配や不気味な音、墓跡のような石積み、木に吊るされた人形状の枝、廃屋。どれをとってもゾワゾワとする画ばかりだ。上映当時、プログラム冒頭にか書かれた「3人の失踪から1年後に撮影されたフィルムが発見。築100年の小屋の土台に埋まっていた」という設定で早くも震えていたことを思い出す。
ストーリー自体は本物っぽく見せたフィクションだが、魔女狩り自体は実際に欧米で起こった惨たらしい黒歴史。魔女狩り裁判として有名なマサチューセッツ州セイラムに行ったことがあるのだけど、地下の牢獄跡とか拷問があった場所とか、とにかく陰鬱で凄惨な事実にうんざりとしたものだった。
おそらく製作側にそこまでの意図はなかったと思いつつ、ひとつの教訓的テーマを強引に引き出せば、「集団のなかで芽生える恐怖ほどタチの悪いものはない」。
登場人物の3人の若者は、見えない何かにじわじわと追いつめられながら喧嘩ばかりしているうちに事態は悪化の一途を辿った。集団ヒステリーが引き起こした魔女狩りと重なる部分ではないか。
かように恐怖が詰まった80分。しかし戦慄を覚えるべきは、映画館で観てから25年以上経ったという事実にかもしれない。


bg
トラウマはともかく、さしたる信条もなく大勢に従順に生きる向きはいつの時代にもいる。マルチェロがイタリアのファシスト政権下で秘密警察に入隊したのも、そうすることで得られる安心を求めていただけ。国や民族など思い思いの(自分勝手な)衣を纏うことで、自らの存在を確認したいひとたちはどの国にも認められるだろう。
マルチェロが暗殺を命じられたのは、かつて教えを受けた反ファシスト派のルカ・クアドリ教授(エンツォ・タラシオ)。パリでの再会でマルチェロが最初に持ち出したのが、プラトンの「洞窟の囚人」だった。
生まれてからずっと洞窟の奥を見て暮らす囚人は、洞窟で見える影こそが世界の真実だと思い込んでいる。しかし外には太陽に照らされた世界 、「真実」や「真理」といったものがある。講義中にクアドリが触れたこの寓話の意味を、まったく理解できていないマルチェロが口にしたことがなんとも皮肉である。
しかし、こうした哲学的なテーマだけが本作の柱というわけではない。マルチェロを惑わすクアドリ教授の若妻アンナ(ドミニク・サンダ)や、明るく奔放で少々おつむが足りないマルチェロの新妻ジュリア(ステファニア・サンドレッリ)といった女たちは、イデオロギーやアイデンティティなど(つまらない)概念に取り憑かれた男たちには見えない「真実」を知っていた。
アンナとジュリアのダンスシーンは、この作品のクライマックスだ。女ふたりの美しい踊りは、男が知らない官能の世界。つまらない大義に命をかける男どものなんとくだらないものか、と思い知らされる。


bg
子供の頃から食に興味がなかった大人が、転職を機に“カレーの街”神保町を去ってから気がついたことは「カレーが恋しい」。
以来カレー好きを公言すると、カレーを話題に誰かと繋がることができる、ということを覚えた。韓国から来た同僚からは、かの地で有名なレトルトカレーをもらったりしたし、誰かと会う口実に「カレーが食べたいからこの店行かない?」と誘うこともできた。
料理がつくれるひとはすごいなあという程度にしか思っていなかったけど、スパイスからカレーをつくる、という趣味を見つけると、食という人間の根源的な営みに対して真摯に向き合う気になった。
2025年に食べたカレーは83食を数えた。カレーを通じてひとに会い、新たな店を発見し、違いを知り、つくって家族に喜ばれ、どれもとても幸せな経験だった。口福で幸福な食べもの、それが自分にとってのカレー。今年も(カレーを通じた)たくさんの出会いを。


bg

君は天然色

bg
はじまりは、ハンガリー動乱の犠牲者への純粋な追悼だった。教師の前で2分間の黙祷という軽率な行動に出たのは若さゆえのあやまちだったかもしれないが、とはいえ、そんな些細な出来事にすら当局が神経を尖らしていたほど、当時の東ドイツは息苦しく自由がなかった。生徒たちは当局の執拗で姑息な“反乱分子”の首謀者探しにより追い詰められていく。
10代がはるか昔となった自分には、もはや若者たちの親の視点でしか観られなかった。がんじがらめの社会主義体制を受け入れているように見える大人であっても、それぞれに戦争の傷があり葛藤があった。たとえ嘘をつかせても子供を守りたいという気持ちはどの親にもあったはずだけど、この問題の発端をつくった子(クルト)の母親が言った「この国から逃げなさい。毎日、毎分、いつも思っているから」という言葉にはひときわ心を動かされた。勇気があり、優しさがあり、愛が詰まった言葉だった。この子とはもう二度と会えないかもしれない。それでもこの子のためには逃げてもらうしかない。そういう覚悟のあらわれだった。
退学が決まったクラスメイトたちを前に、クルトの親友テオは逃亡を呼びかけ、「国を出るか残るかは自分で決めるんだ」と各自に判断を委ねた。そんな大人びたことを口にしたテオも、西側に逃亡する日の朝、家族との別れには涙をこらえきれなかった(し観ている方も泣いた)。邦題の通り「希望」を感じさせる終わり方ではあったけど、払った代償はあまりにも大きかったのではないか。
さて、もし自分が彼らの親だったら、あるいは未来ある子供たちの立場だったら、どうしていただろうか。即答が難しい、重い問いだ。


bg
仮にオッペンハイマーがいなかったとしても、誰かがそれを開発したであろうことは、のちにソ連が核実験を成功させたことからも明白だ。実際アメリカが行った人類史に残る蛮行は許せるものではないが、日本だって、機会とリソースとその気があればやっていたっておかしくはない。これは人類共通の宿痾の話と見るべきだ。
オッペンハイマーは、目には見えない宇宙の真理を求め、ドイツでのユダヤ人の扱われ方に義憤を感じ、社会を変革しようとする共産主義に注目し、そして女性に魅了される、いわばロマンティストだった。科学とは、こうした純粋なまでに理想を追い求める探究心と強い親和性がある一方、軍事とも相性が良く、未知の力を手に入れると、それを使って他を圧倒したいという考えにどうしても帰結してしまう生き物が我々である。このことは、エゴイズムや恐怖に突き動かされた人間の暴力性のあらわれであり、戦争がなくならないのも、人間のこの負の一面が作用しているからだ。
天才的な科学者でありリーダーでありながら、マンハッタン計画の実行と原爆投下のなかでは、オッペンハイマーとて数えきれないほどの人間のうちのひとりに過ぎなかった。彼自身はある時まで万能感を抱いていたかもしれないが、トリニティ実験が成功し、いよいよ世界で初めて原爆が使われるとなった途端、彼のコントロールできうる領域は瞬く間に小さくなり、そこで彼は取り返しがつかないことにようやく気がつくのである。
原爆の完成と実戦での成果に満足し狂気したひとは、ロスアラモスの職員をはじめ多くいただろう。そうした人々の興奮が足音となって響き、良心の呵責を覚えるオッペンハイマーを襲ったシーンは、誰が何に責任を負うのかという問いをかき消すに十分だった。勧善懲悪とはいかないのである。
映画のエンディング、オッペンハイマーとアルベルト・アインシュタインの会話から、痛いほどの救いのなさを感じた。宇宙の真理に手を出してしまった人間の絶望だった。しかし、たとえ映画のなかに救いはなくとも、それはスクリーンの外に委ねられたのではないかと思うと、被爆国に住む日本人にこそこの映画は見られるべきなんじゃないかと思う。


bg

Driving Home for Christmas

bg
#ふたご座流星群

bg
パリを出発、アフリカの砂漠を走り抜けて大西洋に面したセネガルの首都ダカールにゴールする、パリダカの通称で知られる1万5000kmにおよぶ過酷な自動車ラリーの模様を、日本人チーム「ACP」のプレス車に乗って取材・撮影している。
音楽も手がけた宇崎竜童のナレーションは、淡々としながらも冷たさはない。監督の原田は、観る側にいやらしく擦り寄ることも、何かを大袈裟に煽ることもせず、冷静で、少し突き放しつつ、芯の部分には被写体や映画への熱い思いがある、そんな作品に仕上げていた。
競技中の事故も多く、なかには日本人ライダーの死、さらにラリー創始者ティエリー・サビーヌのヘリコプター墜落死という痛ましい出来事もあったが、御涙頂戴にならず、厳しくも清々しい眼差しがフィルムから伝わってくる。
本作の冒頭で、こんなフレーズが語られる。「なぜパリダカなのか。なぜ冒険なのか。なぜ山に登るのか。すべて同じ質問である。登山家ヒラリーの答えは、『そこに山があるから』だった。」
「なぜ山に登るのか。そんなことを聞くならそこに山があるから自分で登ってみろ。ヒラリーはそう言って、尻の重い質問者に冒険を促したのだと思う。」
「なぜパリダカなのか。そうたずねる代わりに、私はプレス車に乗って映画づくりの旅に出た。3人のカメラマンだけを、クルーとして連れて。」
荒涼とした道なき道を猛スピードで疾走し、競技者のみならず自然とも七転八倒し、食うもの食わず寝る暇惜しんで疲労困憊になりながら、何十メートルもの砂丘めがけて突っ込んでいく、おおよそ合理的な説明のつかない行いをしている人間を被写体とするということへの、尊敬と覚悟のようなものを感じる言葉だ。
映画監督をこう評するのはおかしいけど、自らの熱い「映画道」のようなものをしっかりと持っていた。そしてどこかジャーナリストのような冷静さ、厳しい批評眼もあった。内に異なる温度感を持った映画人だったように思う。



bg


A Hazy Shade of Winter

bg
2007年、いまのところ人生最後のガラケー「Media Skin」の、130万画素CMOSの味わい。いまじゃローテク、どこかシュール。なんとなく絵に近い。


bg


bg
この頃、日本企業はアメリカの不動産をはじめ、ハリウッドのコロンビア・ピクチャーズ、MCA(ユニバーサル・スタジオ)などの企業を軒並み買いまくっていた。
プラザ合意により引き起こされた金余りは、のちに泡のようにはじけてバブル経済と呼ばれることになる。当時の日本人の肥大化した万能感が他国のプライドを踏みにじり、相当な反感を買っていたであろうことは容易に想像がつく。
21世紀も四半世紀を過ぎようとしているいま、日本における他国の不動産購入が問題視されている。その不安と懸念は分からないでもないが、いったいどの口が言うのかねえ、と思わないでもない。
写真は、1990年代の前半に撮ったもの。いまから30数年前、このビルの近くにあった紀伊國屋書店にはよく行ったものだった。インターネットがなかった時代、在留邦人にとっての貴重な情報源だったのだ。その書店も、いまでは場所をグランドセントラルに移していることを、いま検索で調べて知った。


bg


bg

メモリーグラス

bg
日頃「〇〇世代」的な表現に馬鹿馬鹿しさを感じているけど(生まれてこのかた、自分のことを「氷河期世代」なんて大雑把な括りで思ったことは一度もない)、この「高市バブル首相説」には納得してしまう。そういう視点で見ると、腑に落ちることが多いから。
たとえばトランプの横で大いにはしゃいでいたのは、お立ち台で踊っていた頃の名残。
「働いて、働いて」の発言は、リゲインのCMが象徴する「24時間戦えますか?」の発想から。
おまけに、変な期待感に突き動かされた異常なまでの株高。
大規模な財政出動は恩師の安倍晋三にならってのことのように見えるが、彼女の場合は青春時代の泡銭感覚からきているのかも?と勘繰ってみたり。
彼女をジェンダーの観点、もしくは保守派の側面で云々することに世の中忙しいようだけど、なるほど、あの周囲がヒヤヒヤするほどのイケイケ感は、たんなる政治的パフォーマンスというわけでもなく、バブル世代ゆえの「恒常的な躁状態」とする説は、高市評としてもっとも支持できるものではないか。
私自身は、バブルのある種の恩恵を直にこうむった世代ではなく(ここでいう世代は、大した社会的地位もなく遊びまくっていた当時の20代)、あの頃まだ子供だった。熱を帯びたギラギラとした時代の空気を肌で感じながら、浮かれた大人たちを冷めた目で見ていた記憶がある。そしていまも、どこかそれに似た心境にある。

bg
SF映画のセットのなかにいるようでただでさえ気持ちは上がるが、YMOファンにとっては、鋤田正義が撮ったトランス・アトランティック・ツアーのオフショット写真でもおなじみの場所であり、今年発売されたブルーレイにも使われている、いわば「聖地」のひとつ。ここをあの3人が通ったんだと思うだけで胸熱の体験であった。
写真集『YELLOW MAGIC ORCHESTRA x SUKITA』で見つけた一枚。細野さんと教授、後ろには矢野さんか?あまりに若々しくて、その場にいたわけでもないけど感傷的になる。異国を巡るツアーでの新鮮な経験、YMOが社会現象となる直前の、未来がまだ決定づけられていない感じが伝わってくる。
同時に、異なる方向に伸びては交錯するエスカレーターが、メンバーやスタッフそれぞれの将来の軌跡を示しているようでもある。
エスカレーターも空港も通過点。ある時は同じ場所を目指し、またある時は違うところに旅立っていく。解釈次第でいろんなイメージがわくのも写真の楽しみ方のひとつだ。



THE END OF ASIA

bg
盟友ポール・マッカートニーもいまや83歳の立派なおじいさん。ジョンがどんな年の取り方をしたかを想像するのも一興だろう。40で鬼籍に入ったのは、やはり早過ぎた。
そんなジョンとポールを写した大好きな写真。撮ったのはポールの妻だったリンダ・マッカートニー。音楽史に残るアーティストも、こうして見ると純粋な音楽好きの青年。リンダは親しく心の通った近しいひとの愛おしい表情を撮るのに長けたフォトグラファーだ。
オノ・ヨーコとの子供であるショーンもバースデーを迎えたことになる。親子そろっておめでとうございます。愛ある誕生日を。


Love

bg


bg

The Doo-Bop Song

bg
有名映画監督グイド・アンセルミが、作品にも人生にも行き詰まり、プロデューサー、女優、妻、愛人、記者たちがそんな彼を容赦なく追い詰める。四十を過ぎた男盛りの伊達者イタリア人の詰んだストーリーだが、全編にわたり諧謔に満ちており、賑やかなラテンの風が吹いているようである。
個人的にもなんか既視感がある世界だな、と思ったら、これはライターズ・ブロック、いわゆる作家やクリエーターのスランプのように見せかけていて、実は「中年の危機」に陥った男の話なのだと気がつく。
八方塞がりで、出口を探すも見当たらない。どうすればいいんだ?と途方に暮れることは長く生きたものだったら程度の差こそあれ経験があるというもの。しかし、出口を探せば探すほど、何かに救いを求めれば求めるほど、迷ってしまうものなのである。
いよいよ逃げ場がなくなったグイドが最後に掴んだ「人生は祭りだ」という言葉は、いままで出会った人々、過ぎ去った時間、そこにあるものたちを受け止めよというメッセージにほかならない。救世主はいない。己を救うのは自分だ。
グイド役のマルチェロ・マストロヤンニのかっこいいこと、妻を演じたアヌーク・エーメをはじめ出てくる女性が肉感的でエロいこと、そんな個性豊かな登場人物を白黒の世界でまとめ上げた映像の美しいこと。映画人をはじめ評価の高い作品だが、たしかに一見の価値はある。特に中年のご同輩にはおすすめしたい。


bg
"Rehab"は、リハビリ施設への入退院を繰り返していた彼女の経験からの歌。
みんなリハビリに行けってうるさいけど、行くもんかって言ってやった。
軽やかに歌ってるけど、「酒なんか飲みたくない」「ひとりでいいから友達が欲しい」と、なんだか無視できない歌詞も出てくる。
ひとの幸、不幸は他人が決めるものではないけど、あなたは歌うたっていて良かったじゃない、と伝えたくなる。

Rehab

bg
関係者パスで行列をスルーして入場できることは特権でもなんでもない。一般のひとが楽しんでいる横でせっせと働いているのだから。
しかし、ひとが楽しんでいるのを見るのは、それはそれで楽しいことなのだ、ということを今回知った。
家族連れ、夫婦、友達同士、老若男女が集まり、それぞれが充実した時間を過ごす。なんて素敵なことなんだろう。
子供の頃からディズニーランドが嫌いだった。あんな子供騙しに何を騒いでいるのか。理解できなかったし正直小バカにしていた。
だけど、ひとの楽しみにケチをつけることこそ、バカバカしいことなのだ。
万博も行く前は(バカにはせずとも)割と冷めた目で見ていたけど、会場で、あるいは行き帰りの電車のなかで、たくさんのひとが笑っているのに気づいた。そんなひとたちが、とても愛おしい存在に感じた。
歳を取るということは、許せなかったものも許せるようになるということなのかもしれない。


bg
風が気持ちいいが、日差しは刺すように鋭い。


bg
たしかに万博会場の主役は木製の大屋根リングであり、実物の存在感は圧巻の一言。トリノにあったフィアットのリンゴット工場の屋上テストコースを彷彿とさせる。


bg


aqua

bg
メディアも「災害級の暑さ」と注意を促すが、この時期に大地震など起これば……想像するだけで嫌になる。
先日、太陽光発電のモニター募集を断ってしまったことを少し後悔している。これから必要なのは、自家発電かもしれない。


bg
生きてるとは食べること。
食べ放題讃歌とは人生讃歌。

ヨーデル食べ放題

bg
冷たいとは「爪が痛くなるほどの刺激」に由来するらしいが、指がちぎれそうなぐらい冷たかったのを覚えている。
アサバスカ氷河は、北米でもっともアクセスしやすい氷河と言われており、最寄りの観光センターから、巨大なタイヤのついた特殊車両に乗って氷河の上まで連れて行ってくれる。
2つの岩山の間から流れ出てくるような文字通りの「氷の河」。その一部は氷から水へと姿を変え、氷面の窪みに川をつくり、勢いよく流れ落ちていた。訪れたのは快晴に恵まれた夏の日だったにもかかわらず、吹く風もけっこうひんやりしていた。日がかげれば寒さすら感じるはずだ。
驚くのは氷河の大きさだ。アサバスカ氷河は「コロンビア氷原」の一角で、あの山の向こうには東京23区のおよそ半分の300平方キロを超える「氷の原」が広がっているらしい。しかも氷の厚さは300メートル以上もあり、東京タワーが収まりそうな深さなのだ。世界にはもっと大きな氷河があるとはいえ、日本で暮らしていると感覚的に想像がつかない。
そんな巨大な氷の塊も、急速に規模を縮小しているとか。たしかにネットで最近の写真を見てみると、ずいぶんと小さくなったような気がする。
最近思うに、「地球温暖化」というネーミングは状況を的確にあらわしていない。気候が暖かなことを温暖というのだから、「地球灼熱化」の方がより実態に近いのではないか。
「global warming」ではなく「global warning」、地球からの大いなる警告だとすると、連日のうだるような暑さもより切実に感じられる。


bg

チューブラー・ベルズ(パート1) (2009年ステレオ・ミックス)

bg
必ずしも標高が高いほど登山の難易度が上がるわけではない、とことわった上で、自分の過去最高峰登山は標高3033mの「仙丈ヶ岳」。余談だが富士登山は「5合目まで」で、5合目以上のハゲ山なんかより自然が豊富で実に楽しい登山だった。
3000m級とそれ以下の山での顕著な違いは眺望にある。なかでも南アルプスの仙丈ヶ岳からのぞむ富士山と北岳(3193m)、国内1-2を並んで拝めるその景色は筆舌に尽くし難いほど美しかった。鷲が羽を広げたような雄大な北岳の向こうに、均整な円錐形が鎮座する独立峰・富士。神々しいとはまさにこの景色のことである。
頂上直下の山小屋で迎えた朝には眼下の雲海の波に心を奪われ、前の晩には、氷河地形の「カール」の上に月がのぼり、異星にでもいるんじゃないかという感覚におそわれた。山頂付近では雷鳥と邂逅することができた。
ネットでは分からないことが、山にはたくさんある。AIの時代にあって、フィジカリティを取り戻すことはより重要になってくるように思える。







bg


Fly Me To the Moon (In Other Words)

bg
圧倒的な東京感を放つぷにぷに電機。せめて心地いい曲で涼やかに。

君はQueen

bg
この季節、特に今日8月6日という日に、ごく自然に、決して軽々しくなく、多くの日本人の耳や心に向けられる言葉。しかし、いったい誰の、なんの過ちなのか、考えたことがあるひとはどれほどいるか。
加藤典洋の『戦後入門』は、日本と世界、そしてアメリカとの間で、複雑に絡み合う歴史の糸を丁寧に解きほぐしてくれる名著だ。
入門なんて妙にへりくだっているタイトルだが、新書にもかかわらず600ページを超える大作であり、教科書には書かれていない、先の世界戦争とその後のありようが詳細に記されている。
日本が抱える対米従属、ねじれの問題に真摯に向き合った一冊としておすすめしたい。


bg
その舞台を実際に体感したのはまだ若い頃で、当時はせいぜいファン歴10年ちょっとではあったけど、若造なりに感慨無量だったことは言うまでもない。とにかく鳥肌ものの経験だった。
観戦の地はパリ、シャンゼリゼ大通りを往復するゴール地点。彼の地がビッグイベントの舞台装置という機能を持つことは、この前のオリンピックを見れば誰もが納得するはず。文字通り“フランス一周”を意味するツール(Le Tour de France)の掉尾を飾るにふさわしいロケーションである。
シャンゼリゼの歩道の観客エリアにひとり陣取り待つこと数時間。近郊からスタートした選手たちがそろそろパリにやってくるかな、という気配は周囲のざわめきで察知。まずはスポンサー各社の広告車両が通過。そして大通りの彼方から響めきが波になってこっちにやってくると思ったら、テレビ中継で見慣れた先導車両、そしてバイク(モーター付き)が、かなりのスピードで迫ってきてはあっという間に通り過ぎた。
間髪入れずに、色彩の群れが一筋になって猛スピードで目の前を流れた。とても人間が動力源とは思えない速さで、色とりどりのユニフォームに身を包んだライダーたちが走り去っていった。これが憧れのツールか、これが自転車レースの最高峰か。若造は若造なりにその光景を胸に刻んでいた。
ただ夢は十分にかなえられたとは言い難かった。ゴールのパリは特別な場所だが、ツールの本当の魅力は、極彩色の選手やバイクとフランスの田舎道、アルプスやピレネーの険しい山々が織りなす一大スペクタクルにある。あれ以来、キャンピングカーでツールを見てまわりたいという夢を持ち続け、もう四半世紀以上がたってしまった。
昨日パリで終わった第112回ツール・ド・フランスで、タデイ・ポガチャルが4回目の総合優勝を飾った。あとひとつでミゲール・インデュラインやベルナール・イノーらの大記録5勝に並ぶが、ポガチャルはまだ26歳だというのだから驚くほかない。
時代は変わり、活躍する選手も様変わりしたけど、ツールのおもしろさは変わることがない。





CHASER

bg
当たり前だけど、植物は生き物。その塊が森になる。
こんなにも自分が森に遠いところにいたんだと思い知った。それは物理的な距離ではなく、心の距離、生き物である自分の「生」自体との距離。畏怖の念とは、こんなことを言うのだろうか。


bg

すばらしい日々

bg


bg


Over the Rainbow
