人気
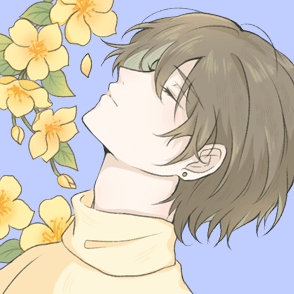
大介
-----------------------------------------
『気配の断章』
Ⅰ章 〜記憶の棲み処〜
この部屋は、
時が止まったまま、
誰かの記憶を抱えている。
もう誰のものでもないのに、
誰かの気配が
まだ、そっと息づいている。
それは声ではなく、
名を持たぬ呼吸のように
壁の繊維に染み込み、
光の粒子に紛れて
いまも漂っている。
Ⅱ章 〜沈黙の層〜
時はここで
まっすぐには進まない。
剥がれた壁紙の下に
幾重もの季節が折り重なり、
沈黙の層となって
床の軋みに宿る。
私は歩く。
けれど、歩くたびに
誰かの足音が先に鳴る。
それは私か、
それとも、
私よりも前にここを歩いた
無数の「私たち」か。
記憶は、
ひとりのものではない。
この空間に触れるたび、
私は"私"でなくなり、
誰かの夢の続きを
そっとなぞっている。
やがて、
私の影もまた
この部屋の一部となり、
未来の誰かが
「気配」として
私を見出すだろう。
Ⅲ章 〜時の外側〜
この空間は
終わることなく
誰かの存在を、受け入れてゆく。
そして私は、
名でもなく、声でもなく、
ただ、触れられぬものとしてここにある。
誰かが
まだ知らぬまなざしで
この部屋を見つめるとき、
私は
揺らぎのように
その瞳に映るだろう。
それが気配と呼ばれるなら、
それでいい。
私はもう、
時の外側で
言葉にならぬまま
在り続ける。
-------------------------------------------
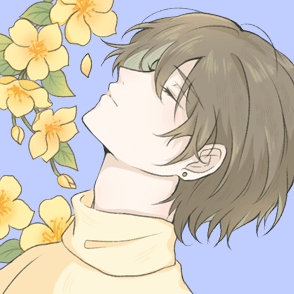
大介
------------------------------------------
『深淵を抱いて』 〜風の日の記憶〜
十一月一日 曇りのち風
朝、窓を開けると、風が枝を撫でていた。
その音を聞いているうちに、ふと、昔の夢に手を伸ばしていたことを思い出す。
届かぬと知りながらも、掌には、触れそこねた時間の名残が残っていた。
確かにあったはずのもの──それは今では輪郭を失い、言葉の奥に沈んでいる。
けれど、その沈みは終わりではない。
それは、音のない対話の始まりだったのかもしれない。
昼過ぎ、散歩の途中で、ふと立ち止まった。
深淵のような静けさのなかに立っていた。
ようやく、自分の影と向き合うことができた。
それは、私が期待していた"私"ではなく、
私自身がずっと恐れていた輪郭だった。
踏み出せずにいた沈黙のなかに、
それでも在るという声が、確かに潜んでいた。
その声に耳を澄ませると、
水面に映る顔が、傷ついたままであることに気づく。
けれど、その瞳だけは、初めて私自身を見つめ返していた。
芽吹きとは、新たな力を得ることではなく、
沈黙の奥に潜む、微かな光に気づくこと──
そう思えるようになった。
夕方、部屋に戻ってから、静かに机に向かった。
喪失の余白には、まだ名づけられていないものが、
静かに、けれど確かに息づいている。
私はそれを抱いて、歩き出す。
輪郭のない風のなかを、
誰にも知られず、
それでも確かに、
歩みが残る場所へと。
夜、風がまた窓辺を撫でている。
その音を聞きながら、今日という一日が、
少しだけ、私を変えてくれたような気がする。
──この風の音が、あなたにも届く日が……きっと。
------------------------------------------
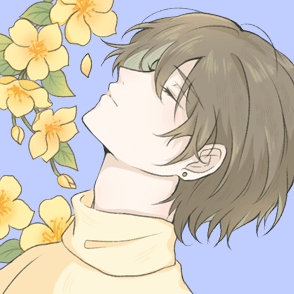
大介
------------------------------------------
『静けさの残響』
第三章:「音のない喪失」
夢が、
遠ざかっていったあと、
時は、静かに積もっていた。
午後の光は、
あの日と同じように、
庭の石を照らしていたけれど、
咲いていたはずの花の影も、
もう、そこにはなかった。
わたしたちは、
手にしたはずのものが、
指先から、こぼれ落ち、
薄れていくのを、ただ、見ていた。
こぼれ落ちた夢の残響は、
夕暮れの空気のなかで、
ひとしずくの静けさとなって、
静かに、消えていった。
そして、
その静けさだけが、
ただひとつ、
手に残るぬくもりのように──
今もなお、
わたしのなかに、
息づいている。
------------------------------------------
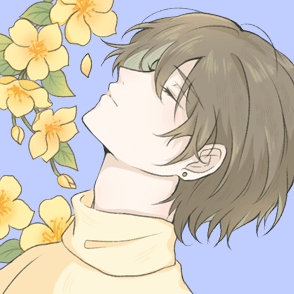
大介
---------------------------------------
『四月十二日』
三月二十日 晴れ
佐伯と神田の裏通りを歩く。風がやわらかく、街の埃さえ、春の光に紛れていた。彼は少し痩せたようだ。頬のあたりに、何かを拒むような翳りが浮かんでいた。歩きながら、ふと立ち止まり、私に言った。
「自分というものが、誰かの瞳の奥底にだけ、あるような気がするんだ」
その言葉が、風に紛れながら、耳の底にそっと残った。私は何も言えなかった。ただ、彼の横顔を見つめながら、どこか遠くのものを見ているような気がしていた。
三月二十七日 曇り
佐伯の部屋を訪ねる。机の上に鏡が置かれていた。彼はそれを見ながら、ぽつりと言った。
「鏡って、揺れるだろう。光が少しでも揺らぐたび、鏡のなかの僕も、形を変えていく。……僕は、そんなものに頼って、自分を見てきたのかもしれない」
彼の声は静かだった。まるで、誰かに聞かせるためではなく、自分の深みに向かって、落ちていくような話し方だった。私はその言葉を受け止めきれず、ただ窓の外の曇り空を見ていた。
四月五日 雨
綾子さんと喫茶店で会う。彼女は佐伯のことをあまり語らなかった。ただ、彼の手紙を一通、私に見せてくれた。
「夜になると、すべてが静かになる。鏡も、僕も。何も映らないそのなかで、ふと、自分がほどけていくような気がする……」
文字は細く、震えていた。綾子さんはそれを読み返しながら、何も言わなかった。私はその沈黙のなかに、彼女の悲しみが静かに横たわっているのを感じた。
四月十二日 晴れ
佐伯が姿を消した。下宿の部屋には、開かれたままの鏡と、誰も座らぬ椅子とが、ただそこに置かれていた。窓から差す光が、鏡の表面を静かに照らしていた。
私はその部屋にしばらく立ち尽くしていた。春の風が、誰にも届かぬ声を、そっと運んでいた。彼がいた気配だけが、部屋の隅に残っていた。
四月十五日 曇り
綾子さんから便りが届く。「彼の言葉は、誰にも届かなかったのかもしれません」とだけ書かれていた。
私はその一文を何度も読み返した。そして、佐伯がいつか呟いた言葉を思い返していた。
「僕は 本当に 存在しているのだろうか──。僕は自分の声が 誰かの口から響く事だけを求めていた……」
その声は、私のなかで、静けさとともに、かすかに揺れていた。春の終わりの風が、窓の隙間から吹き込んできた。
四月二十日 晴れ
今日は、佐伯の部屋の前を通った。誰もいないはずなのに、ふと、鏡のなかに彼の姿が映っているような気がした。もちろん、それは錯覚だったのだろう。
けれど、あの椅子はまだそこにあった。誰にも座られず、ただ静かに、春の光を受けながら。
------------------------------------------
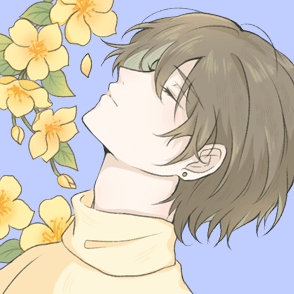
大介
-----------------------------------------
『風と光による変奏曲』
第一章 〜遠い水面〜
彼女の眠りは、遠い水面のようだった。
そこへは、誰の声も届かぬまま、日々が静かに過ぎていった。
夜ごと、
彼女の奥深くにひそむ裂け目が、
音もなく、痛みを育てていた。
私は、それを傍らで、ただ見守っていた。
第二章 〜光のなかの彼女〜
初秋の風は、まだ遠くにあった。
窓の外には、風ひとつない夕暮れがひろがっていた。
薄紅の光が、彼女の頬に、そっと触れていた。
その光のなかで、彼女は、何か遠いものを見ていた。
それは、私には触れえぬ場所であった。
第三章 〜無音の譜面〜
私は、
彼女の横顔を見つめながら、
その痛みのかたちを、思い描こうとしていた。
けれど、それは誰にも読めぬ譜面であり、
彼女の中にだけ響く、無音の旋律だった。
第四章 〜残された部屋〜
やがて、
その痛みは、彼女を越えて、
静かに、空へと昇っていった。
私は、残された部屋のなかで、
夕映えの雲の切れ間に、
彼女の歌声を探していた。
第五章 〜季節の巡りと忘却〜
そして季節は、
彼女の淡い気配を抱えながら、静かに巡っていった。
いまはもう、風も光も、
彼女の名を知らなかった。
第六章 〜風のなかの旋律〜
彼女の、
見えない痛みも、
すでに、ここにはない。
けれど、
初秋の草むらに立つと、
痛みを孕んだ風が、私のなかを通りすぎてゆく。
風が通りすぎるたび、
私のなかで、彼女の旋律が音もなく揺れていた。
---------------------------------------------
最早、すっかり堀辰雄だな…(-ω-)
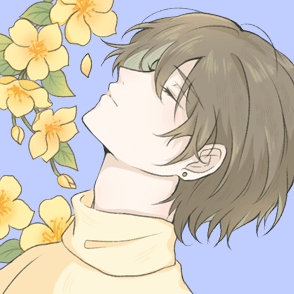
大介
------------------------------------------
『軋む灯火』
Ⅰ 〜夢の残骸と影の存在〜
街は、朝の光を拒むように、砕けた夢の残骸を吐き出していた。
そのなかを、無数の足音が通りすぎてゆく。
私は、それらの音に混じって、いつしか自分の輪郭を失っていた。
ただ、誰かの眼差しに映る、淡い影として、そこに在った。
Ⅱ 〜灯火と声の侵入〜
電線のうえに吊るされた月は、青ざめていた。
それは、欲望の腐蝕に染まった灯火のように、夜の空に、静かに揺れていた。
私は、その灯火の下で、他人の言葉を、舌の裏で転がしていた。
それは、やがて誰かの声に変わり、私の喉から、夜の冷気に溶けていった。
Ⅲ 〜機械化された身体〜
「君は、実に都合がいいね」
その声は、私の皮膚を剥ぎ、骨の奥に、冷たい歯車を軋ませた。
私は、掌の上で軋む、沈黙の器具となる。
自己とは、通りすぎた風の痕跡にすぎない。
指を伸ばしても、空は、掌を拒む。
Ⅳ 〜問いと残骸の答え〜
そして私は、誰かの設計図に沿って、無音の軌道を、静かに廻りはじめる。
夜の底で、私は、声なき問いを沈める。
「私は、誰の夢を、生きているのか」
その答えは、街灯の下に、錆びて落ちていた。
誰にも拾われず、街の底で軋む歯車として。
--------------------------------------------
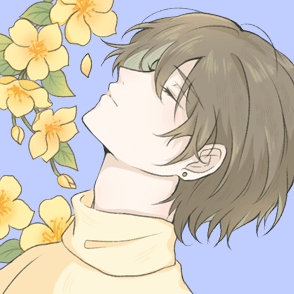
大介
----------------------------------------
『波紋』 〜影の交わるところ〜
Ⅰ 〜午後の町〜
その町では
午後になると 風が止む。
風が止むと
声が よく響く。
舗道を行き交う人々の足音、
誰かが落とした鍵の音、
遠くの教会の鐘の音までもが
水底に沈む鈴のように
静かに、
けれど 確かに
胸に 波紋を描いていく。
Ⅱ 〜光の曖昧〜
その日、
わたしは 駅前の並木道を歩いていた。
銀杏の葉は
まだ 枝にしがみついていた。
空は 薄く曇り、
陽の光は やわらかく
すべての輪郭を 曖昧にしていた。
ふと、
前を歩く ふたりの女子高生の声が
耳に入った。
彼女たちは
ある人物について 話していた。
名は聞き取れなかったが、
その人の仕草や表情、
言葉の端々に
「違和感」を覚えたのだという。
その語り口には
奇妙な熱があった。
わたしは その熱に
なぜか触れたくなくて、
歩幅を ひとつ狭めていた。
彼女たちは まるで
ひとの輪郭を削りながら
自分たちの形を
浮かび上がらせているようだった。
Ⅲ 〜影の交差〜
わたしは 歩みを緩め、
彼女たちの声が 遠ざかるのを待った。
そのとき、
向こうから ひとりの青年が
歩いてくるのが見えた。
彼は
何かを背負っているように
ゆっくりと 歩いていた。
午後の光が 斜めに差し、
彼の背中から 長い影が伸びていた。
その影は
わたしの影と
どこかで 重なった。
わたしは 立ち止まり、
足元を見下ろした。
影が、ふたつ、重なっていた。
どちらが 誰のものか
わからなかった。
ただ、
そこにあるということだけが
胸の奥に 重く響いた。
Ⅳ 〜沈黙の気配〜
ふたりの声が消えたあとも
胸の奥に 忘れかけていたざわめきが残っていた。
わたしは しばらく立ち尽くしていた。
冷たい空気が 頬をなで、
呼吸の音だけが
自分の耳に 響いていた。
町のどこかで
誰かの嫌悪が 音もなく漂っているのかもしれない。
そして わたしもまた
その沈黙の一部だったのかもしれない。
その気配が
空気のように 町の隅々にまで染みわたっている。
けれど
誰も それを口にしない。
ただ、
影だけが
静かに 増えていく。
Ⅴ 〜闇の底で〜
青年は
わたしの前を 通り過ぎた。
そのとき
彼の目が わたしをかすめた。
何も言わず、
何も問わず、
ただ 通り過ぎていった。
その目の奥に
言葉にならないものが あった。
その 言葉にならない深みが
わたしを そっと許していくような気がした。
わたしは 再び歩き出した。
けれど
自分の影が どこにあるのか
もう よくわからなかった。
それは
誰かの影と 混じり合い
ひとつの濃い闇となって
足元に 沈んでいた
-------------------------------------------
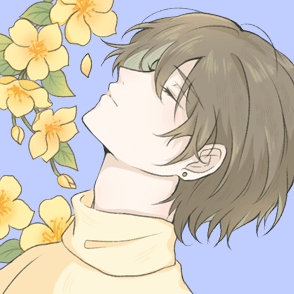
大介
----------------------------------------
『主役という問い』
Ⅰ
人はそれぞれに、
夕暮れの光を追って歩いている。
それが、寂しさの始まりだとは知らずに。
──春の風が、
ひとりの肩をそっとすり抜けてゆくように。
Ⅱ
「わたし」という言葉は、
ときに風に揺れる旗のようで、
その影が、誰かの輪郭を曇らせる。
──そのとき、沈黙が、
足もとに、やわらかく積もりはじめる。
Ⅲ
舞台には、主役しかいない。
誰もが、まんなかに立ちたがり、
誰もが、譲らぬままに。
言葉は渦を巻き、
物語は、行き場をうしなう。
Ⅳ
けれど、「主役」とは、ほんとうは──
語らずとも、そこに在る者。
言葉の消えた舞台に、
ひとり、光を受けとめる影。
Ⅴ
遠くの灯が、かすかに揺れている。
誰かの物語のなかで、
そっと立ちつづけている、私のしるし。
──脇役であることの、
やさしさを、そのとき私は知る。
Ⅵ
「私は、私の主役」
そう思っていた確信は、
やがて問いに変わってゆく。
──それは、ほんとうに
私しか知らぬ物語だったのだろうか。
Ⅶ
主役は、孤高ではない。
共演者の息づかいに耳を澄まし、
舞台の静けさに、身をゆだねる。
──そのとき、物語は、
ふたたび動きはじめる。
Ⅷ
幕が降りるとき、
拍手は、誰に向けられるのか。
それに囚われている主役は、
まだ、物語の途中にいる。
-------------------------------------------
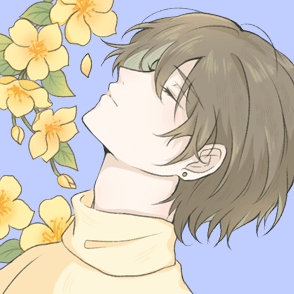
大介
----------------------------------------
『静けさの残響』
第二章:「記憶の綾」
あの夢の話をしたとき、
あなたは、
屋根の色を語った。
わたしは、
揺れるもののそよぎに身をゆだねていたけれど、
あなたは、
風の冷たさだけを残した。
あれは、
同じ夢だった──
そう、ふたりは思っていた。
けれども、
その夢のなかのまどろみが、
ふたりを──
すれ違わせていた。
夢は、
絵のなかで言葉を失ったまま、
そこにあった。
その沈黙は、
見つめるたびに、
かつての彩りを忘れながら、
すこしずつ、
別の絵を描いていた。
それは、もう──
ふたりの絵ではなかった。
----------------------------------------
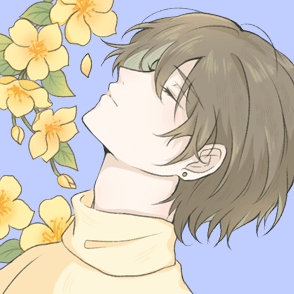
大介
----------------------------------------
『静けさの残響』
第一章:「夢のかたち」
午後の光のなかで──
わたしたちは、
同じ夢を見ていたような、
そんな気配に包まれていた。
それは、
遠くの庭先で、
咲いていたはずの花、
風にほどけた布、
指先に触れかけた記憶の縁。
けれども、
それがほんとうに同じ夢だったのか──
もう、誰にも、確かめようがなかった。
ただ、
その淋しげな錯覚のなかで、
わたしたちは、
目を伏せたままの微笑で交わした約束を、
そっと手にしたような気がしていた。
そしてそれは、
暮れゆく日のなかで、
誰にも届かぬ、
過ぎ去った一片の想いのように、
いまも、どこかで、
ひっそりと、漂っている。
-------------------------------------------
もっとみる 
新着
関連検索ワード
