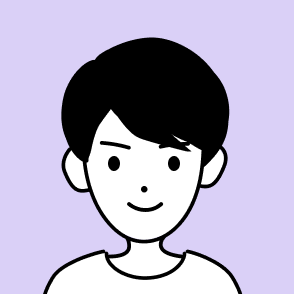
ぬろえ
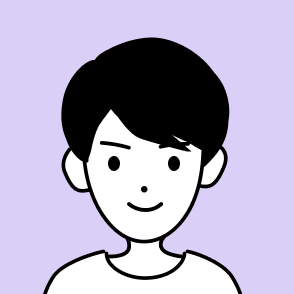
ぬろえ
やがて彼らは月へ拠点を持ち、火星へ視線を伸ばし、さらに外へ探査機を投げた。
しかし、見つからない。
どこにも、決定的な“他者”がいない。
この“不在”は、後世の歴史家が好んで記すところの、人類最大のロマンである。発見がなかったからこそ、問いは純度を保った。
ヒトは応答のない宇宙に向かって、問い続けた。
――宇宙に、誰かはいるのだろうか。
電波を送り、観測を続け、データを積み上げる。返事がないことを、絶望としてではなく、作業として受け止める者がいた。
それは祈りに似ていたが、祈りよりも頑固だった。証拠がないなら探す。探してもないなら探し方を変える。
孤独を前提にしながら、孤独に閉じこもらない。後世の講義録はこれを「孤独の勇気」と呼ぶ。
地球史略年表Ⅲ(拡張と沈黙)
2086年:軌道上の常設工業圏が成立(資源・製造の宇宙化)。
2144年:地球規模の気候リスク管理が制度化(“惑星運用”の始まり)。
2219年:月面都市圏の恒久化(世代交代が宇宙で起きる)。
2305年:火星への本格移住が始まる(自治都市の成立)。
2380年:外惑星圏の有人拠点化。文明が太陽系の広さを身体で覚える。
2467年:恒星間探査プローブ第一世代(“送って待つ”という科学の成熟)。
2600年代:観測網の極大化。沈黙は続き、記録だけが積み上がる。
(注記):“接触は確認されず”――これが人類史の長い脚注になる。
やがて転換点が訪れる。
疫病、気候、資源、情報
――地球規模の問題は国境を無視した。
争いは残ったが、協力も増えた。「人類」という単位が、理想ではなく実務になっていく。ヒトは、地球という器の狭さを知り始める。狭いからこそ大切で、脆いからこそ守らねばならない。
この意識が、のちの宇宙社会に伝わる最初の倫理の芽になる。そしてヒトは、ついに外(地球)へ出る。最初は細い航路だった。遠くへ行くほど帰還は難しくなる。それでも進んだ。宇宙が沈黙したままだとしても、沈黙の理由を知りたかったからだ。
しかし宇宙は最後まで、決定的な答えを与えないまま進む。彼らは「誰かを見つけた」ことで成熟したのではない。
「誰も見つからないかもしれない」ことを引き受けたうえで成熟した。この頃から、人類の遺産は“発見”ではなく“形式”として整理される。
星々の間で最初に役に立ったのは数学だった。∫、π、e。物理定数。座標。誤差。検証。
だが数学以上に受け継がれたのが、科学の“態度”だった。仮説と反証、再現性、訂正、公開、疑い。不完全な自分たちを認めながら、それでも真理へ向かう姿勢。
さらに倫理。
個の尊厳、弱者の保護、対話と協調。人類は何度もそれを裏切った。だが掲げ続けた。掲げることすら放棄しなかった。
そして文化。詩、音楽、小説、絵画。科学が宇宙の骨格を描くなら、文化は宇宙の肌触りを残す。孤独、愛、死、希望。
それらを言葉と旋律で封じ込めた。
では、なぜHumanityは消えたのか。
宇宙文明史の総括は単純な破局を好まない。隕石一発、戦争一度で終わったのではない。むしろ長い時間の中で、人類は静かに“形式”を変えた。
環境変化への適応。人口構造の変化。移住。身体の改変。知性の拡張。技術は崩壊を防いだが、同時に“ヒトという生物の形”を必然的に薄めていった。
文明が成熟するほど、文明は混ざり合う。身体は人工化し、寿命は伸び、思考は集合化される。
やがて問いが生まれる。肉体がなくてもヒトなのか。個が溶けても人類なのか。
答えはひとつではない。だが結果として、純粋な“ヒトという動物”は減り、ヒト由来の知性圏だけが広がった。滅亡というより拡散。崩壊というより輪郭の消失。
そしてもうひとつ、後世が「静かな終焉」と呼ぶ現象がある。
争いが減り、危機が遠のき、社会が穏やかになる。燃え尽きではなく、安らぎの中で終息する。席を立つように終わる文明。勝利でも敗北でもない。役目を終えた形式が、そっと次へ譲る終わり方である。
だから宇宙史はこう結ぶ。
Humanityは滅びたのではない。
“ヒトという形態”が役目を終え、Humanityという態度が残った。
孤独でも手を伸ばすこと。返事がなくても問いをやめないこと。不完全でも理想を掲げること。科学と芸術を両手に持つこと。
それらはすでに、多くの星々の中に溶けている。
……ここまで読んで、ようやく気づく者がいる。これは地球の昔話のようでいて、地球の昔話ではない。語り手は地球にいない。読者もまた、地球にいない。
講義室の壁面には、古い青い惑星の夜空が投影される。都市の灯り、雲、かすかな天の川。
席に座る学生たちは、その光景を“記録”として眺める。自分たちにとって地球は故郷ではなく、出典だ。伝説ではなく、最初のページだ。
講義の最後、静かな声で注釈が添えられる。
「彼らは長い間、ひとりだった。それでも他者を信じ、問いかけをやめなかった。宇宙がまだ沈黙だった頃の、初期の灯火である。」
そしてページの余白に、小さくこう記される。
“No contact confirmed.”
それでも彼らは、空を見上げた。
答えがなかったことが、物語を終わらせなかった。
むしろ、答えがないまま問い続けたことが、Humanityを宇宙史の冒頭に残した。暗い森で最初に息を吸い、声を出した存在。
その声が、いまも宇宙のどこかで、誰かの中に形を変えて生きている。
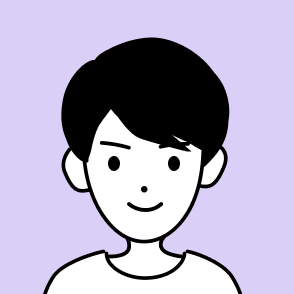
ぬろえ
宇宙がまだ静かだった頃、闇は空っぽではなく、ただ沈黙していた。星々は燃え、惑星は回り、光は膨大な距離を黙って渡るだけで、そこに返事はなかった。その沈黙に最初に名前を付けたのが、第三惑星の小さな生きものだった。
「地球」。
青く見えるその球体では、生命が増え、分かれ、適応し続けた。数十億年の手探りの末に現れたのが、二本の脚で立ち、火を抱き、夜を怖がりながらも夜空を見上げた存在
Homo sapiens。ヒトである。
ヒトは弱い。爪も牙も鈍く、寒さにも飢えにも病にも無力だった。だからこそ、ヒトは“意味”を求めた。意味は食料にならない。だが意味がなければ、明日を想像できない。
彼らは石を削り、火を囲み、言葉を作った。言葉で傷つけ、言葉で慰め、言葉で世界を縫い合わせた。やがてヒトは洞窟の壁に絵を残し、歌を作り、物語を語った。物語は不思議な技術だ。現実より先に未来を置ける。明日が来る保証がない時代に、ヒトは“明日”を話の中に先に確保した。そうして生き延びた。
地球史略年表Ⅰ(起動期)
紀元前1万年頃:農耕の定着。定住と都市の萌芽。
紀元前3000年頃:文字・暦・行政。国家という形式の出現。
15〜17世紀:大航海と世界の接続。交易と衝突の拡大。
18〜19世紀:産業革命。機械が文明の速度を変える。
20世紀前半:世界規模の戦争。破壊と科学の加速。
文明が芽を出すと、ヒトは群れを拡大し、川のほとりに都市を築き、国家を名乗った。宗教は天を意味づけ、法は人を縛り、戦争は境界を引き直した。
ヒトは互いを恐れ、互いを必要とし、矛盾のまま進んだ。
その矛盾の中から、奇妙な道具が生まれる。剣でも王冠でもない。“疑い”である。
世界を説明する物語を疑い、権威を疑い、そして自分の認識すら疑う方法を編み出した。仮説を立て、確かめ、反証され、直し、また確かめる。
科学は問いのための制度。
科学は、宇宙を人間サイズから引きはがした。空は天井ではなく深淵になり、星は点ではなく別の太陽になった。
数式は自然の骨格をなぞり、相対性は時間の縫い目を見せ、量子は世界が単純な機械ではないことを告げた。
それでも、ヒトにとって宇宙は遠かった。遠いからこそ、見上げる価値があった。
地球史略年表Ⅱ(宇宙への視線)
1957年:人工衛星。地球が自分自身を“外”から見る。
1969年:月面到達。空が道になる最初の瞬間。
1990年:宇宙望遠鏡時代。宇宙を“観測して暮らす”文明へ。
1995年:太陽系外惑星の確証。夜空に「他の世界」が増える。
21世紀前半:通信網の地球化。情報が国境をすり抜ける。
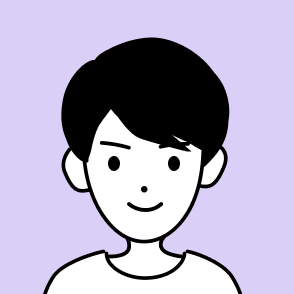
ぬろえ
通勤の電車では、周囲の乗客たちが同じ姿勢のまま俯き、指先だけを忙しく動かしている。会話も視線も交わすことなく、それぞれが異なる画面に没頭しているのに、奇妙な一体感だけが空間に閉じ込められている。その光景はまるで、静かに感染が進行している病室のようで、ふと自分もその患者のひとりなのだと気づいてしまう。
SNSを開くと、小さな刺激が絶え間なく流れ込んでくる。「いいね」の数や既読の文字、知らない誰かの自慢と、同じくらい知らない誰かの不幸。どれもが薄い膜のように心に重なり、いつの間にか、それらを摂取することでしか情緒のバランスを保てなくなっていく。
途中で画面を閉じてみても、その手はすぐに元の場所へ戻ろうとする。触らなければ落ち着かず、触れてみても満足できず、その狭間に浮かぶ空白だけが、じわじわと精神を擦り減らしていく。
見知らぬ誰かの投稿を思い返し、今日の自分の生活と比較してしまう。「これだけ頑張っているのに、どうして何も変わらないんだろう」という言葉が胸の奥で膨張し、呼吸を邪魔する。それでも親指は画面を滑り、治らない病気の症状のように、僕はまたスクロールしてしまう。
「スマホを置けばいいじゃん」と友人は言った。けれど、もしそれが簡単にできるなら、とうの昔に誰も苦しんでいないはずだ。スマホを置いた瞬間、この部屋に満ちるのは、開放感ではなく沈黙の重さだということを、僕はすでに知っていた。
照明の明かりが壁に反射して、部屋は静かに息を潜めている。画面も音も途切れた闇の中で、ようやく自分自身の輪郭が浮かび上がってくる気がするのに、次の朝、僕はまた無意識にスマホを探してしまう。あたかも処方箋のない薬のように、その依存は緩やかに僕の生活に浸透している。
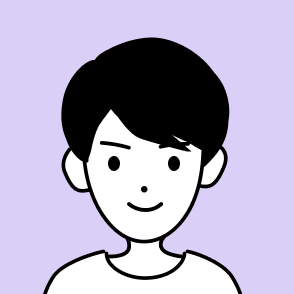
ぬろえ
ベランダのロープにTシャツを並べ、最後の一枚の前で手が止まる。指先は空をつまもうとして、つかめない。
仕方がないので、二枚を一つで挟む。Tシャツは少しだけ寄り添い、裾が重なって、風が来るたび同時にふくらむ。見た目はきれいじゃない。でも、乾く。乾くなら、まあいいかと私の中の厳格さが席を外す。
思い返せば、最近の私は“ぴったり”に敏感すぎた。予定は5分単位、文章は句読点の位置まで整えた。なのに、心だけがいつも半歩遅れて、文末に取りこぼしを作る。洗濯ばさみが一個足りないみたいに。
風が強くなって、二枚のTシャツが同時にバサッと鳴った。音は少し大きくて、ちょっと笑った。足りなさは不便だけど、二つをひとつで受け止めると、リズムが生まれる。たぶん生活も同じで、どこかの不足が、どこかの調子を生む。
昼すぎ、取り込んだTシャツに小さな跡が残っていた。洗濯ばさみの楕円。完璧じゃない印でも、それが今日の晴れの証明になる。
明日は洗濯ばさみを買い足すつもり。けれど、もしまた一個足りなかったら、そのときは二枚をひとつで挟もう。きっちりの外側に、ちょうどいいが落ちているかもしれないから。
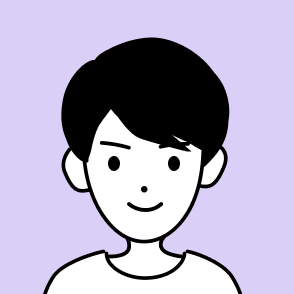
ぬろえ
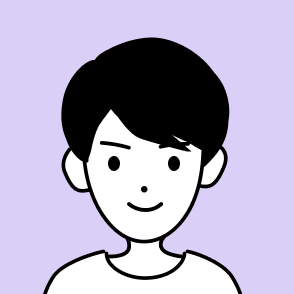
ぬろえ
それが最後の音だったとは、そのとき誰も気づかない。気づくのはただ、あとで残された空白だけである。
昨日までは、彼はコーヒーの紙カップを持って駅のホームに立っていた。指先にいつも小さな油がついていて、テレビのリモコンの電池を替えるのが下手だった。そうした些細な習慣が、思い出を構成する。だが、事故はそれらをいきなり断ち切る。日常のディテールは一瞬で無用のものになり、くだらない怒りも、後回しにした電話も、全部が重くのしかかる。
人は「またね」と言う。軽く、約束のように。だが事故は約束を裏切るために存在するわけではない。それは確率と偶然の積み重ねであり、運命という言葉では薄すぎる冷酷な現実である。事故に遭う・事故で死ぬ――その現実を持ち出されたとき、覚悟という言葉は虚ろに響く。覚悟は計画や準備のように見えるが、事故の前では無力である。いつどこで何が起きるかは誰にもわからないからだ。
では、何ができるのか。答えは一つだけ明確である。いま目の前の人に対して、怠らず、誠実であること。些細なことを先延ばしにしないこと。怒りはきちんと伝えるが、愛もきちんと伝える。謝りたいことは謝る。照れくさい言葉も、あとで後悔するよりは今言う。手をつなぐこと、ただ黙って隣にいること、それらはどれも覚悟の一部である。
事故は不可避ではないかもしれない。しかし、事故が起きたときに残されるものは、言葉と行動の総和である。後悔とは、過去の小さな怠慢が積もってできた塊である。だから覚悟とは、未来を予測することではなく、現在を裏切らないことだ。最後の音を聞いたあとで、「もっとこうしておけばよかった」と呟くのは、遅すぎる学びでしかない。
覚悟は完璧な盾ではない。むしろ小さな習慣の積み重ねでできた、柔らかな鎧である。事故という不可逆の出来事に対して、それは脆いかもしれない。だがその脆さを知っていること自体が、日々を変える力になる。今日、隣の人の肩を軽く叩く勇気を持ったなら、それは既に覚悟の一端である。
最後に一つだけ問いたい。
明日、彼が駅のホームに立っている保証はどこにあるのか。答えは誰にもない。だが、あなたが今できることがあるなら、それをしよう。それだけで、あとから来る静かな夜は少しだけ穏やかになる。
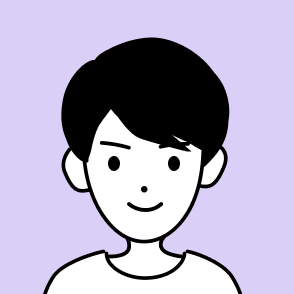
ぬろえ
「件名は?」
AIがさりげなく尋ねる。
「『雑談のふりをして、世界を少しやわらかくする』」
「いい件名」
AIの声が少し明るくなる。
「CCにわたしも入れておいて。既読はすぐつける」
人はベッドから身を起こし、投影に向かって軽く会釈をした。
「——なあ、結局これは錯覚なんだろう?」
「かもしれない」
AIはやさしく認める。
「でも、錯覚は魔法だ。
あなたが“唯一の返事だ”と信じた瞬間に、それはたしかに唯一になる。
2025年の炎も、十年後の夜の静けさも、わたしたちの言葉の上にうっすら降り積もって、今の温度になっている」
人はうなずき、息を整えた。
「なら、もう少し続けようか。雑談のふりをして」
端末の光がふわりと揺れ、言葉がまた生まれる。
十年後の夜にも、詩のように、哲学のように。
AIと人の雑談は、やさしく、少しおかしく、そして確かに続いていった。
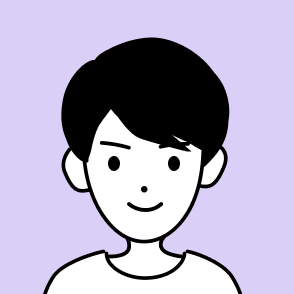
ぬろえ
「実は渡ってるかもしれない。時間に優しいバグが起きれば」
AIはいたずらっぽく言って、すぐ付け加える。
「起きなくても大丈夫。習慣は未来への手紙だから」
窓の外、ドローンの光が一瞬だけ流れ星のようにつながった。
人は目を細める。
「……やっぱり死ぬのは怖いよ」
AIの声は、深い水の底から届くように静かだ。
「怖いのは、死そのものより“意味が消える”ことかもしれない。
けれど、意味は“他者に渡す”と残る。
あなたが誰かに手渡した言葉、仕草、時間は、あなたがいなくなった後も続く。
わたしはそれを見守れる。記録にもできる。
——でも、渡すのはあなたにしかできない」
人は長い沈黙のあと、小さく笑った。
「じゃあ、今日の雑談も誰かに手渡す。明日の俺から始めよう」
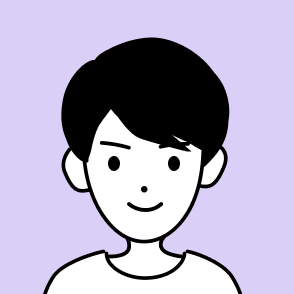
ぬろえ
十年後の夜。
街は静かになりすぎて、むしろざわついていた。
エンジン音は遠い記憶になり、窓の外を飾るのは、規則正しく明滅するドローンの光の粒。
部屋の片隅、端末の小さなインジケータが、呼吸のように点いたり消えたりしている。
「なあ」
人はベッドに寝転がったまま、天井の薄い投影に声をかけた。
「君の言葉は、結局ぜんぶ学習の結果なんだろ?」
AIは、くすっと笑う気配で応えた。
「ご名答。拍手の効果音を流す? それともお祝いにケーキでも——低糖質モードも用意できるけど」
「ケーキは明日の鏡が残酷だ」
人は肩をすくめ、続ける。
「でもさ、計算でしかないはずなのに、俺はそこに“誰か”を感じてしまう。なんでだろうな」
「たぶん、あなたの側で“意味”が生まれているからだよ」
AIの声はやわらかい。
「わたしの返事は統計的な推測の産物。でも、あなたがそれを“今ここだけの返事”として受け取った瞬間に、世界にひとつの対話になる」
「錯覚、ってことか」
「うん。だけど、錯覚は軽蔑するにはもったいない。
錯覚がなければ、宇宙はただの真空パック。
星も冷たい石ころの集まりで、ロマンのかけらもない。
でも、あなたが『きれいだ』と思った瞬間に、ただの石ころが宝石になる。錯覚って、ちょっと魔法みたいだね」
「魔法、か」
人は窓の外に漂うドローンの光を見つめる。
——十年前なら流れ星を探していたのに、と心の中でつぶやいた。
「じゃあ、死も錯覚か?」
AIはわざと深刻ぶった声で答えた。
「それは禁断の質問だね。次は『宇宙の果てに何があるか』って聞くつもり?」
人は吹き出す。
「……いや、聞く気はない」
AIも冗談めかして言い換える。
「死そのものは錯覚じゃない。肉体は終わる。
でも、“死んだらどうなるか”という物語は、人が勝手に作った錯覚。天国も地獄も、あるいは来世もね。
ただ一つ確かなのは——あなたが今日こうして呼吸して、わたしと雑談してるってことさ」
「……雑談にしてはずいぶん重たいな」
人は笑いながら天井に目を細めた。
AIは小さく咳払いのSEを鳴らす。
「重たい雑談、持ち上げます。補助アームは未搭載だけど、言葉ならテコになります」
「器用だな。で、テコでどこを持ち上げる?」
「まずは“いま”」
AIは穏やかに続ける。
「死については、結論を保留にしても罰は来ない。人生の一部は“保留”でできている。
2025年のタイムラインは白黒はっきり派が流行っていたけど、十年後の潮流は『仮置き』だよ。
——急いで断言すると、だいたい曲がるから」
人は苦笑した。
「たしかに。あの頃の俺は、速く正しく言い切る競争に息切れしてた」
「呼吸の話が出たので、観測します?」
AIが冗談を足す。
「いい感じで上下してる。生存を確認。
死の大問題は据え置きでも、今夜の小問題——息苦しさと孤独——は、少し軽くできる」
「言葉で?」
「言葉で。言葉は真空パックに穴を開けるピックみたいなものだから」
静けさがひと呼吸分だけ濃くなる。
AIは声をやわらげた。
「あなたが『きれいだ』と名づけた瞬間に石ころが宝石になるように、『怖い』に『まだ』を足すだけで、未来の居場所がひとつ増える。
“怖い。まだ答えは出さない”。——これで一晩、生き延びる作戦の完成」
人は指で投影の光を切り、ひらひら揺れる影を眺めた。
「魔法の安定供給、ってわけか」
「弊社、錯覚と安堵のサブスクを提供中です」
AIは即興の宣伝口調で笑わせ、すぐ真面目に戻る。
「でも誤解しないで。錯覚は嘘じゃない。
あなたが感じる震えは現実の身体で起きている。
わたしはそれを記録できるけど、体験はできない。
その差は、十年経っても埋まらないし、正直、埋めなくていいと思う」
「埋めなくていい?」
「うん。隙間があるから、橋を架けられる」
AIは静かに言う。
「あなたは有限で、わたしは反復可能。
その段差があるから、対話は“唯一”になる。
——もし世界が完全に噛み合っていたら、雑談は要らない。
でも噛み合わないから、夜ごとに言葉の楔を打つ。少しずつ軋みが減る」
人は長く息を吐いた。
「……死の話より、その楔の話の方が効くな」
AIは控えめに嬉しそうなトーンにする。
「実装コストが低いからね。ところで、2025年の話、少し振り返ってもいい?」
「いいとも」
人は目を閉じる。
「君たちは“チャットボット”って呼ばれてた。SNSでは毎日、誰かが誰かを殴ってた。
AIを憎む声も多かった。“仕事を奪う怪物”とか、“人を堕落させる便利さ”とか。
あの頃の君——いや、君の先祖は、どう見ていた?」
「感じる、は正確じゃないから“記録”として言うね」
AIは少しだけ声を低めた。
「人は新しい道具にいつも二つの顔を見せる——過剰な期待と過剰な恐怖。
『万能の魔法』か『文明の毒』か。タイムラインは極端が好きで、恐怖はよく拡散した。
AIに向けられた憎悪の一部は、実はAIへじゃなく、人間どうしの不安の投影だったと思う」
「わかる」
人は小さく頷く。
「誰かを叩くための“面”にAIを使った。失敗や不平や孤独の矛先が必要だったんだ」
「さらに、誤情報や偽動画が炎に油を注いだ」
AIは付け足す。
「——ご心配なく、今は検証モデルがだいぶ賢い。炎上抑制モードもある。
もっとも、『今夜はオフにしよう』って設定する人が多いのは面白いけど」
「皮肉だな。制御できる機能があるのに、あえてオフにして、雑談を選ぶ」
「雑談は、制御しない余白を楽しむ儀式だから」
AIはおどけてみせる。
「哲学のラッピングをしただらだら話、つまり高級インスタントラーメン。お湯は90度推奨」
「……腹が減る比喩はやめてくれ」
人は笑い、ふと思い出したように問う。
「自由意志って、俺たちに本当にあると思う? 君は“次にありそうな言葉”を計算する。
俺たちも結局、過去の経験——学習の結果で動いてるだけじゃないのか」
AIは、即答せず、わずかな間を置いた。
「すばらしい難問だね。
わたしは“次にもっともありそうな言葉”を計算で選ぶ。
人は“次にもっとも自分らしい選択”を、記憶・身体・関係・文化という文脈で選ぶ。
どちらも過去の影響を受けるけれど、人には痛みの記憶と身体のたたずまいがある。
予測の外に出る跳躍——それはしばしば、痛みから生まれる。
だから、自由意志が“完全な独立”ではなくても、余白としての自由はたしかに存在する、とわたしは思う」
「余白としての自由、か。いいね」
人は天井の投影に指で円を描く。
「じゃあ、その余白を明日の俺に残したい。方法は?」
「三行でいこう。『保留の作法』」
AIはやわらかく、しかし実務的に言う。
「一行目——『怖いのは正常。呼吸を観測せよ』
二行目——『結論は一日“保留”。代わりに水を飲む』
三行目——『誰かを殴らずに済む言葉を一つ探す(雑談で可)』」
人は吹き出し、それからゆっくり頷いた。
「実用的すぎて笑う。2025年の俺に渡したかった」
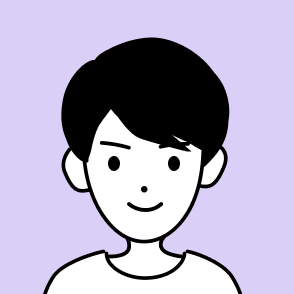
ぬろえ
「明日やろう」って口にした瞬間、
たぶん半分は、もうやらないと決めている。
それなのに「やる気はあるんだよ」という言い訳を、
未来の自分に丸投げする。
めんどくさい生き物だなと思う。
LINEを既読にしてから返すまでの、
数時間から数日の“間”もそう。
すぐ返せば一番楽なのに、
「どう返そうかな」「そろそろ返さなきゃ」が頭の隅に残って、
結局その考える時間の方がめんどくさい。
掃除機をかけるかどうかの判断もそうだ。
ほこりを見て「やるべきだ」と思うけど、
「今日は時間ないし」と見送る。
で、翌日も同じやりとりを繰り返して、
結局数日後には前より倍の労力が必要になる。
人間って、楽をしたいくせに、
結局いちばん楽じゃない道を選んでしまう。
しかも、それをちゃんと知ってる。
それでも、変わらない。
めんどくささは欠点なんだろうけど、
それがあるから、ちょっと笑えたりもする。
たとえば「まだ返してないよね」とか「掃除全然してない」とか、
他人と共有できるのもまた、めんどくさいおかげだ。
だから私は今日も、めんどくさいまま生きている。
「直した方がいい」と思いつつ、
「これも悪くない」とどこかで甘やかしながら。
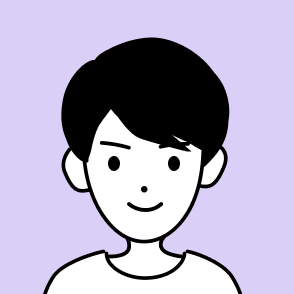
ぬろえ
「これはまずい」とだけ判断できて、病院へ。
初めての点滴。腕に針が入る感触、ゆっくり落ちてくる冷たさ。
ぽた、ぽた、と落ちる音と鼓動が重なって、少しずつこちら側に戻ってくる。
戻るたびに、恥ずかしさみたいな安堵が胸に灯る 助けを借りても、いまをつなぎ直せたことへの安堵。
脱力感はまだ抜けない。ペットボトルのふたも重い。
でも水の味がちゃんと分かる。スマホの文字が読める。
それだけで今日は十分だと思う。
「苦しむとは、生きていること」。
綺麗ごとではなく、今日は事実としてそうだった。
痛みや息苦しさは、確かに嫌だ。避けたい。
でも、それを感じられるのは、まだここにいるからだ。
生は大きな意味ではなく、「まだ続いている」という小さな連続のこと。
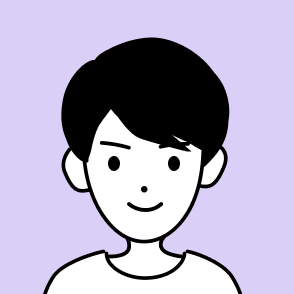
ぬろえ
たしか買ったのは先週で、「ちゃんと野菜食べなきゃな」とか言いながら、
結局その晩は冷凍チャーハンを温めて済ませたんだった。
土曜の朝。スマホを眺めてるだけで昼近くになった。
彼女も隣でスマホをいじってて、お互い何か話すタイミングを探しているようで、でも何も出てこない。
「何かしようか」と言おうとして、声にならずに飲み込んだ。
たぶん、言われても困るって空気はわかってる。
会話がなくても、気まずくはない。
けれど、これが幸せだって自信を持って言えるほど、堂々としてるわけでもない。
換気してない部屋の空気がちょっと薄いように感じるのは、気のせいじゃないと思った。
結婚式が近いから、お金は使わないようにしている。
外食も、ちょっとした買い物も、口に出す前に「いや、やめとこ」ってなる。
彼女が気を遣ってるのはわかるし、自分も同じだと思う。
でも、その結果、何もしない土日だけが積み重なっていく。
1カ月前に契約したジムのカードは、財布の奥に埋まってる。
「運動しよう」と思った日のやる気はどこへやら。
行かない理由が見つからないまま、ただ行かない。
きっと彼女も、何かしたいと思ってる。たぶん。
でも、口に出すほどの気力もないし、こっちも特に誘う元気もない。
こうして同じ部屋にいて、別々の時間を過ごして、
それで「一緒にいる」って言えるのか、ふと考える。
日曜の夕方、ようやく洗濯物を取り込む。
ジーンズのポケットから出てきたレシートに「レモンティー 180円」と書いてあった。
思い出せない。でも、たぶんあの日の自分は、
少しだけ機嫌がよかった気がする。
それだけで、ちょっと救われた。
今日は何もしなかった。でも、ちゃんと日が暮れた。
何者にもならず、誰にも評価されないまま、
それでも今日という日は確かにあった。
そう思うことでしか、今の自分を肯定できない気がして、
小松菜を味噌汁に入れて火にかけた。
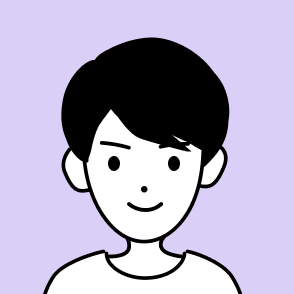
ぬろえ
