人気
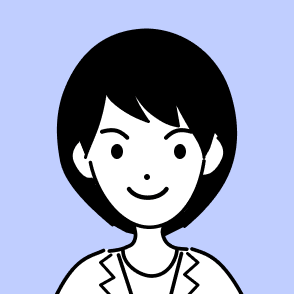
皐月
可愛いので描いてみました♡
(知ってる人いるのかな?)


こうじ
今回は「ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する」の主人公リーシェです

天月 兎
【おまけ】継承の刻 2
ルーヴェリアが挨拶を済ませ、騎士団員達にも挨拶をすると部屋を出て行った後、残された団長3人は深刻な面持ちで経歴書を眺めていた。
彼女が参戦してきた戦いは全て苛烈を極めたものだったからだ。
志願兵として入隊し魔族に占領されていたヴィト・リーシェ湖を奪還。
そのままシュガル山、ファランス山へ進軍し魔族を撃滅しつつ、北西諸国の救援を成功。
北西諸国より1000の兵士達を引き連れサフラニア王国の残存兵力と併せて1200の兵士を率い、ケレテス山脈へ進軍。
魔族を帝国領方面へと後退。
そして帝国軍との戦線を保っていた兵士達と共に残党を処理後、王都へと帰還。
この間僅か1ヶ月弱。
休む間もなく500の兵を率いてエレゾルテ山脈へと進軍。地形を活かした見事な戦術で魔族を圧倒。
そして王都方面へと引き返すと、そのままヘルベ湖の奪還まで完遂。
ディゼン「どれだけの死体を見たことやら……とんでもない奴が来たもんだ」
嘆息と共に経歴書を机に置く。
コルセリカ「あーれーはー、骨が折れるねえ…見た?あの目。光無いどころかどこも見てなさそーだったよ」
困った顔で笑いながら軽い口調で話してはいるが、憐憫の情が渦巻いて仕方ない。
だって記録されているものは、死者数百どころか数千と及ぶ戦いばかりだ。
それを生き残ってきた、というだけで彼女の心の闇の深さが知れる。
それはマルスも同じだ。
マルス「噂に名高い不死身の騎士、かあ…そりゃ、死体に塗れて自分だけ生き残ってりゃ、ああもなるよなぁ…」
しみじみとぼやいてから、数秒の静寂が訪れる。
その静寂を破ったのはディゼンだ。
ディゼン「…私達で支えてやらないといけないな」
ふっと笑ってコルセリカとマルスの方に視線を向ける。
コルセリカ「任せて任せて〜そういうのは超得意だから!」
妙にはしゃぐ彼女にマルスは肩をすくめた。
マルス「あんたは距離の詰め方がおかしいだけだろ…」
コルセリカ「言ったな?マルス?あとで剣の錆にしてやるから覚悟しな」
マルス「斧の間違いだろ…」
ディゼン「ほらほら二人ともそこまでだ。歓迎会の準備を進めるぞ」
二人「はーい」

天月 兎
第三十四話 前編
何だろう、水の音が聞こえる。
さらさらと静かに流れるような音だ。
それと、時々扉が軋んだ時のような音。
いつか夢で同じようなものを見ていた気がする。
それと、ずっと語りかけてくる声もあった。
あの時はただ女性の声としか分からなかったが、今は何故かはっきりとわかる。
ルーヴェリアの声だ。
どの音も、耳に水が入ってしまった時のようにくぐもっていて、はっきりとは聞こえないけれど。
目の前には、少し早く雲の流れる空…が見えているはずだ。多分これはそうだと思う。
はっきりしないのは、厚いすりガラス越しに何かを見ているかのようにしか見えないからだ。
鉛のように動かない体。
指先一つ動かすこともできないし、聞き取りたい音もはっきりとは聞こえない。
でも、あの夢と全く違うことがあった。
それは痛みがあることだ。
鼓動が一つ拍動するごとに、心臓のあたりから全身にかけて、何かが根を張っていくように鋭い痛みが広がっていく。
けれど苦悶の声をあげることすらままならなかった。
だんだんと意識が閉ざされていくようで。
ちゃんと、ルーヴェリアの話を聞いてあげたいのに。
彼女の声を、言葉を、聞いてあげたいのに。
瞼がひどく重くて、心に背いた体はそれに従って視界を暗闇に染めた。
それでもずっと、聴覚は水のせせらぎと彼女の声を聞いていた。
ずっと、ずっと、ずっと聞いていて……いつしか聞こえなくなった。
閉じた瞼の裏に、あの時のことが甦る。
防衛戦で、自分は4万の騎士団を率いて南方から押し寄せる20万の軍勢に立ち向かった。
アドニス「湖を渡らせないよう、弓兵と魔導兵は攻撃を絶やさないで!山脈から来る敵は僕と歩兵で蹴散らすよ!騎兵隊は遊撃に、基本的に負傷者の回収をして看護兵のところに連れて行ってくれ!」
本隊ではなく主力も居ない魔族の軍は、降り頻る鏃と魔法矢の雨に阻まれてヴィト・リーシェ湖を渡り切ることが出来なかった。
しかし何故か迂回するという選択をとらず、ただ死体の山となって積み重なっていくだけだ。
エレゾルテ山脈の麓では歩兵らが魔獣の角を叩き折り、爪を割り、四肢を切り裂く。
アドニスは炎を纏わせた剣を振るい、屍人と植魔を蹴散らしていった。
何物をも焼き尽くす劫火では、地に足がついている植魔でさえ灰燼に帰してしまう。
一歩踏み込めば、剣先より放たれた焔は顎を開いて敵を呑み込み、呑み込まれた敵は悉く塵となって空を舞った。
腹を空かせた猛獣のように、焔は次の獲物を絡め取るよう走っていく。
数の差は大きいが、こちらが圧倒的に有利な状況であった。
負傷兵も出たには出たが、高速移動に長けた騎兵隊と後方にいる看護兵の援護によって戦線復帰も早い。
アドニスは考えた。
もし自分が敵側なら、この状況を打開するために何か別の策を講じてくる筈だ。
突破を目論むなら、消耗一方の戦いになることは避けたい筈なのだ。
なのにどちらの戦線も突撃を繰り返すのみで、どこか違和感を感じる。
開戦から数時間経っても、だ。
何か別の目的があるのではないか、そう予見した時、最後方、つまり自国に巨大な魔力反応を感じた。
振り返ったアドニスが目にしたのは、王都の空を覆い尽くすように広がるゲート。
アドニス「時間稼ぎだったか…!」
しかしこの戦線は維持しなければならない。
自分だけでも国に戻るか、否か。
しかしゲートは皿が割れるように破壊された。
ゲートの破壊にはそれなりに多量の魔力が必要な筈だが…いや、そういえば。
ルーヴェリアが王妃にゲートを破壊できるほどの魔力を込めた短剣を渡していたか。
アドニス「良かった、流石師匠だ」
安堵の笑みを浮かべながら背後に忍び寄る死霊を斬り伏せる。
敵の目論見が破壊された今、自分達がすることは防衛戦ではない。
アドニス「ここからは殲滅戦だ!!残さず狩り尽くせ!!」
号令と共に高まる士気。
威勢の良い声が半数まで削られた魔族らを押し返し、一体、また一体と命を刈り取っていく。
そうして、日が沈んできた頃。
西門付近にゲートが開いたと報告があがる。
ヴィト・リーシェ湖付近を堅めていた騎士団数千名を派兵し、山脈の方に向き直った時だ。
脳裏に、大量の魔族の群れが過った。
砂漠にも似た荒野、聳える砦と立ち塞がる老騎士、その背後に開くゲート。
直感だ。確証はないが確信する。
クレストが危ない!
アドニス「師匠はなんて!」
近くの兵士に声をかける。
「既に西門の援護に来てくださいました!」
アドニスは一つ頷くと、この戦線は彼女に任せ、クレストの援護に向かうと言い残して馬を走らせた。
早く、早く行かないと。
いつか講義で教えてもらったんだ、昔、とある騎士が使っていた砦の魔術。
前方に広がる敵を蹂躙することに特化した牢獄のような砦。
だがその弱点は、砦の外側、主に背後だって…!
何か、胸元がずきりと痛んだ気がしたが思考を遮る程も強くはなかった。
馬より早い脚を持ったルーヴェリアやクレストが羨ましい。
こんなに急いでいるのに、過ぎ去っていく景色が遅く見えてしまう。
地平線の彼方では、既に陽が半分ほど溶け落ちていた。
その前に!!
少し時間はかかったが、クレストの背後に滑り込むようにして馬から降りる。
同時に目の前でゲートが開いた。

天月 兎
第二十九話
玉座の間に集ったアドニス、ルーヴェリア、クレストの3名は度肝を抜かれるような報告を聞くこととなる。
帝国軍国境、旧メレンデス小国、ヴィト・リーシェ湖、エレゾルテ山脈、旧ヤ・クルヌ村、旧ラシェクス小国、それぞれにゲートの出現が確認された。
現れた魔族は各地域に分けても10万は居るという。
アドニス「包囲…されてる…」
そう。サフラニアから見ると八方向をきっちり囲い込めるよう布陣されているのだ。
国王「対するこちらの戦力は、各騎士団総員でも4万に満たない。1箇所を突破するにも数の差が大きすぎるのだ…そして奴らはこちらに向けて同時侵攻を開始している…」
国の終わりが見える。
周囲の人間誰もが絶望の表情を浮かべていた。
ただ、2人を除いては。
ルーヴェリア「策は立てられますね」
クレスト「ええ、問題ございません」
重苦しい空気を裂くように、ルーヴェリアが中空に地図を映し出した。
そして、クレストが作戦を説明する。
まず、6箇所のうち少人数でも守備が容易なのは帝国領国境、旧ラシェクス、旧ヤ・クルヌ村の3箇所です。
山脈や湖に進軍が阻まれる為、地形を利用すれば罠を仕掛けるだけで足止め程度は可能でしょう。
逆に、こちらの守備が手薄となるのは南方のケレテス山脈、ヴィト・リーシェ湖から傾れ込む敵軍です。
よって……。
クレスト「我々騎士団長を除いた全軍をこちらの守衛に回します」
国王「なっ…20万を相手に4万で太刀打ちしろと!?」
自殺行為だと驚愕を隠さない国王に、毅然とした態度で首を縦に振るクレスト。
そこで、ルーヴェリアが口を開いた。
ルーヴェリア「七将は残り2人です。吸血鬼等を従える祖翼レイヴと、死霊術を操る亜祖ノクス。翼を持つ魔族はその特性を生かして山越えや湖越えを狙うでしょう。そして私が各所に配置しておいた魔力感応の魔道具からして、指揮官クラスの魔族はこの2人だけです。頭のない魔族など、ただ前に進むことしか考えられない烏合の衆……その程度では私の鍛えた騎士団員の敵にはなり得ません」
王妃はふむ、と考えた。
その話からすれば、逆に敵指揮官が居るのは4万の騎士を置く位置になる筈だ。
電撃戦を目論むなら尚のこと。
王妃「その機動力があるからこそ、その方面から敵が来るのでは?」
ルーヴェリア「そう考えさせることこそ、奴らの目論見です」
王妃「では、指揮官らは他の箇所から来る…と?」
クレストが地図の北方を指差した。
曰く、魔族が居る南部は何もせずとも機動力で押し切れるが、ネポス山、ケレテス山脈を超えるにはそれを更に凌駕する機動力がなければ完全な包囲は出来ない。
故に、レイヴが現れているのは帝国領国境か旧ラシェクス。
そして数を理にしたいならば、ノクスの力を存分に発揮できるのも死者が多かった旧メレンデスだろう。
つまり北方付近に大きな戦力が集中している、と。
ルーヴェリア「なのであえて南方の守備を堅くしていると見せかけ、北方に集中する敵を逆に誘き寄せるのです」
国王「しかし…全軍を南方に集中させれば動けるのは…」
クレスト「ええ、我々騎士団長のみとなります」
周囲がざわめき出す。
まさか、たった3人で南方の守備が突破される前に北方に電撃戦を仕掛けて敵の頭を潰しにかかり、そのまま敵の背後を突く形で南方の援軍に回るのか。
ルーヴェリア「いいえ」
ざわめく声に首を横に振る。
ルーヴェリア「クレストは守備に特化した騎士ですから、東方から押し寄せる軍勢から守備。国の未来を考え、アドニス殿下には守備の堅い4万の騎士団の総司令官として南方で後方支援をしていただきます」
アドニス「無茶苦茶だ!師匠1人で北方の七将2人と30万の敵を潰して西方に周り、我々の援軍に回ると!?正気じゃない!」
あまりの自己犠牲精神と無茶の過ぎる作戦に、今まで黙って話を聞いていたアドニスがたまらず声をあげた。
アドニス「それにクレストだって…1人で、10万の敵を……もう私兵だって居ないのに…!」
その場に集った誰もが彼と同意見だ。
クレスト「皆さんは、ご存知ありませんからそういった考えに至るのは仕方のないことです」
何故か誇らしげに笑んでいる空気の読めない老騎士。
とうとう年齢のせいで頭がおかしくなったのかとすら思ったが、彼の口からとんでもない話が飛び出た。
クレスト「今から50年前。魔族から停戦交渉を受けた原因となったのは我が師です。あの時、我々騎士団も各国も兵力を消耗し、今のように終わりが見えた時がありました。各国にゲートが開き、各所に七将が出現したのです。我々の兵力といえば、せいぜい3千に足るか…といったところでしたか。騎士団長も私と我が師しか居なかった…そこで我が師は、私と全兵力を国の守備に回らせ、たったお一人で各所に出現した七将全てに致命傷を負わせて回ったのです。魔族側も総力戦に出ていたせいか、それは大きな痛手となったのでしょう。それが原因で停戦交渉に来たのです」
………。
驚きで息を呑む音しか聞こえない。
七将を、たった1人で、それも遠く離れた箇所に存在する者達に致命傷を負わせた。
正しく、化け物だ。
ルーヴェリア「時間もありませんのでこの作戦を決行します。よろしいですね?」
異を唱える者は誰もいない。
アドニスは何か言いたげだったが、空気がそれを許さなかった。
それでも無茶をしてほしくないなんて、言えなかった。
ルーヴェリア「王妃陛下、貴女は魔術棟を管理なさるほど優れた魔術の才をお持ちです」
王妃「え、ええ…そこまで優れているかと言われれば、貴女ほどではありませんが…」
ルーヴェリアは懐から短剣を取り出して王妃に渡した。
ルーヴェリア「これはテフヌト族領で採掘される最も希少な鉱石で造られた短剣です。が、武器ではなく魔道具です」
王妃「どう扱うものなのかしら」
ルーヴェリア「少量の魔力を込めれば、この短剣内部で潜在魔力の解放が為されます。その状態で短剣を投げつければ、開き切る前のゲートなら破壊ができます。一回きりなのが惜しいところではありますが…魔族の軍勢に太刀打ちもできないままよりは良いかと」
それは…ルーヴェリアの読みではこの攻防戦でサフラニア本国自体にゲートが開くと予想しているということだ。
ルーヴェリア「あくまでも万が一に備えて、ではありますが……常に最悪の状態を想定して戦うのが戦争というものですから」
王妃はこくりと頷いてその短剣を受け取った。
王妃「ありがとう。そうですね、貴女の言う通りです。私はいつゲートが開いてもいいよう魔術棟から監視を行います」
ルーヴェリアは頷き、両陛下に頭を下げて退室していく。
どこまで見越しているのか、そんな風に思っている視線が彼女の背中に刺さるのを遮るようにクレストが後に続いた。
アドニス「私も、行って参ります」
頭を下げるアドニスに、国王が声をかけた。
国王「お前の家は、家族はいつも此処に居る。気をつけて行っておいで、そして帰っておいで」
アドニス「…はい」
力強く頷いて退室したが、正直、複雑だった。
第一王子がいない今、次期国王になるのは自分しかいない。
だから優遇されるのもわかる。
でも、自分にだけあの言葉がかけられたのが嫌だったのだ。
自分だけじゃない。
戦いに出る騎士団の全員が、帰る場所はここなんだ。
家族がいて、恋人がいて、一人一人に居場所があって、だからこそ命をかけて守るのだから。
さて、そんな思いを抱えたまま騎士団宿舎の方へ足を運んだ。
既に全員が整列している。
鎧を纏い、武器を手にした騎士団長らが前に並べば、彼らはその身を引き締めるように背筋をぴんと伸ばした。
ルーヴェリア「命令は一つです」
静かな声が、空間に染み渡っていく。
ルーヴェリア「敵に背を向けても構いません。生きることを最優先にしてください」
騎士団にあるまじき発言に、息遣いだけで驚いたのが伝わってくる。
ルーヴェリア「自分の命も、他人の命も、一つしかありません。生きていれば再起出来ますが、死んでしまったら出来ません。大丈夫、訓練の通りに、いつもの通りに、敵を殺せば良い。殺される前に殺しなさい。それが出来ないなら背を向け、機会を伺い刺せばいい」
彼らは安堵した。
そういうことなら、確かに生きること最優先だ。
敵前逃亡ではなく戦略的撤退を選べという意味だったか、と。
ルーヴェリア「貴方達を信じています。それでは各戦線へ、進軍開始!!」
アドニス「進軍開始ー!!」
彼らは南門へ向け、歩調を揃えて歩き出した。
遥か遠方には、魔族の出現によって黒雲が立ち込めているのが見える。
だが、恐怖などない。
「この日のために、この時のために、酷い鍛錬を何度も超えてきたしな」
「何十万を相手にするより、団長1人相手にする方が骨折れるしな」
「我々が負けることなど、万に一つも無いさ」
「そうだな。俺たちには最強の騎士団長達がついてる」
そんなことを隊列の端々から漏らしながら進んでいく騎士団を見送り、ルーヴェリアはクレストを見た。
ルーヴェリア「…………」
死なないでほしい、とは思うがそれを伝えるのは彼の実力に不安があると伝えるのと変わらない。
クレスト「師よ」
ルーヴェリア「はい」
クレストは彼女の手に合うサイズの白い手袋を渡した。
ルーヴェリア「…っ…」
今までの経験からして、これは別れの挨拶だと察する。
クレスト「物理攻撃力の上昇と、速度に関する身体強化が為される術式を施した手袋です。私の魔力で組み込みました」
ルーヴェリア「………」
黙ってそれを受け取ると、クレストはにっこりと微笑んでみせた。
クレスト「この戦いの最中に、貴女の誕生日が過ぎてしまいますからな」
ルーヴェリア「はい?」
確かに、もう数えてはいないからいくつになるのかは分からないが、近く自分の誕生日がある。
クレスト「またお会いしましょう。再会の時まで、私は決して倒れはしません」
ルーヴェリアは少しだけ目を瞠ると、嬉しそうに細め、口角をあげた。
ルーヴェリア「ありがとうございます。また会いましょう」
クレストは軽く頭を下げて東門へと向かっていった。
ルーヴェリアはガントレットを外して、早速手袋を身につける。
ぴったりと馴染む手袋からは、クレストの魔力を感じた。温かなそれは、寄り添ってくれているかのようだ。
ルーヴェリア「……まったく…兄妹揃って私への贈り物が手に関するものだなんて…どう口裏を合わせたんですかね」
ガントレットを装着し直しながら呟く。
そして北方の空を睨んだ。
向こうの状況は読めないが、彼女の索敵魔術が山脈の向こう側でたむろする魔族の群れを捉える。
ルーヴェリア「さて皆さん…殲滅戦のお時間です」
誰ともなくそう言い放ち、彼女はその場から姿を消した。

天月 兎
第二十七話 後編
一方で、第一騎士団が去った後ではあったが、それは現れた。
降り頻る雨粒が地面に弾かれるたびに不協和音を奏で始め、跳ねた水滴が少しずつ魔物の姿を形成していき、水祖セラフィナが構築される。
セラフィナ「…他の方は撤退させたのですか?」
開口一番、ルーヴェリアしか残っていないこの状況に首を傾げてくる。
ルーヴェリア「賢明な判断だろう」
セラフィナはふふ、と笑ってルーヴェリアの言葉に頷いた。
そう、それでいいのだ。
だってセラフィナは、ルーヴェリアを壊すために来たのだから。
瞬く間にルーヴェリアの鎧を濡らしていた雨粒が、足元に広がる血の混じった水溜りが、彼女の全身を包み込んだ。
水の色は暗く、まるで海中深くに潜り込んだ時のような色をしている。
水は呼吸を許さず、数分の後に肺を満たして苦痛を与えた。
が、この程度、彼女の剣で裂けばどうってことはないのだ。本来なら。
何故それが出来なかったのか?
それは、彼女の目の前に広がった光景がそうさせなかったからだ。
砲弾の雨が嵐の如く襲いくる戦場。
着地地点にいた者は、敵も味方も関係なく地面ごと全てを吹き飛ばしていく。
魔術壁が張れるほど進歩はしていなかった時代において、科学を発展させて戦場そのものを蹂躙することに長けていた帝国との戦いは、こうであることが常だった。
これはまだ、ルーヴェリアが騎士団に入りたてだった頃の記憶だ。
少し周りより剣と魔術の才能が秀でていただけの、ただの人間だった時の。
敵兵器を無力化しろ、という無茶な指示に従って前線を走り抜けた。
歩兵の甘い攻撃なんて意にも介さず最後方まで突っ切って、傷だらけの体で砲台を爆裂魔法で壊していった。
でも、出来たのはそれだけだった。
敵地に1人乗り込んだ、それは奴らにとって格好の餌食というわけで。
無論、並の人間より少しだけ剣の才能があったから、疲弊していようと体から血が噴き出していようとも関係なく敵兵を屠って、屠って、屠り続けた。
自分の血で汚れたのか、敵の血で汚れたのか分からなくなる頃には、帝国兵達はこれを相手にするのは分が悪いと判断したのか、別所で魔族との交戦があったのかは分からないが、撤退していた。
自軍の方を振り返れば、自軍もほぼ壊滅状態。
立っているのは2、3人だけ。
こんなことが、毎度繰り返されていた。
それでも、あの頃はまだ、守れたものがある。
家族がいると力を振り絞れていたのだ。
だが、無情にも場面はとある戦場へと切り替わる。
魔族に占拠された、ヴィト・リーシェ湖奪還戦。
朝食を終えて、さあこれから戦だと息巻いて魔族の群れに一丸となって突っ込んでいった騎士団。
戦いは拮抗したままだったが、ついに七将ザルヴォが現れ、残る兵士は今朝ほど共に朝食を摂った同僚と自分だけ。
ザルヴォの蛇の尾が彼を拘束している。
自分はといえば、両脚を負傷したせいでうまく走ることが出来ない。
だってこの時はまだ、ただ周りより少し優れた才能を持っただけの兵士だったから。
それでも、失いたくない。
殺させたくないと必死になった。
腕の力だけで人間と魔獣の屍の上を張って、失血のせいで定まらない視点を気力だけで補って、必死の力を振り絞って、剣を投げつける。
剣は見事にザルヴォの蛇の尾の根元を切れはしたが、同時にかの仲間は圧死してしまった。
届かなかった絶望、救えなかった絶望で目の前が真っ暗になる。
でも確かに、此方へ近づいて来る足音が聞こえたから。
怒りとも、悲しみとも呼べない叫び声をあげながら、ありったけの魔術をザルヴォに浴びせた。
奴は致命傷を負ったと判断したのか、ゲートに帰っていき、ゲートは閉じられた。
……戦闘は勝利したが、生き残ったのは、正確にはまだ息があったために回収されたのはルーヴェリアだけだった。
だが、まだだ。まだ終われない。
回収しに来た兵士200余名を連れて、ルーヴェリアは軋む身体に鞭を打ってシュガル山、ファランス山へと進軍した。
周りの静止も耳に入ってはおらず、目につく敵と思しきものは全て切り捨て、焼き殺し、排除して、北西諸国へと向かったのだ。
激戦地に赴く恐怖で足を止める兵士もいた。
ルーヴェリアは構わず歩みを進めたため、ほぼ1人で北西諸国を襲っていた植魔、水魔の群れを一掃。
その目には敵しか映っておらず、まだだ、まだだ、これ以上奪わせるものかと、たかが剣と魔術の才能に秀でただけの小娘が突き進んでいったのだ。
後方は数多の死体の山が積み重なったが、それすら見えていないかのように踏み越えて。
たったひと月弱で周辺諸国の魔族を撃退し、サフラニア周辺の魔族の群れも、帝国領方面へと追い返してしまった。
帝国は魔族との争いでこちらを攻めるどころではなくなり、結果サフラニアは多くの死傷者を出しはしたが、国そのものは守られた。
その功績を讃えられ、彼女は12歳という前代未聞の若さで、先刻の戦いで穴が開いてしまった第一騎士団長の座に就くことになった。
その記憶の断片を見せられ、ルーヴェリアは考える。
こいつは、何がしたいんだろう、と。
セラフィナの声が水球の中を反芻する。
守りたかったもの、守れなくて残念ですね?
どうやらあの魔物は、自分に過去の記憶を見せることで、所謂トラウマと呼ばれるやつを思い起こさせたいようだ。
ヘルムのおかげでルーヴェリアが何も感じていない表情を図ることが出来ないためか、セラフィナは調子に乗ってこんなことをほざきだす。
セラフィナ「人の体は弱く、命は脆い。でも貴女はどこかの魔女がかけた呪いで体も命も奪えない。でも人の殺し方って、何も命を奪うことだけじゃないんですよ」
ルーヴェリアは「ああ、よく知っている」と頷きたかったが、あえて調子に乗らせておこうと何もしなかった。
相変わらず肺は痛むが、別に死にもしないので放置でいいだろう。
痛みには、慣れている。
セラフィナ「心が壊れてしまえば、それは死んだも同然なのです」
歌うように言いながら恍惚とした表情を浮かべて、さあ次は何を見せようかと思案した。
水球の内側に映し出されたのは、今ではおとぎ話となってしまった概ね50年前の戦いの記憶。
交戦中の他騎士団の援護に向かったあの日。
指定された位置には、敵影も味方もなく。
ただ、地面に戦いの残滓が散りばめられているだけで。
そんな中、見つけたのだ。
内包していた魔力を全て放出し、抜け殻と化している黒いチョーカーを。
その傍に、見知った筆跡で"私が生きた証"と書かれているのを。
ここで交戦していたのは間違いなく、そして敵も味方も全滅したのだ。
救援が間に合わず、かの騎士団長は己と騎士団員ごと敵を葬ったのだと悟らざるを得なかった。
次に映ったのは親友を喪った日の戦い。
唯一、心を預けられる存在だった大切な親友は、陣幕内で息絶え、七将ノクスの力で屍人となった騎士団員に殺されていた。
全身のあらゆる部分を食い千切られた状態で、地に伏していた。
戦う術を持たなかった彼女は、せめて屍人が外に出ないよう、必死に陣幕の入り口を塞いでいたのだろう。ここに敵が居ると叫んだのだろう、大きく口は開いたままで、両腕はぴんと真横に伸ばされた状態だった。
片腕には、親友の誕生日に贈ったブレスレットがしっかりと付けられていた。
内乱はあったものの、援軍に駆けつけてくれた他の騎士団のおかげで勝つことはできたが、大きなものを失ってしまった戦場だった。
色々な戦場の記憶が水球の内側を彩っていく。
死期を悟り、大切なペンダントと共に自分の意思を私に託して命を燃やし尽くした人。
生まれ育った地を守るために、死を厭わず魔獣の群れに攻め入り、劣勢を好転させ勝利に導いてくれた末に死んだ者。最期は騎士団員として履くように強制したブーツを脱がしてやったか。
数多の魔族に囲まれ、もう私と自分しか残っていない状況で、背中合わせで戦い、国一つを守り抜いた。だがその戦いで治療不可なほど深く傷を負って、私が、介錯した。
託されたガントレットは今、私の手を守ってくれている。
私の不在時、文字通り自国近辺を自軍だけで駆け回って多方向からの襲撃からサフラニアを守り切った英傑。彼の者が私に遺してくれたのは、心を守ってくれる兜。
もう、いいだろう。
充分だ。
水球に横一文字の線が描かれた。
線から真っ二つに裂かれた水球は、檻としての機能も鏡としての力も失って弾けるように消える。
ルーヴェリア「人の死を愚弄した感想を聞かせてもらおうか」
躍動感のある声色に、セラフィナは眉を顰める。
なぜ、壊れない。
確かに彼女が心に負った傷を、記憶を具現化させた。
人は傷を負った記憶を直視すれば心は闇に呑まれ、壊れるはずなのに。
ルーヴェリア「私の心を……壊す?のが、目的だったか?」
喉の奥から込み上がる笑いを堪えているような喋り方だ。
心が壊れて頭がおかしくなったのか、兜のせいで表情が見えないので何とも言えないが、セラフィナは一つ確信した。
自分は過ちを犯した、と。
ルーヴェリアの足元に魔法円が描かれる。
瑠璃色の円と朱色の円。それらは幾重にも重なって立ち昇ったかと思えば。
セラフィナ「……!」
体内を流れる魔力が停滞した。
水祖として得た力も、魔族が誇る膨大な魔力も封じられたのだ。
今やセラフィナは、少し常識を超えた姿形をしただけの、陸に上がった、ただの魚だ。
セラフィナ「あんな魔術を使っておいて、どこにそんな魔力を…!」
あんな魔術とは恐らく、屍人達を燃やし尽くした二つの太陽のことだろう。
なるほど、水鏡か何かで見ていたか。
驚愕の声に首を傾げてみせる。
ルーヴェリア「魔族のくせに潜在魔力というものを知らないのか?」
セラフィナはそんなもの、見たことも聞いたこともないようだった。が、魔族としてのプライドが首を縦に振るのを躊躇わせているらしい。
魔力というのは、生まれた時から体内を流れる量が定められていて、それを増やせるか否かは運次第だ。
努力でどうにかなるものでもないので、魔族は生まれたままの自分を受け入れる。
人間よりは遥かに多く内包されているものだから、別段何かをする必要はなかったのだ。
だからこそ人間は、それに対抗するためにどうにかして魔力の内包量を増加させる術を探した。
それが、潜在魔力の解放だった。
身体強化の応用で、魔力に魔力をぶつけて分裂、増幅させることで、本来なら運次第で伸びるか伸びないかの部分すら超越して莫大な魔力量を得る術だ。
体内に内包しきれなくなると、魔力が溢れ出ると同時に身体そのものも爆発四散してしまうので使える人間は限られているが、ルーヴェリアは呪いのおかげで死ぬ事がないので耐える耐えない以前に、そもそも魔力が溢れる事がない。
謂わば、彼女の特権のようなものだ。
ルーヴェリア「…さて。戦いに於いて食糧は大変に貴重なもので、食事はとてもとても大事なことだ」
目を瞠るセラフィナを見て、まあ彼奴からは見えることはないが残忍な笑みを浮かべた。
ルーヴェリア「お前は、どんな味がするんだろうな?」
髪と思しき部分を鷲掴み、ずるずると引き摺りながらルーヴェリアはサフラニアを目指して歩いた。
魔族が、それも七将がなす術なく暴れながら泣き叫ぶ光景を見ることが出来る人物がこの場にルーヴェリアただ1人しかいないのは、非常に残念である。
