投稿
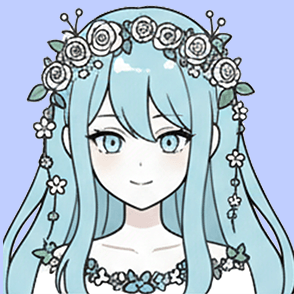
天月 兎
第二十七話 後編
一方で、第一騎士団が去った後ではあったが、それは現れた。
降り頻る雨粒が地面に弾かれるたびに不協和音を奏で始め、跳ねた水滴が少しずつ魔物の姿を形成していき、水祖セラフィナが構築される。
セラフィナ「…他の方は撤退させたのですか?」
開口一番、ルーヴェリアしか残っていないこの状況に首を傾げてくる。
ルーヴェリア「賢明な判断だろう」
セラフィナはふふ、と笑ってルーヴェリアの言葉に頷いた。
そう、それでいいのだ。
だってセラフィナは、ルーヴェリアを壊すために来たのだから。
瞬く間にルーヴェリアの鎧を濡らしていた雨粒が、足元に広がる血の混じった水溜りが、彼女の全身を包み込んだ。
水の色は暗く、まるで海中深くに潜り込んだ時のような色をしている。
水は呼吸を許さず、数分の後に肺を満たして苦痛を与えた。
が、この程度、彼女の剣で裂けばどうってことはないのだ。本来なら。
何故それが出来なかったのか?
それは、彼女の目の前に広がった光景がそうさせなかったからだ。
砲弾の雨が嵐の如く襲いくる戦場。
着地地点にいた者は、敵も味方も関係なく地面ごと全てを吹き飛ばしていく。
魔術壁が張れるほど進歩はしていなかった時代において、科学を発展させて戦場そのものを蹂躙することに長けていた帝国との戦いは、こうであることが常だった。
これはまだ、ルーヴェリアが騎士団に入りたてだった頃の記憶だ。
少し周りより剣と魔術の才能が秀でていただけの、ただの人間だった時の。
敵兵器を無力化しろ、という無茶な指示に従って前線を走り抜けた。
歩兵の甘い攻撃なんて意にも介さず最後方まで突っ切って、傷だらけの体で砲台を爆裂魔法で壊していった。
でも、出来たのはそれだけだった。
敵地に1人乗り込んだ、それは奴らにとって格好の餌食というわけで。
無論、並の人間より少しだけ剣の才能があったから、疲弊していようと体から血が噴き出していようとも関係なく敵兵を屠って、屠って、屠り続けた。
自分の血で汚れたのか、敵の血で汚れたのか分からなくなる頃には、帝国兵達はこれを相手にするのは分が悪いと判断したのか、別所で魔族との交戦があったのかは分からないが、撤退していた。
自軍の方を振り返れば、自軍もほぼ壊滅状態。
立っているのは2、3人だけ。
こんなことが、毎度繰り返されていた。
それでも、あの頃はまだ、守れたものがある。
家族がいると力を振り絞れていたのだ。
だが、無情にも場面はとある戦場へと切り替わる。
魔族に占拠された、ヴィト・リーシェ湖奪還戦。
朝食を終えて、さあこれから戦だと息巻いて魔族の群れに一丸となって突っ込んでいった騎士団。
戦いは拮抗したままだったが、ついに七将ザルヴォが現れ、残る兵士は今朝ほど共に朝食を摂った同僚と自分だけ。
ザルヴォの蛇の尾が彼を拘束している。
自分はといえば、両脚を負傷したせいでうまく走ることが出来ない。
だってこの時はまだ、ただ周りより少し優れた才能を持っただけの兵士だったから。
それでも、失いたくない。
殺させたくないと必死になった。
腕の力だけで人間と魔獣の屍の上を張って、失血のせいで定まらない視点を気力だけで補って、必死の力を振り絞って、剣を投げつける。
剣は見事にザルヴォの蛇の尾の根元を切れはしたが、同時にかの仲間は圧死してしまった。
届かなかった絶望、救えなかった絶望で目の前が真っ暗になる。
でも確かに、此方へ近づいて来る足音が聞こえたから。
怒りとも、悲しみとも呼べない叫び声をあげながら、ありったけの魔術をザルヴォに浴びせた。
奴は致命傷を負ったと判断したのか、ゲートに帰っていき、ゲートは閉じられた。
……戦闘は勝利したが、生き残ったのは、正確にはまだ息があったために回収されたのはルーヴェリアだけだった。
だが、まだだ。まだ終われない。
回収しに来た兵士200余名を連れて、ルーヴェリアは軋む身体に鞭を打ってシュガル山、ファランス山へと進軍した。
周りの静止も耳に入ってはおらず、目につく敵と思しきものは全て切り捨て、焼き殺し、排除して、北西諸国へと向かったのだ。
激戦地に赴く恐怖で足を止める兵士もいた。
ルーヴェリアは構わず歩みを進めたため、ほぼ1人で北西諸国を襲っていた植魔、水魔の群れを一掃。
その目には敵しか映っておらず、まだだ、まだだ、これ以上奪わせるものかと、たかが剣と魔術の才能に秀でただけの小娘が突き進んでいったのだ。
後方は数多の死体の山が積み重なったが、それすら見えていないかのように踏み越えて。
たったひと月弱で周辺諸国の魔族を撃退し、サフラニア周辺の魔族の群れも、帝国領方面へと追い返してしまった。
帝国は魔族との争いでこちらを攻めるどころではなくなり、結果サフラニアは多くの死傷者を出しはしたが、国そのものは守られた。
その功績を讃えられ、彼女は12歳という前代未聞の若さで、先刻の戦いで穴が開いてしまった第一騎士団長の座に就くことになった。
その記憶の断片を見せられ、ルーヴェリアは考える。
こいつは、何がしたいんだろう、と。
セラフィナの声が水球の中を反芻する。
守りたかったもの、守れなくて残念ですね?
どうやらあの魔物は、自分に過去の記憶を見せることで、所謂トラウマと呼ばれるやつを思い起こさせたいようだ。
ヘルムのおかげでルーヴェリアが何も感じていない表情を図ることが出来ないためか、セラフィナは調子に乗ってこんなことをほざきだす。
セラフィナ「人の体は弱く、命は脆い。でも貴女はどこかの魔女がかけた呪いで体も命も奪えない。でも人の殺し方って、何も命を奪うことだけじゃないんですよ」
ルーヴェリアは「ああ、よく知っている」と頷きたかったが、あえて調子に乗らせておこうと何もしなかった。
相変わらず肺は痛むが、別に死にもしないので放置でいいだろう。
痛みには、慣れている。
セラフィナ「心が壊れてしまえば、それは死んだも同然なのです」
歌うように言いながら恍惚とした表情を浮かべて、さあ次は何を見せようかと思案した。
水球の内側に映し出されたのは、今ではおとぎ話となってしまった概ね50年前の戦いの記憶。
交戦中の他騎士団の援護に向かったあの日。
指定された位置には、敵影も味方もなく。
ただ、地面に戦いの残滓が散りばめられているだけで。
そんな中、見つけたのだ。
内包していた魔力を全て放出し、抜け殻と化している黒いチョーカーを。
その傍に、見知った筆跡で"私が生きた証"と書かれているのを。
ここで交戦していたのは間違いなく、そして敵も味方も全滅したのだ。
救援が間に合わず、かの騎士団長は己と騎士団員ごと敵を葬ったのだと悟らざるを得なかった。
次に映ったのは親友を喪った日の戦い。
唯一、心を預けられる存在だった大切な親友は、陣幕内で息絶え、七将ノクスの力で屍人となった騎士団員に殺されていた。
全身のあらゆる部分を食い千切られた状態で、地に伏していた。
戦う術を持たなかった彼女は、せめて屍人が外に出ないよう、必死に陣幕の入り口を塞いでいたのだろう。ここに敵が居ると叫んだのだろう、大きく口は開いたままで、両腕はぴんと真横に伸ばされた状態だった。
片腕には、親友の誕生日に贈ったブレスレットがしっかりと付けられていた。
内乱はあったものの、援軍に駆けつけてくれた他の騎士団のおかげで勝つことはできたが、大きなものを失ってしまった戦場だった。
色々な戦場の記憶が水球の内側を彩っていく。
死期を悟り、大切なペンダントと共に自分の意思を私に託して命を燃やし尽くした人。
生まれ育った地を守るために、死を厭わず魔獣の群れに攻め入り、劣勢を好転させ勝利に導いてくれた末に死んだ者。最期は騎士団員として履くように強制したブーツを脱がしてやったか。
数多の魔族に囲まれ、もう私と自分しか残っていない状況で、背中合わせで戦い、国一つを守り抜いた。だがその戦いで治療不可なほど深く傷を負って、私が、介錯した。
託されたガントレットは今、私の手を守ってくれている。
私の不在時、文字通り自国近辺を自軍だけで駆け回って多方向からの襲撃からサフラニアを守り切った英傑。彼の者が私に遺してくれたのは、心を守ってくれる兜。
もう、いいだろう。
充分だ。
水球に横一文字の線が描かれた。
線から真っ二つに裂かれた水球は、檻としての機能も鏡としての力も失って弾けるように消える。
ルーヴェリア「人の死を愚弄した感想を聞かせてもらおうか」
躍動感のある声色に、セラフィナは眉を顰める。
なぜ、壊れない。
確かに彼女が心に負った傷を、記憶を具現化させた。
人は傷を負った記憶を直視すれば心は闇に呑まれ、壊れるはずなのに。
ルーヴェリア「私の心を……壊す?のが、目的だったか?」
喉の奥から込み上がる笑いを堪えているような喋り方だ。
心が壊れて頭がおかしくなったのか、兜のせいで表情が見えないので何とも言えないが、セラフィナは一つ確信した。
自分は過ちを犯した、と。
ルーヴェリアの足元に魔法円が描かれる。
瑠璃色の円と朱色の円。それらは幾重にも重なって立ち昇ったかと思えば。
セラフィナ「……!」
体内を流れる魔力が停滞した。
水祖として得た力も、魔族が誇る膨大な魔力も封じられたのだ。
今やセラフィナは、少し常識を超えた姿形をしただけの、陸に上がった、ただの魚だ。
セラフィナ「あんな魔術を使っておいて、どこにそんな魔力を…!」
あんな魔術とは恐らく、屍人達を燃やし尽くした二つの太陽のことだろう。
なるほど、水鏡か何かで見ていたか。
驚愕の声に首を傾げてみせる。
ルーヴェリア「魔族のくせに潜在魔力というものを知らないのか?」
セラフィナはそんなもの、見たことも聞いたこともないようだった。が、魔族としてのプライドが首を縦に振るのを躊躇わせているらしい。
魔力というのは、生まれた時から体内を流れる量が定められていて、それを増やせるか否かは運次第だ。
努力でどうにかなるものでもないので、魔族は生まれたままの自分を受け入れる。
人間よりは遥かに多く内包されているものだから、別段何かをする必要はなかったのだ。
だからこそ人間は、それに対抗するためにどうにかして魔力の内包量を増加させる術を探した。
それが、潜在魔力の解放だった。
身体強化の応用で、魔力に魔力をぶつけて分裂、増幅させることで、本来なら運次第で伸びるか伸びないかの部分すら超越して莫大な魔力量を得る術だ。
体内に内包しきれなくなると、魔力が溢れ出ると同時に身体そのものも爆発四散してしまうので使える人間は限られているが、ルーヴェリアは呪いのおかげで死ぬ事がないので耐える耐えない以前に、そもそも魔力が溢れる事がない。
謂わば、彼女の特権のようなものだ。
ルーヴェリア「…さて。戦いに於いて食糧は大変に貴重なもので、食事はとてもとても大事なことだ」
目を瞠るセラフィナを見て、まあ彼奴からは見えることはないが残忍な笑みを浮かべた。
ルーヴェリア「お前は、どんな味がするんだろうな?」
髪と思しき部分を鷲掴み、ずるずると引き摺りながらルーヴェリアはサフラニアを目指して歩いた。
魔族が、それも七将がなす術なく暴れながら泣き叫ぶ光景を見ることが出来る人物がこの場にルーヴェリアただ1人しかいないのは、非常に残念である。
関連する投稿をみつける
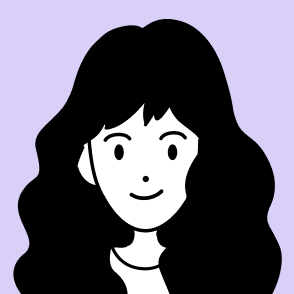
夜食

🌰自己中㌔🈵
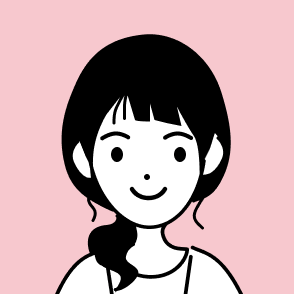
♡
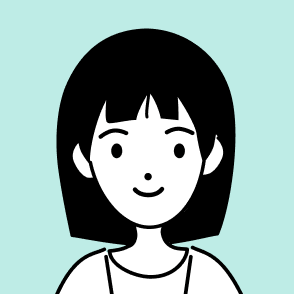
🧂
あ〜もう要らないなこの人って思うくらい私は冷たい
OK
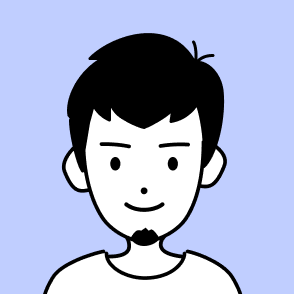
ヤス
はじめまして!気軽に話しかけていただけると嬉しいです!😆
名前:ヤス
趣味:友達募集、筋トレ、大阪、お酒、料理
仲良くしてください✨
もっとみる 
話題の投稿をみつける

ゆでだ
バナンザ最終面にインスピレーション受けてるのだけは確か
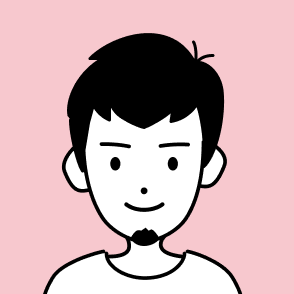
テン
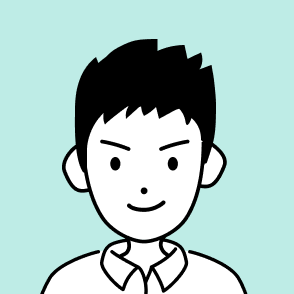
妖怪布
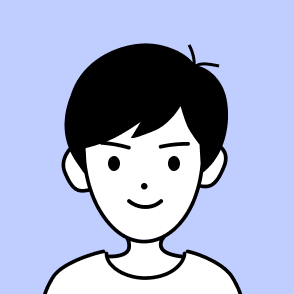
オレ・
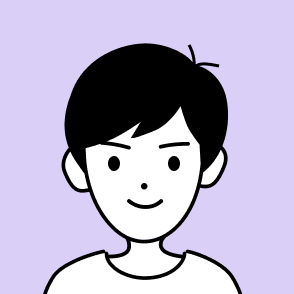
まさ
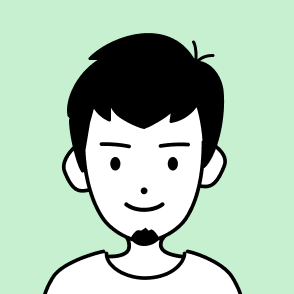
らっこ
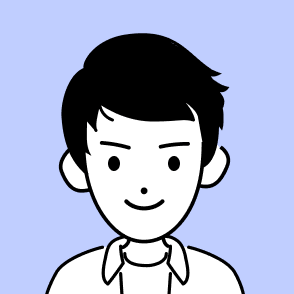
レンカ
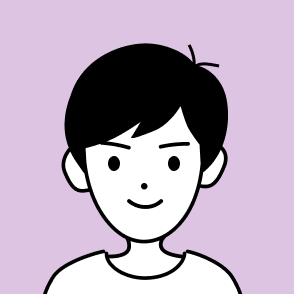
カトリ
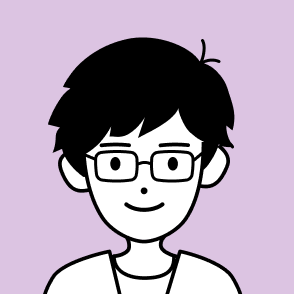
サト@A

𝕾沢
もっとみる 
関連検索ワード
