人気

𝕂𝕒𝕠𝕣𝕚🫧
ゆっくり読書したいなって思ったけど、読書するにも安定した精神と、余裕が無いと出来ないんだなと感じた[照れる]
ゆっくりお仕事スタート🏃♀️
行ってきます⟡.*
#写真好きな人と繋がりたい #ファインダー越しの私の世界 #GRAVITY写真部 #写真愛好家 #読書の星


旅路
Ana
「世界の美しい図書館」
著者:パイ インターナショナル
写真:㈱アフロ他
世界の〜シリーズの図書館。
ユネスコの世界遺産としても登録されている歴史的な図書館や、巨匠による最新鋭の名建築など、世界各国の豪華な図書館やユニークな施設を100館掲載。
学校と記載レイアウトはほぼ一緒です。
1つだけ行けるのなら
街とスラムをつなぐスペイン図書館へ
#読書の星 #読書 #図書館


彼方@休眠中
ポーチなのに、
文庫のブックカバーになる!!
これを見よ!!
#読書好き #読書の星 #読書の秋



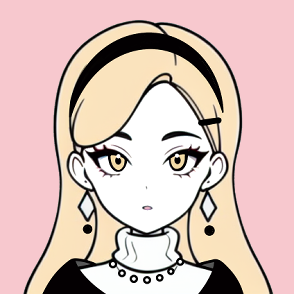
とも
3発目、読み始めました📚️←遅いか🐌💨💦
あぁーーっ‼️えぇー⁉️
何だよ、『国宝』は彼だったのね😳←これまた恥ずかしい話💦
どーか『横道世之介』シリーズも『国宝』も…本で読んでから→画像を見ましょか🤭
#お疲れGRAVITY
#読書の星
#吉田修一

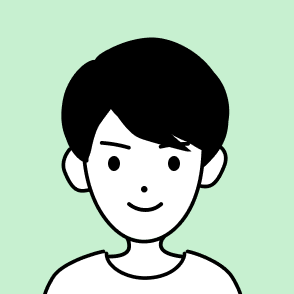
かめ
〈あらすじ〉
IT企業「スピラリンクス」の最終選考に残った波多野祥吾は、他の五人の学生とともに一ヵ月で最高のチームを作り上げるという課題に挑むことに。うまくいけば六人全員に内定が出るはずが、突如「六人の中から内定者を一人選ぶ」ことに最終課題が変更される。内定をかけた議論が進む中、発見された六通の封筒。そこには「●●は人殺し」という告発文が入っていたー六人の「嘘」は何か。伏線の狙撃手が仕掛ける究極の心理戦!
〈感想〉
伏線とミスリードの連続でそれぞれの人物に対するイメージが二転三転。特に終盤にかけて伏線を掻っ攫っていく気持ちよさがたまらない!ただの犯人探しだけでは終わらない人狼的な駆け引きも楽しい!就活あるある満載で就活経験者は笑えると思うし、これから就活する人にもおすすめ!
#読書
#読了
#読書の星

かすみ
下記の本が好きです♪
銀河鉄道の夜/宮沢賢治
星の王子さま&人間の土地
/サン=テグジュペリ
シュガータイム/小川洋子
青い鳥/メーテルリンク
スプートニクの恋人/村上春樹
生まれ出る悩み/有島武郎
赤毛のアン/モンゴメリ
真夜中のピクニック/恩田陸
天使の骨/中山可穂
ムーンライト・シャドウ/吉本ばなな
美しい村・風立ちぬ/堀辰雄
戯作三昧/芥川龍之介
草枕/夏目漱石
魅せられたる魂/ロマンロラン
サロメ/ワイルド
即興詩人/アンデルセン
愛の妖精/ジョルジュサンド
ゲド戦記/ル・グィン
トムは真夜中の庭で/
フィリッパ・ビアス
クローディアの秘密/
カニングズバーグ
ジェニー&トマシーナ/
ポール・ギャリコ
#GRAVITY読書倶楽部
#読書の星

もっとみる 
新着
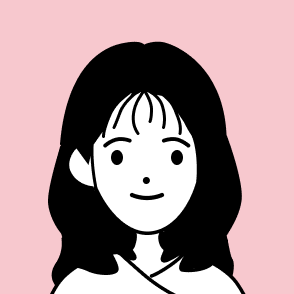
さーな
今日読む本はこの2冊。
シェイクスピアは小学生の時のかな?
年季入ってます✨✨
紙の色が変わっていくのもまた愛おしい。
さむいですから暖かくしてお過ごしくださいね💕︎
#読書 #読書が好き #読書の星



Magic
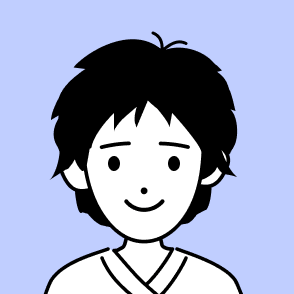
マサヤス 龍之介
#読書の星
☆『年末の一日 / 芥川龍之介』
新潮文庫刊 『戯作三昧 一塊の土』
1976年(昭和51年)8月10日 13刷より
この本は昭和51年の発行である。奥付にそうあるので、私が小4か小5の時に駅前の書店で購入したものだろう。定価は¥180 いい時代だった。
このくらいの価格なら小学生でも容易に手に入れられる。今なら¥500 は下るまい。しかし、今どきの小学生も携帯電話なんぞ持ち歩いているので或いは、青空文庫で読書を済ませるのだろうか。だとすれば味も塩っ気もない話だ。青空文庫は便利には違いないが、ただ字を追うのみである。挿絵も無ければ表紙も無味乾燥。物としてのバリエーションに欠ける。従って想像力の欠如、イマジネーションが培われない。……年寄の戯言だ。
読書子には或いは、この装丁が懐かしい、と思われる方もおられるだろう。今の新潮文庫は完全に違う装丁になっているし、値段だって跳ね上がっていることだろう。
久しぶりに我が敬愛せる芥川龍之介の作品を紹介する。以前芥川龍之介の作品だけを紹介する戯文を連載したことがあるが、この愛すべき小品は抜けていた。
この小品は1926年(大正15年)一月号の『新潮』に初めて発表された。小説というより随筆に近い。今日の様な大晦日にうってつけだ。今から丁度100年前の芥川の年末の一日に起こった小事が書かれている。
『僕』は雑木の生えた、寂しい崖の上を歩いて行った。崖の下はすぐに沼になっていた。その又沼の岸寄りに水鳥が二羽泳いでいた。どちらも薄い苔の生えた石の色に近い水鳥だった。『僕』は格別その水鳥に珍しい感じは持たなかった。が、余り翼が鮮やかに見えるのは不気味だった……そんな夢から起きた『僕』だった。それは、がたがたと云う音が響いていたからであり、その音が年末の大掃除で、妻や伯母のフキが座敷の縁側でせっせと硝子戸を磨いている音だと分かったのは、後架へ小便をしに行った帰りしなにその大掃除の光景を見たからだ。伯母からは「お前、もう十二時ですよ」と言われたが、『僕』は三つの雑誌社から新年号の小説の依頼をけ受けて最後の仕事が終わったのは夜明け前のことだった。芥川の精神疾患については統合失調症であるが、現代ではそういった精神疾患についても普遍化していて、一般的にも可也認知度は広まってきているが、大正末期のこの頃に江戸時代に生まれた芥川の伯母フキにそこは理解してやらないと…と云うのは酷な事なのかもしれない。が、仕事に追われる芥川は田端の自宅では煩い伯母やまだ幼かった3人の子供達がいる以上、静かに小説など書ける環境ではなくこの頃の芥川の夥しい写真は大抵今で云うシティホテルのソファで寛ぐ姿が多いのはそのせいである。芥川はこの文章の中でこう書いている。「朝飯兼昼飯をすませた後、僕は書斎の置き炬燵(こたつ)へはいり、二三種の新聞を読みはじめた。新聞の記事は諸会社のボオナスや羽子板の売れ行きで持ち切っていた。けれども僕の心もちは少しも陽気にはならなかった。僕は仕事をすませる度に妙に弱るのを常としていた。それは房後の疲労※のようにどうすることも出来ないものだった。……」この頃の芥川は統合失調症の諸症状に
頻繁に苛まされ斎藤茂吉のいる青山脳病院へ通院していたが、一向に改善されず悩んでいた。そして芥川が1927年の7月に服毒自殺をとげた最大の要因はこの精神疾患からくる自殺願望の果てによるもの、とされている。そういった背景を頭に入れて読まないとこの時代の芥川の文章は理解し難いと思う。
お昼頃めざめた芥川が朝飯兼昼飯をとった後の二時頃、K君が来訪する。と或る新聞記者でありK君は社用の次いでにちょいと寄った、と言った風だった。「どうです?お暇なら一緒に出掛けませんか」。切り出したのは芥川の方だった。「どこかお出になる先はおきまりになっているのですか?」「いいえ、どこでも好いんです」「お墓は今日は駄目でしょうか?」K君のお墓と言ったのは夏目先生のお墓だった。K君は半年前に芥川と約束した夏目漱石の墓に案内してもらう、という意味だと芥川はここで漸く気付いたのだった。年末にお墓参りをする……芥川自身にぴったりしないものを感じつつ、でも芥川は「じゃあ、お墓へ行きましょう」と安請合いしてしまう。この辺の芥川の気風のよさがいかにも都会人気質でよい。
夏目漱石のお墓は雑司ヶ谷霊園にある。芥川の自宅から一番近い本郷動坂の電停へK君と連れ立った。
「天気は寒いなりに晴れ上がっていた。狭苦しい動坂の往来もふだんよりは人あしが多いらしかった。門に立てる松や竹も田端青年団詰め所と言う板葺きの小屋の側に寄せかけてあった。僕はこういう町を見た時、幾分か僕の少年時代に抱いた師走の心もちのよみ返るのを感じた。」
こういう芥川の文章表現はタイトル通りの読者の期待感を一定量満たすものである。『年末の一日』と言う以上、そこに師走の町の様子が描かれ作者がどういう感慨を抱いたか、を明文化してくれて読者のカタルシスは満たされるからだ。
やがて、護国寺行き路面電車が到着し二人で由無しごとなどを話していた。電車が富士前を通り越した頃、突然電車の中ほどの電球がひとつ、偶然抜け落ちて床で粉々になるハプニングが起こった。「そこには顔も身なりも悪い二十四五の女が一人、片手に大きい包を持ち、片手に吊り革につかまっていた。電球は床へ落ちる途端に彼女の前髪をかすめたらしかった。彼女は妙な顔をしたなり、電車の中の人々を眺めまわした。それは人々の同情を、-ーー少なくとも人々の注意だけは惹こうとする顔に違いなかった。が、誰も言い合わせたように全然彼女には冷淡だった。僕はK君と話しながら、何か拍子抜けのした彼女の顔に可笑しさよりも寧ろはかなさを感じた。」
一見すると芥川のこの女性への眼差しは冷たいように感じるが、最後に女の儚さを感じ入る辺りは人一倍女性にやさしかった都会っ子芥川の面目躍如であろう。
芥川の短編の傑作と言われている『蜜柑』にも似た様な表現があった。横須賀線のボックスシートにたまたま乗り合わせた歳わも行かない少女に対し、散々蔑んだ表現で表した最後の最後で車窓から見送りに来た弟達に対して蜜柑を投げつけた瞬間を切り取り、その神々しいまでの表現で賞賛した。これは芥川固有の表現である。同時に芥川の女性観をよく表しているともいえる。
この後、芥川達は無事に雑司ヶ谷霊園に到着するのだが、案内役だった芥川はあろうことか、不覚にも漱石の墓への道をど忘れしており、小路を行きつ戻りつオロオロしてしまう。幾ら行っても一向に漱石の墓に辿り着かない。最後は施設清掃の女性に聞く有様であった。墓に着くと漱石ファンだというK君はわざわざ外套を脱ぎ、丁寧におじぎをしたが、芥川自身は今更恬然(てんぜん)とおじぎする気にはなれない、というのだ。漱石亡きあと9年が流れた。漱石は芥川文壇にデビューするきっかけを与えてくれた恩師であるはずだが、今の芥川にはそんな感慨に耽るほどの余裕は無かったのだ。これも精神疾患のせいだろう。
やがて、2人はもと来た電車で戻ったが芥川だけ富士前の電停で降りた。東洋文庫にいる石田幹之介に会い、再び動坂に着いた。往来は先程よりも一層混雑していた。「が、庚申堂を通り過ぎると
人通りもだんだん減りはじめた。僕は受け身になりきったまま、爪先ばかり見るように風立った路を歩いていった。すると墓地裏の八幡坂の下に箱車を引いた男が一人、梶棒に手を掛けて休んでいた。箱車はちょっと眺めたところ、肉屋の車に近いものだった。が、側へ寄って見ると、横に広いあと口に東京胞衣(えな)会社※2と書いたものだった。僕は後ろから声を掛けた後、ぐんぐんその車を押してやった。それは多少押してやるのに穢(きたな)い気もしたのに違いなかった。しかし力を出すだけでも助かる気もしたのに違いなかった。
北風は長い坂の上から時々まっ直ぐに吹き下ろして来た。墓地の樹木もその度にさあっと葉の落ちた梢を鳴らした。僕はこう言う薄暗がりの中に妙な興奮を感じながら、まるで僕自身と闘うように一心に箱車を押しつづけて行った。……」
この頃の芥川は、周辺の人々にしきりに自殺を仄めかしたりしていたという。それくらい彼の厭世観はふくれていて、最早それは自分でもおよそコントロール出来ないところまに達していたという。しかし、これを読む限りは、この最後の情景はなんと生気に満ちていることだろう。しかももう自殺願望に漲っていたとされるこの時期に。
これはその死の7ヶ月前に発表された。それでも生きようとしている芥川に私は目頭が熱くなるのを抑え切れなかった。
芥川研究の第一人者だった吉田精一がこの文庫本の解説を書いているが、吉田は、この作品は作者が苦心もし、愛着もあった作品であると書かれている。芥川は箱車のあと口に『東京胞衣会社』
の数文字を書くまで、いく度その一行を書きかえたか知れなかったということである。と解説している。
※ 男女の交合のあと の意味。
※2 出産のとき排泄される胎児を包んでいた膜や胎盤の処理をした会社。
本年も私の様々な雑文をご拝読くださって且ついいね👍をくださった方々に深く御礼を申し上げます。
どうぞ、良いお年をお迎えくださいm(_ _)m
そして、来年も引き続きご厚誼のほどを宜しくお願い申し上げます。
2025(令和7年)年12月31日


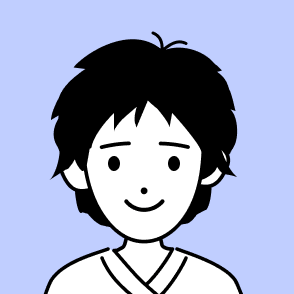
マサヤス 龍之介
#読書の星 #松本隆
☆『風街とデラシネ』田家秀樹 '21 初版 角川書店
『80年代〜大滝詠一との再会 、ロンバケが遅れた本当の理由とは?』
'70年代の終わり頃からニューミュージックが台頭してきていた。歌謡曲とニューミュージックと演歌に洋楽、これらの音楽がヒットチャートを毎週入れ替わり立ち替わり目まぐるしくランダムに乱高下していた。日本の音楽シーンに於いて、若者が"自分たちの音楽"を推す風潮は実は1950年代からすでにあったはあった。ニューミュージックは歌謡曲とは明らかに歌の"造り"が違っていて、歌う楽曲はシンガー自身が作る、所謂シンガーソングライターが大半を占めていた。歌謡曲は作詞家、作曲家、レコードの音を決める編曲家が皆バラバラで餅屋は餅屋の分業制だったのだが、ニューミュージックの潮流を作ったのは、1970年デビューのはっぴいえんどである。但し、シンガーソングライターとはっぴいえんどのやり方はちょっと違っていて、その後台頭するシンガーソングライターたちの大半はレコード化する為の編曲まではプロのアレンジャーに発注したが、はっぴいえんどは自分たちで音を紡いでいった点である。まぁ、バンドだから当たり前、と思うが、1970年当時そこに踏み込むのは、既製勢力の壁が高くレコード業界ではその構図を打ち破るのには相当な勇気が必要だった。日本の音楽シーンにもそれなりの慣習が残っていた時代である。それまでの職業作家だった人たちがこの新たな潮流を嫌っていたのは言わずもがなだったが、一人だけ上手く迎合したのが筒美京平であった。筒美京平の作品はよく、洋楽をモティーフに作られている、と言われたが、その思考や在り方はニューミュージックのシンガーソングライターたちと全く機を一にしている。だから、時代が1980年代に入り洋楽の影響色濃い、ニューミュージックや後のJ-POPの時代に入ってからも筒美京平にはミュージシャンやアイドルからのオファーが絶えなかったのである。要約すると、日本のポップス史とは洋楽を如何に日本人の志向に合わせて作るか?が服部良一の時代からの命題だった、と言える。その日本のポップス史を研究したミュージシャンが大滝詠一だった。彼は1984年にアルバム『EACH TIME』を作り、個人としては初のチャート1位になったのを見届けるかのようにして、あっさりとシンガーソングライターを辞めた。1981年のアルバム『A LONG VACASION』のヒットに端を発して、丸3年間、ミュージシャンとして活躍して、他人への楽曲提供にも応じていたが、その三年間が嵐の様に過ぎ去ると彼は世間から身を潜めるかのように第一線からは遠ざかった。以後、あらゆる趣味に没頭する大滝は、三年周期で様々なことに没入しては印税やラジオの出演料で暮らしていた。活躍していた80年代から彼はテレビという媒体では唄わず全てのテレビ出演を断っていたが、その代わりラジオ📻には積極的に出演していた。そして一度没頭した趣味に回帰することも無かったが、本年9月13日土曜日23:00からNHKEテレで放映されたETV特集でクローズアップされた大滝のドキュメントの中で松本隆がインタビューに答えて……もうちょっと頑固にならずに長生きしてくれてたら、はっぴいえんどの再々結成もあったかもしれない……と語っていた"頑固にならず"は、この趣味癖のことを差しているんだろうなぁ、と私は直感で思っていた。長年の盟友ならでは言葉だった。
そんな大滝がはっぴいえんど以来、作品においては一度も組まなかった松本隆と再び組んだのが、『A LONG VACASION』だった。はっぴいえんど解散後、大滝は自己のレーベル『NIAGARA』(勿論、大滝の名に由来している)を設立したが、レコード会社が難航した。と、云うのも大滝ははっぴいえんど解散後から数々のCMソングを手掛けていて、そのCMソングの音源をレコード化したかった。それを条件に大手レコード会社を回ったが、どこも答えはNOだった。CMの音楽なんて誰が買う?。こんな感じで結局一番好感触を得たのが、大滝が一番嫌がっていたエレックレコードだった。エレックは当時吉田拓郎や泉谷しげる、佐藤公彦、海援隊、ずうとるびらを擁していた会社だったが、印税や契約に関することがアバウトで、大滝が嫌っていたのもそこが一番の要因だったようである。然し背に腹はかえられぬことから大滝は契約したのだが、嫌な予感は当たるもので、エレックレコードは1976年7月15日に倒産した。大滝は自己のレーベル『NIAGARA』を発足し最初に山下達郎や大貫妙子らがいたシュガーベイブのプロデュースを手掛けて、ファーストアルバム『SONGS』を1975年4月に、翌月に自己のアルバム『NIAGARA MOON』 をリリース。どちらも製作費を凌ぐほどの売上は出せ無かった。
田家が書いている通り、当時の大滝は作詞、作曲、編曲、自己のスタジオを持ちレコーディング、トラックダウン、マスタリングのエンジニアまですべて一人で受け持ち、果ては原盤管理に至るまで行った最初のミュージシャンであった。原盤管理についてはフジ・パシフィックの朝妻一郎という音楽に大変造詣の深い理解者がいたので、大滝は自己の音源を他者ではなく自身で管理しなければならない、との信条から1976年7月22日に株式会社ザ・ナイアガラ・エンタープライズを設立、会社の設立資金は朝妻のいるフジ・パシフィックからの援助も受けた。朝妻に関しては大滝のレコーディングに係る必要な資金を供出してくれる正にグレートコンポーザーであった。音楽は文化事業であることを分かってくれていて、単に損得勘定のみで考える人間ではなかった。朝妻がいたから、80年代の大滝の活躍があったと言っても過言ではなかろう。不遇だった70年代の大滝の活動を下支えしたのも朝妻だった。朝妻は、……彼なら間違いなくブレイクするって確信は70年代から思ってました。我々は長い目で音楽を見通さ無ければならないんです。当時の上司からは随分と責められましたが、大滝君や山下君には『時代がまだまだ全然追い付いて無かった』んでしょうね。彼らは先見性をもって音楽と向き合っていたんです。それだけは私の中にもずっとありました。だから、大滝君より山下君の方が♫RIDE ON TIME で先にブレイクしちゃったでしょ?あれれ?ってね(笑) 大滝君の時よりも山下君のブレイクの方が喜びが大きかったかな(笑)信じてたものがやっと報われたんだ、ってね。……
エレックレコードが倒産して大滝はコロムビアレコードと契約したのだが、レーベルは存続可能であり、大滝は契約金まで受け取る事が出来たのだが、大滝は契約そのものより契約金で16チャンネルのマルチトラックレコーダーを購入することの方を嬉しがった、という話は有名だ、と田家は書いている。しかしコロムビアレコードとの契約内容とは3年間でアルバム12枚、シングル12枚、つまり年間で両方4枚ずつというアイドル以上の過酷な条件を突きつけられたという。最終的にその条件はクリアしたが、中には大滝がプロデュースに専念した(2曲はヴォーカルでも参加)シリアポールの『夢で逢えたら』というオールディーズカバーアルバムや大滝の歌が入っていないインストアルバムも含まれていたのだから、コロムビアもよくこれでOKしたな……と思えるアルバムが含まれている。1976年から1979年までの3年余の間は殆ど毎日レコーディングスタジオに居たよ…と大滝の当時"丁稚"だった音楽評論家の湯川学が、後に大滝との回想談を録音したテープの中で親交のあった音楽評論家の萩原健太に語っていた大滝の言である。このテープは今回のETV特集で初披露されていた。田家はこの書の中で、『78年11月、12枚目のアルバム「LET'S ONDO AGAIN」が出て契約満了、彼は晴れて自由の身となった』とある。コロムビア時代の、大滝名義及び大滝詠一名義のみならずとも少なくとも大滝のアルバムとしてカウントできる枚数は総じて11枚であった。これにはエレックレコード時代の『SONGS』と『NIAGARA MOON』のリイシュー盤を含む。田家が指摘した『LETS ONDO AGAIN』以後にはもう一枚アルバムが出ていた。これは契約枚数を消化させる為にコロムビアレコードがナイアガラ時代の山下達郎の音源を編んだベスト盤の様なものだった。それが1980年7月10日にリリースされたTATSURO YAMASHITA FROM NIAGARA / 山下達郎 である。
因みに3年間の内シングルは9枚のみであり、こちらは契約不履行であった。
今月の1日に発行されたナイアガラの丁稚こと音楽評論家の湯川学が嘗て、レコード・コレクターズ誌で連載していた記事が上梓された『A LONG A LONG VACASION』の中でロンバケの担当ディレクターであった旧CBSソニーの白川隆三がインタビューに答えているのだが、大変興味深い証言を取り付けている。今や通説となっている松本隆が妹を亡くしてスランプに陥りロンバケの詞が書けなくなったからキャンセルしてきた、という件のことである。キャンセルしてきた松本に大滝は、発売なんて延期すればいいと言ったのは事実だが、そこで朝妻、大滝、松本、白川の4人が軽井沢で合宿して松本の再起の一助となった、という流れで語られているのは違う、という訳だ。松本隆の妹、由美子が亡くなったのは1980年6月28日のことだという。アルバムの当初の予定が1980年7月28日の大滝の誕生日で設定されていたことと鑑みると、松本の詞が発売の1ヶ月前の段階で上がって無かったというのは直接的には妹の死によるブランクとは関係ない次元でのディレイが生じていた事になる。これは今回出版された湯川の本で改めて分かった事実であった。軽井沢での合宿が発売予定だった1980年7月に行われたことも併せて考えるとロンバケの発売延期はもっと違う理由による制作上の何か、という事に他ならないしその真の理由には誰も何も発言していない。白川隆三はこのアルバムの担当ディレクターでありながら、制作面は全くタッチしていなかったという。白川がディレクターとしてやったことと言えば、大滝のレコーディングためにソニーのスタジオの確保に只管奔走していただけ、と言い切る。大滝の歌入れの為にシナソ(信濃町ソニースタジオ)のスタジオを3ヶ月に亘り立ち入り禁止にしたのは有名な話である。白川は他のディレクター達からのクレームを一身に受けたことは容易に想像できる。発売延期の理由については田家のこの本でも松本隆自身が自分の妹の死で詞が出来なくなり…と語っているCD解説を引用しているため、と紹介しているがこれも事実誤認であることが、今回はっきりしてしまったが白川の発言が如何に貴重な証言かが判るのである。







カナリア諸島にて

猪爪茉莉
起きてから今更ながら、これの長井短ちゃんのを読みました。そろそろいい加減後編買わないと…!
やはり女性の作品のほうが読みやすい!だけでなく、短ちゃんはヲタク女子だから、我々ヲタクはめっちゃ刺さるんだよなぁ[ハートポーズ][最高][すき]
男女のあれこれの話かと思ってたら突然タイトル回収始まって、早く後編読みたい!!
#長井短 #続押し入れの冒険 #読書の星


카오리
本を買う時の決め手を教えてください。
1.表紙のデザインに惹かれた
2.タイトルに惹かれた
3.著者の文体や個性が好きだから
4.帯の紹介文やコメント
5.裏表紙の内容紹介
6.直木賞、本屋大賞を受賞していたり、話題になっているから
7.人から薦められた
8.その他
#現在進行形で読んでる本を教えて
ちなみに私は #片付かないふたり です
#読書
#読書の星
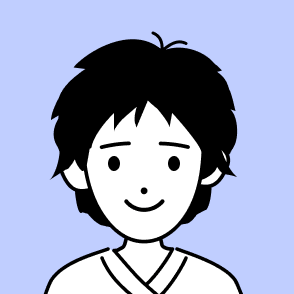
マサヤス 龍之介
#読書の星 #松本隆
☆『風街とデラシネ』田家秀樹 '21 初版 角川書店
80年代〜竹内まりやと山口百恵への提供楽曲
松本隆が79年に提供したその他の楽曲についてもこの本ではしっかりと検証されている。
前回書いたまりやへの提供楽曲♫SEPTEMBER はサウンド的にも作曲者 林哲司自らが編曲に当たりナイーブな松本の詞に彩りを加えている。所収されたアルバム『LOVE SONGS』自体の構成も奮っていて♫SEPTEMBER に入る直前、♫M・A・R・I・Y・A まりや ヒットパレード と云う短いジングルがコーラスで入る。まるでラジオ番組宜しく粋な構成である。間髪入れずに♫SEPTEMBER のブラスで始まるあのOP.が始まる。アメリカのウェスト・コースト調の垢抜けた前奏にギターの短いリフが気が利いている。リズミカルな前奏に続いてまりやの甘いヴォーカルが始まると、もう気分はアメリカンである。そこに終始まりや、大貫妙子、まだデビュー前であったがEPOと云う名前で既にクレジットされた佐藤永子の三人によるよく練られたコーラスワークが巧みで、何ロールも聴き返すうちに段々とまりやの唄よりもコーラスの方にも注意して聴きたくなる、そんな不思議な魅力を讃えた作品である。前回書いたこの楽曲の担当ディレクターだった宮田茂樹が年末の賞レースに参加させるための、勝負シングルに松本を起用する、と云うすでに松本隆はそう云う存在になっていた。だが、松本自身は他方で、ある種の寂寥感を感じてもいて、それがまりやへの他の提供楽曲に色濃く投影された。
話はそこに触れる前に田家は、同時期に山口百恵へ書いた楽曲に触れている。桑名正博へ書いた♫セクシャルバイオレットNo.1 が初めてオリコンチャートの1位になった'79年10月、大阪厚生年金会館のステージに立った山口百恵は俳優 三浦友和との恋人宣言をした。今でこそそう珍しくはないこうした人気タレント同士の交際宣言は、当時波紋を呼び、賛否両論が起こったが世間のムードやマスコミは一様に歓迎・祝福ムードであった。
後に尾道三部作等で評価される名監督の大林宣彦がその殆どのCM作品を演出した百恵と友和共演のグリコアーモンドチョコレートの作品でアツアツ振りを見せつけていた主演の二人が、リアルに交際するという事実にファンからも賛否両論が巻き起こったのだ。そんな事はそれまであり得なかったし、信じたくない、と云うのが素直なファン真理であろう。12月にリリースされた70年代最後を飾る百恵のシングル♫愛染橋 は松本が作詞、アリスの堀内孝雄が作曲であった。…微笑んで渡れば恋がかなう…と云う伝説の橋、大阪・日本橋(にっぽんばし)のすぐ南に位置するこの橋を舞台に、…結婚なんて旧(ふる)い言葉に縛られたくなくて…渡りたいけど渡れない…と云う迷いの歌でもある。CBSソニーのヒットメイカーキングだった酒井政利ディレクターから指定があったと云う関西弁を歌詞に盛り込む、と云う作業は生粋の東京っ子の松本にとっても刺激のある仕事だったに違いない。百恵は翌年'80年3月7日、三浦友和との結婚・引退を表明する。名曲♫SEPTEMBER を含む4曲の松本作品が入ったまりやの3rdアルバム『LOVE SONGS』リリースの2日後のことであった。その中の一曲♫象牙海岸 。
…海岸線沿いに 夏雲が雪崩れると
砂の蜃気楼に 立ちすくむ影ひとつ
人影もない入江 そこが二人の秘密の場所で
象牙海岸と名前までつけた 遠い夏
あれから私 時の波間を
ただ流れ木のように
ひとりで生きて来たの
もう一度 訪ねても
道順さえも記憶の彼方
夢の中で見た 風景のように 遠い夏
あなたのあとに 愛を知っても
ただ流れ木のように
岸辺で踊っただけ
三年をへだてて あなたから来た電話
懐かしい名前に 忘れてるふりをした
冷たいと言われたけど
本当の気持ちもし話しても
過ぎ去った時を埋めるものはない
遠い夏…遠い夏…遠い夏…
♫SEPTEMBER に引き続きこちらも林哲司の作編曲。随所で半和音が活かされた印象的且つノスタルジックな曲構成。まりや自身が後にこう回想している。…今、あらためて感じるのは、林さんは私の声の特徴や歌い癖をうまく捉えて、それを生かすメロディを書いて下さっていたんだなあ、ということ。日本の音楽界でも貴重なMOR(ミドル・オブ・ザ・ロード)の作曲家だと思います…
松本隆は後の自選作品CD集『風街図鑑』の中で、この海岸が何処をモデルにしたのか種明かししている。…伊豆をドライブしていた時にフッと心魅かれた海岸で、二度と自分でも行けない架空の場所…としている。つまり、モティーフは伊豆の海岸なんだろうが、具体的な場所については明かしてはいない。"人影もない入江"とされているから地形が入江になっている伊豆の海岸を探すしかないのだろう。松本に、余り詮索しない事だ、と言われている様なものだ。
もう一つの名曲♫五線紙 。安部 恭弘の作編曲でほぼアカペラのみ、使用されている楽器はギター1本。リズミックで杉真理の楽曲を彷彿とさせる明るい調。それもそのはずで、慶應義塾大学時代は先輩だった杉真理の主宰していたリアル・マッコイズに所属、従って竹内まりやとも知遇を得ていた。安部のデビューは'82年だからこれはまだデビュー前の作品ということになる。早速松本の書いた詞を見てみよう。
…あの頃のぼくらは
美しく愚かに
愛とか平和を詞(うた)にすれば
それで世界が変わると信じてた
耳元を時の汽車が
音もなく過ぎる
ぼくの想い出の時計は
あの日を差して止まってる
十二弦ギターの
銀の糸張りかえ
旧い仲間もやって来るさ
後ろの席でひっそり見てくれよ…
松本が『風街図鑑』の中で書いたところによると…今みたいにはっぴいえんどが伝説になっていなかった時代だから、(竹内まりやが)あの曲を選ぶセンスを渋いなぁと感心した。だからその人に詞を頼まれたときに、12弦ギターを抱いた大滝(詠一)さんや細野(晴臣)さんが行間に見え隠れしてしまったんだね。きっと一人で作詞家してるのが寂しかったんだと思う…と非常に深い心情を語らせていた。この発言は松本の当時の心境が実にしみじみと語られいて、興味深い。そう言えば、この曲は以前竹内まりやのアマチュア時代に牧村憲一が何とか口説いてレコーディングさせた鈴木茂の曲になる
♫8分音符の詩(うた) のアンサーソングであると田家は分析している。はっぴいえんど結成から丁度10年の節目、この年の松本隆の感傷なのであった。松本自身も丁度30歳になっていた。
続





象牙海岸
Y
#読書の星

もっとみる 
関連検索ワード
