人気

あぐら

酒桜
回答数 26690>>

しん
#忍たま乱太郎



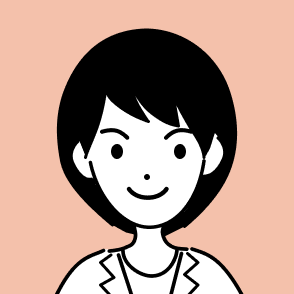
🪦しゅ
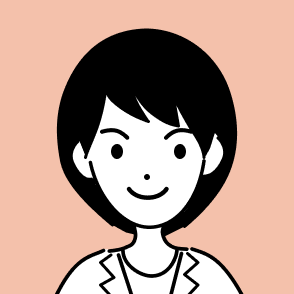
🪦しゅ
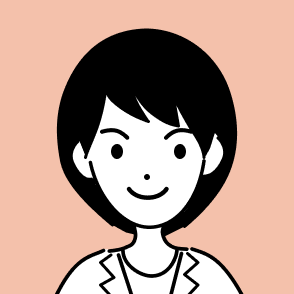
🪦しゅ
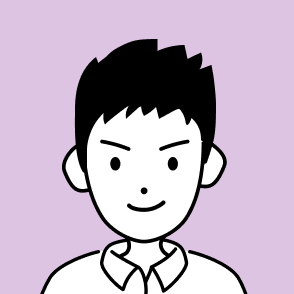
いな
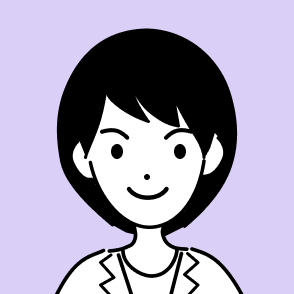
南の島
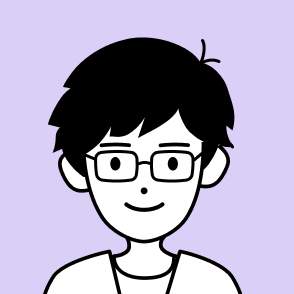
ジュラ
もっとみる 
関連検索ワード
新着
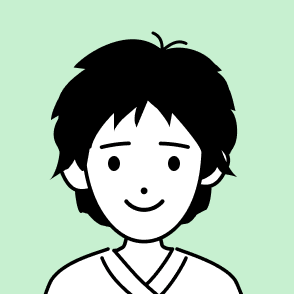
サウス
empty
私はデジタルカメラでそれを撮影し、紙を外の王盟に渡した。もし金歯が戻ってきたら、直接返すように。私が故意にそれを横取りしたと思われたくない。
私の祖父は長沙の土夫子、つまり墓荒らしだった。祖父がこの行に入ったのは、全く不思議なことではない。現代風に言えば世襲だ。私の高祖父のさらに高祖父が13歳の那年、華中一帯で旱魃が起きた。あの時代、旱魃が起きれば飢饉になり、金があっても食べ物を買うことができなかった。当時、長沙の辺鄙な地域には何もなかったが、古墓だけは多かった。だから、山に寄れば山を食べ、墓に寄れば墓を食べる。村人総出で墓を掘り返した。あの数年、どれだけの人が餓死したかわからないが、彼らの村だけは一人も死ななかった。全て墓から掘り出した物を外国人と食料と交換していたおかげだ。
後になって時間が経つにつれ、これが一種の文化的な蓄積となった。私の祖父の代になると、すでに行規や流派の区別ができていた。歴史的に盗墓は南北二派に分かれる。土夫子は習慣で分けるなら、南派に属するべきだろう。主に土を探って古墓を探し、民国以前は探錐(たんすい)を使い、民国以後は洛陽鏟(らくようさん)を使った。鼻一つで深さや朝代を断定できた。今の多くの小説では、何かにつけて洛陽鏟と描写されているが、実は北派は洛陽鏟を使わない。彼らは陵墓の位置や構造の正確な判断に長けており、いわゆる「尋龍点穴」である。
南北派は文人墨客が分けた大派閥で、もともと江湖の世界とは関係がなかった。しかし、幾度もの乱世を経て、半端な者が多くなり、次第にこれらのものがこの業界に持ち込まれた。私の祖父は以前、自分自身に定義を下したことはなかった。後になって弟子たちが尋ねてきて、初めて自分のやり方はおそらく南派に属するのだと意識した。二派は確立以来、絶え間ない争いを続けた。南派は北派を、不実で小賢しく、墓を盗むのにそんなにたくさん名目を設け、中に入って物を取ったらさっさと出てくればいいのに、一叩き二叩きと官僚主義的だ、と言った。南派には規則が少なく、かつ死人を忌避することもなかった。北派の者は南派を土狗(どけん)と罵り、文物を台無しにし、盗んだ墓で崩壊しなかったものは一つもなく、死人まで引っ張り出して売ると言った。南派は北派を偽君子と罵り、明らかに賊のくせに何か特別なことのように振る舞うと言った。後になって、両派の者が墓を探す際、一つの墓を巡ってしばしば乱闘騒ぎにまで発展した。湘西地方では even 墓の中での死者を巡る争いも発生した。最後に両派はついに長江を境に分かれた。北派は「倒斗(ダオドウ)」(墓をひっくり返す)、南派は「淘沙(タオシャ)」(砂をあさる)または「淘土(タオトゥー)(土をあさる)と呼んだ。洛陽鏟は分かれた後に発明されたもので、北派は使おうともしなかった。
解放後になると、南北派の境界線はそれほど明確ではなくなった。私の祖父は自分を南派だと言っていたが、彼の仲間の古老たちの中には北派も少なくなかった。彼らの子供世代はさらにごちゃ混ぜで、これらのことを細かく追究する必要もない。
私の祖父は字が読めなかった。解放後、文盲撲滅クラスに入った時、彼はまだ砂をあさることしかできず、字を学ぶのはほとんど死ぬほど大変だった。彼が文化的な教養を得たおかげで、彼の経験のいくつかを記録することができた。長沙の鏢子嶺のあの三番目の兄貴、つまり私の祖父のこれらの出来事はすべて、彼が古びたノートに一字一字記録したものだ。私の祖母は教養人で、名家の令嬢だった。彼のこれらの話に惹かれて、最終的に祖父は杭州に婿入りし、ここに家を構えた。
あのノートは我が家の家伝の宝といえる。祖父の鼻はあの事件後、完全に駄目になってしまった。後来、彼は犬を訓練して土の匂いを嗅がせ、「狗王(ゴウワン)」というあだ名を送られた。これは実話で、今でも長沙で土夫子をしていた者、古老たちは皆知っている名前だ。
祖父がその後どうやって生き延びたのか、私の二伯父と曾祖父、さらにその上の曾祖父が最後どうなったのか、祖父は決して教えてくれなかった。私の記憶の中には、片目で片腕の二伯父の姿はない。おそらく本当に凶多吉少だったのだろう。このことに触れると、祖父はため息をつき、ただ「それは子供が聞く話じゃない」と言うだけだった。私たちがどんなに聞いても、どんなに甘えても、彼はひと言も漏らそうとしなかった。最後に、私たちが年齢を重ねるにつれ、子供時代の好奇心も次第に失われていった。
empty
50年後、杭州の河坊街にある西泠社。私は祖父のノートを読みふけっていたが、老人に声をかけられ、思考が中断された。私はノートを閉じ、彼を一瞥した。
「ここでは拓本、買い取ってもらえますか?」彼は聞いてきた。様子がどこか普通ではなく、何か特別な用件があるようだった。
臨時の客など、私はあまり相手にしない。骨董市場での取引のほとんどは水面下で行われるものだ。表向きの商売は小さな取り引きばかりで、大した儲けにはならない。だから適当にあしらった。「ええ、買い取りますよ。ただ、高値は付けられませんけどね」——要するに、良さそうな物がなければさっさと失せろ、本を読む邪魔をするな、という意味だ。
「へえ、じゃあ、いくつか紹介してもらえませんか?」その男は聞いてきた。スーパーでもやってるような口ぶりだ。
私は少しいらついた。この商売は、三年に一度の取り引きで三年食べていくような世界だ。普段はのんびりしているから、半可通の客に構うのは最も嫌いなことだ。骨董品というものは、一つ一つに物語がある。本当に説明し始めたら、何日かかっても終わらない。客一人一人が来るたびに紹介などしていたら、商売にならない。いっそのこと喫茶店を開いたほうがましだ。
私は手を振って、「こちらでは紹介業務は行っておりません。隣に何件かございますので、そちらへお回りください」と言った。
彼は少しきまり悪そうに私を見たが、去ろうとしない。「では、一つお聞きしたいのですが、ここに戦国帛書(はくしょ)の拓本はありますか? 50年前に長沙であくどい盗掘者たちが盗み出して、アメリカ人にだまし取られたあの巻物の?」
「アメリカ人にだまし取られたって、あなたがおっしゃってるじゃないですか。まだあるわけないでしょう」私はむっとして言った。「拓本を探すんなら、もちろん市場をあさるものです。特定の一冊を指定して探せるもんですか。見つかるはずがないでしょう」
彼は声を潜めた。「あなたにコネがあると聞きました。老癢(ラオヤン)の紹介で来たんです」
老癢という名前を聞いて、私は内心驚いた。老癢は一昨年、刑務所に入ったんじゃなかったか? まさか、私のことを自供したのか? そうすると、目の前のこの男は公安か? 私は少し慌てて、言葉もどもってしまった。「ど、どの老癢です? 知りませんね」
「わかります、わかります」彼はへらへら笑い、懐から懐中時計を取り出した。「ほら、老癢はこれを見ればわかると言ってましたよ」
その時計は、老癢が昔、東北地方にいた時に初恋の人がくれたものだ。彼は命のように大切にしていて、酔っぱらうとこの時計を取り出しては眺めながら、「鵑(ジュエン)か、麗(リー)か」などと叫んでいた。私は「お前の女ったら、いったい何ていう名前なんだ?」と聞いたものだ。彼はしばらく考えたが、結局泣き出してしまい、「俺、どうも忘れちまったらしい」と言った。この老癢がこの男に時計を渡したということは、この男には確かに何か来歴があるのだろう。
しかし、私はいくらこの男を見ても、嫌な顔つきで、まともな人間には思えなかった。だが、老癢の紹介なら、多少は顔を立てなければならない。それに、向こうから訪ねてきているのに、話を最後まで聞かせずに追い返せば、恨みを買うかもしれない。
私は少し考え、やはりさっぱりとした態度をとることにした。手を上げて、「このお方、では老癢さんの友達ということで、私に何のご用ですか?」と言った。
彼は歯を見せて笑い、大きな金歯を一本見せた。「私の友人が山西から何かを持ち帰ったんですが、本物かどうか見ていただけませんか?」
私はこれを聞いて、だいたい察しがついた。この田舎者は盗掘者だろう。何か良い物を掘り出したが、自分では見分けがつかず、鑑定を頼みに来たのだ。まったく、世の中にはいろんな奴がいるものだ。正規の骨董市場にまでやってくる奴がいるなんて。
だが、こういう連中は大抵命知らずだ。できることなら敵に回したくない。私はサービス業の標準的な笑顔を作り、彼に言った。「あなた、いかにも北京なまりでいらっしゃる。北京の大物がわざわざ南方まで私に相談に来るなんて、お持て成しすぎですよ。北京には優れた方はたくさんいらっしゃるでしょうに。おそらく、あなたの真意は他にあるのでしょう」
彼はにんまり笑った。「南方の人は抜け目ないって、ほんとうですね。あなたはお若いのに、なかなか見透しがきく。実を言うと、今回私が訪ねてきたのは、実はあなたではなく、ご老爺様にお目にかかりたいのです」
私は内心激しく動揺し、たちまち表情が硬くなった。私の祖父の経歴は非常に特異で、彼のことを知る者はごくわずかだ。誰かが尋ねてくるということは、大概悪い知らせである。冷たく彼に聞き返した。「私の祖父に? いったい何のつもりだ?」
金歯の爺さんは私の表情が一変したのを見て、驚いたように慌てて言った。「何のつもりもありませんよ、ただの普通の骨董愛好家です。ただ、ご老爺様が当年、長沙の鏢子嶺(ビャオズーリン)で戦国帛書を盗み出された後、拓本を一、二部お手元に残されていないか知りたいのです。私たちは一部購入して、私たちが持っている巻物と同じかどうか確かめたいのです」
彼の言葉が終わらないうちに、私は傍らで居眠りしている店員に向かって怒鳴った。「王盟(ワンメン)、客を送れ!」
金歯の老爺さんは慌てた。「ちょ、ちょっと待ってよ、なんで話している途中で追い出すんだ?」
「遅すぎたんだよ」私は言った。「老爺は去年、あの世に行ってしまった。彼に会いたいなら、帰って歪んだ木に首を吊って死ねば、ひょっとしたら会えるかもしれないな!」そう言いながら、彼を外に押し出し、戸口のところまで追いやった。
大金歯の老爺さんは驚くほど厚かましく、戸口の外の柱にしがみついて、どうしても離れようとしない。「待て待て、もう一言だけ言わせてくれ、もう一言だけ!」
私はしばらく引っ張ったが、彼を動かせず、どうしようもなかった。「早く用件を言え。商売の邪魔をするな!」
「小僧、ずいぶんと聞き苦しい物の言いようだな」彼はずるそうに笑った。「老爺さんが亡くなられたのは構わない。別にどうこう言うつもりはないんだ。せめて、私が持ってきた物を見てくれよ。老癢の顔も立ててくれないか?」
私は彼を一瞥した。この男は作り笑いを浮かべ、ここに居座るつもりでいるようだ。しかも、外には彼に惹かれて大勢の観光客が集まっている。このまま騒ぎが続けば、明日の新聞に載ってしまうだろう。私は仕方なくうなずいた。「わかった、中に入ってゆっくり見せろ。ここでサルみたいな真似はするな。ただし、醜い前言っておく。何かわかるかどうか、保証はできないぞ」
「はいはい、私もこの業界の者です。ルールはわかっています!」
実は、この戦国帛書は20巻以上あり、各巻がそれぞれ異なっている。祖父が当時盗み出したのは、そのうちのごく一部に過ぎない。確かに何点かの拓本が現在まで残っており、それは我が家の秘蔵の宝で、市場に出回っている金では買えないものだ。私がでたらめを言おうとも、この老爺さんには絶対に気づけない。
私たち数人は奥座敷に戻り、私は王盟に老爺さんにお茶を出すよう言い、彼に品物を出すよう求めた。金歯の老爺さんは少し照れくさそうに懐から白い紙を一枚取り出して私に渡した。私はそれを見て腹が立った。おいおい、コピーじゃないか。
「そうですよ、あの宝物をそんなところに持ち歩けるはずがないでしょう。ちょっとした衝撃でも壊れてしまいますから」彼は言い、わざとらしく声を潜めて「私にコネがなければ、とっくに国外に流出していましたよ。人民への奉仕といったところですかね?」と付け加えた。
私はあははと笑った。「君の様子からして、どう見ても盗掘者だよ。売りに出せないんだろう? これは国宝だ。首が飛びたくなかったらな!」
一言で見抜かれて、老爺さんの顔色は青ざめた。しかし、私に頼み事があるので、我慢しなければならない。「そうとも言い切れませんよ。どの業界にもそれぞれの流儀があります。あなたの老爺様が当年、長沙で土夫子をなさっていた頃は、それこそ名を轟かせていたんです…」
私は人差し指を彼の鼻先に突きつけて言った。「余計なことは言うな。これ以上うちの爺さんの話をしたら、この品物は自分で持って帰ってゆっくり見てろ!」
「はいはい、もうやめます。早く見てくださいよ。私もさっさと逃げ出したいんです」
私はその白い紙を広げ、中のレイアウトを見ただけで、これは保存状態の良い戦国帛書だが、祖父が当時盗み出したものではないとわかった。しかし、よく見ると、本物とはいくつか異なる点もあった。一旦見ると約束した以上、いい加減なことはしたくない。後で彼らがトラブルを起こしに来るのも困る。だから、その品物をルーペの下に置き、注意深く観察した。
タバコ一本分ほど時間が経って、私はようやく見当がついた。期待に満ちた目で私を見つめる金歯に向かって、首を振った。「コピーから見える線の様子からすると、年代は古いものの、後世の朝代、つまり漢代のものと推測される偽物です。これはなかなか扱いにくい代物です。あなたのこのコピーは質が悪すぎて、確信を持っては言えませんが、おそらく漢代のものでしょう。つまり、偽物と言えば偽物ではないし、本物と言えば本物ではない。そういう品物です」
「では、これはあなたの老爺様が盗み出したものですか?」
「正直に言うと、老爺が盗み出したあの巻物を、彼自身一目も見ないうちにアメリカ人にだまし取られてしまったんです。あなたのその質問には、とても答えられません」私は誠実そうな様子を装ってため息をついた。もし彼に私が拓本を持っていると知られたら、きっと外部に漏れ、他の者を呼び寄せることになり、対処が難しくなる。彼を丸め込んで、自分で他の方法を探させるほうがよい、と考えた。
金歯の老爺さんは私の様子を見て、本当に信じ込んだようだ。ため息をついた。「それは本当に不運でした。どうやらあのアメリカ人を探しに行くしか、望みはなさそうですね」
「どうして、あなたたちはどうしてそんなにあの一巻にこだわるんだ?」私は聞いた。これは奇妙なことだ。古籍の収集は縁によるものだ。戦国時代の古籍20巻全てを揃えようだなんて、どうも欲張りすぎる。
「小兄弟、隠さずに言うと、私は本当に盗掘者じゃないんです。私のこの体を見てください。とてもそんなことをする体力がありませんよ。ですが、私の友人は確かにこの道の専門家です。彼が何を考えているのか、私にはわかりません。とにかく、本人には本人の道理があるので、あまり詳しくは聞けないんです」彼はへらへら笑い、首を振ってもう一度ため息をついた。「では、あなたのそのお言葉を頂いたので、私は諦めます。これ以上小兄弟の邪魔はしません。先に失礼します」
そう言って彼は立ち上がり、私に拳を合わせると、振り返らずに去っていった。彼ががっかりして去っていくのを見て、私は少し気の毒に思った。しかし、この商売をしている者は、どこでも細心の注意を払わなければ絶対にやっていけない。彼のような些細な問題は、せいぜい時間を少し余計に費やす程度だ。私は考え、思い直した。
その時、私は彼がそのコピー用紙を持って行かなかったことに気づいた。おそらく、先ほどのショックが大きすぎたのだろう。私はそれを手に取り、内容を見た。すると、ある興味深い図柄を見つけた。それは狐のような人の顔で、瞳孔のない二つの目が立体的に浮かび上がり、紙面から凹み出しているかのようだった。私は思わず冷やっとした息を吸った。先ほどは年代の判断に気を取られて、内容をよく見ていなかった。今見ると、これもまた珍しい貴重な品物らしい。老癢が出てきたら、このコピーを使って偽物の拓本を何枚か作り、楽しむこともできそうだ。

コトリバコ
東京公演配信初日昼しか見てなかったから、全景がよりいいなと思えたし、内容も同じはずなのに日替わりでより面白くしてくれたり、殺陣が凄かった
あら長夜間訓練の殺陣の時ずっと縄鏢で首使ってましたか?私は全景で初めて見たんですけど凄すぎな?
そして発表された劇団、リブート。キャス変言われてるけどどうなんだろう。私は今年ハマったから今までの弾切り替わり後に見てる訳よ。今回の4年生とかも。今からその瞬間に当たると思うと泣きそう。
勿論現キャストでやって欲しいのもある。でも変更になった時温かく受け入れる覚悟もしなきゃね!!だって忍ミュファミリーだから!
empty
七星魯王 第一章 血屍
日本語訳(現代的な表現に意訳)
50年前、長沙の鏢子嶺(ビャオズリン)で、四人の墓荒らしが小さな丘の上にしゃがみ込み、全員が無言で地面に刺さった洛陽鏟(らくようさん/探り棒)をじっと見つめていた。
鏟の先には、地下から持ち上げたばかりの土がついていた。しかし奇妙なことに、その土は絶え間なく真っ赤な液体を滲み出させており、まるで血に浸したばかりのように見えた。
「こりゃ、大変なことになったぞ」老練なリーダー格の老煙頭(ラオイエントウ)は、キセルを地面でトントンと叩きながら呟いた。「下には“血屍”(ちし/血の屍)がいるに違いない。下手をすると、俺たち全員、ここでお陀仏だぞ」
「やるのか、やらないのか、はっきりしてくれよ!くどくど言うな!」片目の若い男が言い放った。「親爺、足腰が悪いんだから、無理して下りるなよ。弟と二人で行くからよ。何がいるか知らないが、やつらに機関銃の一斉射撃を浴びせてやる」
老煙頭は怒るどころか笑い、傍らにいる大男の大胡子(ダフーズ)に言った。「お前のところの次男坊は、やけに調子に乗ってるな。いつひっくり返ってもおかしくないわい。もっとしっかりしつけをしろ。俺たちの商売は、銃さえあればどうにかなるもんじゃないんだぜ」
大胡子は若い男を睨みつけた。「小僧、どうして老爺さんにそんな口の利き方をするんだ!老爺さんが土を掘っていた頃、お前はまだ母親の腹の中にいたんだぞ!」
「だって…間違ってないだろ?ご先祖様も言ってたじゃないか、血屍は良いものだ、下には宝物がたくさんあるって。下りなきゃ、せっかくのチャンスを棒に振るぞ」
「この小僧、まだ口答えする気か!」大胡子が手を挙げて殴ろうとしたが、老煙頭がキセルで制止した。
「親父さんも親父さんだな、殴ることしか知らないのか。今、自分がどこにいるのか分かっているのか?お前だって若い頃は同じだっただろうが、親がそうなら子もそうなるってやつだな!」
片目の若者は父親が窘められているのを見て、うつむきながらこっそり笑った。老煙頭は一度咳払いをすると、その片目の青年の頭をキセルで軽く叩いた。「何を笑ってるんだ?血屍に遭遇するなんて、大げさな話じゃない。この前、お前の二爺さん(祖父の弟)が洛陽でこれを見つけた時は、気が狂ったまま今でも正気に戻ってないんだぞ!お前みたいな口ひげも生えていない小僧が、そんなに軽率なことをするなんて、命がいくつあっても足りないぞ」
「じゃあ、結局やるのか、やらないのかよ!」片目の青年はイライラしながら頭を掻いた。
老煙頭は何度かキセルをふかふかと吸い、空を見上げて、どうやら決心が固まったようだった。大胡子に向かって言った。「やるしかあるまい。まず俺が下りる。お前はその後について来い。次男坊は土耗子(ツーハオズ/道具の一種)を持ってしんがりを務めろ。三男坊は下りるな。四人も下りたら、いざという時に退却できん。お前は土耗子の尾綱をしっかり持っていて、俺たちが中から合図したら、すぐに引き上げろ」
一番年下の少年は不服そうだった。「嫌だよ!ひいきするな!お母さんに言っちゃうぞ!」
老煙頭は大笑いした。「ほら見ろ、三男坊はまだ未熟者だな。いいから騒ぐな。後で金の短刀を取ってやるからな」
「いらないよ。俺が自分で取るから」
すると、片目の次男がカッとなり、三男の耳を捻じった。「てめえ、俺に因縁をつけてんのかよ?本気で怒らせたいのか?」
末っ子の少年は普さんから殴られ慣れていたので、兄が本当に怒っているのを見て声も出せず、父親に助けを求めるように見つめた。しかし父親はもう道具の準備を始めていた。次兄は得意げだった。「お前はどうしてこうも憎たらしいんだ?今回は親父もお前の味方じゃないぞ。これ以上騒いだら、股間を捻り潰してやる!」
三男は驚いて慌てて股間を押さえ、逃げ出した。
その時、大胡子の叫び声が聞こえた。「次男坊、いつまでもダラダラしてるんじゃねえ!道具を持て!行くぞ!」そう言うと、彼は既に旋風鏟(シャンフェンサン/掘削道具)を振り回し始めていた。
30分後、盗掘穴は深くて底が見えなくなっていた。時折、息継ぎに上がってくる次男以外は、穴の中からはほとんど音が聞こえなかった。三男は待ちくたびれて、穴に向かって叫んだ。「おじいさん、掘り抜けたかー?」
数秒後、穴の中からかすかな声が聞こえてきた。「わ…からない…上に…いろ…綱を…しっかり持て…!」次兄の声だ。そして老煙頭の咳き込む声が聞こえた。「静かに…しろ…聞け!何か動きがある…」
その後、死のような静寂が訪れた。三男は下で何か異変が起きたのだと悟り、怖くて声も出せなかった。突然、穴の中から足の踏み場もないほどの不気味な音が聞こえてきた。「ケケケケ」という音は、田んぼのカエルの鳴き声のようだった。
そして次兄が下から大声で叫んだ。「三男、引け!」
三男はためらわず、地面を蹴って土耗子の尾綱を握り、力一杯引き上げた。数回引いたところで、突然綱がピンと張り、下で何かが綱を噛みついたように、反対方向に強く引っ張られる力を感じた。三男はこんな状況になるとは夢にも思わず、穴の中に引きずり込まれそうになった。とっさに機転を利かせ、すぐに綱を自分の腰に巻き付け、全身で後ろに倒れこんだ。背中は地面と30度の角度になっていた。これは村で他の男の子たちと綱引きをした時に使った技で、こうすれば体重全体が綱に掛かり、ロバ一頭分の力にも対抗できる。
果たして、これで穴の中の何かと拮抗状態になった。双方とも力を込めていたが、互いに微動だにしなかった。10数秒ほど僵持状態が続いた後、穴の中で拳銃の発砲音が聞こえ、父親の叫び声がした。「三男、逃げろ――――――!!!」そして綱が急に緩み、土耗子が「ビュッ」という音と共に穴から飛び出してきた。何かがぶら下がっているようだった!その時、三男はそれどころではなく、土耗子を受け止めるやいなや、振り返らずに全力で走り出した。
彼は一気に2里(約1km)以上走ってから、ようやく足を止めた。懐から土耗子を取り出して見ると、驚いて叫び声を上げた。土耗子には何も引っ掛かっておらず、血まみれの切断された手だけがぶら下がっていた。そしてその手が彼の次兄のものだと認識した。どうやら次兄は、死ななくても重傷を負ったに違いない。
三男は普段から次兄にいじめられていたが、兄弟の絆は深かった。今回本当に大変なことになったかもしれないと思うと、頭に血が上り、危険を顧みず兄と父親を助けに行こうと決意した。ちょうど振り返ったその時、背後の葦の茂みの中に、真っ赤な何かがしゃがみ込み、まさしく自分をじっと見つめているのに気づいた。
三男もただ者ではなかった。普段から父親について危険な目に遭い、奇怪なことを数多く見てきている。地下では何が起こってもおかしくないこと、最も重要なのは慌てふためくことではなく、臨機応変に対処することだということを知っていた。どんな化け物だろうと、機関銃の一斉射撃を浴びせて粉々にしてしまえば、もう怖くはない。
彼は心を落ち着け、退くどころか、一歩一歩そのものに近づいていった。片手には拳銃をしっかり握りしめている。赤いものが少しでも動きがあれば、まず頭目がけて弾の雨を浴びせてやるつもりだ。
その真っ赤なものは草むらにしゃがんだまま、微動だにしなかった。三男が三步の距離まで近づき、よく見ると、頭皮が痺れるような感覚とともに、胃の中がぐるぐる回るのを感じた。それは明らかに皮を剥がれた人間だった!全身血まみれで、まるで自分自身で人皮から絞り出されたように見える。これが血屍の正体なのか?
彼は下唇を噛みしめ、腰の長い馬刀を抜き、それが何なのか確かめようと突き刺そうとした。しかし、身をかがめる前に、その怪物は突然身を反らし、飛びかかってきた。三男は眼前に赤い光が走るのを見たが、もう避けるには遅すぎた。電光石火の間、彼は両足を滑らせ、勢いで後ろに倒れこむと同時に、拳銃の全弾を至近距離でそのものの胸元に浴びせた。そのものは血しぶきを上げながら数歩後退し、草むらに倒れこんだ。
一方、三男もその勢いで転がり、すぐに跳び上がった。振り返ってそのものの頭を狙い、引き金を引いた。しかし、「カチッ」という音とともに、銃がジャムってしまった!
この旧式拳銃は、彼の二爺さんが昔、ある軍閥の墓から掘り出したものだ。使われてからそれほど年月は経っていないはずだが、残念ながらここ数年、父親についてあちこち駆け回り、手入れする暇もなかった。普段撃つ機会もほとんどないので、銃身が熱くなるとすぐにジャムってしまう。全く、ついてない時は何をやってもうまくいかない。
三男は血まみれのものがもがきながら起き上がってくるのを見て、内心で呪いながらも、先ほどまでの捨て身の勢いは消え失せていた。手近にあった拳銃を振り回して投げつけると、当たったかどうかも確かめず、振り返って逃げ出した。今度は後ろも振り返らず、前方の大木を目指して一直線に走った。どうせ奴は木には登れまい。まず木の上に逃げ込んで身を隠そうと考えた。
そう考えていると、突然足が何かに引っ掛かり、地面に思い切りぶつかり、顔全体を木の切り株に打ちつけて、鼻と口の中が血だらけになってしまった。
この転倒はかなりひどく、三男は目まいを感じた。歯を食いしばって立ち上がろうとしたが、片腕全体に力が入らないことに気づいた。その時、背後に風切る音が聞こえ、振り返ると、怪物がほんの数歩の距離まで迫っていた。閻魔大王が名を呼びに来たのだ!
三男も割り切りのいい男で、自分に死期が迫っているのを悟り、恐れることもなく、ただ苦笑いを一つ漏らした。そしてあえて地面に伏したまま、死を待つことにした。刹那間に、怪物は彼の背中に飛び乗り、その足で強く踏みつけた。三男は喉の奥から甘い味が広がり、胆液まで吐き出されそうな感覚を覚えた。同時に、背中に猛烈なかゆみが走り、眼前がすぐにかすんでいった。
自分が毒にやられたこと、そしてその毒性が極めて強いことに気づいた。かすんだ視界の向こうに、懐から飛び出した次兄の切断された手が、何かを握りしめているのが見えた。
彼は必死に目をこすり、よく見ようとした。それは一枚の絹の布切れだった。三男は思った。次兄が命を懸けて盗み出そうとしたものは、きっと普通のものではないはずだ。今、彼らがどうなったかは分からない。俺がこの品をしっかりしまっておかなければ。万一、俺が本当に死んだとしても、彼らが俺の屍体を見つけた時、ここからこれを見つけ出せる。そうすれば、次兄の手も無駄にはならないし、俺も無駄死にはしない。そう考え、彼は必死にその絹の布を切断された手から引き抜き、自分の袖に押し込んだ。
その時、彼の耳も耳鳴りがし始め、目は紗がかかったようにかすみ、手足は冷たくなっていった。これまでの経験から、今ごろズボンの中は大小便でぐちゃぐちゃになっているに違いない。
「屍毒に当たった者は皆、死に様が酷い。隣村の二丫頭(ある少女の名前)に見られなければいいが」彼は朦朧とした意識でふと思った。脳はもう彼の言うことを聞かなくなっていた。その時、盗掘穴で聞いたあの「ケケケ」という不気味な音が、かすかに聞こえ始めた。
三男は漠然と一抹の不安を感じた。この音はさっき穴で聞いたのとは何か違う…。しかし、もはや思考する力もなく、条件反射のように顔を上げようとした。そこに見えたのは、巨大な奇怪な顔が、身を乗り出して自分を見下ろしている姿だった。瞳のない二つの目には、まったく生気がなかった。
(訳注)
本文は中国の小説『盗墓筆記』の一節です。独特の方言や土俗的な表現が含まれるため、完全に直訳すると非常に分かりにくくなるため、日本語として自然な表現になるよう意訳を中心に処理しました。固有名詞(人名、地名、道具名)は、原文の音やイメージをなるべく残しつつ、日本語で読みやすい表記を心がけました。必要に応じて説明を追加しています

愛理(雑
もっとみる 
おすすめのクリエーター

しん
最近はおやすみイラスト投稿してます、おやすみと言いながら寝てない
ウルトラマンは永遠のヒーロー
フォロワー
0
投稿数
133

コトリバコ
もう今は忍たま忍ミュどハマり野郎です‼️
同士の方は仲良くしてください(/// ^///)
食べることとディズニー行くのが好き♡
フォロワー
0
投稿数
111
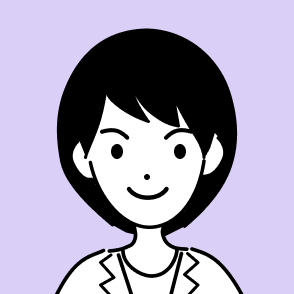
南の島
成人済み。⚠️共感できない人はコメント残さないでください。不愉快です。
アニソン聴きながらイラスト描いてます。シン様9割。時々他版権、BLも描きます。アクセサリーやアニメグッズ、ファッションが好きです。
フォロワー
0
投稿数
81

酒桜
Mortal Kombatをメインにゲームしてるよ
気の合う人うえるかむ
仲良い人しかフォロバせん
ただの中学生で健全な男子(?)です
ぜひ仲良くしてください(´・_・`)
psのID
pai_no_mori
フォロワー
0
投稿数
52
empty
私は日本語を無理している中国人です。日本人の友人を作りたいので、よろしくお願いします。たまにAIで中国小説の日本語版を翻訳することがあります。(小説の作者は私ではありません。)
フォロワー
0
投稿数
12
