関連惑星
町中華の星
39人が搭乗中
参加
皆様の身近な町中華、地域の違いで種類も違う🎶
町中華を楽しみましょう🍜🍥
蝶華の星
24人が搭乗中
参加
⟡.·*.··············································⟡.·*.
Belleの惑星へようこそ₊˚⊹ 𐦍༘⋆₊ ⊹
好きな事投稿して頂けたらと思います♡
⟡.·*.··············································⟡.·*.
豪華客船クルーズの星
18人が搭乗中
参加
🚢 豪華客船クルーズの星へようこそ🌟
クルーズに興味のある人、これから乗ってみたい人、クルーズが大好きな人♥️
未経験者も経験者もどなたでも大歓迎🌊
▫️おすすめの客船・寄港地情報
▫️船旅の服装・持ち物
▫️これから乗りたいクルーズの話
などなど、自由に語り合える“船好きの港”のような場所にしたいです⚓️💕
気軽に自己紹介や旅の写真もどうぞ📸
#クルーズ #船旅 #海のある暮らし
#豪華客船 #船友さん大募集
#クルーズに狂うず仲間募集
#海の上の居酒屋
麗華の星
12人が搭乗中
参加
愛する事を知らなければ
こんなにも辛くないのに
愛される事を知らなければ
こんなにも君を想う事もないのに
だけど僕は後悔はしない
愛し愛される事を教えてくれて
ありがとう君がくれたこの宝物は
ずっと心に残るから
紅蓮の星
10人が搭乗中
参加
雪華たちの戯言の星
4人が搭乗中
参加
雪華のメモ帳です
人気
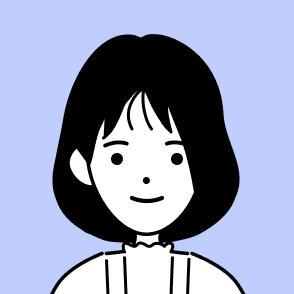
うろ









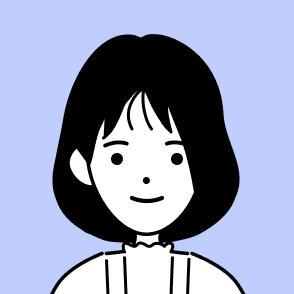
ゆきち
蓮ノ三連華! #蓮ノ空活動記録
変顔フェチ
26時のマスカレイド
森みはると中村華蓮の顔面ラップ






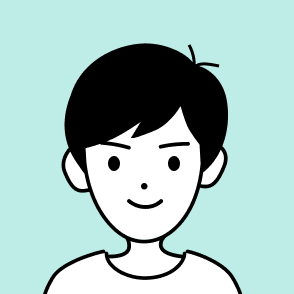
アッシュ7
蓮の葉蒸しご飯!
夏にピッタリのメニュー。
今度自宅でも挑戦します!
#銀座
#中華
#ランチ




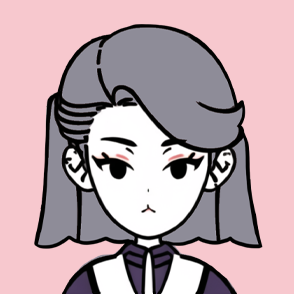
かさるい
水族館のチケット沢山もらったんだけど、華蓮ちゃんいる?
デートで使ったら?
いい人。

やまだにしき
東区にある中華蓮華(れんか)さん
控えめに言っても
ホントにオススメ
麻婆豆腐が美味しいのよ
ゴチソ━(人 'ч'。)━サマッでした✨
#中華 #ランチ



藤川四角


Hiro


もっとみる 
関連検索ワード
新着
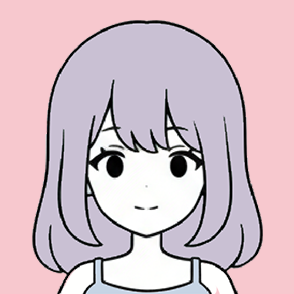
さくら
出前で中華やパスタを頼んで食べても満たされなかった。
でも愛する人や心が通じ合う人が出来て心が安定した時に薄味でも美味しく感じられた。
やはり心の安定が大事だと分かった。
empty
「どうしたんだ、お前?」
龐博の声が耳に届き、肩が強く揺さぶられた。
葉凡は夢から覚めたように現実に引き戻された。どこにという仏音もなければ、禅唱もなかった。古寺は相変わらずで、分厚い塵が積もっている。他の人々も、さっきまで何も聞いていなかったかのように振る舞っていた。
「本当にここが大雷音寺なのか……?」
葉凡は小さく独り言を漏らした。さっきの体験は短かったが、あまりにも真実味があった。彼はぼんやりとし、あれが何だったのかを深く考え込んだ。
手にした青銅の古灯を凝視するが、もう特別な感覚はまったくない。表面には幾つかの装飾文様が刻まれているが、古めかしく、どこにでもあるような平凡な形状で、異常な点は微塵も感じられない。
「蒲団だ!」
ある男の学生が、灰の山から一枚の古びた蒲団を見つけ出し、それを掲げた。歳月を経てもなお、その形を保っていた。
間もなく、別の女子学生が分厚い塵の中から一粒の紫檀の念珠を見つけ出し、塵を吹き飛ばすと、時を経てもなお、かすかに光沢を放った。
その頃、ケイドは石仏の前の塵の中から、半分に折れた木魚を見つけ出した。その表面には三尊の菩薩が刻まれており、荘厳さや慈悲深さが、生き生きと表現されていた。
この瞬間、葉凡の頭の中は様々な思いでいっぱいだった。もし本当にここが伝説の大雷音寺だとしたら、ここは神々が遺した場所である。出土した全ての器物は、非凡なものに違いない!
「当!」
王子文の足が何かに当たった音が響き、金属的な震えが伝わってきた。隅の灰土を掻き分けると、掌大の欠けた銅鐘が現れた。鐘壁の一部が欠落しているが、様式は古風だった。
「当……」
彼が銅鐘を揺らすと、すぐさま優雅な鐘の音が響き渡った。それはまるで仏音が缭繞(りょうねつ)するようで、心を静め、精神を安らかにさせた。
葉凡の思索は遮られ、思わずその銅鐘に視線を向けた。流雲紋が刻まれており、素朴さの中に禅意と仏韻を感じ取ることができた。
龐博は小さく呟いた。彼は先に古寺に入ったのに、何も見つけられなかった。運が悪かっただけだとしか言いようがなかった。
ほぼ同時に、李小曼が石仏の足元から半分になった玉如意を見つけ出した。塵を拭うと、透明感あふれる欠片となった玉が、たちまち点々と光を放った。
古寺はがらんどうに見えたが、何人かが塵の下から器物を見つけ出している。他の人々もすぐに動き出し、次々と探し�始めた。
葉凡はそれらの器物には興味を示さなかった。古寺で唯一、塵一つ付かず、完全な形で残り、灯り続けている青銅の古灯を手に入れている以上、他の器物と比べるべくもなかった。
「絶対にあるはずだ……」
龐博が呟く。
「しっかり探せ。何を見つけようと、すべて回収しておけ。」
葉凡は古灯を龐博に手渡し、その明かりを頼りに探させた。一見するとこれらの破損した仏器に神妙な点は見えないが、もし世の中に神々が存在するのなら、これらは間違いなく非凡な物であるはずだ。
葉凡は銅灯を龐博に預けると、自分は古殿を出て、寺前の菩提樹に向かった。今や彼は元の思考パターンから脱却し、神々の存在を信じることにした。
古寺が大雷音寺だとするならば、その傍らにある菩提樹を見逃す手はない。もし世に仏陀がいるのなら、あの枯れた古木も尋常ではないに違いない!
菩提樹は仏教の聖樹である。『大唐西域記』に記されているように、仏陀は阿難に「世の中に礼拝すべき三種の器物がある。仏骨舎利、仏像、そして菩提樹である」と語ったという。
仏陀は菩提樹の下で悟りを開いた。菩提樹を見る者は、仏陀を見るが如し。
眼前の枯れた古木は、龍のように蒼々として力強く、六、七人でようやく抱えきれる太さだった。幹はすでに中空になっており、地面から二、三メートルの高さに垂れ下がった枯れ枝に、六枚の葉が残っている。それは翡翠のように晶々と輝き、美しかった。
この古木が仏陀と関係あるかどうかは別として、この六枚の緑玉のような葉だけでも、その非凡さは明らかだった。
葉凡は樹下に立ち、菩提古樹を丹念に観察した。巨大な枝はほとんど古寺の上に覆いかぶさるように伸びており、もし葉が茂っていたら、空を覆い尽くすような光景だったに違いない。
その時、葉凡の心に閃きが走った。六枚の晶々とした緑葉から、かすかに緑霞(りょくか)が漏れ出しているのを発見したのだ。一部は遠くの五色祭壇の方角へ、大部分は根元へと吸い込まれていく。
点々とした緑霞は糸のようで、絶え間なく緑葉から溢れ出し、生命力の息吹と、限りない生気を感じさせた。
葉凡はしゃがみ込み、根元の土を掻き分けてみた。いったい何が、菩提葉が溢す緑霞を凝集させているのか。
土の中には神異な物体はなく、ただ一粒の菩提子(ぼだいし)があるだけだった。光も輝かず、華やかさも集まらず、霞も纏わらない。色は地味で、普通の土くれと間違えるほどだった。
ただ一つ、特別なのはその大きさだった。普通の菩提子は爪の先ほどだが、この灰暗色の菩提子は、まるで核桃(クルミ)のように大きかった。
葉凡は驚きを隠せなかった。まさか、菩提葉が溢す緑霞を、この子が吸収しているのだろうか?しばらく観察すると、糸状の緑霞が流れ込み、この菩提子の三寸手前で消えてしまうのがわかった。
吸収しているようには見えなかったが、原因はおそらくこれだろう。
葉凡はその菩提子を掌に載せ、丹念に観察すると、驚いた表情を浮かべた。この灰暗で平凡な菩提子に、天然の紋路が繋がり合って、まるで慈悲深い仏陀の姿になっていたのだ!
仏陀は天生のもので、完全に自然の纹理が交差して生まれたものなのに、あたかも精巧に彫刻したかのようだった。
灰暗な仏図は、古雅で自然な趣があり、かすかに禅韻が透けていた。
「天生の仏陀図とは……も难道、二千五百年前、釈迦牟尼は本当に菩提樹によって悟りを開いたというのか?」
菩提樹には、知恵樹、覚悟樹、思惟樹という別名もある。伝説によれば、人の神性を開き、己れを悟らせるという。
葉凡はその菩提子を頭上高く掲げ、上の六枚の緑葉に向けると、緑霞が溢れ出す速度が急に速くなり、生気溢れる気配が一層濃くなった。すべて菩提子に集中する。もちろん、光華は依然としてその三寸手前で消えていた。
「啵!」
一声の軽い音が響き、一枚の晶々とした菩提葉が最後の一筋の緑霞を流し出すと、粉々に砕け、塵となって舞い落ちた。
至此、葉凡は確信した。菩提子は見かけ倒しで、しかし非凡な物であると。慎重にそれを懐に納めた。
この時、地面には多くの粉末が散らばっていることに気付いた。それはさっきの菩提葉が化した塵と同じものだった。も难道、この巨木の葉はすべてこうして消えていったというのか?葉凡は相当に驚いた。
天生の仏陀図を持つ菩提子。葉凡はそれが非常に重要だと感じ、かすかに、石仏に寄り添う青銅の古灯よりも重要だとすら思えた。
菩提古樹にはまだ五枚の緑葉が残っているが、先ほどのように晶々とはしておらず、色も鈍くなっていた。葉凡はそれを摘み取らなかった。一粒の菩提子を得ただけで十分だ。目立つことは避けたかった。
この頃、まだ誰一人として大雷音寺から出てこない。葉凡は菩提樹を離れ、再び古寺へと戻った。
この時、さらに七、八人が仏教の器物を見つけ出していた。劉云志はなんと石仏の後ろから半分になった金杵を見つけ出し、塵に埋もれて何年も経つというのに、今再び土を掘り返すと、依然として光り輝き、重厚で凝練された感じを与えた。一端が欠損していなければ、完璧な鋳造の傑作と呼べただろう。
この杖のような形の杵は、仏教で「金剛杵(こんごうしょ)」という威風堂々たる名前がついており、「敵を粉砕する」という意味合いを内包している。無敵不摧(むてきふさい)の知恵と真如の仏性を象徴し、諸尊の聖者が持つ器杖である。
もし世に仏陀が存在するのなら、この金剛杵は間違いなく聖物であり、非凡な異相を呈するはずだ。山を裂き、川を断つ神秘の偉力があっても不思議ではないが、今はその神妙さは窺えない。
劉云志が力いっぱい振ると、半截の金剛杵は金色の稲妻のように光り、威勢の良さを示した。
「お前たち、もしもこれらの器物が神々が持っていたものだとしたら、その使い方を俺たちが見つけ出せたら……いったい、どんな驚天動地なことになると思う?」
劉云志の言葉に、仏器を見つけた全員が、思いを馳せた。
empty
瓦礫の果てに、一軒の古びた寺が姿を現した。静寂に包まれ、規模は小さく、壮大さとは無縁だった。古殿が一つあるだけの小さな建物で、中に立つ石仏は分厚い塵に覆われている。そばには一盏(あかし)の青銅の古灯が、かすかに灯をともしていた。
寺の前には、蒼々とした菩提樹(ぼだいじゅ)の古木が相伴っていた。六、七人でようやく抱えきれる太さの幹はすでに中空になり、地表から二メートルほどの高さに、零星と五、六枚の葉が残っているだけだった。しかし、その葉は翡翠(ひすい)や神玉のように瑩(うる)やかに緑光を放っていた。
古寺と菩提樹が寄り添い合い、古雅な趣を呈していた。時がゆらりと流れ、歳月が移ろいだような感覚に包まれ、人々は心静かで、どこか寂寥とした趣を感じ取った。
ここまで来た全員が驚異の色を隠せなかった。後方の壮大な宮殿群はすべて瓦礫と化しているというのに、この小さな古寺だけが依然として存続している。それは、華美を極めたものよりも、むしろ「真」に近い感覚を与えた。
「どうしてこんなところに寺があるんだ?」
「あの菩提樹に残るわずかな葉っぱが、なぜ光を放っているんだ……」
菩提樹は仏教と深い縁がある。伝説によれば、二千五百年前、釈迦牟尼は菩提樹の下で悟りを開き、仏陀となったという。
眼前の菩提樹と古寺は、いずれも尋常ならざる趣を帯びており、人々を驚かせた。
「なぜか、歴史の長河が流れているような気がする。眼前の光景が、あまりにも遠い昔のもののように感じられるんだが……」
五十メートルという距離は短く、すぐにその近くまで到達した。誰もが奇妙な感覚に包まれた。目の前の光景は、一枚の古い絵巻のように、時間の息吹を漂わせていた。
「まさか、これは神々が住まう神殿なのか?」
「この世に本当に仏陀が存在したって言うのか?古寺は荒廃しているが、それでも平穏で安寧とした禅の境地を感じさせる。」
古寺は静寂そのもので、祥和に満ちていた。
「あそこに看板がある。文字が刻んであるぞ。」
荒廃した寺の入り口には、錆びついた銅の扁額(へんがく)が掛かっていた。そこに刻まれた四文字は、龍蛇が絡み合うようにも見え、無限の禅意を宿していた。複雑で判読しにくい鐘鼎文(金文)だったが、最初の「大」の字は誰にでも判読できた。
「最後の字は『寺』だ。」周毅は鐘鼎文に通じており、最後の字を読み解いた。
「この四文字は……『大雷音寺』だ。」
その時、葉凡が四文字をすべて読み上げた。
場にいた全員が驚愕した。信じがたいという表情を浮かべた。
「大雷音寺……?聞き間違えたかと思ったよ!」
「そんなことがあり得るのか……」
伝説の大雷音寺は、仏陀の住まう寺とされ、仏教の至聖之地(最も神聖な場所)である。しかし、眼前の古寺は小さく、荒れ果てており、壮大さのかけらも感じられない。たった一軒の古殿が、なぜ「大雷音寺」と名乗るのか?
九匹の龍屍を目の当たりにして以来、人々はもはや神々の存在を否定できなくなっていた。だが、それでも火星の地に「大雷音寺」なる古寺があるという事実は、心を大きく揺さぶった。もしかすると、多くの歴史や伝説は、まったく別の解釈を必要とするのかもしれない。消滅した古史の一片が、今、明らかにされようとしていた。
「仏音が説法を preach し、その声は雷鳴のごとし。」それ故に大雷音寺という!
眼前の古寺が、本当に伝説の寺であるというのだろうか?
推測が正しければ、それは極めて衝撃的な事実だった。赤褐色の土と礫に覆われた火星に、塵に隠された古寺が存在し、しかも驚くべき由緒を持っているというのだから。
見れば見るほど、この古寺は尋常ではないように感じられた。
後方の「天宮」はかつてどれほど雄大で壮麗だったか。だが、結局は滅び、瓦礫の山と化した。それに対して、この古寺は荒廃しているように見えながらも、依然として堂々と立ち続けている。それは、一種の奇異な対比を成していた。
菩提樹が相伴い、青灯古佛(あおきなる燈と古き佛)、ともす灯は一豆(ひとつのま)の如し。
平々淡淡、清清静静。時間の試練に耐え抜き、残されたものこそが「真」である。華美なものは、いずれ過眼雲煙に過ぎない。
一灯、一仏、一寺、一樹。それらはまるで古来より変わることなく、この世に長く存在し続けているかのようだった。
すべてが祥和で安寧としており、人々は春風に吹かれるような心地になり、かすかに禅唱が聞こえてくるような錯覚にとらわれた。
「もし本当にこれが伝説の大雷音寺だとしたら、寺前にあるこの菩提樹は、もしかして釈迦牟尼が悟りを開いたあの菩提樹じゃないのか?」
「そんなことがあるわけないだろう。あれは宗教的な伝説にすぎない。まさか、二千五百年前の釈迦牟尼が、火星の古木の下で七日七晩座禅を組み、仏陀になったなんて信じるのか?」
「俺たちの遭遇した出来事からすれば、何もあり得ないことはないだろう。」
場にいた全員が、今日の出来事に現実感を失っていた。だが、それらは紛れもない事実だった。
その時、葉凡が突然、足を踏み出した。龐博がそれに続き、二人はそのまま古寺の中へと入っていった。同時に、周毅も素早く後に続き、王子文もその後に続いた。
後方で、劉云志は何かを思い出したように顔色を変え、一目散に駆け寄った。他の人々も夢から覚めたように動き出した。ここが大雷音寺だとすれば、そこには神々が遺した器物が存在するかもしれない。荒廃し、塵に覆われていても、ここは非凡な場所なのだ。
古寺は小さく、一室の仏殿があるだけだった。中はがらんどうで、ほとんど何もなかった。葉凡はまっすぐ石仏の前に歩み寄り、傍らにあった青銅の古灯を手に取った。
灯は平凡無奇で、古めかしいだけの形状だった。しかし、手にした途端、金属特有の冷たさではなく、温玉(あたたかな玉)のような温かみを感じ取った。驚くべきことに、寺内は分厚い塵に覆われているというのに、この古灯だけは一粒の塵も付着しておらず、まるで塵を拒んでいるかのようだった。
何年も掃除されていない寺で、灯だけが塵を避け、なおも灯り続けている。葉凡はそれを不思議に思い、まさかこの遠い古代から、ずっと灯り続けているというのだろうかと疑念を抱いた。
「まったくきれいだな。石仏とこの灯以外には何も残っていない。」
龐博が周囲を見渡したが、残念ながら他の器物は見当たらなかった。
その時、二人の後を追って入ってきた周毅が、分厚い塵を踏みしめた足元から「哐当(こうとう)!」という金属音が響き渡った。彼の足元から、一つの鉢が転がり出たのだ。
同時に、劉云志らも古寺内に駆け込み、誰もが黙々と探す始めた。
最初は、全員が地球にいた時の感覚から抜け出せず、目の前の古寺に驚きと疑念を抱いていただけだった。だが、葉凡が最初に行動を起こしたことで、皆がはっとした。我々は今、異星にいるのだ。そして、目の前にあるのは、伝説の仏陀が住まうとされる大雷音寺かもしれない。そこに、神々の遺した器物が残っている可能性がある!
古寺の中で、葉凡は塵一つ付かない古灯を手にした。そのやわらかな光が寺内を照らし、光と影が交差する。
突然、葉凡はかすかに聞こえる禅唱を耳にした。それは、まるで天外から響いてくるようだった。最初は錯覚かと思ったが、仏音は次第に大きくなり、古寺全体に響き渡った。黄鐘大呂(皇室の雅楽)が鳴動するかのような荘厳さ、壮大さ、高邁さ、玄奥さ。
そして、古寺内の塵はすべて退き、無塵無垢の世界となり、六字真言が響き渡った。
「嗡、嘛、呢、叭、咪、吽……」

ばつ
求)星粒(青薔薇のきみ/陽葵 華/白峰 詩織/紫峰 綾香は2000〜2500即決)
お値下げにも対応いたしますので、お気軽にご連絡お願いします!





みかん
華やかな時間が終わり、人の波がスッと引いた後のシー。
さっきまであんなに笑い声に包まれていたのに、閉園後のパークにはアナウンスとbgmだけが静かに響いている
楽しい場所のはずなのに、なぜか少しだけ切なくて、でも温かい。
夢は消えるんじゃなくて、ちゃんと誰かの心の中に持ち帰られて行くんだな、と知る瞬間
光が強くキラキラした世界ほど静けさは優しい。
あの落差まで含めて、きっと魔法なんだと思う
また日常に戻るのに、少しだけ前を向ける夜でした。


ストローボーリング🍓
色も香りも味もいい感じ✌️
#料理 #中華料理 #おうちごはん

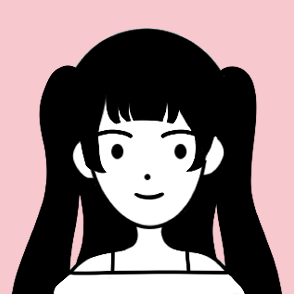
🩸
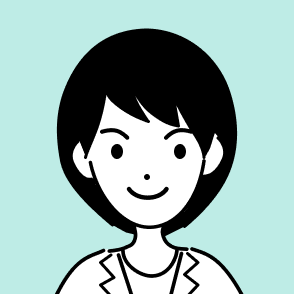
もろきゅう
美味しかったなぁぁ
占いの店多すぎる中
でっかい肉まん屋さん、やっててくれて
ありがたみ&温かみ

empty
「私たちは一体、どこに来てしまったの……。家に帰りたい……」
ある女子学生が堪りかねて泣き出してしまった。
「またしても五色祭壇か……」
龐博と葉凡が並んで立ち、互いに視線を交わすと、そして同時に首を横に振った。大学時代から最も親しかった友人同士であり、卒業後も頻繁に会っていた二人は、お互いのことをよく理解している。今、二人とも状況が芳しくなく、全員の立場が危ういことを感じ取っていた。眼前には未知と変数が満ちていた。
その頃、他の人々も果てしない荒漠の景色から視線を戻し、焦燥と混乱に満ちた目で周囲の様子を窺っていた。
巨大な青銅棺椁が彼らの後方に横たわっていた。そしてその棺椁の下には、宏壮な五色石壇が存在した。泰山で見た巨大な祭壇と非常によく似ており、五種類の異なる色の巨石で築き上げられていた。
五色石壇は広大な面積を有しており、建設当時は確かに壮大な工事であったことが想像された。しかし、長年にわたる風沙にさらされ、本来は地上高くそびえ立つべき巨大な祭壇はほとんど完全に地下に埋もれてしまい、今や赤褐色の砂礫に覆われた大地と同程度の高さになっていた。
今日、九龍拉棺がここに到着し、地面に強く衝突したことで、周囲の砂礫が震え飛ばされ、祭壇の輪郭がようやく浮かび上がったのである。巨大な青銅棺椁が祭壇上に横たわるだけでなく、九匹の巨大な龍屍もまたその上に載っていることから、五色石壇の宏大さが窺える。
「私たちは……道に迷ってしまった。帰る道が分からない……」
ある繊細な女子学生が泣き声を上げ、体をよろめかせた。支えていないと、その場にへたり込んでしまうところだった。
多くの人々が青ざめた顔をしていた。この瞬間、人々は様々な可能性を連想した。目の前に広がる光景は、まるで見知らぬ世界のようだった。誰一人としてその事実を受け入れたくはなかったが、泰山は消え、眼前には果てしない荒漠がある。それを見て、誰もが沈黙を守らざるを得なかった。
「慌てたり、恐れたりするな。解決策があるはずだ。」
葉凡が大声で呼びかけた。
「どうやって解決するんだ?どうやって帰る?どうやってこの見知らぬ世界から抜け出すんだ?」
男学生たちの中にも、声を震わせ、強い恐怖と不安を露わにする者がいた。
未知は一部の人間に畏敬と恐怖を抱かせるが、同時に他の一部の人間には探求の欲求を生み出す。
葉凡と龐博は、九匹の巨大な龍屍を避けながら、前方へと歩み始めた。近くの状況を確かめようというのだ。
李小曼が近くにいた。彼女は寒さを感じているようで、両腕を抱えていた。美しい顔は青ざめていたが、それでも蓮の花のように清楚で、薄暗い中で静かに咲き誇っていた。葉凡が通り過ぎる際、上着を脱いで差し出したが、彼女は「ありがとう」とだけ言い、首を横に振って断った。
葉凡は何も言わなかった。取り返そうという気持ちもなかった。彼は上着を羽織り直し、龐博と共に歩みを進めた。巨大な龍屍と青銅棺椁を迂回すると、李小曼のアメリカ人同級生であるケイドもまた周囲の状況を観察しており、口から時折「God」という感嘆が漏れていた。
五色石壇から少し離れた場所に、巨大な岩が横たわっていた。高さだけでも二十メートル以上ありそうだったが、傾斜はそれほど急ではなく、登ることが可能だった。
葉凡は身長約一七九センチメートル。見た目は文弱だが、実際には身体が非常に丈夫で、大学時代はサッカー部の主力選手であり、グラウンドではよく「野蛮人」と呼ばれていた。
一方、龐博は名前が示す通り、「磅礴(壮大)」な印象を与えた。肥満ではなく、本物の筋骨隆々とした大男で、腕は普通の人間の脚ほど太かった。
二人の体力は非常に優れており、巨岩の前で素早く駆け出し、用心深く登ることもなく、そのまま一直線に駆け上がった。巨岩の上から遠方を眺めると、薄暗がりの中から点々と微かな光が透けて見えた。二人はかなり驚異を感じた。
「俺たち、戻れそうにないな。」
最も親しい友人には隠すことはない。葉凡は自分の推測と判断を率直に口にした。
「ここは確かに、俺たちがいた時空間とは違う場所だ。」
「ここが本当に俺たちのいた時空間じゃないってことか。」
龐博は普段は大雑把だが、真剣な話題になると冗談を言わない。彼は遠くに見える微かな光輪を注視し、眉をひそめて尋ねた。
「お前は思うか?この世に神様なんて本当にいるのかってな。」
「龍屍なんてものを見てしまった俺たちだ。目の前に生きた神様が現れても、驚かないと思うよ。」
葉凡もまた、遠くに揺らめく光を見つめていた。
「生きた神様が目の前に現れたら……どんな光景になるんだろうな。」
龐博が呟いた。
背後から音が聞こえてきた。身長一九〇センチメートルもあるケイドが巨岩に登ってきたのだ。彼は遠方の光を見た瞬間、思わず叫び声を上げた。
「賛美を……慈悲深い神よ。俺は……光を見た!」
彼はあまり流暢ではない中国語でそう言い、すぐに身を翻して後方へと手を大きく振り、人垣の中の李小曼に向かって大声で叫んだ。
「光を見たぞ!」
それから彼は巨岩を下り、李小曼の元へと駆け寄った。
ケイドの叫び声は、たちまち人々を混乱させ、多くの者がその場へと駆け寄ってきた。
龐博は近くに立つ李小曼とケイドをちらりと見て、葉凡に尋ねた。
「あの洋鬼子、本当に李小曼のボーイフレンドなのか?」
「俺に聞かれても分からないよ。」
「本当にあきらめるのか?」
龐博は斜めから葉凡を睨んだ。
「ある出来事はたとえやり直しができたとしても、元の地点には戻れない。たとえ同じ道を二度歩いたとしても、元の気持ちには戻れないものだ。あれは過去の出来事だ。人は前を向いて歩かなければならない。」
葉凡は首を振ると、何か思い出したように笑って言った。
「お前こそ洒脱でいいじゃないか。夜遊びは多種多様だろう?」
「俺はお前を軽蔑するよ。お前の生活の方がよっぽど賑やかなんじゃないのか?」
龐博は葉凡を見て、そして近くの李小曼を見て、言った。
「男の直感として、俺は二人がまた何か起こる予感がするんだがな。」
「余計なことを言うな。」
葉凡は笑って言った。
「お前も女みたいに第六感でもあるのか?」
この状況下、笑顔を見せられるのはおそらく彼ら二人くらいのものだった。二人とも悲観的な性格ではなく、どんな時でも滅入りそうな顔をすることは滅多になかった。
間もなく、多くの人々が巨岩に登り、遠方を眺めた。微かな光は、まるで蛍が瞬くように、薄暗がりを貫いて人々の目に映った。その光源は明るくはなかったが、人々の希望の灯を灯したかのようだった。多くの女子学生たちが歓声を上げた。
前方に微かな光がある。依然として未知は満ちているが、誰もが前に進みたがった。おそらく、これは人間の性分なのだろう。暗闇を恐れ、光を求める。
「どうか、がっかりさせないでくれ。」
「奇跡が起こることを願うしかない。」
人々は次々と巨岩を下り、五色祭壇の前で対応策を相談した。
「ここは俺たちにとってまったく未知の世界だ。前方に光があったとしても、用心すべきだ。」
王子文は慎重な性格で、このような提案をした。
周毅はこれまでずっと冷静だったが、それにも頷いた。
「そうだ。まずは数人を先遣隊として道を確かめさせるべきだ。あの光はそれほど遠くにも見えないし、念のためにな。」
他の人々も同意した。未知の前路は誰にも予測できず、見知らぬ環境では何事も慎重を期すべきだった。
「砰!」
突然、激しい震動が走り、五色祭壇の上の銅棺から金属音が響き渡った。
「何が起こった?」
「私は、銅棺の内部から音がしたように感じたわ……」
銅棺に最も近かった女子学生が青ざめた顔でそう言った。
その言葉を聞き、全員の顔色が変わった。なぜなら、巨棺の内部には、遺体を納めた小銅棺が存在するのだから。
もっとみる 
おすすめのクリエーター
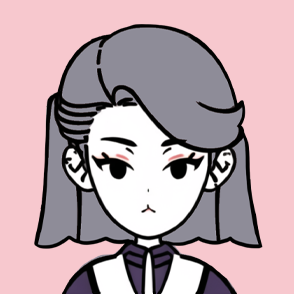
かさるい
フォロワー
0
投稿数
4732

Hiro
書道と英語好き。書道は日本習字→6段、斯華会→4段。タイピング検定1級。英語発音技能検定1級、英検準1級。アメリカに8年、フィリピンに5年住んでました。アメリカではたまに数百人のアメリカ人に英語で講演してました。
新潟生まれ
→静岡
→山梨
→静岡
→東京
→埼玉
→東京
→静岡
→サンフランシスコ
→ワシントンD.C.
→神奈川
→ロサンゼルス
→ニューヨーク
→フィリピン
→東京(現)
フォロワー
0
投稿数
681

ばつ
ドール/ベイブレード/ゲーム(原神、ゼンゼロ、鳴潮)
小学生のまま
フォロワー
0
投稿数
463

やまだにしき
フォロワー
0
投稿数
303

藤川四角
なにかしら作っている者です。なにかしらの投稿をする予定はありません。
フォロワー
0
投稿数
275
