人気
キキ
#キセル #タバコ



🚬れん
ルーム中にバカスカ吸ってるやつ🚬

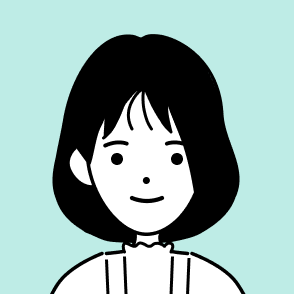
toi
#今日の音楽
#キセル
⁂ 2025/12/08



ベガ
hoku
People from another planet
#キセル
#タコ的
#拳法
#イラスト #絵 #art #illust #drawing #illustration #art #artwork #drawing #1823日目


鮎
いいね等してくれると嬉しいです!
#キセル っぽいやつ
#イラスト #オリキャラ


τ
煙管って正直どうなんですか?
#質問をしたら誰かが答えてくれるタグ #タバコ #煙管 #キセル
まる。
もっとみる 
関連検索ワード
新着

たまおち

サメちゃん💐🦋
昔の人ならキセルは知ってるかも


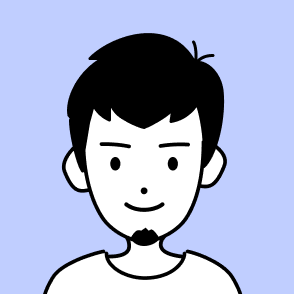
3photo
キセル吸った残りの松風🐎
けっこう量あるなこりゃー😎🚬💭
#暮らし #ニコチン #タバコ #シャグ #手巻きタバコ

HALHAL
花の慶次という遊戯台でござい。
千円使ったところで、保留変化ってのが発生、青保留でした。(期待度5パー)
それがいざ抽選といふところで、赤枠、赤セリフ、擬似連3回、好機の文字、青保留が赤保留に変化(赤になると来たか〜!!というナレーションが入る、期待値80パーくらいか?)スペシャルリーチ、キセル演出(この時点で期待値95パー、激アツ)
パチンコなんてしない人が殆どでなんのこっちゃでしょうが、こりゃ、当たったでしょ。。
もらったぁぁあ!!
織田裕二的に言えば、
キィィィィイイィィィイィーー〜〜タァァアァ!!
って感じだ。
昔、目薬さした位で馬鹿みたいに騒ぎやがって!!とCM観ながら思った。。
しかし、今、正にビッグウェーブが来ている!!
圧倒的追い風!!その風は圧倒的!!
同じようなことを2回言いたくなる程度にはワクワクタイムである。
多分この魔力というか、ワンオブ脳内物質が出るが為に、賭け事は楽しく感じられて、時に破滅に追いやるんですね。間違いない。
昔ホールでタバコ吸えてた頃ならタバコに火をつけて通称ドヤタバコで当たりを生暖かく見守る至福の時。。稀に、、外すと隣のおっさんにニヤニヤされたりして。
それがしはただ、、あの時あの瞬間タバコに火をつけただけでごわす!おいどんは当たると思って余裕ぶっこいてたのではないでごわす!!などと猿芝居。。内心はクッソー!!こんちくしょう!である。。
分煙前の方が個人的には好きだったけど、皆様の健康を鑑みると、良いことではあったのでしょう。
んで、、例のリーチですが、、すんなり図柄が揃うと見せかけて〜、、ハズレの演出が出て、、襖が閉まり、お、、ハズレた。。と思ったらリーチ図柄がふわふわして、、ハズレと思わせておいて当たりでした!!ギャギャギャギャーン!!と盛大に音が鳴り画面がビガァー、殺人的にフラッシュ、大当たり〜!!
とか。。
小癪な。。(でも当たったから嬉しいが、、)
個人的見解に過ぎませんけど、95%当たりとか、そういう展開やったらすんなり素直に当たれよ!!と思う。
わっ!!強い演出!お!激アツ演出!
と思わせてハズレでした〜からのやっぱり当たってたんでしたー!ごめんなさいねー!当たり!当たってるんですよ大将!!
みたいな。
ぬらぬらしてて気持ち悪い(けど当たったから嬉しい)
この落差が好きな人もいるとは思うんやけど、。
ショボ過ぎて期待してなかったのに、実は当たってましたー!!ってのが普通の使い方だろ!?とは思うが、そういうのはまずない。。
何だかなー。
#おすすめの音楽垂れ流し計画
どうでも良い私見。
500円勝った。

Playing It Cool
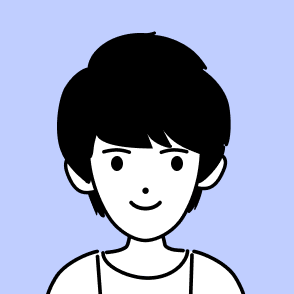
喪に服すおじょん
衝撃的すぎてキセルした人を撮っちゃった(笑)
画面右側ニット帽被ってるおっちゃん。
60~70代ぐらいかなぁ
正々堂々切符入れずにそのまま行った。
たぶん手口としては今日は電車の大遅延が起きてた。
自動改札口の横の、精算所が遅延証明書でわちゃわちゃしてる間に堂々とキセルする。
んー、たぶんプロキセルはこんな感じの常套手段使うのだろうか(笑)


穀潰し

もっとみる 
おすすめのクリエーター

穀潰し
感情を 抑圧すること
フォロワー
0
投稿数
7445
HALHAL
わいと嫁とムスメ、ほいでムスコの4人パーティです。
基本的に音楽垂れ流しアカウントです。フォローは気をつけて下さい。変な音楽も垂れ流しです。アウトサイダー的な人、洋楽、酒、子供と自然探索するのが好き。花〜虫〜樹木〜海の生き物とか。コーデックスとか。ボードゲームとかなんやかんや。オタク気質。
めちゃくちゃニッチな方に走りがち。
音楽の投稿よくしますが皆さんが思ってるより全然浅いです。笑
フォロワー
0
投稿数
5125
まる。
限界トリマーの人生ハードモード^_^
フォロワー
0
投稿数
3462
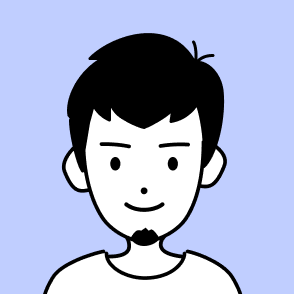
3photo
相互フォローさんとのんびりやっていきたいので、フォロー増やし目的のフォロー解除はブロックさせていただきます。
2021.5月にGRAVITY開始。
40代既婚ワケアリムスメあり
趣味は写真撮影……だが最近はお休み、代わりに葉巻にドハマり中、GRAVITY初めてからはお絵描き少々
三輪車乗り
フォロワー
884
投稿数
2606

サメちゃん💐🦋
はじめまして
鬼滅が好きで特に禰豆子としのぶが大好きです
ぜひ仲良くしてくれる方友達になってくれる方いたらよろしくお願いいたします
フォロワー
0
投稿数
2333
