人気
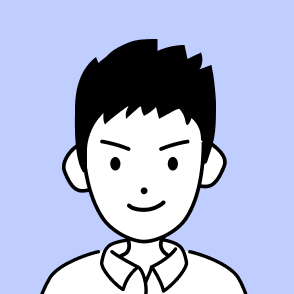
空き缶
回答数 132>>
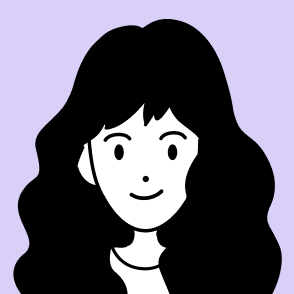
羊夢た
牧谷、ゴルレオ、ガニメデ、ウィーズ、ゾーハンが思いつく
壁山はムキムキってよりムチムチだし
恋ちゃんやスカウトのキャベツちゃんはふかふかなイメージだな
はな
確かに度が過ぎることもあるけど、いつだって誰かを楽しませてきた双子が本当に好き……
塩分
「お母さん、やめます」。この言葉がSNSでつぶやかれた瞬間、ネットは賛否の嵐に包まれた。子育て中の母親が、家事や学校準備を放棄する宣言を投稿したところ、「身勝手だ」「産んだ責任を取れ」との批判が殺到。一方で、「私も同じ」「母親でいることに限界を感じる」との共感の声が広がった。この投稿は削除されたが、波紋は収まらない。ある調査では、母親の約8割が「母親をやめたい」と一度は思った経験があるという。これは個人の弱音ではなく、社会全体の歪みを映す鏡だ。2025年、少子化が加速する日本で、母親たちの悲鳴を無視すれば、家族の崩壊は避けられない。政府や地域は、支援の網を張り巡らせ、母親が「人間」として息をつける社会を急務とすべきだ。
問題の根は深い。核家族化の進行と長時間労働が、母親を孤立無援に追い込んでいる。とある母親のケースは象徴的だ。3歳の長男の「イヤイヤ期」と双子の世話に追われ、ワンオペ育児で心が折れ、「顔も見たくない」「お母さん、やめるね」と吐露した。児童相談所に相談するまで、ネガティブな感情が募ったが、相談員の言葉でようやく光が見えたという。別のシングルマザーも、10歳の息子の反抗期に「一緒に住みたくない」と感じ、距離を置くことで関係が改善した。こうした体験は珍しくない。X(旧Twitter)では、2025年に入って「母親やめたい」との投稿が相次ぎ、産後うつの母親が「仕事と育児の二重負担で自由時間がゼロ」と吐露する声が目立つ。
ある母親は「毒親になりそうで怖い」と、保育園入園を必死に訴えたエピソードを共有。こうした叫びは、母親の「失望期」や「諦め期」を示す。立憲民主党の泉健太議員が指摘するように、子どもに「イヤイヤ期」や「反抗期」があるように、親にもそんな時期があると認めれば、心の準備ができるはずだ。
データがその深刻さを裏付ける。厚生労働省の母子保健施策動向(2025年)では、妊産婦のメンタルヘルス支援が強化されているが、精神科連携の脆弱さや専門人材不足が課題だ。
令和6年度の妊産婦メンタルヘルスケアアンケートでも、地域差が浮き彫りになり、公的補助の不十分さが指摘されている。
東京都医学総合研究所の研究(2025年6月)では、妊娠中の社会的つながりが産後うつを防ぐ鍵とされ、特に25歳以下の若年初産婦で効果が高いことが示された。
一方、出生率は2024年に1.20を下回り、2025年はさらに低下の見込み。原因のトップは「経済的負担」(43%)で、次いで「自由時間の喪失」(37%)。
ヤフコメの声もそれを反映する。「女性の社会進出を求めつつ、サポートが追いつかない」「地域のつながりが失われ、孤立する」との指摘が相次ぐ。
イスラエルなどの高出生率国では、家族や社会の支えが鍵だという研究もあり、日本は「頼って当たり前」の文化を再構築せねばならない。
では、どう対処するか。まず、既存の支援を活用し、拡大する。NPO法人ウィーズの「エブリリーフ」半里親制度は画期的だ。フランス発祥のこの仕組みは、親が休める時間に「リーフメイト」と呼ばれる大人が子どものニーズを満たす。釣りに行きたい子には同行し、話を聞きたい子には耳を傾ける。2025年6月に始動し、10月から親子交流支援の料金をゼロに。登録メイトは30人超、GPS付き端末で安全を確保する。
また、「お母さんをお休みする日」のようなリフレッシュを、全国的に制度化すべきだ。また、政府の「こども・子育て支援加速化プラン」(2025年4月本格始動)は、予算の8割を保育・相談に充てる。精神科医の藤野智哉氏が提言するように、行政と精神科の連携を強化し、「相談先がわからない」母親に情報を届ける。
Xの体験談でも、「第三者に相談したら心が軽くなった」との声が多い。
さらに、社会意識の変革が必要だ。「母親神話」――「無条件に犠牲を払う存在」という幻想を捨て、「親も人間」と認める。とあるヤフコメのように、「周りが親を育てる」空気を作ろう。地域のファミリーサポートや「日本版ネウボラ」(妊娠・出産時の相談窓口)を増やし、父親の育児参加を促進する。JILPTの研究(2025年)では、父親の残業削減が出生率向上に寄与するとされ、夫婦分担が母親の負担を軽減する。
子ども家庭庁を「子ども社会庁」に進化させ、社会全体で子育てを支える仕組みを加速させるべきだ。
これらの取り組みが実を結べば、未来は明るい。WHOの2025年世界健康デー宣言「健やかな始まり、希望の未来」通り、母親のメンタルヘルスを守れば、家族の絆が強まり、出生率も回復するだろう。あるX投稿のように、「限界を感じたら第三者に頼る」文化が根付けば、母親は「やめたい」ではなく「続けたい」と思えるはず。
社会は今、母親の叫びを「批判」ではなく「支援の合図」として受け止める時だ。そこから、真の「子育て大国」への一歩が始まる。
塩分
「お母さん、やめます」。この言葉がSNSでつぶやかれた瞬間、ネットは賛否の嵐に包まれた。子育て中の母親が、家事や学校準備を放棄する宣言を投稿したところ、「身勝手だ」「産んだ責任を取れ」との批判が殺到。一方で、「私も同じ」「母親でいることに限界を感じる」との共感の声が広がった。この投稿は削除されたが、波紋は収まらない。ある調査では、母親の約8割が「母親をやめたい」と一度は思った経験があるという。これは個人の弱音ではなく、社会全体の歪みを映す鏡だ。2025年、少子化が加速する日本で、母親たちの悲鳴を無視すれば、家族の崩壊は避けられない。政府や地域は、支援の網を張り巡らせ、母親が「人間」として息をつける社会を急務とすべきだ。
問題の根は深い。核家族化の進行と長時間労働が、母親を孤立無援に追い込んでいる。とある母親のケースは象徴的だ。3歳の長男の「イヤイヤ期」と双子の世話に追われ、ワンオペ育児で心が折れ、「顔も見たくない」「お母さん、やめるね」と吐露した。児童相談所に相談するまで、ネガティブな感情が募ったが、相談員の言葉でようやく光が見えたという。別のシングルマザーも、10歳の息子の反抗期に「一緒に住みたくない」と感じ、距離を置くことで関係が改善した。こうした体験は珍しくない。X(旧Twitter)では、2025年に入って「母親やめたい」との投稿が相次ぎ、産後うつの母親が「仕事と育児の二重負担で自由時間がゼロ」と吐露する声が目立つ。
ある母親は「毒親になりそうで怖い」と、保育園入園を必死に訴えたエピソードを共有。こうした叫びは、母親の「失望期」や「諦め期」を示す。立憲民主党の泉健太議員が指摘するように、子どもに「イヤイヤ期」や「反抗期」があるように、親にもそんな時期があると認めれば、心の準備ができるはずだ。
データがその深刻さを裏付ける。厚生労働省の母子保健施策動向(2025年)では、妊産婦のメンタルヘルス支援が強化されているが、精神科連携の脆弱さや専門人材不足が課題だ。
令和6年度の妊産婦メンタルヘルスケアアンケートでも、地域差が浮き彫りになり、公的補助の不十分さが指摘されている。
東京都医学総合研究所の研究(2025年6月)では、妊娠中の社会的つながりが産後うつを防ぐ鍵とされ、特に25歳以下の若年初産婦で効果が高いことが示された。
一方、出生率は2024年に1.20を下回り、2025年はさらに低下の見込み。原因のトップは「経済的負担」(43%)で、次いで「自由時間の喪失」(37%)。
ヤフコメの声もそれを反映する。「女性の社会進出を求めつつ、サポートが追いつかない」「地域のつながりが失われ、孤立する」との指摘が相次ぐ。
イスラエルなどの高出生率国では、家族や社会の支えが鍵だという研究もあり、日本は「頼って当たり前」の文化を再構築せねばならない。
では、どう対処するか。まず、既存の支援を活用し、拡大する。NPO法人ウィーズの「エブリリーフ」半里親制度は画期的だ。フランス発祥のこの仕組みは、親が休める時間に「リーフメイト」と呼ばれる大人が子どものニーズを満たす。釣りに行きたい子には同行し、話を聞きたい子には耳を傾ける。2025年6月に始動し、10月から親子交流支援の料金をゼロに。登録メイトは30人超、GPS付き端末で安全を確保する。
また、「お母さんをお休みする日」のようなリフレッシュを、全国的に制度化すべきだ。また、政府の「こども・子育て支援加速化プラン」(2025年4月本格始動)は、予算の8割を保育・相談に充てる。精神科医の藤野智哉氏が提言するように、行政と精神科の連携を強化し、「相談先がわからない」母親に情報を届ける。
Xの体験談でも、「第三者に相談したら心が軽くなった」との声が多い。
さらに、社会意識の変革が必要だ。「母親神話」――「無条件に犠牲を払う存在」という幻想を捨て、「親も人間」と認める。とあるヤフコメのように、「周りが親を育てる」空気を作ろう。地域のファミリーサポートや「日本版ネウボラ」(妊娠・出産時の相談窓口)を増やし、父親の育児参加を促進する。JILPTの研究(2025年)では、父親の残業削減が出生率向上に寄与するとされ、夫婦分担が母親の負担を軽減する。
子ども家庭庁を「子ども社会庁」に進化させ、社会全体で子育てを支える仕組みを加速させるべきだ。
これらの取り組みが実を結べば、未来は明るい。WHOの2025年世界健康デー宣言「健やかな始まり、希望の未来」通り、母親のメンタルヘルスを守れば、家族の絆が強まり、出生率も回復するだろう。あるX投稿のように、「限界を感じたら第三者に頼る」文化が根付けば、母親は「やめたい」ではなく「続けたい」と思えるはず。
社会は今、母親の叫びを「批判」ではなく「支援の合図」として受け止める時だ。そこから、真の「子育て大国」への一歩が始まる。

