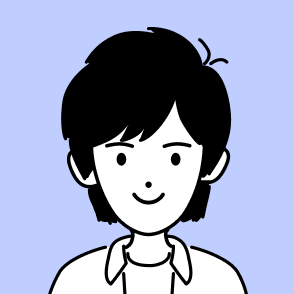
日本語初心者ウェンタ
音楽が好きで、談笑も好きですが、喧騒が好きではなく、毎日歌を聞いたりゲームをしたりする大学生です。私たちの間には違うおしゃべりがあるかもしれません。
学生
猫
文学
読書
音楽
米津玄師

日本語初心者ウェンタ

日本語初心者ウェンタ

日本語初心者ウェンタ
大きな太陽がようやく雲を払い、光を大地に降り注いだ。これは福生の午後で、除雪車がゆっくりと通り過ぎる様子が見え、道の本来の姿を少しずつ露わにしていく。
小さな食堂の前には人が群がり、一台の古いビートルがカレー屋の前の駐車スペースに停まっていた。信之助と恵子が車から降り、向こう側の人物に指定された住所に従ってここへ来た。あの同級生と会うためだ。
佐々木三郎は、かつて信之助の高校の同級生だった。大学を卒業後、大阪へ行き親戚の紹介で銀行に就職し、今では小さな責任者にまで出世していた。彼は信之助を助けられる情報をいくらか持っているようだ。
カレー屋の前のガラス越しに、少し禿げた目が鋭い男が古びたスーツを着て、隅の席に座っているのが見えた。彼の前には既に二杯の飲み物が用意されており、客の到着を伝える必要もなさそうだった。
信之助が手を上げると、中の男は彼に向かって手を振った。
「行こう、恵子」
二人がカレー屋に入ると、ちょうど除雪車が通り過ぎ、道の雪を一掃していった。
私たちを阻んでいたこの雪も、一度除かれれば、少しは速く進めるようになる。薬を飲んだ後、佐久間は明らかに体中に力がみなぎるのを感じた。姑が客を見送り、自分で部屋の片付けを終えると、自室の襖の後ろに黒い箱があるのに気づいた。
西条がすでに文良のものをいくつか整理していたようだ。毎年法事の後、これは行うべき過程なのだが、今年は佐久間が目にしたことのないものがいくつか並べられていた。
「お義母様」
佐久間が自分でその箱を運んでいるのを見て、西条はほほえんだ。
「見てごらん。あなたが目を覚ます前に、私が覚えているものを少し整理しておいたのよ」
佐久間が箱を開けると、最初に目に入ったのは彼がこれまで見たことのない一本の名簿だった。姑がどこから探し出したのかもわからない。
「これは文良が高校を卒業したときのクラス写真のアルバムよ。確か…30ページが彼女のクラスだったと思う」
西条がそう言っている間、卒業アルバムの扉に、よく保存された手紙のようなものが挟まっているのに気づかなかった。しかし、名前は書き忘れたのか、それとも何かの間違いか、「山田」の二文字だけが見え、もう二文字は青い横線になっていた。差出人も山田だった。
二つの「山田」が並んでいるのを見て、西条と佐久間はしばらく沈黙した。
「ラブレター?」
佐久間の第一印象は、これはよくあるラブレターだろうということだった。誰にだって過去にそんなことがなかったと言えるだろうか。そんな気持ちで、佐久間は封筒を開けた。
内容を読み始める前から、その筆跡だけで文良のものだとわかった。佐久間の印象は強く、文良は公文書のような字で会社で威厳を示していた。このラブレターの字もその公文書のような文体とそっくりで、あまりにも整いすぎていて、一見して男性が書いたものとは気づきにくい。
そして手紙の内容はこうだった。
「山田君、12月の雪が再び降りました。まるである古い友人のように。彼はここに来て、春の潔さを残していきました。この3年間、まるで昨日のことのように、何度も雪が来ては去りましたが、今この時、3月の陽光に向かわなければなりません。雪はこの時、溶けていくのです。
純粋なものは激しく訪れるけれども短い、ということをあなたは知っています。まるで私がいつも思うように、12月の最も純白な雪が私の心配を覆い隠してくれるように。たとえ反響が聞こえなくても、少なくともそれは私のそばにいてくれる、目の前にある確かなものなのです。
しかし運命に『もしも』はありません。3月の風が来て、春の訪れの温かさが純粋な雪を水流に変え、こうして東や他の終わりのない方向へ去っていくのです。
私の12月への懐かしさは、雪が水に変わって静かに去っていくことに気づかなかったのかもしれません。あれは雪ではなく、ただ私の涙だったのでしょう。3月の福生の山で、最後の一片の雪が水滴となって去り、私もここで私にふさわしい指輪を迎えなければなりません。彼が同じ景色を私の生活にもたらしてくれると信じています。
さようなら、記憶の中のあなた。もう一つの12月に、たとえ違いがあっても、あなたが私のそばにいてくれることを願っています。
山田xxx(インクの染み)
悲しみの3月に、遂に会えなかった人に別れを告げて」
佐久間の両手は震え、眉をひそめた。これは本当なのか?しかし短い激怒の後、彼は深く息を吸った。これは遺品だ。どんなに怒っても壊してはならない。
「人の記憶には、本当に忘れられない人がいるのですか?お義母様」
西条がお茶を運んできたが、急いで答えようとはせず、佐久間の手に触れながら、手紙を自分の手に取った。
「文生、あなたにも何年たっても鮮明に覚えている人はいませんか?」
この問いかけに、佐久間の緊張した筋肉が緩み、体が傾き、両目が少し虚ろになって天井を見つめた。
おそらく佐久間には、この感情は今のところ理解できないだろう。
「文良は子供の頃、とても内気で内向的な子でした。高校に上がったばかりの年、家に帰ってくるといつもとは違う様子で、ある男の子のことを話すことがありました。名前は覚えていないかもしれません」
西条は佐久間が黙っているのを見て、先ほどの質問を続けようとはせず、佐久間にもう一杯お茶を注いだ。自分が話している間、佐久間はなぜか目的もなく、お茶を一気に飲み干し、苦しそうに飲み込んだ。
部屋の中では、佐久間が咳き込みながら、西条がこれらの昔話を続けていた…。
除雪車が一往復する間、信之助と恵子、そして向かいの佐々木は楽しく話し、それぞれビールを一瓶ずつ飲んだ。
「私たちは少なくとも…4年は会っていなかったよね、信之助」!
佐々木が口を開くと、やはりあのなじみ深い関西弁だった。
「4年どころじゃないよ。一日会わなければ、三秋も会わなかったようなもんだ。乾杯しよう」
信之助が社交辞令を言うと、恵子が二人に酒を注いだ。彼らの学生時代、よくこのカレー屋で食事をしたものだ。
「この女性は?」
酒を飲んだ佐々木は、初めてこの眉目秀麗な女性に気づいた。
「私の後輩、恵子です」
そう言いながら、恵子は軽くお辞儀をした。
「よろしくお願いします」
佐々木も慌てて自己紹介した。
「私はもう年だけど、名前は悪くないよ、佐々木三郎」
三人は大笑いした。
「さて、雰囲気も良くなったところで、早速本題に入ろう、信之助」
佐々木は時計を見た。もうすぐ銀行の午後の出勤時間だ。
「君が調べてほしいと言った人物は、時間がだいぶ経っているけど、記録の中に確かにこの名前はあった」
佐々木は単刀直入に言い、信之助に自分がすでにいくつかの資料を手にしていることをほのめかした。
「そうですか?今日あなたをお招きして、本当に正しい人を頼んだようです」
信之助が言葉を受け、恵子が再び二人に酒を注いだ。
「君も少しは知っているだろうが、私たちは最近住宅ローン優遇の販売を進めていて、確かに君が言った山田という人物がうちで一つ購入していた。当時の記録も見つけたが、規定により、コピーしか渡せない」
佐々木は声を潜め、信之助に自分が調べた資料を伝えた。
「これで十分だと思うよ、佐々木」
信之助は立ち上がった。テーブルの上のカレーはほぼ食べ終わり、酒はちょうど最後の一杯だった。
「本当に、これらのものは今のところ私を大いに助けてくれると思う。後で休みの日には必ず教えてくれ」
信之助と佐々木は握手を交わし、佐々木は鞄から封筒を取り出して信之助に渡した。その後、信之助がすでに勘定を済ませているのを見て、笑いながら信之助を指さした。
相変わらずだな。
「信之助先輩、今すぐ佐久間先輩のところに行くんですか?」
恵子は精巧な封筒を持ち、潤んだ目で店を出てたばこに火をつける慣れた先輩を見つめた。
「いや、西条さんからの電話を待たなければ」
信之助は知っていた。西条が明言していないこともあるかもしれない。今はもう少し待つ必要がある。
しかし、目の前がきれいになった地面を見て、道端に残った雪の残骸や、最初から動いていない車の屋根の上に、白い衣のように雪が残っているかもしれないが、信之助は佐久間の連絡先を恵子に伝えるのを忘れなかった。
こうして二人は封筒を持って車に乗り、大きな大学へ向かった。恵子は卒業論文の準備をしなければならず、別れ際に自分が買った薬を後部座席に置いた…。

日本語初心者ウェンタ

日本語初心者ウェンタ
回答数 6>>

日本語初心者ウェンタ

日本語初心者ウェンタ
雪後の風が骨身に染みる。それはまるで監督の振るう革鞭のように、福生(ふっさ)の人波を急き立てる。大通りは、慌ただしい呼吸の音、疾走する車の音、クラクション、そして電車の汽笛の音が入り混じっていた。暖冬の雪はすでに市街地では溶けたらしく、道路の輪郭がうっすらと現れている。しかし、この雪が心に深く根を下ろしたのなら、雪後の晴れ間ごときでゆっくりと溶かせるものだろうか?
その問いに、西条にも答えはなかった。
陽光が西条家の庭に降り注ぎ、ベランダを抜けて佐久間の眠る部屋へと差し込む。部屋の暗闇はいくらか追いやられたようで、陽の光が落ちる場所から三、五歩の距離に、マホガニーらしき棚があるのがはっきりと見える。その上には一枚の写真が飾られていた。文良(ふみよし)が微笑みながら佐久間を抱きしめている。
下には小さな文字で写真の日付が記されている。しかし、幾多の月日が過ぎ、その写真はいつしか誰かの手によってそっと動かされ、文良の最後の白黒写真に替えられていた。
光は佐久間の布団の右、三歩ほど離れた場所で止まっていた。ちょうど棚の上、その遺影をことさらに際立たせるかのように。
二年前、文良も佐久間と同じ稲田(いなだ)会社の社畜だった。二人はある時、偶然にも一緒に東京ドームへ出張し、クライアントと商談することになった。
「すみません、遅れました!」
佐久間はネクタイの曲がりも構わず、よろめきながら文良の前に現れた。その顔には慌ただしい色が浮かんでいる。しかし、目の前の女性同僚は振り返ると、半分ほども黙り込んでしまった。
この人…どうしてこんなに見覚えがあるんだろう?
文良は一瞬、目が眩んだのかと思った。同じカーブを描く前髪、瓜二つの顔立ち、同じようにすっと通った眉。何年も経って、とうに封印したはずの記憶が、なぜこんな悪戯をするのだろうか?
「佐久間文生(さくま ふみお)です。はじめまして」
相手がまだ自分のことを知らないのだと思い、佐久間はすぐに自己紹介をした。ブリーフケースを握る手で、何度もズボンを擦っている。
「山田文良(やまだ ふみよし)です。よろしくお願いします」
その名前を聞いた途端、文良の瞳に灯りかけた希望の光は、まるで冷水を浴びせられたかのように消えてしまった。ただ無理に笑みを浮かべて、この見覚えのある見知らぬ人に向き直るしかなかった。
とはいえ幸いだったのは、佐久間が事前に天気を調べてくれていたことだ。二人が腰を落ち着ける前に、彼は先に東京ドーム近くのホテルを見つけ、チェックインを済ませてくれていた。
「佐久間?…どうしてそんな奇妙な名前なの?」
文良は、その男が彼らの荷物を甲斐甲斐しく片付け、夕食を注文し、自ら階下まで取りに行くのを、訝しげに見ていた。
しかし佐久間は、記憶の中の男と同じように、まるで熱した鍋の上の蟻のようにそわそわと忙しく立ち回るばかりで、一言も余計なことを口にしようとしない。おかげで、聞きたかったいくつかの質問も、喉元でつかえてしまった。
この最初のやり取りで、文良は目の前の若者を横目で見ながら、どうにも満足がいかなかった。少なくとも、彼女はこういう何を考えているか分からない、無口な男は好きではなかった。明日の会議は一体どうなることやら!
外で車のクラクションがけたたましく鳴り響いた。その音に呼応するかのように、佐久間の驚きの声とともに、この回想の夢は終わりを告げた。
陽光に照らされてひときわ目を引く遺影。自分を介抱してくれた人物の手だろうか、あの日、寒さで真っ赤になっていたはずの手が、血色を取り戻しているように見える。それにこの服…信之助(しんのすけ)のものか?
混乱した思考の中、佐久間はさらに重要な一点に気づいた。自分がいる場所は、義母の家だ。自分は雪の中、文良の後を追う道を選んだはずなのに、いつ、どんな不思議な力によってここに運ばれたのだろう。
手に残る香水の匂いが、自分が何か失態を演じたかもしれないことを思い出させた。途端に不快感がこみ上げ、彼はうなだれた。少なくとも確信できることが一つある。「自分はまだ生きている。そして、きっと何かしてはならないことをしてしまった」と。
まさか、もっととんでもないことをしでかしたのか?佐久間は自分が香水を使わないことを知っている。まさか、後輩の恵子(けいこ)に何かしてしまったのだろうか?その考えが浮かんだ途端、激しい頭痛が襲い、彼の悪い想像は中断された。振り返ると、部屋のドアが開け放たれている。
「お義母さん、ご迷惑をおかけしました」
佐久間は頭を揉みながら愛想笑いを浮かべたが、西条が何かお椀のようなものを持って、少し険しい顔で近づいてくるのが見えた。
「あんたはね、いつも人に面倒をかけるんだから。みんな、あんたの気持ちは分かってる。でも、どうしてあんなことをする必要があったの?今の自分の姿を見てごらんなさい」
西条は容赦なく釘を刺した。葬儀はもう終わった。幸いにもあんたに大事がなかったからよかったものの、そうでなければ、もう一つ葬式を出すところだったのよ、と。
「…申し訳ありません」
佐久間は、あの日の自分の行動を義母がすべて見ていたこと、そして自分がもう少しで大惨事を引き起こすところだったことに気づき、愕然としながらそのお椀を受け取った。
「これは?」
「解熱剤よ。この数日は安静にして、あちこち出歩かないこと。薬を飲んだら、家の片付けでもしなさい」
西条はゆっくりとそう言った。埃をかぶったばかりのようなエプロンから、彼女が何かを見つけたことが窺える。しかし、この解熱剤がどこから来たのかについては、彼女は口にしなかった。
佐久間は半分ほど飲んだところで、ふとあることを思い出した。
確かこの家では、文良の父、つまり義父が亡くなってから、この種の薬はほとんど常備していなかったはずだ。葬儀の前に来た時、棚の上に置かれていた空の薬箱が、西条の部屋でひどく場違いに見えたのを覚えている。この薬は一体どこから?
「その通りよ。恵子さんが買ってきてくれたの」
西条は目を上げ、佐久間の反応を窺った。佐久間が目覚めたらこの薬に気づくだろうと分かっていたようだ。しかし、佐久間は本当に高熱で記憶が途切れているらしかった。
おそらく彼は忘れているのだろう。自分が恵子の腕を掴みながら、文良のことばかりを話していたことを。
義母にそう指摘され、佐久間は顔を真っ赤にして、返す言葉もなかった。
「恵子さんはいい子よ。でも、今のあんたじゃ、まだ少し足りないわね」
佐久間は虚を突かれた。
「何を言ってるんですか、お義母さん。僕たちはただの…先輩と後輩ですよ」
それを聞くと、西条はふっと微笑んだ。
「この朴念仁。なんて言ったらいいのかしら」
その一言に、佐久間はどうしていいか分からなくなった。恵子の腕を掴んだ後、一体何が起こったのか、彼には全く分からなかった。少なくとも、目覚めるまでの間、彼の頭の中は文良との思い出でいっぱいだったのだから。
ドアが鳴り、西条は立ち上がって部屋を出て行った。佐久間に薬を必ず飲み干すようにと念を押して。
佐久間は一息に薬を飲み干すと、全身から汗が噴き出すのを感じた。しかし、義母が何か手伝わせようと準備万端で待っていることを敏感に察知し、足音と話し声が聞こえても、すぐには動かなかった。ただ、義母に呼ばれるのを待っていた。
一方、信之助は大阪へ向かっていた。元同級生の佐々木三郎(ささき さぶろう)を訪ねるためだ。昨夜のメールで、山田文良の過去を調査するよう彼に依頼していた。佐久間のために、一筋の道を切り開きたいと願って。
佐々木は快くその依頼を引き受けてくれたが、すでに数日が経過しても、まだ返事はない。
「信之助先輩、本当にこれでうまくいくんでしょうか?」
恵子は訝しげな目を向けた。
というのも、昨夜西条と話した際に聞いた「古い家は今の場所に移築されて、元の場所は福生電車の6号線の小さな駅になった」という一言だけが手がかりなのだ。
こんな調べ方で本当に結果が出るのだろうか?恵子は自信満々の信之助を見つめた。
「絶対に大丈夫だ。俺のダチなら、きっとやってくれるさ」
信之助は悠然と煙草を咥え、まるで一つの謎が、彼独自の手法によって解き明かされようとしているかのようだった。
福生の晴れ空に、雲が流れ込んできた。大地に降り注いでいた陽光は、現れたり隠れたりしている。それはまるで、今の佐久間の途切れ途切れの思考のようだ。答えが何なのか、おそらく彼自身にも分からないのだろう。

日本語初心者ウェンタ

日本語初心者ウェンタ
ラッシュアワーの車列さながらに、猛吹雪がこの暖冬に静かに訪れた。福生県(ふっさけん)の環状高速道路はすでに長い渋滞ができていた。佐久間(さくま)は此时、意識が朦朧(もうろう)としているようだった。恵子(けいこ)が自分の腕を持ち上げるのを見ていると、次の瞬間、まるで荷物のように担ぎ上げられ、何かを呟く義母の後ろ姿に見送られながら車に放り込まれた。
「まったく、昔の福生はこんな雪の降り方じゃなかったのに」信之助(しんのすけ)はハンドルを握りながら、手慣れた仕草でポケットからタバコを一本取り出し、窓を少しだけ開けた。
「本当に申し訳ありません」
信之助がタバコに火をつけると、助手席の西条(さいじょう)は微笑んで頷いた。
恵子は佐久間の隣に座り、彼の口から体温計を抜き取った。彼女が持ってきた氷嚢(ひょうのう)では、鬱火(うっか)か厳しい寒さから来るのか分からない体熱を抑えきれなかったようだ。冷たい水銀柱は39度と40度の間で止まっており、恵子はわずかに首を横に振った。
「一途な想いというのは、人をここまでにしてしまうものなのね!」
恵子が片付けをしようとしたその時、自分の右手が冷たいながらも力のこもった手に覆われるのを感じた。驚いて振り返ると、佐久間がうっすらと目を開け、何かを口の中で呟いている。
「西条おばさん……」
前の席にいた二人が、はっと振り返った。
「よん……四十度近くあります」
西条は驚愕した。目の前の渋滞は、少なくとも百メートルは続いている。
「信之助くん、渋滞が解消されたら、福生の病院まであとどれくらいかかる?」
「三十分ほどです」
信之助はハンドルを握り、振り返ってしばらく黙っていたが、西条が片手で助手席のグリップを叩くのが見えた。
「家に帰りましょう!病院には行かないわ」
恵子と信之助は、佐久間の義母の突然の決断に信じられないという顔で見つめ合い、互いに言葉を失った。
突然の高熱で佐久間の意識が混濁しているのかもしれない。彼は自分の腕を抱く恵子を見ている——いや!もしかしたら文良(ふみよし)の亡霊が恵子に乗り移ったのかもしれない。だからこそ、今の佐久間はうわ言を口にしながらも、恵子の腕を離そうとしないのだ。
この一幕に、西条の微笑んでいた顔がさっと強張った。「この子をどうすればいいのかしら!」
「文良……家……着いたのか?」
車内は一瞬にして静まり返った。
恵子は急いで顔を上げ、西条を見た。その眼差しから何かを察したようだった。彼女は俯き、佐久間の頭を撫でた。
「馬鹿ね、もうお家よ」
佐久間はそれ以上何も言わなかったが、力を込めていた両腕が緩み、鉄の万力のように掴んでいた手を放した。
その時、わずかに目を開けた佐久間の意識は、再びあの交通事故の時に飛んでいたようだった。同じく福生の高速道路で、同じく雪の日。出張だったか、それとも家に帰る途中だったか……。
この一途な男を天が見捨てなかったのか、渋滞はすぐに解消された。信之助はすぐにタバコを投げ捨て、高速道路を疾走し、福生路の陸橋を渡り、市街地の信号を抜けていく。光が絶えず車内の三人の顔の上を交互に照らし、明滅する中で、恵子はその手がまだ離れていないのを感じた。しかし、佐久間のうわ言は止み、眠ってしまったようだった。
車は最終的に、佐久間の家の北西にある駐車場で轟音を立てていたエンジンを止めた。この時、佐久間はずっと眠り続けていた。
信之助は空から雪がようやく止んだのを見て、そっと息をついた。
この雪は、まるで追い払うことのできない怨霊のようだった。信之助が市街地を抜け、佐久間の家の北側にある小さな橋を渡る頃に、ようやく止んだのだ。佐久間の体温はまだ上がり続けている。信之助が西条を説得しようとしたが、彼女が片手を挙げ、それ以上言うなと制した。
「この子のことは私が看ますから、心配しないで。送ってくれて、まだお礼も言えていなかったわね」
信之助と恵子は顔を見合わせた。その時、西条が家のドアを開け、素早くスリッパを二足取り出し、お茶でも飲んでいくよう促した。
「まあ、なんてこと。夕飯の準備もしていなかったわ。あなたたちまで疲れさせてしまって、本当にごめんなさいね」
その言葉に恵子と信之助は恐縮し、「お構いなく」と返しながら、佐久間を寝かせたら手伝いに行きますと伝えた。
「西条おばさん、手伝います」
恵子が見ると、信之助はすでに休む間もなく佐久間を担いで部屋に入り、西条が持ってきた布団の上に彼を寝かせ、掛け布団をかけていた。
「信之助先輩!」
恵子は自分のバッグから何かを取り出し、信之助に手渡した。
「まずいわ……」
別の部屋で、西条は必要な薬を見つけられずにいたようだった。彼女は壁に寄りかかり、部屋の引き戸の隙間から漏れる光が足元を照らしていた。外からは彼女の下半身しか見えず、その顔にどんな表情が浮かんでいるのかは誰にも分からなかった。
何年も前のものだろうか、佐久間の義父の遺影の下に、空の解熱剤の瓶と、いつ落ちたのか分からない薬の箱がいくつか転がっており、それが何かを静かに物語っているようだった。
西条の顔の強張りが少し和らいだ。壁一枚を隔てて聞こえてくる恵子と信之助がかいがいしく動く音に、彼女の不安が少しだけ紛れたのだ。
蛇口から水が流れる音、信之助に応える恵子の声、そしてはっきりとした「タオル」という一言が西条の耳に届いた。彼女は壁に寄りかかったままゆっくりと座り込み、棚の上で微かに光を反射する夫の遺影を見て、手を合わせた。
「あなた、どうかこの不憫な婿を守ってやってください」
そう呟くと、西条はゆっくりと立ち上がり、半分しか光が差していなかった部屋の戸を閉め、様子を見に行こうとした。
すぐに、お茶と皿が西条によって準備された。恵子と信之助は佐久間の額にタオルを乗せた。そして、目立つように置かれた解熱剤の箱が、西条の強張った表情を、どこか借りを作ってしまったような苦笑いに変えた。
「本当に、ご迷惑をおかけしました」
西条の口調も和らいでいた。二人は佐久間が熟睡しているのを確認すると、その薬の箱を持って西条と共に居間へ向かった。
「どうぞ、西条おばさん」
恵子は自分の薬を西条の手に渡した。
「私も数日前に熱を出して、この薬をずっと持ち歩いていたんです。ちょうど今日、役に立ってよかったです」と恵子は付け加えた。
恵子の誠意に満ちた瞳を見て、西条は少し戸惑ったように箱を受け取り、かける言葉も見つからない様子で、苦笑しながら恵子の肩をぽんと叩いた。
「よくやってくれたわ」
西条はゆっくりと二人に茶を注ぎ、信之助にも一杯出した。
「当然のことをしたまでです」
「いえ、大したことではありません」
信之助と恵子は声を揃えた。
西条はそれ以上は応えず、苦笑いを一つ浮かべて台所へ向かった。
雪上がりの福生の夜空は雲に覆われ、時折見える微かな光を遮っていた。その光が、灯りの消された佐久間の部屋に差し込む。遠くから見ると、それはまるで閉ざされた宮殿の暗闇に差し込む一条の眩い光のようで、暗闇の中で希望を見出したかのように、思わず手を伸ばし、前へ進みたくなる光だった。
食卓では、西条が料理を並べた時には、恵子と信之助はすでに静かに立ち去っていた。一枚の書き置きがそこに置かれている。無言だが、何かを残していく。彼らが望んでいたのは、自分たちが介入することではなく、西条が見守る中で、佐久間自身が新たな希望を見つけ出すことなのかもしれない。
この問題は、おそらく傍観者である恵子と信之助には、今のところ良い手立てがないのだろう。
手紙にはこう書かれていた。
「西条おば様
今夜は心のこもったおもてなし、そしてお忙しい中、私たちのために夕食までご用意いただき、誠にありがとうございました。
恵子は学業があり、卒業前に片付けなければならないことがいくつかあります。ですが、彼女の存在が新しい希望となることを願っています。私の考えすぎかもしれませんが、これが何かのきっかけになることを心から望んでいます。
このような暗い日々は、必ず終わりが来ます。
追伸:恵子が今後のための解熱剤を買っておきました。当面の会社のことはご心配には及びません。私が代わりに稲田社長に休暇の連絡を入れました。どうか佐久間さんには、心配せずゆっくり休むようお伝えください。こちらには私と恵子がおりますので、万事お任せいただければと存じます。
今夜のおもてなしに、重ねて感謝申し上げます。
恵子、信之助」

日本語初心者ウェンタ

日本語初心者ウェンタ
AIと想像力が結びつくとき、もしかしたら楽しい機会がまた一つ増えるかもしれませんね!








日本語初心者ウェンタ

日本語初心者ウェンタ
---
2年の月日が流れた。毎年一度は意識を失う佐久間文生という会社員は、今日は稲田社長の許可を得て、亡き婚約者・山田文良のお墓参りに訪れていた。
暖かい冬はいつも予想外にやってくる。11月から福生では雪の姿を見たことがなかったが、今日はことさら強い雪が降りしきり、佐久間が車を降りた瞬間、振り返ったその顔に激しく打ちつけてきた。
一方、文良の母・西条秋実は墓地の控室で親戚たちと談笑していた。
「西条さん、今年も二回目の参拝です。仕事が忙しくて、去年も来られなかったので、どうかお許しください」
ある親戚が恥ずかしそうにつぶやく。昨年の法要にも顔を出さなかったことを気にしているのだ。
「この子は、いつでも皆さんに話しかけてもらえるのを喜んでいますよ」
秋実さんはそう言うと、控室の窓から外を眺め、誰かを探して二人を連れてきた。雪の中、佐久間が何やらぼんやりと立ち尽くしていることに気づく。親戚たちは控室で待っているというのに、これはいかん!
「西条さん、任せてください!」
信之助という若者はすぐに察した。彼にとって、この親友の母親が何かするはずがないとわかっていたからだ。
「恵子、私の服どこにいった?」
信之助がもう一人の若い女性に声をかけた。小柄で肩までの髪を流すその姿は、今日の陽射しを浴びながら、一瞬秋実さんの前に文良が現れたかのように錯覚させたが、すぐに信之助に引き戻された。
文良の墓前に立った佐久間の顔から緊張がほぐれ、風雪にもかまわずコートも着ないまま深呼吸し、雪の上に腰を下ろした。
「文良、教えてくれ。。。すべてを失う瞬間の感覚って、どんなだった?。。。」
そうつぶやくと、突然鋭い雪片が頭上に降りかかった。
まるでこの氷が自分にぶつかって砕け、見知らぬ恐怖の温度に融けて地面に撒き散らされ、やがて清掃車に運ばれていくように。これが文良の答えか?
佐久間は雪の冷たさに構わず横たわり、ドローンのカメラから見下ろす福生墓園は純白のヴェールに包まれ、悲しみさえも一時的に隠されているように思えた。ところどころ足跡がつけば、小指の爪ほどの氷粒が降り注ぎ、佐久間の頭を打ちつける。
「その瞬間、本当にこうだったのか?」
佐久間は確信する。あの日、休日に文良を送ってあげなかったのが災いし、出張先から戻る途中、福生のどこかの道路で彼女の車は暴走車両に衝突され、ほぼ真っ二つに。発見されたとき、文良の顔は真っ赤に染まり、何かを握りしめていたという。
ますます感情に浸る佐久間は、雪が自分の体力を奪い去っていることに気づかない。眠りにつきそうになったそのとき、強引に誰かに引き起こされる。信之助だった。
「本当に命知らずだな!こんなことで悩みを忘れられると思ってるのか?」
信之助はすぐさま恵子に熱い甘酒を運ばせ、一口飲んだ佐久間の体が震える。ぼんやりと彼は自問した。
「文良か。。。いや、これは。。。恵子さん?!」
「まったく、神様もお前の命を残してくれたもんだ。探し回らせたぞ!」
信之助は怒鳴るように言うと、二杯目を手渡した。
「飲んで体を温めろ。まだやるべきことがあるだろう」
恵子はこの情けない先輩を少し不憫に思いつつ、尋ねた。
「佐久間先輩、大丈夫ですか?」
その声に佐久間は身を震わせた。聞き覚えはあるが、もう故人の声ではない。
だが信之助はその場を長引かせまいと、コートも着ていない佐久間を肩に担いでしまう。
「工藤先輩、待ってください!西条さんに見られたら。。。」
恵子が慌てて追いかけるも、信之助の豪快な性格には歯が立たない。
こうして佐久間は招待所の入り口まで連行され、壁際に立てられた。信之助と恵子が雪を払い落とすのを手伝っている間、佐久間の手は真っ赤に腫れ上がり、震えていた。
「痛覚はまだある。。。」
婚約者の世界へと旅立とうとしていたのに、こうして引き戻され、後輩にまで恥を晒してしまった。佐久間は恥ずかしさで顔を上げられない。
恵子はそんな彼に予備の服を手渡す。どうやら工藤が何かのイベントのために用意していたらしい。
「しゅ。。。ありがとうございます。。。」
頭を下げたまま、佐久間は親戚たちが西条さんの先導で墓参りに向かう様子を見守る。
これは年中行事。熱い甘酒を墓前に注ぎ、それぞれが一言二言かけていく。まるで彼らが文良を見守ってきたように。
恵子が毛布を持ってきてくれたが、信之助が服を交換するまではそれさえも包まることができない。
しばらくの慌ただしさの後、佐久間は仕方なく信之助の宴会服を借りることになった。当然、後でより良いものを返すと約束する。
信之助は突然振り返り、佐久間に言う。
「服はあげる、ただし条件がある。それが叶えられたら、プレゼントとしよう。どうだ、やるか?」
佐久間が驚いていると、続けて何回もの噴嚏が飛び出し、風邪をひいてしまう。
呆れる信之助が去り、恵子が不快そうに見送った。
ドローンが再び現れ、墓地の上空を旋回する。
親戚たちは次々と甘酒を注ぎ、蒸気とともに謝罪の言葉を捧ぐ。「仕事で来られなかったけど許してね」「ここはあなたの新しい家よ」など。
最後に秋実さんが注ぐと、儀式は終わった。皆帰宅の準備をする。
だが佐久間の失態に、親戚たちは急な宴を企てた。
「西条さん、酒を持ってきて!」
当初の予定を変更し、誰かが盛り上げようとする。秋実さんも皆の熱気に押され、二つの酒樽を運ばせた。
皆が再び杯を交わす中、佐久間は毛布にくるまり、体温計をくわえていた。38.6度の熱を測りつつ、恵子に「宅配便のように」包まれた格好は滑稽だ。
運転もできない状態に。
「佐久間先輩って、本当にいい恋愛してきたんですね。うらやましいです」
突然の恵子の発言に、佐久間は目を見開いた。
「え。。。?」
「あんなに情熱的な彼氏、友達はみんな夢にも思ってないですよ!」
佐久間が笑みを浮かべかけたそのとき、体温計を無理やり抜かれ、笑みを堪えることになった。
こうして、皆は時計をにらみながら宴の終わりを待った。
---

日本語初心者ウェンタ

日本語初心者ウェンタ
回答数 7156>>

日本語初心者ウェンタ
太难了,日语好难

日本語初心者ウェンタ
回答数 4367>>

日本語初心者ウェンタ


日本語初心者ウェンタ
回答数 2963>>

日本語初心者ウェンタ

日本語初心者ウェンタ

日本語初心者ウェンタ



日本語初心者ウェンタ


日本語初心者ウェンタ
❖名前❖
Ri Bun to
❖趣味❖
学生、猫、文学、読書、音楽
よかったら仲良くしてください✨よろしくお願いします!♪

