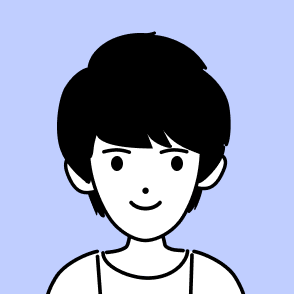
Jerrychen
08 大学生
京都
海外
学生
IT・Web
旅行
文学
読書
アニメ
猫
J-pop
RADWIMPS
音楽
ヨルシカ
ラップ
新海誠
映画
Aimer
月曜から夜ふかし
散歩
JPOP
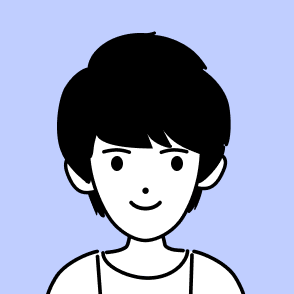
Jerrychen
高校のピアノ室はいつも古い木と本が混ざった匂いが漂っていた。あのヤマハのいくつかの鍵盤は塗装が剥がれ、下の淡い木地が見えていた。私はそのピアノで、この曲を覚えた。サビの部分になると、胸が少し締め付けられるような気がした。まるでそのメロディーが、居場所のない青春期全体を封じ込めることができるかのように。
寮の階下にあるこの練習室はずっと良い。相変わらずヤマハだが、かなり新しく、音色も正確だ。ただ壁が薄く、時々廊下を通り過ぎる同級生の足音や笑い声が聞こえる。それは悪くない。ピアノを弾くことが、もはや完全に静かな世界に逃げ込むことではなく、生活の一部、授業や実験レポート、サークル活動の合間の息抜きであることを思い出させてくれる。
不思議なことに、このより慣れない鍵盤の上で指が懐かしい筋肉の記憶を取り戻すとき、思い浮かぶのは練習そのものではなく、高三の夜自習の休み時間に、同級生と一緒に廊下の手すりにもたれて、遠くの都市のぼんやりとした灯りを見ながら、はるか遠い未来について話していたことだ。それらの顔は今、あちこちに散らばっており、彼らの「現在」は私にとって、SNSで読み込まなければならない画像となってしまった。
和音を一つ押さえると、音が小さな練習室に響き渡る。ふと気づく。懐かしんでいるのは、おそらくあの古いピアノでも、特定の誰かでもなく、何事もまだ起こっておらず、未来が依然として巨大な未知数だったときの気分なのだと。その気分は、実は今この瞬間と全く同じだ——大学生活の出発点に立ち、前方には微積分、英単語、見知らぬ名前で構成された見渡す限りの霧が広がっている。
しかしピアノを弾くことの利点はここにある。楽譜全体を見通す必要はなく、ただ一音一音、一小節一小節、先へ進めばいい。未来もおそらくそうだろう。一度にすべて眼前に現れるのではなく、それぞれの「次」の動作によって築かれていくのだ。
ピアノの蓋を閉めると、鍵舌がかちりと澄んだ音を立てる。練習室を出ると、寮の明かりが次々と灯っていく。一つの窓の向こうには、今まさに展開されている物語がある。私の物語も、まだ数行しか書かれていないのだ。


忘れてください
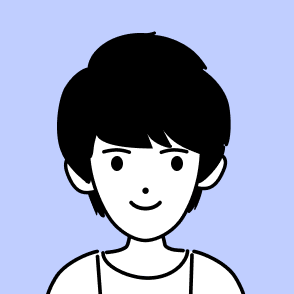
Jerrychen









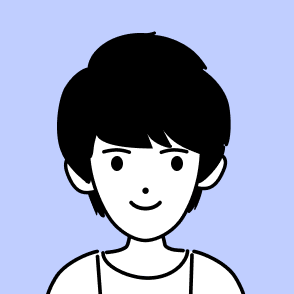
Jerrychen
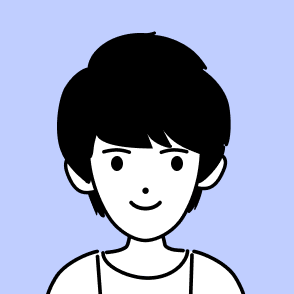
Jerrychen







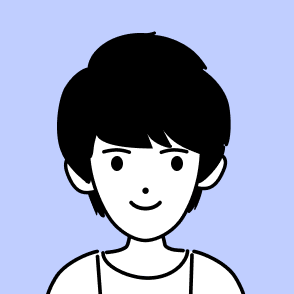
Jerrychen
『一週間の観測実験』
第一章 D-7: 雨の夜、ビール、そして非合理な提案
ルームメイトの歓声で引きずり起こされた時、スマートフォンの画面は凌晨1時を表示していた。まあいい、どうせ腹は減っている。元彼女が置いていった青いストライプのスリッパをサンダル代わりに履き、私は夜航船のように部屋を滑り出た。
雨はしとしとと、疎らに降っていた。顔に付着しても別に感じはない。彼女が去ったあの日の雨と同じだ。ふと、猫の鳴き声がした。喉の奥から絞り出した毛糸玉のような声だ。振り向くと、十メートル先の街灯の下に一匹の黒猫が立っており、その尾は黒い疑問符のように跳ね上がっていた。
コンビニまで十分ほどの道のりだ。メロディを口ずさむ、たぶんビートルズの時代の曲だろ、題名はとっくに忘れた。小雨に濡れながらも、わざわざ避けもせず、この郊外之地では文明社会の野人となることをすっぱりと決め込んだ。
「ピンポーン──」
ドアが開くと同時に、冷気と甘ったるいコンビニのBGMがどっと流れ出た。店員の瞳孔は眠気で溶けかけのアイスクリームのようだ。私は軽く会釈すると、まっすぐにコールドケースに向かった。指がガラス瓶の列をなぞり、最終的にキンキンに冷えたビールの缶一本で止まる。金を払い、カウンター席に座る。一連の動作が流れるように終わった。
冷たい酒液が胃袋に流れ込む。そのなめらかな喉ごしは、なぜか前回のデートで食べたステーキの上でとろけていたバターを思い出させた。白状すると、あのデートは災難級に最悪だった──会話はドアを間違えた訪問販売員のように気まずく淀んでいた。にもかかわらず、その結末で私は訳もなく彼女に告白してしまった。多分アルコールの仕業だろう。
窓外の雨粒は密度を増し、ガラスを打つ音は、レコードの中で永遠に続くジャズドラムのソロのようだ。わけのわからない焦燥が、ふいに糸の切れた凧のように私の心の中でひと渦巻きすると、まっすぐに墜落していった。
ビールはあの滑稽なフランス料理同様、何かを満たす間もなく底を尽きた。最後の一滴を啜り、私は魂を抜かれたように帰ろうとした──丁度、あの女性が、私の貧弱な二十数年分の人生を味見尽くした後、振り返りもせず去っていったように。一陣の雨のようで、しかも確かに現実だった。何しろ彼女は去り際に、私の錆びたギターを持ち去り、このスリッパ一足だけを、存在の証として残していったのだから。
その時、「ピンポーン」という音が再び雨夜の静寂を切り裂いた。
しかし、私は店員の背後から聞こえる足音に釘付けにされた。
その音はとても軽く、ポンポンとしていて、まるで誰かが焼きたてのフランスパンを抱えて雨の中を歩いているかのようだ。私は入口を見た。
アルコールのせいか、あるいは雨幕の歪みか、入口に立つ影の輪郭は、人間というより、ずぶ濡れの子猫のように見えた。だが、私は賭けてもいい、人間だ。とてつもなく若く、目が眩むような少女だ。私は目をこすった。視野の中の血走った血管は、旧式テレビの干渉縞のようだ。子供の頃、言うことを聞かないテレビを叩いたように、自分のこめかみをポンと叩いた。
よし、映像は安定した。確かに少女だった。風一陣で吹き飛びそうなほど華奢で、野良猫一隻より少しばかり大きい程度だ。
彼女は爪先立ちになり、棚の一番高い所に置かれた華やかで精美なドイツビールの缶を懸命に手探った。「へえ、通だな」と私は心中で考えた。彼女の年齢では、明らかに合法飲酒年齢に達していないが、あの電池残量30%の店員さんには、とやかく言う気力もないだろう。
この深夜のコンビニは意外と趣味がいい、空気の中にベートーヴェンの『月光』が流れている。彼女はまっすぐにバースツールに向かい、よじ登る様は、まるでミニチュア版の富士山を征服するかのようだった。
彼女は深く息を吸い、重大な使命を完遂するかのように、そして目を閉じてプルタブをあけた。酒はまだ口に入っていないのに、彼女の頬にはもう二つの紅暈が飛んでおり、ゲームに憤慨したルームメイトの顔色よりも鮮やかだった。
「ともかく、雨に濡れて帰ってもあの騒々しい猿ども二人に直面しなければならないのだ、ここで少しばかり避難した方がましだ」そう考えながら、私は軽くビールの缶を叩き、身邊のこの「難友」を仔細に観察し始めた。
彼女の瞳は大きかった。私は天文学者ではないが、断言できる、それは銀河系でも指折りのブラックホールに違いない―――全ての投向される視線と思緒を、音もなく吸い込み、少しの心思も吐き出さない。
「おい、小僧。」私は口を開いた。
彼女は顔を上げた。瞳孔に緑がかった光が一瞬走ったように思えた。「おい、老いぼれ。」彼女は言い返した。その口調の敵意は、まるで尾を踏まれた野猫のようだ。
私は彼女の逆立った毛を無視して言った。「こんな天気に、こんな時間に、小娘一人でここにいるべきじゃないだろ。」 「だから何?」彼女は挑発的に顎を上げた。「警察に電話して、家まで送ってもらうつもり? 騎士さん。」
「そのつもりだ。」
「ありがと」彼女は鼻で冷や笑いを一つ。「遠慮しとく。」
「誰がお前さんに構えって言ったんだ。」私は愛想なく言い返したが、視線は興味深そうな出土文物を観察するように、彼女の顔を細かに見回した。アルコールの反応が彼女の顔で城略地を攻め落とし、先前のリンゴ赤は完全に陥落し、ある種の熱烈なドラゴンフルーツ色へと進化していた。
「おじさん、あなたも相当な負け犬なんじゃない?」彼女の言葉は弾丸のように迸り、驚くほどの早口だった。「だって見てよ、この白Tシャツに青いスリッパっていう伝説的災難コーデ。」
彼女は口早にまくし立て、いら立って挑発的な様子だったが、自分から我慢できずに「ぷっ」と笑い声を漏らした。
私にとって、女の子を笑わせること以上に存在価値を確認できるものはこの世にないだろう。だから私は鄭重にうなずき、あたかも何かの终身成就賞を授与されたように、自身の敗北者という現実を欣然として受け入れた。
「そのお世辞……どこで覚えたんだ?」 彼女の話匣子は一度開くと、決壊したように止まらなかった。「よちよち歩きの小っちゃな子から、皺だらけの老人まで、みんな見るのが好きなの。多分、自分自身の心に沸き起こる漣漪が限られているからこそ、余計に他人の顔に現れる嵐をすくい上げるのに夢中になるんだろうね。」
「ねえ、彩票売り場である夜で大金を掴んだギャンブラーを見たことある? 私は見たよ。彼のあの顔―――もう全然人間の表情じゃなかった、まさに満月の夜に天に向かって遠吠えする狼男そのもの、狂喜してるけどぞっとするほど気味が悪かった。」
「でもさ、」彼女の話鋒は突然変わり、声には探検家が新大陸を発見したような躍動感が宿っていた。「いっぱい観察してきたけど、『一个人がどうやって另一个人を好きになるか』っていう全過程は、まだちゃんと観測したことないんだ。ねえ、これってさ……とっても面白い実験だと思わない、おじさん?」
言葉が終わらないうちに、彼女はもう頭をこちらのほうに寄せてきた。温かな呼吸は、いたずらをした後で甘えてくる子猫のように、私の頸動脈にひとつひとつ、吹きかけてくる。そこの皮膚は、心跳の鼓動に合わせて、一陣一陣、緊張していた。
私は手を伸ばし、そっと彼女の頬を一インチほど押しのけた、あたかも過度に精美な割れ物を押しのけるように。その時、私のあらゆる感官は、空気中に漂うその甘い、発酵しそうな匂いを貪欲に摂取していた。
彼女はとっくに、私のこの徒労な防御陣を見抜いていた。彼女の口元はかすかに気づかれないほど微妙な弧を描いて上がり、すぐに指先で覆い隠された。全ての忍び笑いは手の甲の後ろに収められ、目の中にだけ勝利の光がきらめいていた。
「あなたって、」彼女の大きな瞳はまたたきもせず私を見つめ、その瞳孔は深遠で危険で、一つの約束のようでもあり、一つの警告のようでもあった。「本当にわかりやすすぎて困るね。」
私は負けじと見つめ返し、あの底知れぬ黒い水域から、彼女に関する何か真実の断片をすくい上げようと試みた。
だが、失敗した。 その両眼の中に、私にはっきりと見えたのは、ただ私自身だけだった―――表情が狼狽し、視線が泳ぎ、コンビニのカウンターで最後の一片の体裁を維持しようとしている、一人の映りこんだ男の姿。
「いいよ。」 私は自分の声が、遠くの方から来るように聞こえた。 「どうせ俺の一週間なんて、このビールの缶と同じで安っぽいんだ。」 「実験開始だ。」









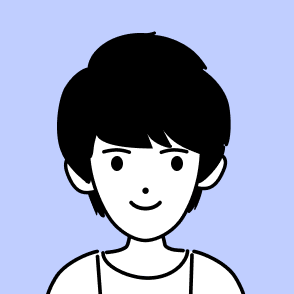
Jerrychen









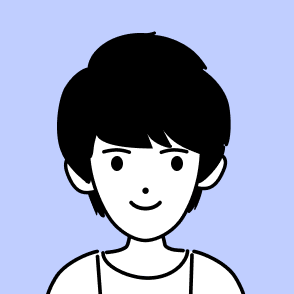
Jerrychen
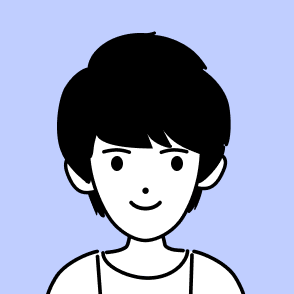
Jerrychen

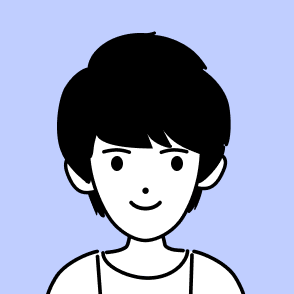
Jerrychen


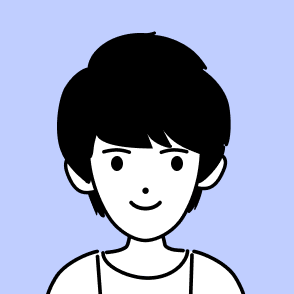
Jerrychen
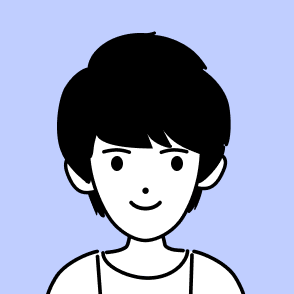
Jerrychen

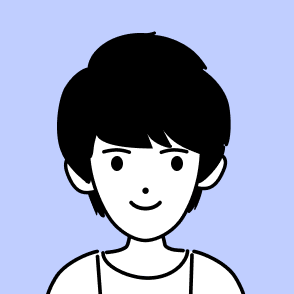
Jerrychen

晴天
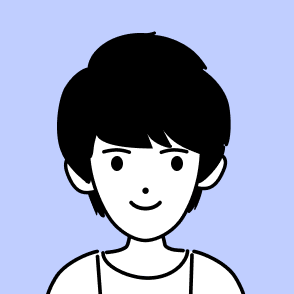
Jerrychen

死別
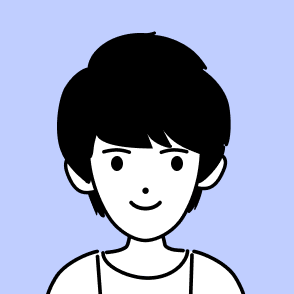
Jerrychen

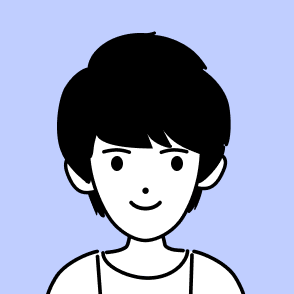
Jerrychen

LOVE 2000
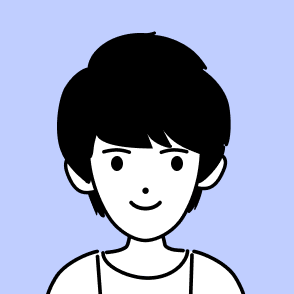
Jerrychen
Nice to meet you! I would like to talk with all kinds of people. 😊
Feel free to comment me to be friends!
