人気
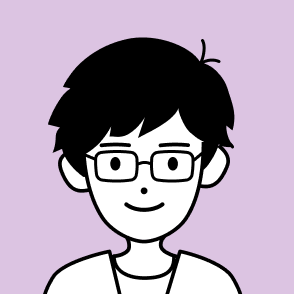
なお
こんにちは、石川尚寛です。
日本にはたくさんの仏像があります。寺に行けば立派な仏像が並び、街の中でも小さな仏像を見かけることがあります。ふと、「仏陀自身は仏像をどう見ているだろう?」と考えました。仏陀はきっと、像そのものではなく、そこに込められた心や学びを大切にしたのではないか。そんな問いが、僕をモーセ五書の十戒の二番目の戒律へと導いてくれました。
出エジプト記20章4節にはこうあります。
「あなたは自分のために、像を造ってはならない。天にあるもの、地にあるもの、水の下にあるものの、いかなる形も造ってはならない。」
ここで使われているヘブライ語は「פֶּסֶל (pesel)」。これは「刻んだ像」「彫刻」を意味します。ただの造形物ではなく、それを拝む対象にしてしまうことへの警告だと感じます。
僕が心を動かされたのは、この「像」という言葉が、石や木で作られた偶像だけを指しているのではない、ということです。仏像も本来は心を映す鏡であって、像そのものを拝むことが目的ではないはずです。僕の日常で言えば、スマホの通知や数字の増減に心を奪われることも、一種の「像」になり得るのではないか。目に見えるものに安心を求めてしまう弱さを、聖書は静かに映し出しているように思えました。
この戒めは「禁止」というよりも、「心を自由にするための言葉」として響いてきます。何かに縛られるのではなく、見えないものに信頼を置く勇気を持つこと。僕自身、まだ答えを持っているわけではありませんが、この問いを抱えながら生きること自体が大切なのだと思います。
これからも、モーセ五書をマンガという形で描きながら、自分の学びを少しずつ分かち合っていきたいです。
気になった方は、ぜひAmazonで「創世記 マンガ 石川尚寛」と検索してみてください。無料で読めますし、続きもどんどん公開しています。
#モーセ五書マンガ
#十戒を学ぶ
#無料で読める聖書

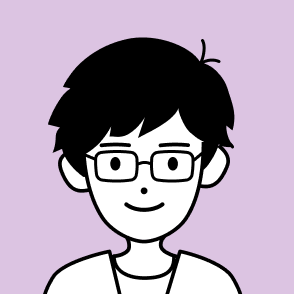
なお
僕は最近、こんな自分自身の経験を思い返していました。
ついカッとなって、大切な人にきつく言ってしまった後、「ああ、またやってしまった…」と後悔する瞬間です。
その時、聖書の中のモーセの一つのエピソードが、以前よりも深く胸に刺さるようになりました。
民数記20章に記された「水が出る岩」
荒野を旅するイスラエルの民が、またしても水がないと不平を言い始めました。
その時、神はモーセにこう命じられます。
「杖を取り、兄弟アロンと共に民衆の前に進み出よ。彼らの目の前で岩に命じて水を出させなさい」(民数記20章8節、大意)
ここでヘブライ語原文を見ると、神が命じた言葉に注目すべき点があります。
神は「岩に命じなさい」と言っています。
ヘブライ語で「命じる」を意味する「דַּבֵּר」(ダベール)は、言葉で語りかけることを指します。
つまり、神はモーセに「岩を打て」ではなく、「岩に言葉で語りかけよ」とお命じになったのです。
モーセの「二度打ち」
しかし、モーセはどうしたでしょう。
彼は民の前でこう叫びました。「聞け、反抗する者たちよ。われわれがこの岩から、あなたがたのために水を出さねばならないのか」(同10節、大意)
そして、岩を二度、杖で打ったのです。
確かに水は出ました。民と家畜は飲むことができました。
でも、僕がこの場面を読むたびに感じるのは、モーセの行動の中にある「わずかな、しかし決定的なズレ」です。
神は「岩に語りかけよ」と命じられたのに、モーセは「われわれが…出さねばならないのか」と言い、岩を打ちました。
その「二度」という動作の中に、僕はつい見逃してしまいそうな重大なことが隠れている気がしてなりません。
カナンの地に入れなかった理由
神はその後、モーセとアロンにこう宣告されます。
「あなたがたはわたしを信じず、イスラエルの人々の目にわたしの聖なることを現さなかったから、この会衆をわたしが与えた地に導き入れることはできない」(同12節、大意)
たった一度の、岩を二度打った行為。
なぜそれが、約束の地カナンに入れないという、これほどまでに重い結果につながったのでしょう。
僕が思うに、ここでの核心は「行為そのもの」よりも、「行為に表れた心の姿勢」にあるような気がします。
モーセはその瞬間、神の指示を正確に伝える「器」としてではなく、民の不平に苛立ち、自分自身の力と権威を示そうとしてしまったのではないか。
「神の聖なること」を民の前に現すべきところを、「自分たち」を前面に出してしまった。
そのわずかなズレが、神との関係における決定的な違いを生んでしまったのだと、僕は感じずにはいられません。
僕自身に問いかけること
この話を読むたび、僕は自分自身に問いかけます。
自分もまた、神に委ねるべき場面で、つい自分の力や方法に頼ろうとしていないか。
人々の前に立つ時、神の栄光を現すよりも、自分の正しさや能力を示そうとしていないか。
モーセのこのエピソードは、神と共に歩むことがいかに細やかで、全人格的な関わりを求めるものかを教えてくれます。
たとえ長年信仰の道を歩んできた者でも、一瞬の心の緩みが、神との関係を損なうことがある。
それほどまでに、神は私たちの「心の向き」を大切にしておられるのだと感じます。
---
僕は今、モーセ五書をマンガで学び直しています。
一つの場面、一つの言葉の重みを、じっくりと味わいながら。
もしこのモーセの物語に興味を持たれた方がいらっしゃったら、ぜひマンガ版でその深みを感じてみてください。
気になった方は、ぜひAmazonで「モーセ五書 マンガ 石川尚寛」と検索してみてください。無料で読めますし、続きもどんどん公開しています。
#モーセ五書マンガ
#民数記
#神との歩み

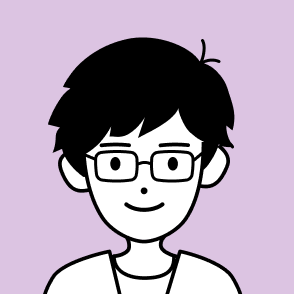
なお
最近、ふと気づくことがあります。
親しい人、特にお世話になっている人に対して、なぜかふとした瞬間に「もしかして……」と疑う気持ちが湧いたり、理由もなくイライラしたりすることはありませんか。
僕自身もそんな経験があって、どうしてだろうと悩んだことがありました。
そんな時、ふと『創世記』の、あの有名な場面が思い浮かんだんです。
エデンの園で、何が起こったのか
創世記3章1節から5節に、こういう出来事が描かれています。
蛇が女(エバ)に近づき、神が「園のどの木からも取って食べてはならない」と言われたことについて問いかけます。
ここで、僕がとても大切だと思うヘブライ語の単語があります。
蛇がエバに言う言葉、「神はほんとうに、『園のすべての木の実を食べてはならない』と言われたのですか」という部分の「ほんとうに」という言葉。
これはヘブライ語で 「アフ」(אַף)という言葉が使われているんです。
この「アフ」には、「本当に?」「まさか?」という、根本を揺るがすような疑いや、ちょっとした嘲りや皮肉のニュアンスが含まれていると言われます。
蛇は、神がエデンの園に人を置き、すべての木の実を食べることを許したという、大きな恵みと信頼の事実には一切触れません。
代わりに、たった一つの禁止事項だけをクローズアップして、「ほんとうに? そんなこと言ったの?」と、神の言葉とそのお心への疑いの種を、そっと植え付けるんです。
疑いは、恵みを忘れるところから始まる
僕はここに、とてもはっきりした構造を見る気がします。
蛇は、エバが毎日享受していた大きな恵み──安全な場所、豊かな食物、何より神との親しい交わり──については完全に無視します。
そして、たった一つの制限だけを強調して、「この制限があるのは、あなたのためじゃないかもしれないよ」と囁く。
これは、私たちの人間関係にも通じるところがあると思いませんか。
親密な人、特に多くの恵み(世話や支え、愛)を与えてくれている人に対して、私たちは時に、その膨大な恵みを当たり前のように思い、感謝の記憶が薄らいでしまいます。
その状態の心に、ほんの小さな「もしかして……」という疑い(「アフ」)が入り込むと、すべての関係がその疑いを通して歪んで見え始める。
そして、その疑いが怒りや憎しみへと変容していくのではないでしょうか。
エバはこの「アフ」の問いかけに乗ってしまい、神の言葉を少し自分流に言い換え(3章3節)、ついに禁断の実に手を伸ばしてしまいます。
その根底には、自分を園に置き、すべてを与えてくださった神への信頼が、わずかな疑いによって覆い隠されてしまったことがあったように思えてなりません。
僕自身への問いかけ
この創世記3章の出来事を読み直すたびに、僕は自分に問いかけます。
「今、自分が享受しているこの関係、この恵みを、きちんと心に留めているだろうか」
「小さな『アフ』(疑い)に耳を傾ける前に、圧倒的な恵みの事実を思い出せているだろうか」と。
疑いや怒りが湧いた時、それはむしろ、それだけ深い関係性の中で多くのものを与えられていたという「証」なのかもしれません。
そして、その感情とどう向き合うかのカギは、エデンの園で起きたことを逆にたどること──まず、与えられてきた確かな恵みを、心を込めて思い出すことから始まるのだと、僕は学び始めています。
モーセ五書を学ぶことは、こうした人間の心の根源的な動きを、深く、そして優しく照らし出してくれます。
僕自身、毎日が新たな気づきの連続です。
もしこのような、聖書の言葉に触れることを通した心の発見に興味を持たれた方は、ぜひAmazonで「モーセ五書 マンガ 石川尚寛」と検索してみてください。
無料で読めますし、続きもどんどん公開しています。
僕の学びの旅路を、少しでも多くの方と共にできたら嬉しいです。
#創世記の人間心理
#モーセ五書マンガ
#聖書から学ぶ関係性

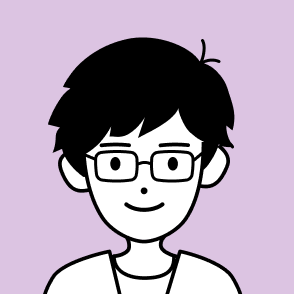
なお
聖書を読んでいると、細かい地理の違いに「なぜ?」と感じることがありますよね。
先日、読者の方からご指摘をいただき、僕自身もあらためて学び直したことがあります。
実は、約束の地への境界には重要な二つの川があるんです。
ヨルダン川とゼレド川、その決定的な違い
確かに、一般的に「約束の地に入る」と言えば、ヨルダン川を渡る場面を思い浮かべます。
ヨシュア記のクライマックスですからね。
しかし申命記2章13節を見ると、主がこう言われています。
「さあ、立って、ゼレドの川を渡れ。わたしたちはゼレドの川を渡った。」
この「ゼレドの川」を渡ることが、38年ぶりの決定的な一歩だったのです。
ここで、僕は地図を広げてみました。
すると、ゼレド川は死海の東側、現在のヨルダン国内を流れる川で、約束の地の東の境界線の一つでした。
一方、ヨルダン川はその西側、カナンの地そのものへの入り口です。
つまり、ゼレド川を渡るということは、「約束の地の境界地域に入ること」であり、そこからさらに進んでヨルダン川を渡り、「カナンの地そのものに入ること」が次の段階だったのです。
ヘブライ語が示す「境界」の重み
申命記2章13節の「渡れ」という命令のヘブライ語は「イブルー」(עִבְרוּ)です。
これは「通過する」「向こう側へ行く」という意味で、単なる地理的な移動以上の、象徴的な意味合いを持っています。
38年の荒野の旅を終え、ついに「約束の地の境界」であるゼレド川を渡る。
これは、単なる移動ではなく、「神の約束の領域へ足を踏み入れること」を意味する決定的な瞬間でした。
僕はここに、深い象徴性を見いださずにはいられませんでした。
私たちの信仰の歩みにも、「ゼレドの川」のような境界線があるのではないでしょうか。
完全な約束の成就(ヨルダン川渡渉)の前段階として、まず「約束の領域の入口」(ゼレド川渡渉)に立つ時がくる。
その一歩一歩が、神様の計り知れない導きの中にあるのだと感じます。
「あの川」を渡る勇気
申命記2章14節には、こう続きます。
「カデシュ・バルネアを出てから、ゼレドの川を渡るまでに、三十八年かかって、そのときまでに、宿営のうちの戦士たちがことごとく滅びうせた」
38年かかって、ようやくゼレドの川にたどり着く。
それだけの時間を必要とするほどの、信仰の「準備期間」があったのです。
古い世代の戦士たちが滅び、新しい世代が育ち、いよいよ約束の地の境界を目の前にする。
このゼレドの川を渡る決断は、ヨルダン川を渡るための「予行演習」であり、「信仰の宣言」でもあったのだと思います。
私たちの人生にも、「ゼレドの川」と呼べるような境界線があるかもしれません。
完全な約束の成就の前に、まずその入口に立つことを求められる時。
そこで必要なのは、38年の待ち時間を経て与えられた「今、一歩を踏み出す勇気」ではないでしょうか。
このモーセ五書を描き、学びながら、僕自身も多くの「ゼレドの川」と向き合っています。
一歩を踏み出すための信仰が、少しずつ与えられていくのを感じます。
もしこの荒野の旅路に興味を持たれたら、ぜひAmazonで「モーセ五書 マンガ 石川尚寛」と検索してみてください。
無料で読めるマンガ版で、この深い旅路を共に追体験できたらと思います。
#モーセ五書マンガ
#申命記の地理
#ゼレドの川

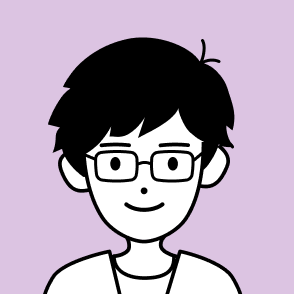
なお
僕が見つけた、「今、ここ」を生きる言葉
最近、僕はよく考えます。
明日の仕事のことが気になって、目の前のコーヒーの味がわからない。
過去の失敗が頭をよぎって、今やるべきことに集中できない。
そんな「今、ここ」から心が離れてしまう瞬間が、たくさんあるなと。
そんなある日、モーセ五書を読み返していて、神様がモーセに語られた一節で、はっとさせられたんです。
それが、出エジプト記3章14節。
神が燃える柴の中からモーセに現れ、イスラエルの民をエジプトから導き出す使命を告げる、あの有名な場面です。
モーセは神に尋ねます。
「彼らが『あなたを遣わしたのはどんなお方ですか』と私に尋ねるとき、私は何と答えたらよいでしょうか」
すると神はこう答えられました。
「わたしは『わたしはある』という者である」。
僕はずっと、この「わたしはある」という言葉を、神の自己紹介、あるいは神秘的な宣言としてしか捉えられていませんでした。
でも、ヘブライ語の原文を見て、その意味の深さに気づかされたんです。
原文は 「エヘイェ・アシェル・エヘイェ」(אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה)。
これを直訳すると、「わたしは、わたしがそうありつづけるものでありつづける」というような、とても動的で「在り続ける」という現在進行形の響きがあります。
神の名前の核心は、「在る」という状態そのもの。
しかも、それは過去や未来に限定されない、まさに「今、ここ」に在り続ける「在り方」を表しているんだ、と学びました。
神はモーセに、「わたしは『今、ここであなたと共に在る者』だ」と語りかけていた。
壮大な歴史の計画を前に、不安でたまらなかったモーセに、神が伝えたかったのは、「未来の結果」ではなく、「今、この瞬間に、わたしが共に在る」という確かな現実だったんじゃないか。
僕はそう思うようになりました。
僕たちは、モーセのように大きな使命を前にしているわけではないかもしれません。
でも、目の前の小さな課題、人間関係、自分の内なる不安に直面した時、「今、ここ」から心が離れ、足がすくむことはあります。
そんな時、この「エヘイェ」という言葉を思い出したい。
神は、「今、ここに在る」ことをご自身の名前の本質にまで高められた。
ならば僕も、過去の後悔や未来の不安に心を奪われるのではなく、「今、ここ」に自分が在ること。
そして、その「今、ここ」に、支えや意味を見出してくださる方が共に在ることを、信じて一歩を踏み出してみよう。
そう思わせてくれる一節でした。
聖書の言葉は、時代を超えて、僕たちの「今」に直接語りかけてくる力がある。
モーセ五書には、こんな気づきの瞬間が、まだまだたくさん眠っているように感じます。
僕自身も、この学びを続けていきたい。
もし、このモーセと神の出会いの物語を、もっと鮮やかに、臨場感を持って感じてみたいと思われた方がいらっしゃったら。
ぜひAmazonで「モーセ五書 マンガ 石川尚寛」と検索してみてください。
無料で読めますし、続きもどんどん公開しています。
マンガという形だからこそ伝わる、神とモーセの「今、ここ」での対話を、感じていただけたら嬉しいです。
#今ここを生きる
#モーセ五書マンガ
#聖書の気づき

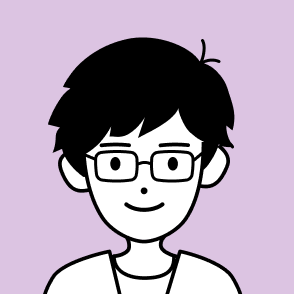
なお
こんにちは、石川尚寛です。
先日、コンビニで小さなできごとがありました。僕の前に並んでいたお年寄りの方が、小銭を探しながらもなかなか見つからず、後ろに行列ができ始めたんです。その時、後ろにいたサラリーマンの方が、さりげなく「大丈夫ですよ、ゆっくりで」と声をかけ、自分も一緒に待っていました。ふと、その場の空気が優しいものに変わったのを感じたんです。
帰り道、その光景が頭に残っていました。ほんの少しの思いやりが、その場をどれほど軽やかにするのだろう、と。そして、ふと聖書の一節が心に浮かんだんです。レビ記の、あの言葉です。
僕が今、マンガで描きながら学んでいるモーセ五書のうち、レビ記19章18節にはこんな教えがあります。
「復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛さなければならない。わたしは主である。」
ここで「愛する」と訳されているヘブライ語は、「アハヴ」(אָהַב)です。この言葉、単なる感情としての「好き」というより、もっと能動的で、意志的な「愛し行動する」という意味合いが強いんです。選択であり、実践なのです。
そして「隣人」と訳された「レア」(רֵעַ)という言葉。これは文字通り「隣に住む人」だけでなく、出会う人、関わる人、つまり自分の周りにいるすべての人を指します。コンビニで出会った、あの見知らぬお年寄りも、サラリーマンの方も、まさに「レア」だったわけです。
この教えの前に、「復讐するな」「恨みを抱くな」とあるのが、とても興深いなと思いました。神が勧めている利他の実践は、ただ「親切にしましょう」という精神論ではなく、まず自分の中にある「復讐心」や「恨み」といった、他者を遠ざけ、傷つける心に気づき、そこから解放されることから始まるのではないか、と。
「あなた自身のように」愛しなさい。
これは、自分を大切にできるからこそ、他者にも同じように心を向けられる、という逆説的な知恵のように感じます。自分を責め、貶めながらでは、本当の意味で他者を慈しむことは難しい。自分への誠実さが、他者への誠実さの土台になる。
あのコンビニで、サラリーマンの方が取った行動は、特別なことではなかったかもしれません。でも、その「さりげなさ」こそが、レビ記の教えの本質に近い気がするんです。大げさな自己犠牲ではなく、日常の一瞬一瞬で、目の前の「隣人」に対して、ほんの少し心を開き、手を差し伸べる選択。神は、そんな実践の積み重ねの中に、共に生きる社会の基盤があることを、教えてくれているように思います。
僕はまだ、レビ記を学びながら、この「アハヴ」という能動的な愛を、自分の生活の中でどれだけ実践できているのか、問い直す日々です。あなたの「隣人」は、今日、どこにいますか?
気になった方は、ぜひAmazonで「レビ記 マンガ 石川尚寛」と検索してみてください。無料で読めますし、続きもどんどん公開しています。
#モーセ五書マンガ
#レビ記の教え
#隣人を愛する

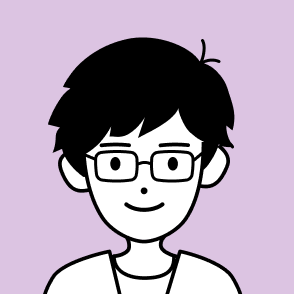
なお
こんにちは、石川尚寛です。
先日、ある友人と話していて、「人生って、まっすぐ進めたことなんて一度もないよね」という言葉が印象に残りました。
たしかに、思い描いた通りに進むことなんて、ほとんどない。
むしろ、うまくいかなかったことや、後悔している選択のほうが、心に残っていたりします。
でも、そんな「うまくいかなかった道」の先で、思いがけず誰かに出会ったり、大切なものを見つけたりすることもある。
その話を聞いて、ふと、創世記38章のユダとタマルの物語を思い出しました。
創世記38章は、ヨセフ物語の途中に突然挿入される、ちょっと異質な章です。
ユダは兄弟たちとヨセフを売ったあと、家族から離れてカナン人の女性と結婚し、三人の息子をもうけます。
長男エルの妻となったのが、タマル。けれどエルは「主の目に悪」とされて死に、次男オナンもまた、兄の名を継がせる役目を果たさずに命を落とします。
ユダは三男シェラが成長するまでタマルを実家に帰しますが、やがて彼女を忘れてしまいます。
タマルは、自分の未来が閉ざされたまま放置されていることに気づきます。
そこで彼女は、顔を覆い、遊女のふりをしてユダを誘惑し、子を宿します。
やがて妊娠が明らかになると、ユダは「火あぶりにせよ」と言い放ちますが、タマルが自分の子を身ごもったと知ると、「彼女のほうが私より正しい」と認めます(創世記38章26節)。
この「正しい」は、ヘブライ語で「צָדְקָה מִמֶּנִּי(ツァドカー・ミンメニー)」と書かれています。
「ツァダク(צָדַק)」は「正義」「義」を意味する言葉。
ユダは、自分が果たすべき義務を果たさず、タマルがそれを補ったことを認めたのです。
彼女の行動は、決して褒められるものではないかもしれない。
でも、彼女は自分の命をかけて、義を貫いた。
そしてその子孫から、ダビデ王が生まれ、やがてメシアへとつながっていきます。
僕はこの物語を読むたびに、「まっすぐじゃない人生の中で、まっすぐに選ばれることもあるんだ」と思わされます。
ユダも、タマルも、決して完璧な人ではなかった。
でも、神の物語の中で、彼らは大切な役割を担っていきます。
僕たちもまた、失敗や後悔の中にいるときこそ、何か大きな物語の一部になっているのかもしれません。
これからも、そんな視点でモーセ五書を読み続けていきたいと思っています。
気になった方は、ぜひAmazonで「創世記 マンガ 石川尚寛」と検索してみてください。
無料で読めますし、続きもどんどん公開しています。
#モーセ五書マンガ
#創世記からはじめよう
#無料で読める聖書
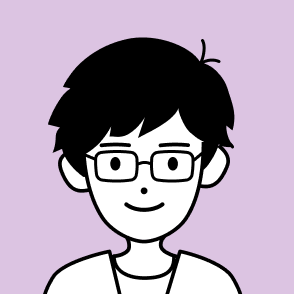
なお
こんにちは、石川尚寛です。
皆さんは、誰かにじっと見られていると緊張してしまうことってありませんか。
僕は以前、車の運転をしている時にパトカーとすれ違うと、何も悪いことはしていないのに、なぜかドキッとしてハンドルを握る手に力が入ってしまうことがありました。
「怒られるんじゃないか」「罰を受けるんじゃないか」
そんなふうに、相手の顔色をうかがってビクビクしてしまうこと。僕は長い間、聖書に書かれている「神を恐れる」という言葉も、これと同じような意味だと思っていたんです。
神様に見張られていて、少しでも間違ったら叱られる。だから震えながら従う。そんなイメージを持っていました。
でも、モーセ五書、特に「創世記」を漫画にするためにじっくりと読み込んでいくうちに、僕の中でのそのイメージが少しずつ変わっていったんです。
今日は、僕が創世記の物語を通して出会った、少し新しい「恐れ」の感覚について、皆さんと分かち合えたら嬉しいなと思います。
僕がハッとさせられたのは、創世記22章12節の言葉です。
ここは、アブラハムという人が、自分の最愛の一人息子イサクを神様に捧げようとする、とても緊迫した場面です。その直前で神様が彼を止め、こう言われます。
「あなたが神を恐れる者であることを、私は今、知った」
この「恐れる」という言葉。
ヘブライ語の原文では「ヤレー(yare)」という言葉が使われています。
確かにこれには「怖がる」という意味もあるのですが、深く調べていくと、単なる恐怖心とは少し違うニュアンスが見えてきました。
それは「畏敬(いけい)」、つまり、あまりにも偉大な存在を前にした時に、自然と頭が下がったり、息をのんだりするような感覚です。
面白いことに、この場面でアブラハムは、この場所を「アドナイ・イルエ(主は備えてくださる)」と名付けます。この「イルエ」という言葉は「見る」という意味を持っています。
実はヘブライ語では、「恐れる(yare)」と「見る(ra’ah)」という言葉は、音がとても似ていて、深いところでつながっているそうなんです。
僕はここで、ふと気づかされました。
アブラハムにとって「神を恐れる」とは、お化けや猛獣に怯えるようなことではなかったんじゃないか。
そうではなくて、「神様が今、私をしっかりと見ておられる」ということを、全身で感じることだったのではないか、と。
僕たちは日常生活の中で、誰も見ていないところでは、つい気が緩んだり、時には自分勝手な振る舞いをしてしまいそうになります。逆に、人目があるところでは、よく見られようと背伸びをしてしまいます。
でも、アブラハムの姿を見ていると、彼は誰がどう思おうと関係なく、ただ神様という「たった一人の方」の視線を意識して生きていたように思うんです。
それは、監視カメラで見張られているような冷たい視線ではありません。
自分の最も大切なものを手放してでも信頼できるような、そんな圧倒的な愛を持った方が、自分のすべてを「見て」いてくださる。
その視線を常に感じて生きること。
神様の存在を、目の前の現実よりも「リアル」に感じること。
それが、聖書が教えてくれる「神を恐れる」ということの正体なのかもしれない、と僕は思うようになりました。
そう考えると、なんだか肩の力が抜けていくような気がします。
ビクビクして縮こまるのではなく、むしろ「神様が見ていてくださるから大丈夫だ」と、背筋がスッと伸びるような感覚です。
誰にも理解されないような苦しい時も、孤独を感じる時も、神様だけは見ていてくださる。
その安心感の中で、嘘をつかず、誠実に生きていこうとすること。それが、僕たちが今日からできる「神を恐れる」方法なのかもしれません。
僕自身、まだまだ人の目ばかり気にしてしまう弱いところがあります。
だからこそ、アブラハムのように、神様の愛ある眼差しだけを意識して歩んでいきたい。そう願いながら、今日も聖書の言葉に向き合っています。
皆さんは、今日、どんな時に神様の視線を感じるでしょうか。
もし、この創世記の物語をもっと深く味わってみたいなと思われた方は、僕が描いた漫画も読んでみてください。
気になった方は、ぜひAmazonで『創世記 マンガ 石川尚寛』と検索してみてください。無料で読めますし、続きもどんどん公開しています。
#モーセ五書マンガ
#創世記からはじめよう
#無料で読める聖書

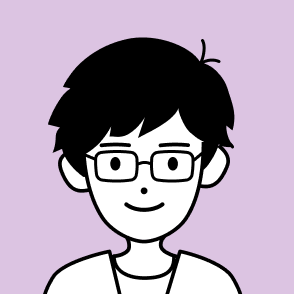
なお
こんにちは、石川尚寛です。
最近、夜にふと目が覚めてしまうことがありました。理由は特にないのですが、静かな部屋の中で「この先どうなるんだろう」と漠然とした不安が浮かんでしまうのです。眠れない時間は長くはないのですが、その瞬間だけは心が揺れてしまいます。そんな時に思い出したのが、創世記のある場面でした。
創世記15章6節。「アブラハムは主を信じた。すると、それが彼の義と認められた。」
この短い一節に、僕は立ち止まらされました。ヘブライ語原文では「וְהֶאֱמִן בַּיהוָה」(vehe’emin b’Adonai)と書かれています。「信じた」という動詞は「アーマン(אָמַן)」から来ていて、もともとは「支える」「揺るがない」という意味を持っています。つまり、アブラハムが神を信じたというのは、ただ心の中で「そうだ」と思ったのではなく、存在そのものを委ねて支えられることを選んだ、というニュアンスがあるのです。
僕はこの言葉に触れて、自分の不安が消えるわけではないけれど、「支えられている」という感覚を思い出しました。信じるとは、未来を完全に理解することではなく、揺れる心をそのまま差し出して、支えに身を置くことなのかもしれません。アブラハムもまた、約束がすぐに見えたわけではなく、ただ「信じる」という行為を選んだ。その姿に、僕自身の小さな夜の不安が重なって見えました。
この一節を読むたびに、僕は「信じる」ということを新しく問い直しています。信じるとは、方法ではなく、日々の中で「支えられている」と感じる瞬間を受け取ることなのだと。まだ答えは出ていませんが、その問いを持ち続けること自体が、僕にとっての学びになっています。
気になった方は、ぜひAmazonで「創世記 マンガ 石川尚寛」と検索してみてください。無料で読めますし、続きもどんどん公開しています。
#モーセ五書マンガ
#創世記からはじめよう
#無料で読める聖書

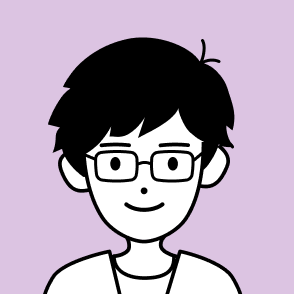
なお
最近、僕はある一つの聖句にずっと引き込まれています。
申命記6章4節。
「聞け、イスラエルよ。我らの神、主は唯一の主である。」
この言葉、ユダヤ教では「シェマ」と呼ばれ、最も大切な祈りの一つです。
「シェマ」とはヘブライ語で「聞け」という意味。
ただ音として耳に入れるのではなく、心を澄まして、全身で受け止めよ、という強くて深い呼びかけです。
「主は唯一」というヘブライ語は「アドナイ エハド」。
この「エハド」は、単なる数学的な「一」ではなく、調和した統一性を表す言葉だと言われています。
神はばらばらではなく、すべてを結び合わせ、関係性そのものであるような「一」。
この一節だけで、申命記、いや聖書全体の核心に触れる気がするのです。
僕がこの言葉に込められた重みを感じたのは、それが単なる教えではなく、約束の地を目前にしたモーセが、これから様々な誘惑や困難に直面する民に、何としても伝えたい「命綱」のようなものだったからです。
エジプトでの奇跡も、荒れ野での試練も、すべてはこの「聞く」姿勢と、唯一の神との関係性の中で意味を持つ。
申命記は、歴史の繰り返し叙述ではなく、その核心を「今、ここで」生きる民へと更新し、受け継ぐための書なのだと気付かされました。
だからこそ、申命記には「覚えていなさい」「忘れてはならない」という言葉が何度も繰り返されます。
それは過去に囚われろという意味ではなく、あなたがたの「今」は、この神との出会いと契約の延長線上にある、ということを刻み込むため。
祝福と呪いが語られるのも、それが遠い神の裁きではなく、私たちの選択が今ここに生きる関係性を形作っていく、という厳粛な現実だからです。
僕はまだ、この「聞く」という姿勢を、自分の生活の中でどう生きるか、模索しているところです。
スマホに流される情報をただ受け取るのではなく、心を澄まして、本当に聞くべきことは何か。
バラバラになりがちな日常の出来事を、どんな「一」へと結びつけていくのか。
申命記は、そんな根本的な問いを、僕の胸に静かに、しかし確かに置いてくれました。
このモーセの最後の説教に込められた切実さや、神と人との関係性の深さは、言葉で読むだけではなかなか伝わりづらいものもあります。
僕自身、石川尚寛さんの「モーセ五書マンガ」で、モーセの老年のまなざしや、民への思いがビジュアルで表現されているのを見て、ハッとさせられることがたくさんありました。
気になった方は、ぜひAmazonで「モーセ五書 マンガ 石川尚寛」と検索してみてください。
無料で読めますし、続きもどんどん公開しています。
#申命記
#シェマイスラエル
#モーセ五書マンガ

もっとみる 
関連検索ワード
