投稿
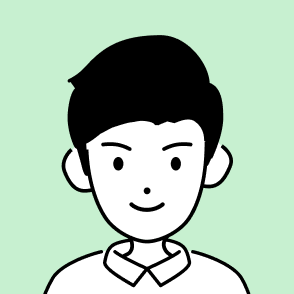
アッチャー
【届いた柿の味】(全5話)
⑤ 柿の味(後)(最終回)
「哲生です。お久しぶりです。…近くに仕事があったので、この辺りまできてみたんです。」
「…あ、どうも。お久しぶりです」
「まさか会えるとは思いませんでした。お元気そうで」
「あ、はい…」
哲生は次の言葉を待った。幸代は突然のことで何を話したらいいかわからない様子だった。哲生が期待する言葉はおろか、世辞のひとつも幸代からは返ってこなかった。
哲生は幸代に近寄り、余分に買っておいた沖縄の土産菓子の袋を差し出した。幸代はそれに手を伸ばさず戸惑いを見せた。哲生は袋からパイナップル模様の箱を取り出して腰を落とし、幸代と手をつないだままの女の子に手向けた。女の子は幸代の顔を見上げ、幸代がうなづくのを確認してから菓子箱を受け取った。
「ありがとうございます」
幸代が哲生の胸元あたりに視線を向けて言った。言葉はそれだけだった。
「突然お邪魔しちゃって…それでは失礼します」
幸代の母に会釈をして、哲生は小杉家の門を出た。
訪ねるべきではなかった。
哲生は幸代から届けられた柿の皮を剥きながら思った。50年余の人生の中の、幼少期のほんの5年か6年のあいだ近くに暮らしていただけの、幸代にとっては思い出す必要もない存在。そんな人間が予告もなく突然、安全であるはずの実家に姿を現すという無神経さを、哲生は今になって恥じていた。
なぜ幸代は、平日の午後に小さな子と共にあの家にいたのか。哲生にその理由を知る術もなければ、知る必要さえもなかったが、突然の外来者を幸代が喜んでいないのは明らかだった。
哲生は小さくカットした柿を口に入れた。
過熟ぎみの、ぬるく甘ったるい果肉が口の中で溶けた。哲生は自分の中にあった執着心を思った。
「冷やしたほうがうまそうだな」
心の隅に沈む未解決の執着は、それを知覚し言語化した時に昇華への処理が始まる。
青い琉球ガラスの皿に盛られた柿を、哲生はラップで覆い、冷蔵庫のチルド室にしまった。
(おわり)
最後まで読んでくださりありがとうございます。
©️2024九竜なな也

話題の投稿をみつける
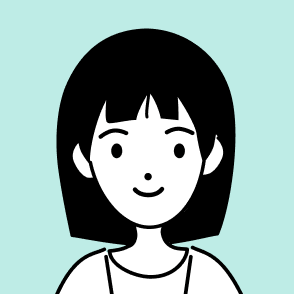
ちぇり
そんなに美味くないよ?もっと若い子から吸ってくれよw
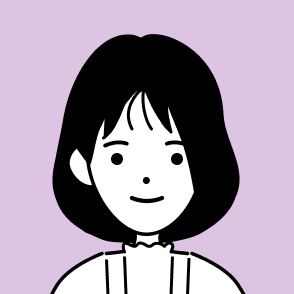
さらこ
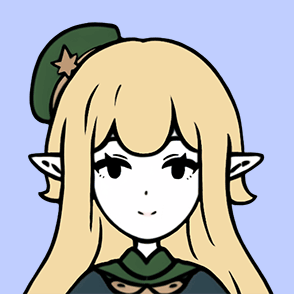
熊野に
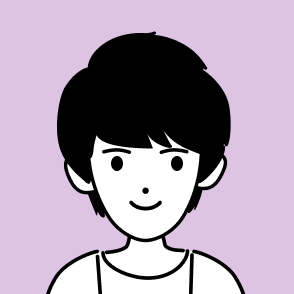
鱈れ芭
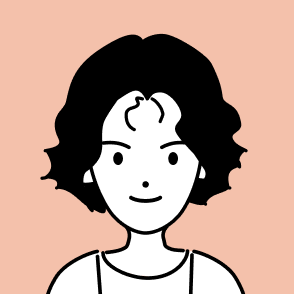
終わり

憲弥(か
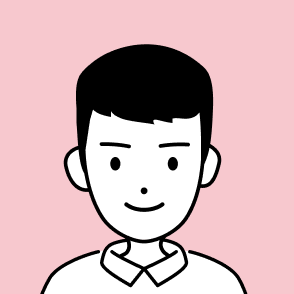
誤楽苑

mig
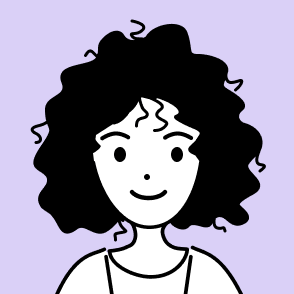
はな
ブロマイドのビジュ良すぎる
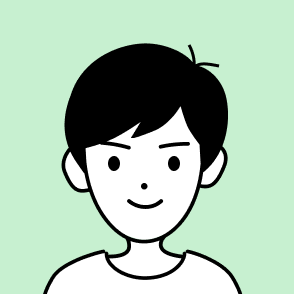
こーろ
もっとみる 
関連検索ワード
