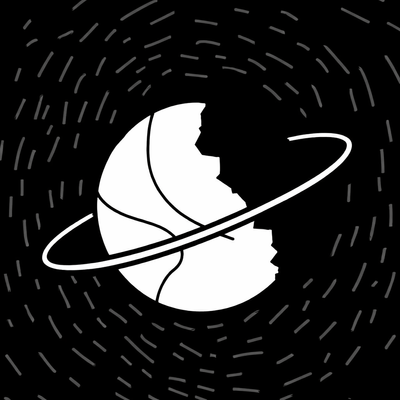投稿

よん
恒一郎は今日も机に向かわず、肘掛椅子に深く身を沈めて本を開いている。そこにあるのは、かつて彼自身が書いた文章であったが、今の彼にとってそれは、もはや自分の肉体から剥がれ落ちた、他人の皮膚のようなものであった。
眼鏡の奥で、文字はひそやかに脈を打つ。
それを読む彼の指先だけが、妙に白い。
女中は、そこに居る。
居る、というより——在る、と言うほうが近かった。
用向きをすべて終え、名目を失った時間が訪れると、彼女は自然の理に従うように、恒一郎の膝元へ身を寄せた。断る理由も、断られる理由も、存在しない。
触れているのは、肩口と、髪の先と、体の重さ、その一部だけ。
その限られた重なりこそが、彼女にとっては完全であった。
恒一郎の指が、思惟を伴わぬまま、彼女の髪に触れる。
引き寄せることも、撫でることもない。
ただ、乱れてはならぬものが、乱れていないかを確かめるように。
女中は、恒一郎の指先に、触れてはならぬやさしさが紛れ込んでいることを、皮膚より先に知る。
目を閉じる。
眠っているふりをするのは、恥を悟られぬためではない。意識を保ったまま触れられることのないように。
——起きていれば、望みが生じる。
頁を繰る音が、雨と重なり合う。
その微かな反復の中で、彼女の内側には、名づけようのない快が沈殿していく。
やがて夕闇が書斎に忍び込み、ランプに火が灯される。橙色の光の下で、恒一郎は一瞬だけ、本から目を離した。
——言葉は、必要とされていなかった。
言葉というものは、最初から、この二人のあいだに差し挟まれる余地を持たなかったのである。
彼女の重みを崩さぬまま、恒一郎は再び頁へと視線を戻す。
雨は、なおも静かに降り続いている。



ポルターガイスト
関連する投稿をみつける
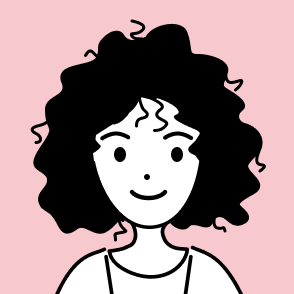
サカナ
もう30分くらい座り込んで、髪びしょびしょのまま置きっぱなしにしてて…。
明日、頭痛出ませんように(自分で乾かせばいいじゃん、、
それも今日一日で急にいっぱいニキビが出ちゃった…もうアレルギーみたいひどくなっちゃった
ホルモンの乱れのせいかな、それとも最近気分が落ち込みすぎてるせいかな

🦦
全てお世辞か冗談だと思って受け取ってる。
嘘つかれてばっかりだからさ。
ねねねねね ᙏ̤̫

我降臨
ただそこにいる自分を愛してあげて


era it
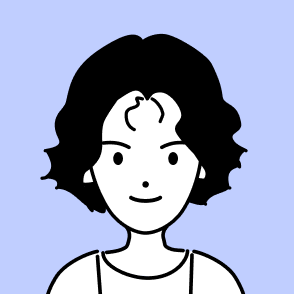
俺私又は僕
お前死にたがってるだけやぞ
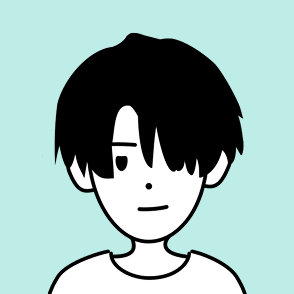
みやざわ
更生しても犯罪者扱いとか終わってるって
もっとみる 
話題の投稿をみつける
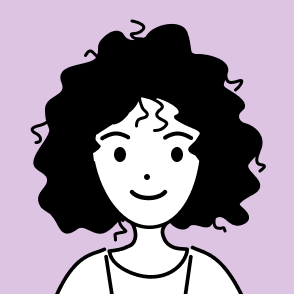
ルンル
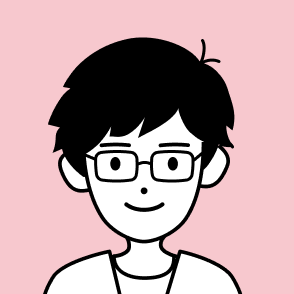
黒之
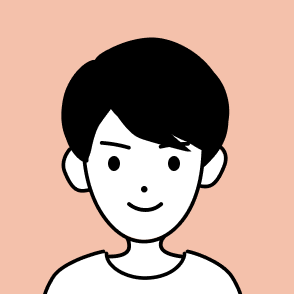
はる
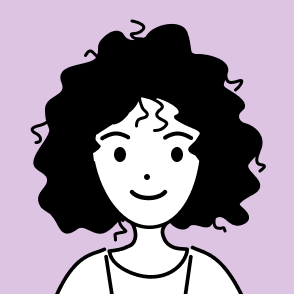
ルンル
#ラヴィット
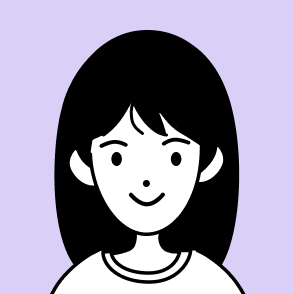
とむち
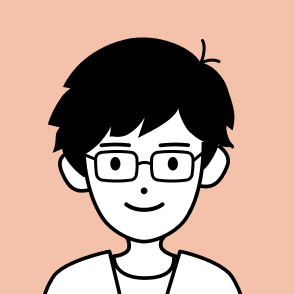
えむぽ

ジェン
スマホケースにしたい

幾果
武士かよっていわれたけど、心にとびっきりの一振りを磨き上げて、いつでも振るえるようになっときたいよなーというのがあるといいますか。
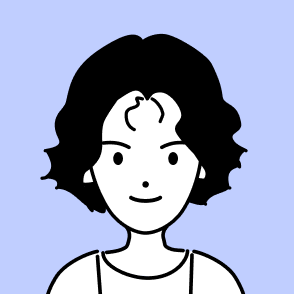
カナイ
いいとか悪いじゃなくて落ち着かなくて意味ないからそんなんならそもそも行かない。
乳幼児なんてそんなもんなのよ。
まれに大人しく座ってられる子は別として。
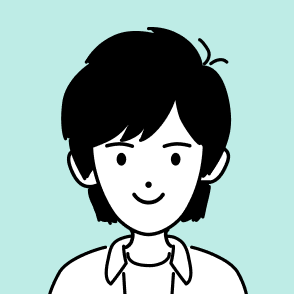
モーセ
もっとみる 
関連検索ワード