投稿
おにぎり
進路希望調査の紙が、机の上で風にひらひら揺れている。
あと少しで提出期限だというのに、私はまだ一文字も書けていなかった。
——何になりたいんだろう、私。
教室の窓から差し込む午後の光はきらきらして
いて、絵を描くのが好きな自分をそっと背中から押してくれるようにも思える。
けれど「これがやりたい!」というはっきりした気持ちは、どうしても見つからなかった。
放課後、帰り道。
梨花は嬉しそうにスマホを見せてきた。
梨花「ねぇねぇ見て!美容の専門学校のオープンキャンパス!絶対行くの!」
「へぇ、いいじゃん。梨花、ずっとやりたいって言ってたもんね。」
梨花「そう〜親を説得するのはまだこれからだけどさ〜」
「説得できたらいいね。うまく行けれたら、だけど……」
梨花「しろ、それ“行けたら”ね。“行けれたら”は言わないから!」
「あ、またやった……?」
慶も、部活帰りの汗をぬぐいながら言う。
慶「俺は公務員。安定しているし稼げるからな。」
梨花「ほ〜う、将来は結婚相手に専業主婦とかして欲しいっていうタイプだな〜?」
慶「べ、別にんなじゃねぇよ!事実だろ!」
梨花「はいは〜い」
ふたりとも、未来の話をすると目が輝く。
その光は眩しくて、楽しそうで、
——私には、なにもない。
そんな不安が胸の奥にじわりと広がった。
家の前に着くと、父親がちょうど帰ってくるところだった。
父「おう、シロ。今日はちょっと多めに獲れたぞ。」
父は漁師で、深海漁を生業としている。
競りでさばけなかった売れ残りの魚をいつも持って帰ってくる。
その発泡スチロールの箱の中に色んな種類で少しグロテスクな見た目の魚も混じっていた。
母親が手際よくそれを調理し、食卓に並べる。
母「今日のは身がしっかりしてるわよ。シロも食べなさい。」
「うん……ありがとう。」
私はいつも通り夕食を食べ、自分の部屋に戻り、
いつも通り布団にくるまって眠りについた。
ーーー暗い。
だけど怖くはない、静かな場所。
どこか、海の底を思わせるような暗さ。
(……やあ。)
突然、耳の奥に声が落ちてきた。
(今日、君に食べられた“さかな”だよ。)
「……え?」
自分の声が、水の中に溶けていくみたいに響く。
(ちょっとだけ、話がしたくてね。
深海の外のこと、知ってるかい?)
姿は見えない。
だけど、その気配は確かにそこにあった。
(深海よりもっと上。「そら」っていうものがあるんだ。
「しばふ」の上で食べる「さんどいっち」は、とても美味しいらしいよ。)
「……空? サンドイッチ?」
(うん。僕はね、それを一度でいいから見てみたい。食べてみたい。)
静かに、淡々と語る声だった。
深海で生きるさかなが、ほんの少しだけ抱いた夢。
そんなものがあるなんて、私は考えたこともなかった。
しばらく沈黙が続いたあと、私はふっと笑った。
「……そのくらいなら、すぐ叶うよ。」
(え?)
「簡単だよ。空も芝生も、すぐそこにあるし。
サンドイッチくらいパパっと作れるよ。」
(……本当に?)
「うん。だから、楽しみにしてて。」
さかなの気配が、ほわっとほどけていくように薄れた。
――夢の中なのに、すごくあたたかかった。
⸻
ぱちっと目を開けると、朝の光がカーテン越しににじんでいた。
夢――だった。
でも、不思議と忘れたくない気持ちが胸の奥に残っていた。
(サンドイッチ……作ってあげるって、言っちゃったし。)
変だな、と自分でも思う。
相手は“魚”。
しかも“食べたあと”に見た夢。
それでも。
誰かのために何かをするのは嫌いじゃない。
むしろ昔から、人に頼られたり喜ばれたりすると嬉しかった。
だったら――
「……作るか。」
私はエプロンをつけ、冷蔵庫の中の材料を探し始めた。
卵、レタス、トマト。パンを軽く焼いて、マヨネーズを薄く塗る。
思いのほか手が動くのは、きっと
“誰かのため”だと張り切ってしまう自分の癖だろう。
完成したサンドイッチをタッパーに詰め、家を出る。
朝の空は高くて、遠くて、澄んでいる。
深海とはまるで違う世界だ。
温かい陽の光が、まぶたの上からじんわり染み込んでくる。
芝生の上に寝転んで、私はひとりサンドイッチを頬張っていた。
さっきまで風が心地よく吹いていて、
鳥のさえずりと子どもの笑い声が遠くから混じり合って聞こえていた。
サンドイッチを食べ終え、
ふぅ、と息をついた途端、
眠りがすとんと落ちてきた。
そのまま、いつの間にか眠ってしまった。
⸻
夢の中
(……ありがとう。)
暗い海のようでいて、どこかあたたかい世界に、あの声が響いた。
(「さんどいっち」、すごく美味しそうだった。
「そら」も……「しばふ」も。本当にあるんだね。)
「うん。私たちにとっては当たり前にあるものだけど……喜んでくれてよかった。」
(君はやさしいね。
僕の小さな夢を、こんなにあっさり叶えてしまうなんて。)
くすぐったいような、照れくさいような気分になる。
(だから今度は、僕が君の夢を叶える手助けがしたい。)
「……え?」
夢の中なのに、胸がどきっと跳ねた。
(だって、君にはまだ“夢”がないだろう?
君の中にいて、なんとなく分かったんだ。)
図星だった。
私は言葉に詰まる。
「……うん。やりたいこと、分かんないんだ。
みんなみたいに、未来に向かって進んでる感じもなくて。
私だけ、止まってるみたいで……。」
さかなはすぐには答えなかった。
深海のような静けさが広がる。
(じゃあ、一緒に探そう。
どこにあるのか、どんな形なのか分からないけど……
君の夢が見つかるまで、僕はそばにいるよ。)
その声は、海の底から浮かび上がる泡みたいに優しかった。
「……ありがとう。」
そう言った途端、世界が淡くほどけて――
⸻
ぱちりと目を開けた。
空はすっかり橙色に染まり始めていた。
長い影が芝生の上にのびていて、少し冷たい風が吹いてくる。
「……夕方だ。」
寝ていた身体を起こすと、胸の奥にさかなの言葉が残っていた。
――一緒に探そう。
私は空を見上げた。
青からオレンジへ変わっていくその色は、
静かな町ではあまり見られない鮮やかさだった。
この町が嫌いなわけじゃない。
でもここにいる限り、私はずっと同じ毎日を繰り返す気がした。
みんなが進んでいくのに、私だけ進めない。
自分が何者か分からないままで、ここに留まることが
急に怖くなった。
「……どこか遠くに行ってみよう。それにどうせなら行くなら人が多い都会にしよう。」
ぽつりと口にした言葉が、思った以上にしっくりきた。
#短編小説
関連する投稿をみつける
フェンリル5150
その後のことはあんまり覚えてない。
気がつくと、久美子に貰った住所を頼りに、千秋の家まで全力疾走してた。
なかなか出逢わなかったのは、入退院を繰り返してたからだ。
クリスマスが毎年来ないだなんて、千秋には明日も不確かだったからだ。
一気に符合する彼女のピース。
俺はバカだ。本物の大バカだ。
くそったれ。
家に着くと
優しそうなお父さんが出迎えてくれた。
お母さんは一緒にアメリカに渡ってるらしい。
僕の名前を告げると、涙を滲ませて、奥から何冊かのぼろぼろのノートを出して来た。
「もしも君に会えるなら、渡そうと思ってたんだ。これは千秋の日記だよ。5年前。あの子が病院で王子様に出逢った時から書き始めた、王子様への想いを綴った日記だよ。君にはとても重いものだろうし、申し訳ないとは思うんだけど、帰って来れるか分からない娘のためにも、それを読んでやって欲しいんだ。あの子の王子様、君への想いがどれほどのものかを、覚えていてやって欲しい。どうかお願いします」
僕は黙ってうなずき、ノートを開いた。
***
涙が止まらなかった。
高1の秋。
僕は確かに千秋に逢っている。
大事故に遇って、大手術からの奇跡の生還。
しかし、楽しいはずの高校生活を送るはずだった彼女に与えられたものは、いつ爆発するかも分からない爆弾だった。
体力的にも精神的にも限界だった頃に、ふと、見舞いで病院を訪れていた僕に出逢って、病院の庭に咲いていた金木犀の花を手渡され、がんばろうって励まされた。
僕が、同じ高校の同級生と知った彼女は、辛いリハビリにも耐え、退院後も何度も何度も挫けそうになる自分を、僕が渡した金木犀で作ったポプリを身にまとって、奮い起たせながら頑張って来た。
いつか、僕と並んで歩く日を夢見ながら。
大学で初めて出逢った時、僕が見覚えがあるって言ったことが、どれほど嬉しかったか。
どんな無茶を言っても、どんなわがままを言っても、優しく受けとめてくれたこと。
そして、生命を脅かされ、ずっと苦しんで来たこの血腫に立ち向かおうと決められたって。
来年も再来年も、ずっとずっと僕と一緒に笑っていたいって。
僕が、笑ってない千秋は嫌だから、元気に直してまた逢おうぜって、背中を押してくれたって。
くそったれ。
僕はどんだけバカなんだ。
君は、どんだけ身勝手なんだよ。
君が。
君が居ない世界なんて、もう考えられなくなってるんだよ。
神様。
どうか、彼女を
僕の千秋を無事に帰して下さい。
千秋の笑顔が見たいんだよ!
神様!
***
10月。
あれから一年。
お父さんからはわりと細やかに連絡を貰ってた。
手術は成功。
生命に危険はもうないらしい。
千秋は、爆弾に勝ったんだ。
術後の処置やらリハビリやらで、ずっとアメリカに居たんだけど、つい先日、帰国して、かかりつけの大学病院に転院してる。
結論を言うと、彼女の記憶はない。
家族すら忘れているほど
見事に記憶が抜け落ちているらしい。
でも、僕は待つんだ。
あの日、千秋が言った言葉を信じてる。
「また逢おうね。行ってきます」
だから今日も
僕はここで座って、帰りを待ってる。
世界中にひとりくらい
こんな王子様、居てもいいだろ?
僕のお姫様が
目覚める日を夢見ながらね。
ほら。
金木犀のにおいが。
#GRAVITY創作部
#短編小説
フェンリル5150
もう9月。
今まで
早ければ一週間。
遅くても一ヶ月は空いたことはなかった。
いつも突然に
金木犀の香りを連れて、彼女はやって来ていた。
あれからもう三ヶ月。
彼女は一向に姿を見せない。
さすがに心配になった僕は、初めて彼女を探してみることにした。
かといって、手がかりはない。
どこの学部なのかも分からない。
誰か友達が居たのかも知らない。
仕方なく
大学の事務局で尋ねると、学部は同じ理学部。
コースは違うけれど、だいたい僕と同じ講義を取っていた。
自宅や連絡先を聞いてみたが、やはりプライベートな部分はお答え出来ませんと断られた。
それならと、同じコースのやつを片っ端から聞いて回ってみると、僕と同じ高校出身の女の子、須藤久美子が知っていた。
「何言ってんのよ?千秋でしょ?
私たちと同じ高校出身の板野千秋。知ってるに決まってるじゃないの」
「……へっ?」
「…呆れた。同級生の顔も名前も知らないなんて、さすが人間嫌い海くんね。まぁあの子の場合、仕方ないのかもしれないけど…」
「…どういう意味?」
ふぅっと大きくため息をついて、久美子はすごい事実を語り始めた。
「あのね。千秋は高1の春に酷い交通事故に遇って、三ヶ月入院してたの。信号無視のトラックにひかれてね。奇跡的に一命はとりとめたんだけど、脳に大きな爆弾を抱えちゃったの。血腫。いつ裂けるか分からない血の塊が、よりによって手術出来ないような脳の神経の中に出来ちゃってるの。それは年々少しずつ膨らんで、いつかは生命も危険になるんだって。それがいつになるか分かんない。ただ、すごく難しい手術だけど、同じような患者を何人も救った医者が、アメリカに居るんだって。だから今、千秋は休学してアメリカに渡ってるよ」
「………………」
あまりにも想定外の事実に、言葉も出なかった。
「……海くん最近、千秋と仲良かったもんね。聞いてなかったの?手術決めたの、突然だったんだよ?私たちもびっくりしたもん」
「……いつの話だ?」
「……んー。6月くらいだったかなー。ここに入学してからも、ずーっと入退院繰り返してて、血腫の状態がまた悪くなったとかで、手術するかどうか迷ってるって言ってたんだよ。それが突然、手術することに決めたからって。そうそう!やっぱし6月だわ」
「……連絡先と自宅、教えてくれる?」
「…いいけど…あの子があなたに言ってないのなら、逢わないであげたほうがいいんじゃない? だって……もし手術が成功したとしても、確実に後遺症は残るそうだから…」
「…後遺症?」
久美子は一度深呼吸をして、僕に向き直って言った。
「記憶障害。無くしちゃうんだって。記憶を。」
#GRAVITY創作部
#短編小説
フェンリル5150
「海くーん!」
12月。
大学構内の銀杏並木を下校中、今はもう聞きなれてしまった声が、後ろから追いかけて来た。
僕は大きくため息をついて、いつものように振り向きもしないで歩く。
突然背中に柔らかい衝撃と金木犀のにおい。
「どーん!」
「わゎっ!何すんだ!」
体当たりで抱きつかれ、つんのめるのをこらえながら、それでも彼女を守らなければと、結果、おんぶすることになる。
ふくよかな背中の柔らかさに顔が紅くなる。ミニスカートじゃん。生足。ふえぇぇ。
回りから冷やかしの指笛が鳴り響く。
「危ないだろ?!」
「へへー。やっぱやっさしいなぁ。ちゃーんと受け止めてくれるんだもんねー」
おんぶした背中越しから耳元に話されて、背中のおっきな柔らかさも相まって、真っ赤になる。
あれから
千秋とはこうして時々、突然の邂逅を果たす。
いつだって突然。
学科もどこに住んでいるのかも知らない。普段どこに居るのかも知らない。同じ大学に居るにもかかわらず、不思議とぜんぜん逢わないからだ。
でも、こうして出逢うと、いつも僕は、すっかり彼女のペースに巻き込まれることになる。
身勝手で、無邪気にわがままな、彼女のペースに。
「ねっ! クリスマスだよっ? イヴだよ?海くん彼女居ないし予定もないよね?今日は買い物につきあってよね」
「………なんで彼女居ないって分かんだよ」
その言葉に、千秋の顔が少し曇った気がした。
「……何?誰かと予定…ある?」
あぁ。
この目だ。
こんな捨て犬みたいな上目で言われると、僕はすごく弱い。
ほんと、千秋はズルい。天然なのが余計にムカつく。
「……分かったよ。行くよ。どこ行けばいいんだ?」
とたん、花咲く笑顔。
あぁ。ダメだ。すっごい可愛い。
「やったー! じゃぁねー。名古山のパティスリーでお茶してねー。大津イオンのストーンショップ行ってねー。えーと、えーと」
「やけに盛りだくさんだな?! 絞らないと全部回れないんじゃ?」
「いいの!今日は初めてのイヴなんだから!」
「…?? 初めてのイヴってなんだよ? クリスマスなんて、毎年来るぜ?」
「だーめ!毎年来ないの! 今日しかないって精一杯生きなきゃ、人生はもったいないことだらけなんだよー!」
「…大げさだなぁ。 まぁいいけど。じゃぁ、早く名古山行こうぜ」
「はーい! 」
それから、いろんなところをたらい回しにされ、夜遅くまで散々引っ張り回され、帰路についたのは、日付をとっくに越えたクリスマスの夜だった。
へとへとに疲れるくらいに、引っ張り回されたものの、僕はずーっと笑っていることに気づいた。
こんなに笑ったのなんて久しぶり。
いつしか僕は、こうした身勝手な彼女との逢瀬を、楽しみにするようになっていた。
***
「どうしたんだ?」
6月。
二回生に上がって、ルーキーたちも落ちついてきはじめた梅雨の始まり。
講義を受けていると、金木犀のにおいを連れて、後ろからそっと千秋が隣に座って来た。
顔色が悪い。
「んー。何でもない。風邪かなぁ?」
それでも、くしゃっと笑った彼女の顔は、ひどく弱々しく見えた。
「代返しといてやるから、帰って寝てろよ?……熱…あるみたいだし」
おでこに手を当てると、彼女は一瞬身体を震わせた。
ぽーっと紅くなる。
座ってても差のある僕のほうを見上げた千秋の紅い顔に、前触れもなくひとすじ涙が伝う。
「えっ? えっ? 痛かった? ごめん! 」
千秋はふるふると顔を振って
「ううん。ほんとにやさしいなぁって。……嬉しいなぁって」
「何言ってんだよ? とにかく今日は帰って病院でも行きな。笑ってない千秋見てんの、なんかやだし。ちゃんと直して、また元気に笑って逢おうぜ?」
そう言っておでこを撫でてやると、みるみる彼女の目にいっぱい涙が溜まっていく。
「わっ!泣くなってば。なんでだよ?落ちつけ!」
「……海くん…あたしね…………ううん。……ありがとね。じゃぁお言葉に甘えて病院行こっかな」
「…? まぁいいや。気をつけろよ?」
「うん。また……また逢おうね。じゃぁ……行ってきます」
「あ? あぁ。またな。」
そして彼女はよろよろと立ち上がり、満面の笑顔で小さく手を振って、教室を出ていった。
それが、彼女を大学で見た最後だった。
#ひとりごとのようなもの
#短編小説
#創作活動
フェンリル5150
『Oneday in autumn』
君はいつだって身勝手だった。
わがままで、得手勝手。
気分屋で、小悪魔気味。
気まぐれに僕を振り回して、いつだって楽しそうに笑ってた。
想えば
初めて出逢った、あの秋の日から
君は身勝手に、不躾に
土足で僕の中に入り込んで来たんだ。
こんなものなんて、いらないんだよ。
そんなことより、もっと……くそったれ。
あの頃に戻れるなら、僕は……
***
「海かいくんだよね? 隣いいかなぁ?よいしょっと」
「えっ?ちょっと?! そこ連れが来るんだけど」
「いいからいいから。あー。この教授の講義ってかったるいのよねー。ね?そう思わない?」
「…僕は好きだよ。細かく詳しく教えてくれる。それに、勉強熱心だ」
「…ふーん。そうなんだー。じゃぁあたしも今日から好きになるよ。うん」
「ってか、あんた誰? なんで僕のこと知ってんの?」
「ふふー。あたしは千秋ちあき。君と同じく一回生ね。
君、有名だからねー。
知らないの? この学校の女の子たちみんな、こぞって君を狙ってんだよー。かっこいいんだもん」
「……うぜぇ…。何しに大学来てんだよ…」
「そういうとこ。君、他の男の子と違って、ちゃらちゃらしてないじゃん? 真面目で頭良さそうなのに、ダサく無くてすっごく垢抜けてる。大人のひとみたい。そんなとこがたまんないんじゃないのー?」
「……じゃないの…? あんたはそう思ってないってことか?」
「ふふっ。ひみつー。さっ。教授来たよ? べんきょーべんきょーっ」
「………」
そう言って、ノートを開いてシャーペンを走らせる彼女の横顔に滑り落ちる、少し赤みがかかったさらさらの髪。
そのあまりの美しさに、僕は少し言葉を失った。
この子、すごい綺麗だ。
背中まで伸ばした紅いハイレイヤーが、胸の豊かな曲線をなぞってる。小顔のキャンバスに乗ったパーツは、絶妙に整っていて、どこか異世界の住人のよう。
着てる服も何気にいいセンスだし。
垢抜けてんの自分のほうなんじゃん。
何より、このにおい。
すごくいいにおい。
金木犀?かな?すごくやさしいにおい。
なぜだか懐かしい。
「何? 見蕩れてくれてるの?」
突然、彼女が振り向いてにこやかに笑う。
音が聞こえるくらい胸が鳴った。
僕は慌てて目をそらし、平静を装う。
「…いや。君、なんか見たことあるなって思って」
一瞬、彼女の顔が泣きそうにほころんだように見えた。
でも、すぐ意地悪そうな笑顔に変わる。
「ほんとに? 光栄だなぁ。学内イチの人気男子に覚えて貰えてるなんてねー」
彼女は本当に嬉しそうに、またノートに向かった。
僕は、ついに講義が終わるまで、横目で彼女を追うのをやめられなかった。
#ひとりごとのようなもの
#短編小説
#創作活動
フェンリル5150
5000字くらいの掌編をひとつ分割してここにあげてみます。
ちょうど秋〜冬だからぴったりのお話。
企画で、『突然お題を渡すから5000字までで、今すぐに書いて明日までにあげろ』みたいなお題だったと思います[目が回る]
#ひとりごとのようなもの
#短編小説
#創作活動

サッキー
突然、彼女がそんなことを聞いてきた。
僕「いえ……」
彼「『奇跡』なんだって。まるで私たちみたいじゃない?」
僕「?」
彼「も~、ちょっと来て‼」
彼女は僕の腕を引いて青い薔薇の前に座った。
彼「見て、青い薔薇。こんな綺麗な薔薇を綺麗な花に囲まれて私みたいなカワイイ彼女と一緒に見れてるんだよ? これって奇跡じゃない?」
僕「はぁ……」
彼「もう‼ 反応が薄い‼」
僕「だって、今から一緒に死のうとしてるところでそんなこと言われても……」
彼「人生最後なんだよ? もうちょっと楽しくいこうよ。せっかくの最後なんだから」
僕「今まで楽しくなかったから自殺するのでは……」
彼「まぁ、そうなんだけど……」
彼女はしょんぼりとした顔で薔薇をつついた。
彼「はい」
彼女は小瓶から自分の分の薬取り、瓶を僕に渡した。
彼「じゃあいくよ?」
僕と彼女は同時に薬を飲んだ。
彼「よし。じゃあ一緒に寝ようか」
彼女は横になり、僕はその隣に寝そべった。
彼「ねぇ、私といれて幸せだった?」
僕「そうですね……。一緒にいれた時だけは幸せでした」
彼「フフッ。良かった」
彼女はそう言って笑った。
彼「地獄でまた会えると良いね?」
僕「はい」
彼「それじゃ、おやすみなさい」
僕「おやすみなさい」
彼女は目を閉じた。
僕もゆっくり目を閉じた。
意識の薄れゆく瞬間、風が舞い、花びらが散っていくのを感じた。
僕は微笑んだ。
僕「僕も愛してますよ。貴方のこと」
#花彩命の庭
#短編小説
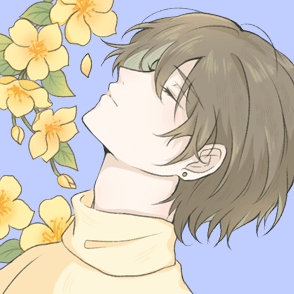
大介
-----------------------------------------
『眠りは夢のなかにて』
窓辺に立つと、夜の気配がそっと肩に触れた。
彼女は、薄いカーテンの向こうに広がる闇を見つめながら、かすかな夜風が頬を撫でてゆくのを感じた。
それは、まるで誰かの声のようだった。
遠くから、あるいはずっと昔から、彼女の耳に届いていたような、かすかな囁き。
部屋の灯を消すたびに、世界が少しずつ遠のいてゆくのがわかった。
壁に映る影が、ゆらゆらと揺れている。
それは彼女自身の影だったのか、それとも、かつてそこにいた誰かの残像だったのか。わからなかった。
ただ、その影だけが、今日という日を生きた証のすべてのように思えた。
──あの夏の午後のことを、ふと思い出す。
十七のとき、彼と最後に会った日。駅までの道をふたりで歩いた。彼はほとんど何も話さなかった。
ただ、蝉の声が遠くで鳴いていた。
別れの言葉もなく、彼は列車に乗り、窓の向こうで小さく手を振った。白い駅舎の壁に、彼の影が一瞬だけ映って、それが彼女の記憶に焼きついた。
あの影が、今もこの部屋の壁に揺れているような気がしてならなかった。
彼女は、夢の扉の前に立っていた。けれど、その扉はまだ開かれていなかった。誰の手にも触れられず、ただそこに在るだけの扉。
彼女は、終わりという言葉を、心の奥でそっと拒みつづけていた。
終わりが来ることを、どこかで知っていながら、それを受け入れることができなかった。
机の引き出しを開けると、古びた便箋が一枚、折りたたまれていた。宛名はなかった。
彼女が書いたものか、それとも誰かから届いたものか、もう思い出せなかった。
そこには、たった一行だけ、こう綴られていた。
──この夜が永遠であればと願っています。
彼女はその紙をそっと閉じ、また引き出しに戻した。
まるで、それが夢の断片であるかのように。
眠りは、やわらかく彼女を包もうとしていた。
けれど、その静けさには、名を与えることができなかった。
言葉にしようとすればするほど、それは遠ざかってゆく。まるで、霧のなかに手を伸ばすように。
明日という名の見知らぬ街が、彼方にあるという。
けれど、彼女はまだ、その街へ旅立つことを恐れていた。
そこに何があるのか──誰が待っているのか──わからないままに。
この夜が、もし永遠に続いてくれるなら──そんなことを思いながら、彼女は耳を澄ませていた。
風の音が、かすかに、けれど確かに、窓の外から聞こえていた。
終わりなき始まりを、彼女は探していた。けれど、それはどこにも見つからなかった。
夢だけが、まだ、今日という日を夢みていた。
まるで、眠りのなかに、もうひとつの夢があるかのように。
夜が明ける少し前、彼女はそっと窓を開けた。
風はまだ冷たかったが、遠くに灯りがひとつ、瞬いていた。 それは、見知らぬ街の気配だった。
彼女は、まだ夢のなかにいた。
けれど、その夢の底で、かすかに、何かが動きはじめているのを感じていた。
それが、始まりなのかどうかは、まだわからなかった。
ただ、彼女は、もう一度、目を閉じてみた。
そうして、そっと歩き出していた。
──そして、また、眠りのなかの、終わらぬ夢に。
おにぎり
1週間後。
私は故郷の海岸に立っていた。
どうやってここまで来たのか、記憶がところどころ途切れている。
携帯すら、ルアの部屋に置きっぱなしだった。
潮風が髪を揺らし、
白く濁った波がゆっくり足元へ寄せては返す。
そのとき――
胸の奥で、小さな“声”がした。
さかな 「……夢は、見つかった?」
懐かしい声だった。
あの日、夢の中の海で出会った、小さな魚の声。
私はゆっくり目を閉じる。
(夢……?私は……今、どこにいるんだろう)
頭の中が暗い海に沈んでいくような感覚に包まれて、
波音が遠くなっていく。
世界が水に浸るように、ゆっくり静かに沈んでいく。
深く、深く、
心だけが“暗い場所”へ沈んでいく。
そこで私は考えた。
(私の夢って……なんだったんだろう)
(もし……もしもう一度やり直せるなら)
(もう一度、“夢を見てもいい”のなら)
(今度はあの空の下、芝生の上でサンドイッチをみんなで食べよう。)
私は溺れていく。
誰のものでもない私だけ。
深海で溺れていく私のーー。
#短編小説
もっとみる 
話題の投稿をみつける
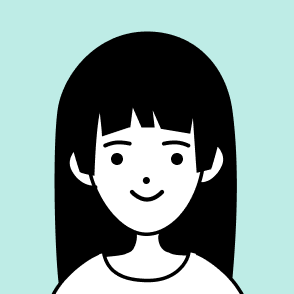
みよか(
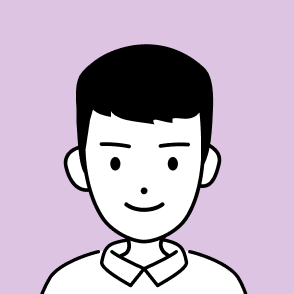
🐯あー
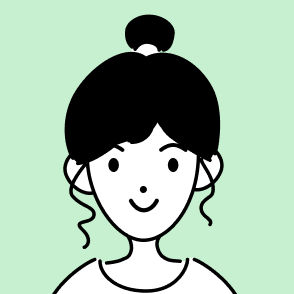
ににに
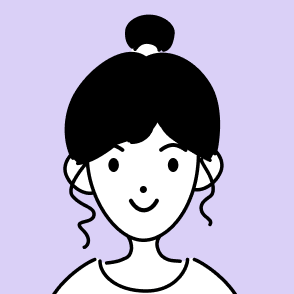
ルビ姉(
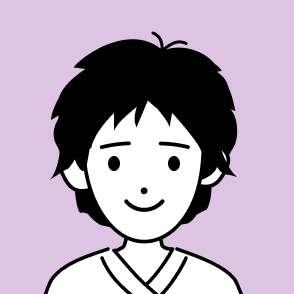
りゅう
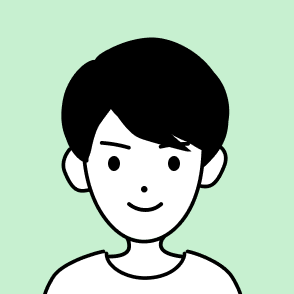
YS☂️
伊藤の盗塁でカバーできたけど
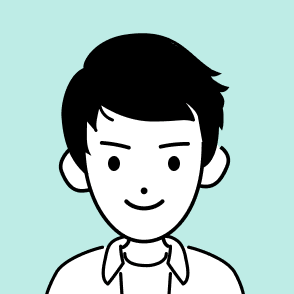
おおち
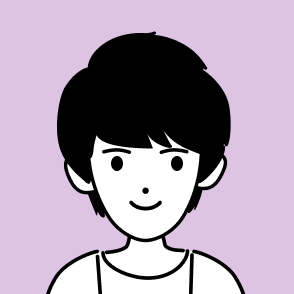
り た

☮️soo
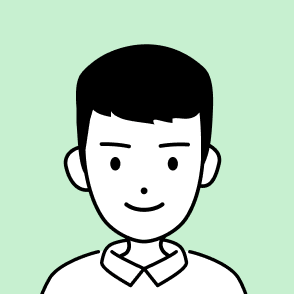
あてし
もっとみる 
関連検索ワード
