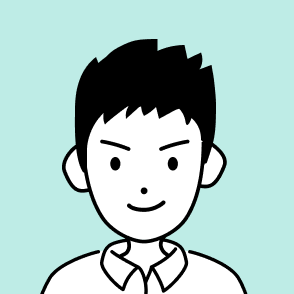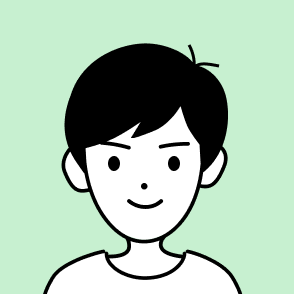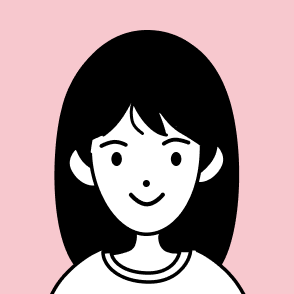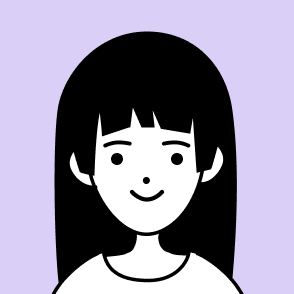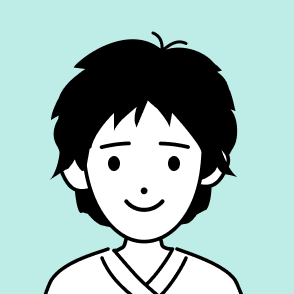ふわふわの毛皮に包まれし虚無の爪が月影を裂き、魚の骨が夢を呑み込む蒼き瞳の果てに、にゃあ。
影は螺旋を描きながら舞い上がり、夜空を切り裂くように広がった。星々はその軌跡に囚われ、まるで猫の爪先に絡み取られた光の糸のように震えた。
月光がその身を隠すとき、闇はひそやかにささやき始めた。
「にゃあ」
と、か細くも鋭い声が木々の隙間を抜け、風に溶けて消えた。だがその声は、確かに存在しないものの輪郭を縁取り、その奇妙な残響は影と影の間に潜む何かを呼び起こした。
「にゃあ。」
再び響く。
そこには猫がいた。黒く艶めいた毛皮に覆われ、蒼い瞳が夜を切り裂くように輝いている。猫は魚の骨をくわえ、虚無の中に佇んでいた。その瞳に映るものは、何もかもが霞んでいる。虚無の爪は地面を引っかき、そこから血のように赤い花が咲いた。花弁はゆらりと揺れ、風に舞い上がって夜空へ溶けていった。
猫はふと耳を立てた。遠くで泣く子供の声が聞こえる。泣き声は虚無に吸い込まれ、影の向こうへと消えていく。猫はじっとその方向を見つめ、蒼い瞳に僅かな感情を浮かべた。それは憐れみとも寂寥ともつかぬ、形のない思念だった。
「にゃあ。」
猫はもう一度、今度はやや優しく声を上げた。
すると地面が軋み、亀裂が走る。そこから現れたのは、魚の骨で編まれた小さな塔。塔の頂きには、猫の毛皮を思わせる黒い布が絡まりつき、その中にひっそりと光る蒼い宝石が埋め込まれている。猫は慎重に近づき、鼻先で宝石をつついた。
突然、宝石が強烈な光を放ち、塔が崩れ去ると同時に黒い霧が立ちこめた。その霧は猫の周囲にまとわりつき、毛皮をなぞるように撫で回す。猫は身をよじり、爪を立てて霧を引き裂こうとするが、そのたびに霧は増殖し、猫の動きを鈍らせた。
「にゃあ!」
今度は鋭く吠えるような声が響いた。霧は一瞬だけたじろぎ、猫はその隙を突いて一跳びで塔の跡地を飛び越えた。しかし、霧は追いかけてくる。その中から無数の手が伸び、猫の毛皮を引き裂こうとするが、猫の動きは疾風の如く、誰一人として触れることができない。
そして、猫はやがて静寂の中心にたどり着いた。そこにはもう霧も手もなく、ただ蒼い月光が降り注ぐだけだった。猫はゆっくりと座り込み、虚無の爪を舐めた。すると、霧の残滓が音もなく崩れ落ち、大地に溶けていった。
猫はその場でしばらくじっとしていたが、やがて蒼い瞳を細め、何かに気づいたように顔を上げた。月光が柔らかに降り注ぎ、遠くでまた
「にゃ