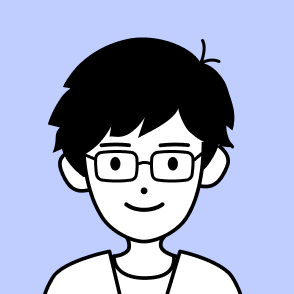
サラダ
文学
読書
ヨルシカ

サラダ

サラダ

サラダ


サラダ

サラダ
僕は君を許せない きっと許せない
でも許可はいらない いらない
暗い月光の許で僕の夢を見た
君は僕を許すかな きっと許せない
でも許可はいらない できない

サラダ

サラダ


サラダ

サラダ


サラダ

サラダ


サラダ



サラダ


サラダ


サラダ

サラダ

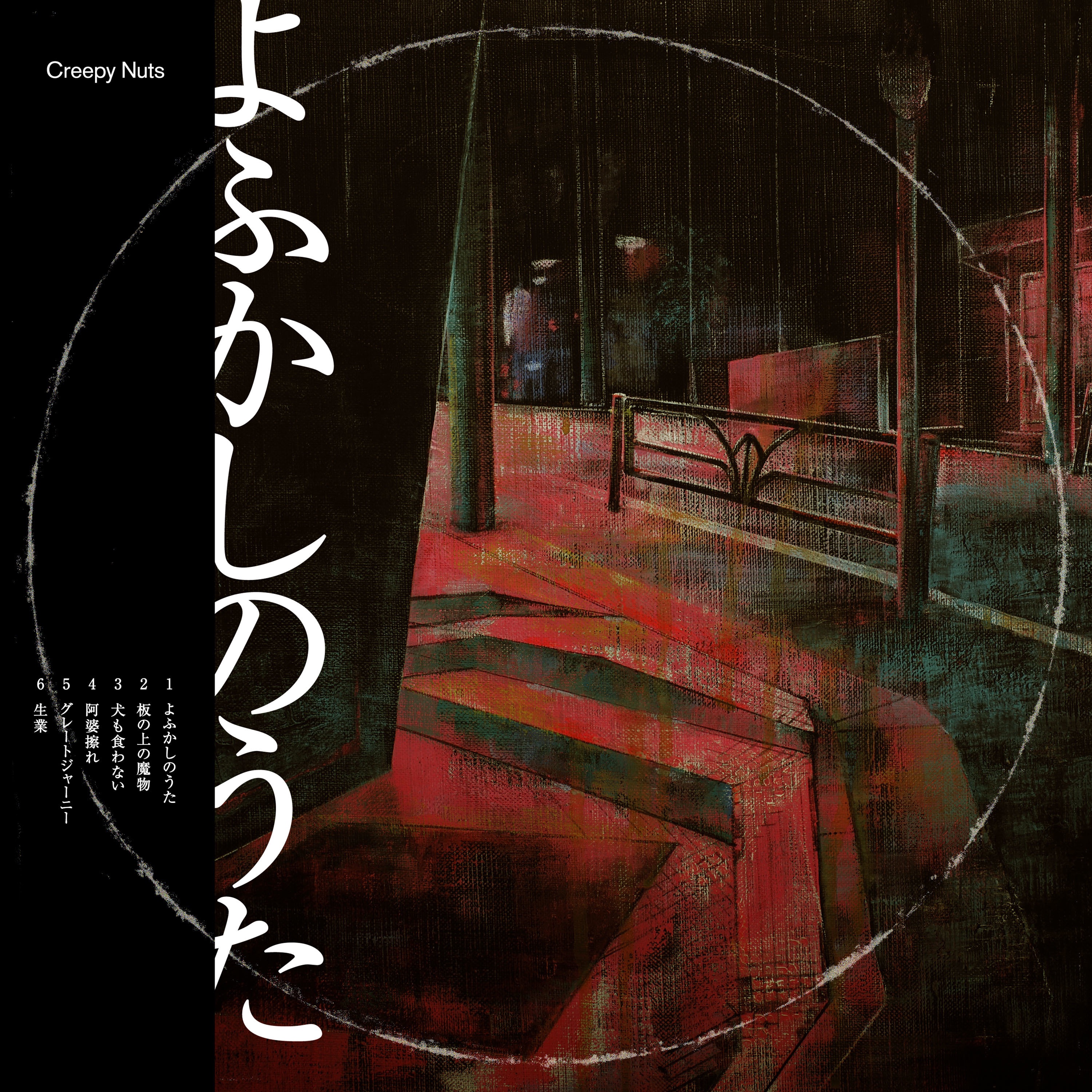
よふかしのうた - Yofukashino Uta

サラダ


サラダ

サラダ
あぶらの後は 灰も残らず

サラダ

サラダ

サラダ

サラダ
僕が泣き出す迄 君は眠らない

サラダ

サラダ

サラダ

サラダ
僕は歩きながら道に落ちている何ともない石ころを蹴ってみる。石ころは音もなくころがって、ほんの数十センチ動いたところで消えてなくなった。そう、この世界はどうでもいいこと、即ち「僕」が「石ころを蹴る」なんて行為はこの二次元世界の作者からはまったくどうでもよくて、作画コストをかけたがらないのだ。だから僕を構成する線は荒くて太いし、声もほとんど出せない。
学校に着く。クラス全体を見渡す。僕のクラスは、やけに作画が凝っている。きっとこのクラスの中の誰かが重要人物かなにかで、そこに力を入れなくてはいけない理由みたいなのがあるんだろう。
「綿貫君っ」
語尾にクレシェンドの記号がついてそうなセリフだ。
宮城 園。彼女の構成される線は細く繊細で、髪は焦げ茶色の柔らかい長髪。目は髪と同じ色をしていて、キラキラと光を放っている。彼女を構成する要素は、ほとんどアニメの主役そのものだ。彼女の画角の中はいつも細い世界でできていて、見応えがある。それに、彼女に話しかけられると今まで僕になかったはずの声帯が復活するのだ。
「おはよう、また課題?」
僕は自然に、脇役そのもののようにふるまう。“ふるまわされる”。
「うん、数学で分からない問題があって。」
綺麗な声だ。自然で、「訓練された声」。
「君には岸君がいるじゃないか。それに僕は数学は得意じゃないよ。」
半分言わされたような気がするが、半分は本心だ。
「“あれ”は今はいいの。今は綿貫君に聞いてるんだから。」
その声の響きはよく訓練されているせいか、怒りの感情を含んでいるんだと理解出来る。
淡々と、数学を教える。それは不思議な程にスムーズに、まるで早く終わりにしたいと言わんばかりに短い時間で終わった。きっと無駄なパートなのだ。
「ありがとう!これで蟹先(担任)に当てられてもへっちゃらだね」
彼女はそう言ってウインクをして舌を出す。
(きっとこのポーズを描きたくてこのパートを描いたんだろうな…)
「あっ、あのさ!」
急に大声を出されたので、驚いて彼女の方を向く。その声色は緊張に溢れていて、でも訓練された分かりやすさとはまた違う、あどけなさから出た緊張のように聞こえる。僕は唾を飲み込む。
「今日の帰り、図書館に寄ってかない?模試も近いし、勉強を教えて貰いたくて…」
今度は最初のクレシェンドとは逆に、デクレジェンドの記号がついたみたいに心もとないセリフだ。もはやセリフというよりは、ただの会話みたいにも聞こえる。
僕は応えようとする。もちろん拒否する内容で。しかし声帯が動かない。きっともう物語の中ではないのだ。僕は何かないかと慌てた結果、笑顔で親指を立ててしまった。そして放課後まで“スキップ”される。
「ほんとごめんねー、今回数学やばくてさ!助かるよー」
いつも通りの、クレシェンド気味のセリフに戻る。僕の声帯も元に戻る。
「僕は全然いいんだけどさ、岸君とは何があったんだい?彼なら数学も得意じゃないか。」
今度は自分でも意識していない、棘のある言い方だ。こんな言い方はしたくなかった。
「またそれ。だから、今は“あれ”はいいんだって。取り敢えず、数学だけに集中すればいいの」
宮城は、本当に滑らかに歩く。線の細さもさることながら、立体感ももちあわせているようだ。そういうことを実感する度に、僕は不安になる。本当に僕はここにいるべきなのか。このままでは、この物語の引き立て役のようなものになって痛々しい役になってしまわないだろうか。茶色く、太陽の光に当てられてこよなく輝く彼女の長髪とは裏腹に、僕の不安はより深く、渦になって頭の中を這いずり回った。
電車のシーンが挟まれる。席はびっくりする程空いていて、僕らが乗った車両には僕と宮城しか乗らなかった。宮城は僕の前に座った。彼女は僕を、目を凝らして見る。僕の気持ちはお構い無しに、ずっと長い間舐めまわすように見る。僕は赤くなる…はずだったが、そんな作画コストは許されていないようだ。
急に、電車は宙に浮く。細く、細くなってゆく。電車の窓に映る雲は緻密に表現されていて、遥か彼方に浮かんでいるとは到底思えない程に、鮮明に揺れていた。落ちる。ゆっくりと、スローモーションになって落ちる。それは比喩ではなく、物語における「表現」だった。宮城が、僕の胸に頭から倒れ込んでくる。それをきっかけにか、線はもっともっと立体感を増してゆき、僕までをも巻き込んで細くなる。だけど、落ちるスピードは急に早くなる。今度は実際に落ちるスピードよりももっと早く電車は落下する。そして、効果音もなく電車は地面に突き刺さった。
目を開ける。落下の衝撃のせいか、世界がぼんやりと滲んで見える。さっきまで細かった線達は太く荒くなっていた。そして、僕は心臓が止まりそうになる。宮城の焦げ茶色の美しい長髪を僕が握っていて、その先に宮城の体が見当たらないのだ。僕は立ち上がる。すると、足に乗っかっていたものがずるりと落ちる。宮城の体だ。いや、頭もある。宮城がぱちりと目を開ける。そこには前のキラキラとしたものは感じられない。
「綿貫君…?」
そう言って僕を見つめる彼女の髪は黒い短髪で、僕が持っていたのは鬘だった。

サラダ


サラダ

サラダ

サラダ


サラダ


サラダ


サラダ

サラダ


サラダ

サラダ


サラダ


サラダ

サラダ

サラダ

サラダ

サラダ
特にお前

サラダ
