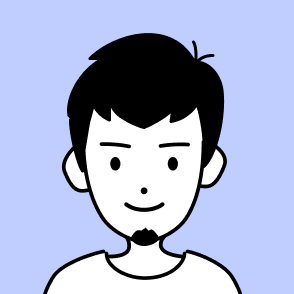
に
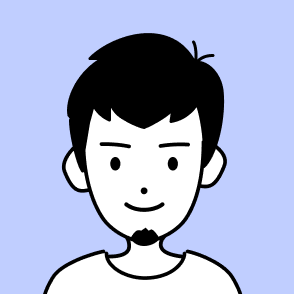
に
花彩命の庭 ― 星波の綴り手
夜の帳が落ちるたび、庭の奥にある“星波の池”は静かに光を帯びていく。
その輝きは水面からではなく、もっと深いところ──水底のさらに奥、時間と記憶の隙間から滲み出しているようだった。
「今日は、昨日より静かね」
池のそばでひとり、灯(ともり)は膝を抱えて呟く。
彼女はこの庭の“綴り手”と呼ばれる存在だが、自分ではそんな大層なものとは思っていない。それでも庭に迷い込む誰かのために、今日もここにいる。
しかしその夜、池に落ちる光の粒はいつもより重たかった。
ひとつ、またひとつと沈むたびに、胸の奥がざわつく。
──誰かが、強く願っている。
──それは、救いの形をしていない。
灯が立ち上がった瞬間、池の表面が揺れ、光の帯が空へと引き延ばされた。視界が反転し、身体が吸い寄せられるように、光の中へ落ちていく。
⸻
目を開けた先は、見知らぬ海岸だった。
風は冷たく、波は色を失っている。灰色の世界。
その中央で、ひとりの青年が膝をついていた。
「呼ばれた…の?」
灯が近づくと、青年はゆっくりと顔を上げた。
その瞳には、深い海の底と、長く閉ざしてきた孤独が宿っていた。
「……君は誰だ」
「灯。花彩命の庭の綴り手。あなたの呼び声が届いたの」
青年はしばらく何も言わず、ただ海を見つめていた。
やがて波がひとつ砕けるとともに、彼はぽつりと呟く。
「俺は、海斗(かいと)。
大切なものを、ひとつ残らず手放してしまった。
その重みを抱えて生きるには、俺は弱すぎたんだ」
彼の言葉は、波の色と同じくらい冷たく沈んでいた。
灯はそっと彼の隣に座り、海へ視線を向けた。
灰色でも、波は止まらない。形を変えながら、確かに寄せ続けている。
「海斗。あなたはまだ終わりを選んでいない」
「終われなかっただけだ」
「終われなかったのは、願いをまだ手放してないからよ」
海斗は目を細め、灯を見つめた。
その視線には怒りでも哀しみでもなく、たったひとつの問いがあった。
「……願い、なんて生き物は、まだ俺の中に残ってるのか」
灯は微笑んだ。
「残っているわ。
だからこそ、私がここに来れたの。
“庭”は、もう少しだけあなたを連れて行きたい場所があると言っている」
彼女が手を伸ばすと、海の色がゆっくりと変わり始めた。
灰色は淡い藍になり、藍は星影を映し込む深い青へと変わっていく。
「海斗。帰りましょう。
あなたの願いを、あなた自身がまだ知らない場所へ」
彼はしばらく迷ったが、灯の手を取った瞬間、世界がふたたび光に包まれた。
⸻
次に目を開けたとき、そこは花彩命の庭の中心──“記花の大樹(きかのたいじゅ)”の前だった。
四方から色とりどりの花片が舞い上がり、大樹の幹に触れるたび、音のように優しく光を放つ。
海斗は息を呑んだ。
「……ここが、君の庭か」
「そう。ここには、来た人の“願いの種”が眠ってる。
海斗の種も、ずっと前からここに転がってたのよ」
灯が指を差す。
大樹の根元に、ひとつだけ黒い種が落ちていた。
海斗がそっと手に取ると、その表面に薄い亀裂が走った。
「これは……俺の?」
「あなたがずっと握りしめてきた後悔。その奥に隠れていた“願い”の形。
後悔と願いは、同じものから生まれることもあるの」
亀裂は光へと変わり、小さな芽が現れた。
その光は海斗の胸へ流れ込み、凍っていた何かを溶かすように温かかった。
海斗は静かに息をつく。
「……こんな感覚、忘れてた。
まだ……何かを望んでいいのか?」
灯はうなずいた。
「望んで。
願いは、あなたが生きる理由になる。
理由がある限り、あなたの物語は終わらない」
海斗は芽を胸に抱きしめた。
その瞬間、大樹からひとつの花弁が舞い降り、彼の肩にそっと触れた。
まるで「ようこそ」と告げるように。
⸻
「灯」
帰り際、海斗が振り向いた。
その表情にはまだ影が残るが、もう灰色ではなかった。
「……ありがとう。
もしまた迷ったら、ここに来ていいか?」
灯は微笑む。
「もちろん。
この庭は、迷った人のためにあるんだから」
海斗は小さく笑い、光の道へ歩き出した。
彼の足跡は、庭に柔らかな色を落としていく。
灯はその背中を見送りながら、胸の奥でそっと呟いた。
──今日もまた、ひとつの願いが息を吹き返した。
──花彩命の庭は、まだ誰かを迎えに行くだろう。
そして、夜の帳が落ちる。
新しい波が、また誰かをここへ運んでくるために。
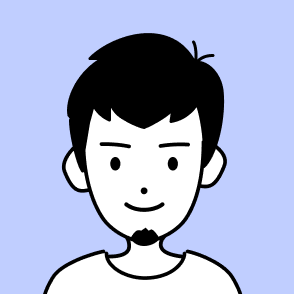
に
花彩命の庭の中心には、歌う花がある。その歌声は聞く者の過去と未来を優しく紡ぐ。
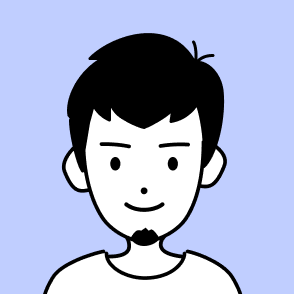
に
月光が差す夜、花彩命の庭の花々がそっと持ち上がり、空へ浮かんだ。少女はその光景を「天の絵筆」と名付けた。
