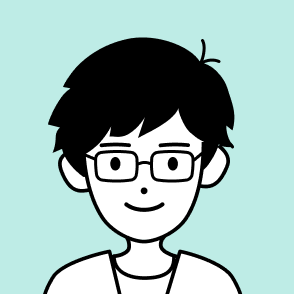ミッドナイト・フェスティバル
投稿

あお
会いたい
でも もう
叶わない
「いつ忘れられるの?」
と訊いたあとで
「忘れたいの?」
と 自分が問い返す
同じ時代
同じ世界
あなたはどこかで
生きているのに
もう
二度と
会えないなんて
そんな
残酷なことが
ほんとうに
あるなんて
自分の記憶
自分の心
なのに
なのに
どうして
私の言うことをきいてくれないの?
忘れたいのに
忘れたくない
忘れたくないのに
忘れたい
叶わない
ただ
それだけなのに
どうしてこんなに
痛いんだろう
#ずっと夜の心

あお
葉のすき間からこぼれる月の光は、まるで誰かのためらいのように弱々しく、足元を白く染めていた。
おこじょさんは、岩の上にひとり座っていた。
小さなからだを丸めて、しっぽを前足に巻きつけて。
目を閉じるでもなく、なにかを見るでもなく、ただ、じっと。
「また、やりすぎたかしらね」
ひとりごとのように、そっとつぶやいた声が、夜の空気に吸いこまれていく。
おこじょさんは、思ったことをそのまま言ってしまう性分だった。
それが長所でもあり、短所でもあった。
ちいさなころからそうだった。
気になることを見過ごせず、考えたことを飲み込めず、誰かに言ってしまう。
「本当のことを言ってるだけだもん」
それは、嘘じゃなかった。
でも、たいてい誰かを怒らせた。
あるいは、泣かせた。
そして、距離ができた。
あの夜の、狐さんの話だってそうだった。
言ってることとやってることが矛盾していて。
だから、つい言ってしまった。
「見られたくないなら、描くな。
見てほしいなら、素直にそう言え。
そのどっちもできないなら、黙って森の奥で描いてな。」
――たしかに、言いすぎたかもしれない。
カサッ、と音がして、足元に何かが落ちていた。
月の光に照らされて、白い紙切れがひらひら揺れた。
おこじょさんはそれを、そっと広げた。
そこには、ぎこちない文字で、こう書いてあった。
「あんたの言葉、ムカついた。
でも、ちょっとだけ、本当だった。
ありがとうとは言わないけど、
もう逃げないって決めた。
だから、また描く。」
少し、にやけてしまった。
そして、気づけば目元が熱かった。
思えば、狐くんの絵は、いつもどこか歪んでいた。
角度が混ざって、視点がずれて、まるで一枚のなかにいくつもの顔があるようだった。
どこを向いて、何を思っているのか――よくわからない。
けれど、それが彼なりの、表現だったのかもしれない。
「……キュビズム、ってやつかしら」
おこじょさんは、ちょっとだけ笑った。
風がやさしく吹いた。
森の奥で、何かがまた始まる気がした。
その夜、おこじょさんは泣いた。
でも、それは前よりすこし、うれしい涙だった。
おしまい
#狐さんの悩み事返歌
#おこじょさんが泣いた夜
#ことばりうむの星
@モ!
あめ
慰めるようにキスをした
あんなに好きだった頃は
一度も会いに来なかったのに
夢の中の君も
なかなか意地悪だ

涼
闇がそっと呼吸をひそめる
月は仮面をかぶり 星たちは観客席へ
風が舞台袖で衣を揺らし
一夜限りの夢が始まる
きらめく屋台の光は
記憶をキャンディみたいに包んで
笑い声、手のひら、恋の匂い
すべてが今夜の魔法になる
触れたら消える
それでも掴みたくなる
この瞬間は
火花よりも、あなたよりも熱い

あお
「欲しがらない魔法」
選びきれないの?
ふふ、それなら——選ばなければいいのに。
だってね、
わたし、もう持ってるの。
ひだまりのにおい
眠る前のまぶたの重さ
木々が揺れて、笑ってる音
それだけで、胸がいっぱいになるのよ
冠も、杖も、名前も
そんなの、どこかに置いてきた
それより大事なもの
ずっとここにあるから
欲しい、って気持ちも
すてきな魔法だと思うけど
いらない、って思えるとき
世界がとっても静かになるの
あれもこれも、じゃなくて
ひとつで十分
ひとつがあるだけで、わたしは大丈夫
わたし、愚者なんかじゃないよ
なにも持ってないんじゃない
大切なものは
もう持ってるから🧚♂️

あお
選びきれない?
ならば、すべて手に入れよ。
欲望とは、断つものではない。
——調えるものだ。
冠も、宝石も、秘密も。
悦びも、哀しみさえも。
この手の中で輝かせてこそ、
王の器というもの。
あれも欲しい。
これも欲しい。
そう思うのは、生きている証だ。
取捨選択は、民のすること。
我は王だ。
選ぶのではない——采配するのだ。
愚者? 上等。
愚かであったからこそ、今の我がある。
影を愛し、矛盾を抱き、
それでも笑う。
それが、我が流儀。
この世の美酒は苦い。
だが——喉ごしを楽しむのが、王というもの。
誰と眠ろうが、
何を纏おうが、
「どれにしようか」などと悩む姿さえ、
我を映す万華鏡よ。
「全部楽しめなければ意味がない?」
まったく、その通りだ。
意味など、自ら与えるもの。
欲しいものは、つかみとれ。
我こそ、王。

モ!
貪欲の悪魔「マモン」よ
人々の心に浸潤したる現代の王よ
殺戮と安寧の天秤を担うものよ
なぜ私を誘惑する?
なぜ私に対価を求めようとさせる
黄金の花冠
銀の杖
私の名を呼ぶあの柔らかき声
もう十分に持ってるではないか
こんなにも恵まれているじゃないか
なのになぜ求めさせる
黄金の花冠を被りながら
紙で作ったパーティー帽を羨むような
銀の杖をつきながら、稚児の木の枝を妬むような
私の名前を三人称の無味乾燥な言葉に変えるような
愚かな交換を求めるのだ
なぜ質よりも量にこだわる?
鋭い紡錘形は所詮球にはなれぬ
それでも私はそれが欲しい
ああ、それも欲しい
ああ、全部欲しい
☮️ピース☮️
大地は眠り陽の熱は冷め風のない静寂と手を伸ばしても祓えない帳がおりていた
静止した世界でただ唯一聞こえるのは自分の呼吸、心臓、衣擦れ
本当に独りだけのとても狭く冷たい味のしない感覚に動けずにいた
消え去りたいとあれほど強く考えていたのに
ほんとうの闇を目の前にして本能的に恐怖した
ここから逃げ出したい
境界線から離れたい
あの人に会いたい
絞りだされた感情を強く念じる
頬を伝う汗
僅かな夏の匂い
揺れる木々
喉が渇く
雲がほどける
ほんのわずか
蒼い光が零れ落ちた
それは言葉よりもあたたかく
名前のない不安をそっと撫でていく
やわらかな光が肩に触れて
私は歩き出していた

モ!
「俺は太陽が欲しい」
月の玉座に座る獣は言った
星たちは不安そうな顔をした
「太陽は本来俺のものなのだ」
獣は遠吠えをした
ビリビリと黒い森が大きな手で撫でられるように、薙いでは元に戻り、元に戻っては少し行きすぎて、また元の定位置に戻った
「ああ、妬ましい」
獣の声は霜となり大地に落ちた
「あたいは月が欲しい」
太陽の玉座に座る娘はそう言った
閑雲たちは怪訝な顔で娘を見た
「月は本来あたいのものなのだ」
娘は金色の目を怒らせ腕で宙を薙いだ
炎が飛び散り緑の森が燃え上がる
世界はうんざりするほど輝いた
夕刻
太陽と月がかち合う刻
太陽の玉座から娘は飛び出し
炎の蛇で月の獣を襲う
月の獣も玉座を離れ
凍える龍で娘を襲撃する
丁々発止
炎の蛇と凍える龍は絡み合い
シュウシュウ蒸気をあげて消えた
幾度も両者の炎と氷は放たれ消える
その度に雲は増え
その度に星も増えた
やがて太陽は玉座ごと海に落ちる
「覚えておきな」
娘は叫び煙を上げて骸となった
獣は唸った。今日も太陽が奪えなかった
星々は鮮やかに輝き出した
月はそれよりもなお輝く
何が惜しくてこの夜を手放したがる?
星々は心から思う
そしてきっと明け方が来れば
骸になるのは月の獣の方だろう

みっちー
ぼんやり浮かぶ
朧月
それを見ながら
飲む酒美味し
もっとみる