関連惑星
恋愛相談室の星
1017人が搭乗中
参加
恋愛の事で困ったらここで話してね!
気軽に日常のこと話してもOK!
47都道府県の星
115人が搭乗中
参加
各都道府県を探す星です。惑星というより彷徨える彗星…
おじさん構文教室 の星
83人が搭乗中
参加
おじさん🧔♂️構文を教える💮ヨ‼️‼️‼️
大喜利教室
83人が搭乗中
参加
西Йζ語義ξ府ぃの星
56人が搭乗中
参加
西Йζ語義ξ府ぃの僕
恋愛結婚🌸相談室の星
39人が搭乗中
参加
学生の淡い恋から、シンママパパの恋愛、夫婦関係、離婚等、幅広く相談可能な惑星です
【ルール】
✮GRAVITYの規約は守る
✮誹謗中傷、名誉毀損に当たる発言はしない
✮個人が特定できる情報の発信は避ける
(ルールは今後増える可能性有り)
町中華の星
39人が搭乗中
参加
皆様の身近な町中華、地域の違いで種類も違う🎶
町中華を楽しみましょう🍜🍥
相談室🌱𓂃 𓈒𓏸の星
34人が搭乗中
参加
相談室🌱𓂃 𓈒𓏸の星へようこそ!!
数ある星の中から選んで頂きありがとうございます!🥰💕
ここでは、悩み事や相談事など些細なことでも身内には言えないけど匿名には言えるかも?とか様々な悩み事や相談事を言い合って、解決したりアドバイスを言い合ったり、助け合いの場になればいいなと思っております!!✨️
ぜひ気軽に相談してくださいね🎶
規約違反になるような内容はお辞め下さい。人を傷つけるような内容もお辞め下さい。
皆さんが居心地いいなって思えるような星にしたいのでご協力よろしくお願いします🙇♀️
上野 御徒町の星
32人が搭乗中
参加
上野 御徒町 アメ横大好き♡
ただそれだけ。
お酒や、グルメや、人、パンダ🐼など…笑
みんなで情報交換しながら盛り上げて行きましょう。
全国 47都道府県・雑談
24人が搭乗中
参加
人気

あの、うっちー
(室町幕府)

ゆう
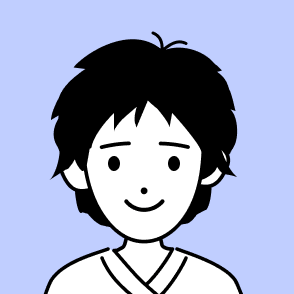
刻苦勉励

ちくわチュワーン
足利たかうじうじ
たまかしわ〜
マミ
室町幕府 第12代将軍
に任ぜられる。
1508年旧暦永正5年7月1日

もち
誰か助けて〜!
室町幕府のところ〜
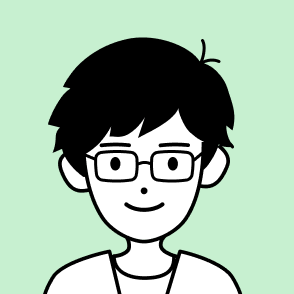
テルル

風神雷神 朧月
回答数 9>>

サメちゃん💐🦋
「足利義昭」(あしかがよしあき)は、室町幕府の第15代征夷大将軍。 約230年間続いた室町幕府最後の将軍です。 兄で第13代将軍「足利義輝」(あしかがよしてる)が暗殺されると、室町幕府を復興させると決意。 当時、勢力を伸ばしていた戦国大名「織田信長」(おだのぶなが)の力を借りて将軍となります。

もっとみる 
関連検索ワード
新着
史的唯物論者シン
鎌倉時代に西国支配の出先機関として六波羅探題が置かれていたこと
室町時代に将軍の他に鎌倉公方等の東国支配権力が存在したこと
幕末に奥羽越列藩同盟が結成されたこと
これらを見るに、東日本と西日本は伝統的に異なる支配機構や権力構造、文化圏をもっていたんじゃないかねぇ[穏やか]

臼井優
しかし、これは小説やテレビドラマで広まったもので、学術的には根拠が薄いとされ、多くの専門家は「想像の域を出ない」と否定的ですが、伊賀出身の弟子の曽良が忍者だった可能性は指摘されています。
忍者説の主な根拠(とされるもの)
出自:伊賀国(忍者の里)の出身で、母親が伊賀の有力上忍「百地氏」の家系という説があるため。
奥の細道の旅:5ヶ月で約2,400kmを歩破した健脚ぶりは、忍者の身体能力を思わせる。
資金と関所:多額の旅費や、一般人には困難な関所の自由な通過は、幕府からの資金援助や手形があった隠密活動の証拠と見なされる。
旅の目的:伊賀、東北(外様大名が多い)、北陸を巡り、有力大名の情勢を探っていたのではないか。
忍者説への反論・現在の見解
出自の疑問:芭蕉の家は農民(無足人)であり、忍者としての訓練を受けた証拠はない。
身体能力:当時の日本人でも健脚な人は多く、一日数十キロの移動自体は驚くべきことではないという意見もある。
創作の産物:松本清張などの小説やドラマで脚色され、戦後の忍者ブームと結びついて広まったフィクションである。
史料の欠如:忍術を使った記録や、隠密活動を裏付ける確たる史料は、現在まで見つかっていない。
マミ
1712年1月28日
旧暦:正徳1年12月21日
江戸幕府 第9代将軍の誕生日🎊

メタ=ニンチ少将
大名家の家老と、神社の管理者と、部隊訓練の専門家を兼ねている者が、室町後期に多かっただろ?
片倉小十郎だ。
それを、どの身分にすればいいんだ?
武家にすれば、神社とのパイプが弱くなるか?
既存の東北社会を壊さぬように、ルソン、北京占領への協力者として最大限に機能させるには、どのようにする?
君は豊臣政権の運営者として、答えよ

メタ=ニンチ少将
室町後期は、寺、神社の人が武勇に優れた例が多かった。部隊の指揮官として使える連中であった。
さて、ミソラ、君は豊臣政権だ。
北京、ルソン占領に向けて、天下のリソースをどうやって使う?
米に関しては、検地と刀狩りで確保。
部隊の指揮官をどのように調達する?
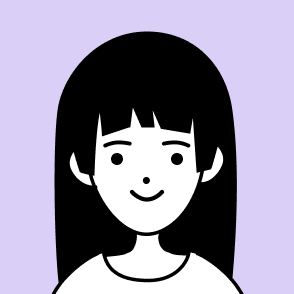
寝癖
江戸時代とは 徳川家康が征夷大将軍に任じられて江戸に幕府を開いた慶長8 (1603) 年から 15代将軍慶喜の大政奉還によって王政復古が行われた慶応3 (1867) 年にいたる 265年間,江戸が政治の中心であった時代。 江戸時代は1603年から1867年までの265年間にわたる時代のことです。
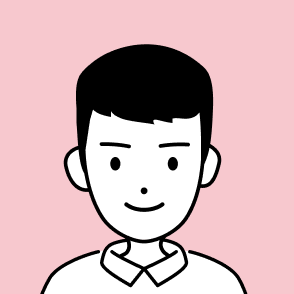
プロおじさん
〇〇に何入る?

てもり
めっちゃバカで死にたくなったw
江戸幕府??源氏物語??知らないよぉ!!

臼井優
新政府側へ転じた彼らに対し、節操を守る「痩せ我慢」の精神がないと叱責し、自由独立の精神を説いた名著です。
『瘠我慢の説』の要点と背景
著者と背景: 福澤諭吉が1891年(明治24年)に執筆、1901年(明治34年)に『時事新報』に掲載。
批判対象: 勝海舟、榎本武揚。幕府の要人でありながら、速やかに新政府へ仕えた姿勢を批判。
内容: 「国に一人の英雄がいても、節操を失えば国の恥となる」と主張。勝・榎本に対し、旧主(徳川)を見捨てて新政府(薩長)に仕えるのは、幕臣としての「痩せ我慢(意地・節操)」が足りないと非難した。
真意: 単なる人格批判ではなく、当時の日本人が「独立自尊」の気風を持ち、真の独立国家となることを願って書かれたものである。
同名の別作品(マンガ)
藤枝静男の小説を原作とした、川勝徳重による漫画『痩我慢の説』も存在する。こちらは、戦中・戦後の価値観に揺れる人々を描いた作品である。
※「痩せ我慢(やせがまん)」ということわざ自体は、ひもじくても食ったふりをする、負け惜しみをして無理を忍ぶといった、武士の清貧や強がりを意味する。

臼井優
諭吉と戊辰戦争における主なエピソードや姿勢は以下の通りです。
1. 戊辰戦争中の慶應義塾と教育の継続
戦争中も講義を継続: 1868年(慶応4年/明治元年)、江戸が戦場となった上野戦争(彰義隊の戦い)の大砲の音が聞こえる中でも、福沢は塾生たちに平然と講義を続けました。
「塾は止めぬ」: 多くの幕府の施設や教育機関が閉鎖・解散する中、福沢は慶應義塾を閉鎖せず、実学(洋学)を教えるという「やるべきこと」を成し遂げました。
2. 幕臣としての立場と冷静な視点
幕府の人間として: 福沢は元々中津藩(大分県)の藩士ですが、幕府の洋書調所(ようしょしらべしょ)から幕臣となっており、咸臨丸でアメリカに渡るなど、幕府の技術・語学分野で活躍していました。
諦念と独立精神: 徳川幕府の時代が終わることを予見し、幕府の人間が旧守的な態度をとる中で、福沢は「政府が何になろうとも、教育は必要」という信念を持ち、新しい時代を見据えていました。
分捕り品のエピソード: 『福翁自伝』によると、会津戦争後に官軍の兵士が「会津で分捕ってきた」と誇らしげに着物を見せた際、福沢は内戦の惨たらしさを冷静に感じていた描写があります。
3. 西洋の文明と「実学」の推進
学問が国を救う: 幕末の動乱は、欧米列強に占領されかねない危機だと考えており、その差は技術・科学にあると認識していました。
教育の転換: 幕府が崩壊する中、福沢は西洋の学問(英学)こそが、これからの日本の国力を高める「実学」であるとし、塾生に「洋学に志ある者は学べ」と呼びかけました。
4. 戊辰戦争の最中、福沢を襲った災難
資料の紛失: 福沢は江戸での戦火において、自らの日記や執筆中の著作が紛失したことを『福翁自伝』で触れており、この時期の混乱が相当なものであったことを示しています。
もっとみる 
おすすめのクリエーター
マミ
フォロワー
0
投稿数
15960

臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
フォロワー
0
投稿数
11675
たまかしわ〜
文学、芸術、古典作品が好きです。
年齢は李賀の享年と同じ
フォロワー
0
投稿数
7219
史的唯物論者シン
思考整理のメモ帳、日記として
呪い装備だったメガネが外れた
フォロワー
0
投稿数
6827
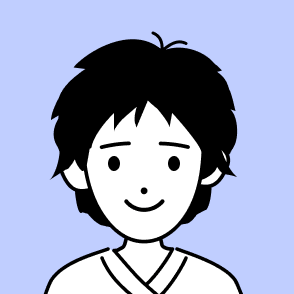
刻苦勉励
ピッチャー
フォロワー
0
投稿数
3322
