人気
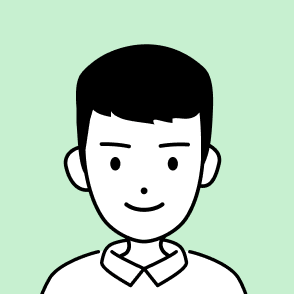
めんちかつ
哲学への最初の扉は「死」だった
「哲学とは、死について考えることである」
この衝撃的な言葉を知ったのは、大学生の時。中島義道先生の著書『哲学の教科書』を読んだときのことでした。
そして、その言葉の出典を辿ると、16世紀フランスの偉大な思想家、ミシェル・ド・モンテーニュの『エセー』にたどり着きます。モンテーニュは、まさに「哲学するとは、いかに死するかを学ぶことである」と述べています。
なぜ、哲学という学問は、生きている私たちが「死」について考えることから始まるのでしょうか? そして、この「死」というテーマこそが、一般の人々が西洋哲学を難解だと感じる理由を解き明かす鍵になるのです。
一般の人には理解されない「西洋哲学」の壁
「西洋哲学」と聞くと、多くの人が「難しい」「何を言っているのか分からない」と感じるかもしれません。
私たちが学ぼうとする「存在論」「時間論」「世界論」といったテーマは、日常生活からかけ離れているように見えます。
例えば、
存在論:「存在する」とはどういうことか?
時間論:「時間」は客観的に流れているのか?
世界論:「世界」は本当に私が知覚している通りに存在しているのか?
これらの問いは、私たちの「自分は生きていて、時間の中で世界に存在している」という当たり前の前提を揺さぶります。なぜ哲学者たちは、わざわざそんな遠いところから物事を考え始めるのでしょうか?
「死」を学ぶことが哲学の中心にある理由
その答えこそが、「死」です。
モンテーニュが言うように、「哲学をするとは死について考えること」です。
私たちが「死」という避けがたい事実と真正面から向き合ったとき、初めて西洋哲学が追求する根源的な問いが、切実な問題として立ち現れてきます。
「私が死ぬ」ということを考えたとき、「私とは何者か(存在論)」という問いが生まれます。
「私の死」は「私の時間が終わる」ことを意味し、「時間とは何か(時間論)」を問わざるを得ません。
「私が消滅した後の世界」を想像したとき、「世界は私がいなくても存在するのか(世界論)」という根本的な疑問に直面します。
つまり、西洋哲学の難解なテーマとされる「存在」「時間」「世界」は、「私は必ず死ぬ」という最も切実な事実と切り離せない、「死」にまつわる哲学的な諸問題だったのです。
死を知ることで、真に哲学の問いを共有できる
私たちが日常で触れる「死」は、悲しみや喪失感といった感情的な側面が中心です。しかし、「哲学の学び」としての死は、そこから一歩踏み込みます。
死を学び、死について深く理解すること。それは、西洋哲学が本質的に問おうとしてきた「真の問い」を、哲学者たちと共有するための出発点になります。
「存在論」や「時間論」といった言葉の難しさに惑わされる必要はありません。
まずは、「私はいずれ死ぬ」という避けられない事実から、あなたの哲学を始めてみませんか。それは、難解な学問ではなく、あなた自身の生と世界を理解するための、最も根源的で切実な学びとなるはずです。
#哲学 #死 #モンテーニュ #中島義道 #哲学入門

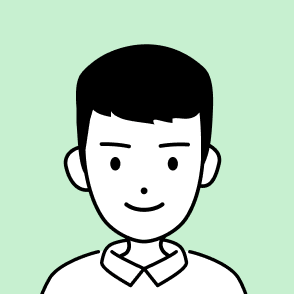
めんちかつ
Ⅰ. 哲学の起源:知恵を愛する者たちの根源的な探求
私は多くの人が哲学について誤解が生じていると感じます。哲学、狭義での西洋哲学、フィロソフィーの意味は「知恵を愛すること」、そしてそのためには原因を探求するための学問だったのです。
それでは古の賢人たちはなぜ物事の起源を探求しようとしたのでしょうか。それは、私たちがこの世に理由もなく産み落とされ、理由もなく死んでいくという事実を他者やこの世界の事物の観察から学び取り、自分が死ぬ前にせめて自分が生まれてきた意味、この世界が存在する意味を知りたいという願望を持って生まれてきた故ではないでしょうか。
アリストテレスの『形而上学』という本に、有名な**「すべての人は知ることを欲する。」**という言葉があります。人間というものは常に何かしら、何かを知ることを欲しているというすごく著名なこの言葉は、その後の人間社会を説明するのに多く使われたわかりやすい言葉だと思います。
では、なぜ人は知ることを欲するのでしょうか。このアリストテレスの言葉には続きがあり、「とりわけ人間は視ること(視覚)を他の感覚よりも欲する。」といってます。彼にしてみれば、私たちが日常的におこなう、聞いたり、目にしたり、さわったりする感覚的な動作も、知ることに結び付いているというのです。そうです、これは逆を考えればすぐにわかります。私たちはたとえば、暗い中で何も見えなかったり、目が見えない、失明したらそれをひどくいやがりますし、悲しみます。感覚するという行為は知らぬところから欲求に結び付いており、それができないことは不快なわけです。アリストテレスはこの快の感情というのをその哲学を語るうえで重要視しました。
Ⅱ. 「なぜ生きるか」を問う個人の軌跡と「死」の哲学
さて、哲学の話に戻りますが、私は若い時期に哲学を学ぼうと決断し、講談社現代新書や岩波文庫をできるだけ多く読むように心がけてきました。私はそのうち自分の中にある疑問が生じてきて、私はなぜ他の人に比べて物事の意味や存在の意義、何かがこうであるという仕組みやルールよりも、なぜそれが必要なのか、存在しているのか、理由を深く問う人間でした。
西洋哲学を勉強し始めた時もその影響は強く、西洋哲学史を読み始めると、世界の存在、認識についてから教科書の説明は始まります。私は世界の存在の意味とか、私たちの物事に関する認識について、全く興味がないわけではありませんでした。しかし若い時の私は直接的になぜ生きるのか、どうやって人は生きるべきなのか、という問題意識が強く、それは他者にもひどく目が行き、人間というのはなぜこうも同じ存在として生まれてきているのに違うのだろうかと感じ始めるようになりました。
ただ、私にも光明が差してきたと申しますか、明治大学の経営学科に、八田隆司というドイツ哲学が専門の先生がおりまして、彼のゼミに二年時から入りました。彼が最初にとりあげた哲学書というのが、『死と生きる 獄中哲学対話 池田晶子 陸田真志』でした。当時はなぜ彼がこの著作をゼミでとりあげたのかわかりませんでした。この本は簡単に説明すると、殺人事件を起こして死刑囚となった陸田真志と、牢屋の外にいる池田晶子氏が文書でやりとりしていくという話です。
当時大学に入学して大量の書物を読んでいた私は、この本がとりたてて面白いとも、重要な本だとも思いませんでした。そこで語られているのは、陸田真志がひたすら語る哲学や教養、学問への愛です。私は彼がヘーゲルの論理学とか、難解な書物を日本語訳とはいえ読んで理解し、ひどく感動を覚えているというのに不快感を覚えました。哲学科の学生でも学者でもない死刑囚、学歴のない人が、そういった難しい哲学書を理解できるはずがないし、むしろそれらを最後まで読み通せるというのも信じがたく、私はまじめに彼の文章を読んではおりませんでした。
八田隆司は陸田真志氏のことを高く評価していました。彼は陸田氏が獄中で西洋哲学に目覚めたのは、死刑囚として服役する中で、自分の死にいく運命というのを自覚し、死について考察、それにより人間存在や世界の意味を問うという事の重要性に気づき、西洋哲学に目覚めたのだと、少し補足するとそんな感じでちらっと八田氏は彼が私たちにこの本を読ませた理由を話しました。
Ⅲ. 現代の哲学者への疑問と「哲学の教科書」からの教え
私はいろんな学者や哲学者に会いに行きました。それは単純に学者たちと話したいという欲求と、自分の寂しさもありましたし、自分の学問的な意見や知的理解が正しいのか確認したかったからであります。
西洋哲学を勉強すると、まず西洋哲学史から学ぶわけでありますが、本当にたくさんの哲学者や思想家が出てきます。それぞれの考え方も全然違います。しかしながら、いにしえの古人がみな申すように、学問とは実践だと考えますと、すべての哲学者の意見を現代において実践するのは不可能です。しかし、彼らの意見をすべて理解したものと仮定し、翻訳や解説書を書いたり、あるいは講義をしたりするのが現代の、とりわけ日本や世界にいる哲学者なわけです。わからないもの、知らないものを、さも自分はよく知ってるかの如くふるまい、理解し、ましてや他者に教えてしまう、それが現代の哲学者や思想家なのであります。
私は今思いますのは、哲学研究者、西洋哲学者の多くが、この哲学というものに関して、古人とは別のスタンスを取っていることに気づきました。
では真の哲学者とはどうあるべきなんでしょうか。私は当時友人から勧められて、中島義道氏の『哲学の教科書 講談社学術文庫』を読みました。
彼はその著書の中で、私が哲学を経営学科という狭いところで学んでいくうえで、重要な道筋を立ててくれました。というのも、哲学に名を冠した書物は当時大量に出ておりました。それらは哲学史やどこかの哲学者の入門書か訳書であるとか、哲学そのものとはとても違いました。そして一番困ったのは、彼らのいう哲学書というのを読んでふたを開けてみると、
哲学と人生論を同じにしているもの: 厳密に言うと文学とかエッセイに該当するものだと感じます。それが哲学であるかないかは、彼らが事物の原因を問うているかいないかですぐにわかります。
哲学とは芸術だと説いているもの: ある画家の作品を取り上げて、この芸術は哲学的だとか、感想を述べて、それを哲学だと定義づけてしまっているケースです。いくら文化芸術が好きだからと言って、それらがすべて哲学だといわれてしまうと、西洋哲学史を一から勉強した身としてはとても混乱するのです。あなたの芸術作品は哲学的かもしれないが、それがただちに西洋哲学、とりわけ形而上学には該当しないという事です。
哲学は宗教であるという誤解: 宗教も世界について、人間について、考察しますし、語ります。しかし、どこに違いがあるかと申し上げますと、哲学がそれらのあり方に関し、常に批判的に考察し、対話、議論をするという事です。あくまで哲学は信仰ではありません、いかなる考え方にもメスを入れて、常に真理に近づいていくという、そういう精神が肝要なのであります。
Ⅳ. 日本人の意識の混乱と「現象学的還元」の必要性
ながながと説明しましたが、では本来哲学とはどうあるべきなのでしょうか。私たちは日本という世界からすると辺境の島国に生まれて、たまたま薩長が作った明治政府、西洋化、近代化を推奨する政策によりその価値観や生活が欧米化され、それがとりわけ戦後はアメリカに占領されたり政治的に影響を受けたりして強まったと感じます。
しかし、誤解しないでいただきたいのは、こうしたここ数百年の歴史的な自称、流れ、すなわち西洋との衝突が、必ずしも私たちの思想や考え方が西洋化されたわけではないという事です。それは私たちに近代文明をもたらしたという、ヨーロッパ人と話してみればすぐにわかります。彼らと私たちは見た目がまず違いますし、その話し方、考え方、生活の仕方まで異なるものです。
それなのに私たちはその科学文明を享受したという理由で、私たちは彼らの精神性も理解したと思い込んでいることです。もちろんもともと和魂洋才という言葉があるように、私たちは私たちのままで良いじゃないか、日本人であることに喜びを感じるべきだとか、日本人として誇りに思うべきだ、尊敬されるべきだという考え方もわからなくはないです。しかし私たちは事に関係なくすでにその考え方、生活様式に至るまで、西洋、あるいはほかの国の影響を受けています。私たちの脳内はひどく混乱した状態です。
明治時代、西洋の学問を取り入れるのに、無理やりnatureを自然とかの語に代替したように当てはめていったとされます。西洋人にとって制圧、克服すべきだったネイチャー(nature)という観念が、東洋人にとっての共存すべき対象、自然に置き換えられたのは大きなことだったと思っています。
つまりここで申し上げたいことは、私たちは多かれ少なかれ、たとえば言語に関しても西洋の影響を大いに受け、混乱し、ごちゃごちゃになり、めちゃくちゃになっているという事です。そしてそれをひもといていくには、欧米の思想や哲学、宗教など、彼らの根底としているものを学びなおすしかないのだと思っています。
日本人にとっては私たちの意識にイメージされているすべてを、(いわゆる現象学的還元)ある意味私たちがどのようにとらえているのか、端的に言って私たちは自分たちの思考を分解してみる作業が必要なのです。いろいろな哲学者の思想を学ぶと、私のこういう考え方は彼の哲学から影響を受けていたのだなとか、この言葉の意味は英語の何からきていたのだなとか、徐々にですが、わかってきます。
Ⅴ. 自分の居場所を知ること、そこから哲学は始まる
先日中島義道氏に自分が思った西洋と日本の、いわば文化的相違についてメールをいたしましたが、彼からは文化論的な話は哲学的でないと返事がありました。しかしながら、彼にこうした所作が必要でなく、いきなりウィーンの哲学科に入門したりしてやっていくことができたのは、そうした現地の体験とは不可分だったと思います。私は精神的な不健康により、直接海外の現地に行って大学に入り、学ぶという行為ができませんでした。いえ、ほとんどの日本人が海外の大学に入学したり、勉強したりする時間的な余裕や金銭的な余裕も持ちませんし、今思うと彼が特殊で、私は普通だったのかなとも感じます。
とにかく私は、とりわけ日本人にとってはまず西洋哲学史の、できるだけ多くの哲学者や思想家の考え方を学ぶべきことだと思うのです。そうしてまず自分が山の林のどこで迷っているのかを確認し、その後に改めて自分の居場所から自分の哲学、世界論や認識論について語ればいい事なのです。
そこからすべてが始まると思っています。
#哲学とは何か
#西洋哲学
#アリストテレス
#死と生きる
#中島義道
#現象学的還元
#哲学入門
#日本人と哲学
#知を愛する

関連検索ワード
