投稿

テク
第1章:右も左もわからないまま
――全ては、飛び込んでから始まった。
彼が不動産業界に入ったとき、手元にあったのは名刺だけ。
知識も、経験も、人脈もゼロだった。
物件の見方も契約書の意味もわからず、ただ先輩の背中を追いかける日々。
「あんなふうに、堂々と契約を決められたら……」
その一心で、彼は必死に学んだ。
法令、接客、ローン、土地調査。夜遅くまでテキストを読み込み、現地に足を運んだ。
そして、初めて売れた物件。
一見すると普通の一軒家。
だが、道路の通行権が絡む複雑な案件だった。
何度も壁にぶつかり、法務局と役所を行き来して、やっと契約にたどり着いた。
「俺にも、できるんだ」
初めての成功。それは、小さな光だった。
第2章:売るのではなく、買わせる
順調だったのは、ほんのわずかの間だった。
次第に、契約が取れなくなった。
案内しても響かない。お客様の反応がどこか薄い。
焦れば焦るほど、空回りしていく。
ある日、先輩に言われた。
「売りたい気持ちが前に出すぎなんだよ。お客さんにバレてる」
図星だった。
そこから彼は、営業という仕事を根底から見直した。
「売る」のではなく「買わせる」。
「ぜひ買ってください」ではなく「買うならこう動いてください」と主導権を持つ。
不思議と、お客様の反応が変わっていった。
「営業じゃなくて、選ばれる存在になれ」
その日から彼の営業は、“説得”から“共感と提案”に変わった。
第3章:引き金
営業成績は上がり、気づけば先輩と肩を並べていた。
そして、ある日ついに――追い越した。
そんなある日、先輩が言った。
「俺、実家に帰るわ。独り身だし、もういいかなって」
驚きながらも、どこか納得していた。
「なぁ……俺の家、売ってくれないか?」
「もちろんです」と即答した。
彼は、相場の倍に近い価格を提示した。先輩は笑った。
「マジで言ってんのか?」
でも彼の目は真剣だった。
“この家には、それだけの価値がある”と信じていた。
内覧希望の若い夫婦が来た。
決まりかけたが、経済的不安で断念された。
「下げてもいいぞ」
先輩は言ったが、彼は粘った。
「まだ、売れます。任せてください」
数日後、再び問い合わせが入り、今度は本契約に至った。
しかも、希望額通りで。
「ありがとうな。お前がいたから、踏ん切りがついたよ」
先輩が去る日、彼は駅のホームで静かに手を振った。
「引き金を引いたのは……俺だ」
誇らしさと、少しの寂しさが混ざった感情が、胸に残った。
第4章:静かな退場
先輩が去った営業所には、ぽっかりと穴が空いたような空気が流れていた。
売上は好調だった。
数字も評価もついてきた。
だけど、心はどこか空っぽだった。
「勝ちたいと思える相手がいないなら、やる意味があるのか?」
ロープレ、商談、契約。すべてが“作業”になっていた。
ある日、鏡の前で自分を見た。
スーツに身を包み、笑顔を貼り付ける自分。
「……演じてるだけだな」
その日、彼は辞表を出した。
「もったいない」と言う声もあった。
「何が不満なんだ」と聞く者もいた。
「やりきったんです。俺にとって、ここはもう十分です」
営業所を出る日、彼は何も持たずに去った。
送別会も花束もいらない。ただ静かに、風の中へ――。
第5章:投資家としての再出発
静かな時間の中、彼はじっくり考えた。
「次は、自分の力で価値を生みたい」
営業ではなく、今度は仕入れる側として。
自分で物件を見て、調べ、交渉し、買い付ける。
最初はうまくいかなかった。
だが、不思議なことに――調査と交渉なら、誰にも負ける気がしなかった。
“価値は、目に見えるものだけじゃない”
その感覚は、営業時代に先輩と築いた武器だった。
1軒、また1軒と投資用物件を仕入れ、少しずつ、賃貸経営も回り出した。
「営業からの転身」という物語が、彼の中で“第二の物語”として動き出していた。
そして――いつか、過去の自分に語りかける日が来る。
「お前がやってきたことは、間違いじゃなかった」と。
話題の投稿をみつける
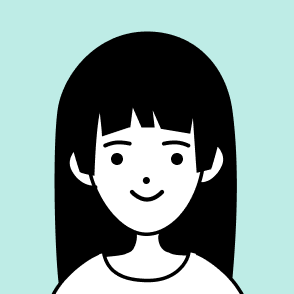
柚々

み も(
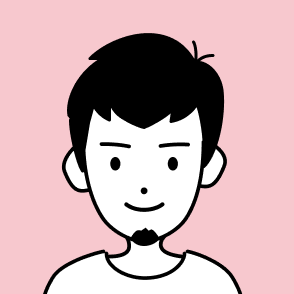
半永眠
全部同じ人からだと思うけど
なんかなんもする気になれない。全部監視されているようで怖い
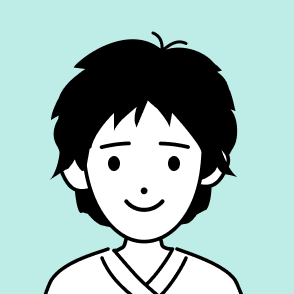
なたま

ウッカ
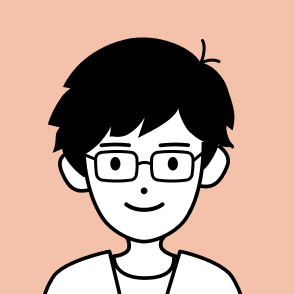
モアイ
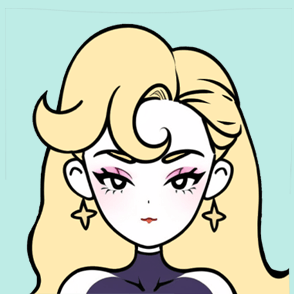
そめい
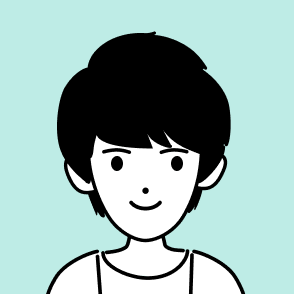
匿名な
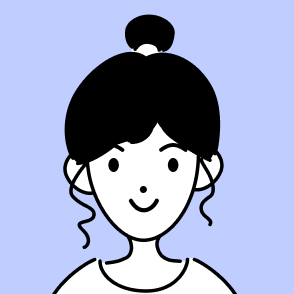
ゆうな
ありがたい
#チェルラバ
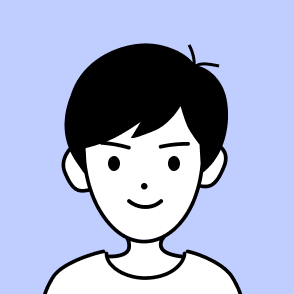
りくま
葡萄酒(火炎瓶)を抱き枕にしないと寝れなかったり、キノコを友人に振舞ったりする可愛い子だよ
もっとみる 
関連検索ワード
