投稿

信仰の
話題の投稿をみつける
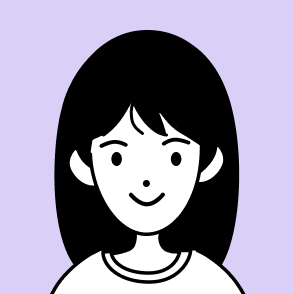
のっぴ
ご両親、長期ホテル滞在しんどくないかな?と思ってたんだけど、そばにいるのは女優のお姉さんかな?だとしたらすごいオrグrダブルで見れたわけね!

とらこ
今回も胸糞展開のような気がする
今のところは長男の周懐璟が一番クロなんだけど
それぞれが少しずつ周竣皓には思うところあり
道路に逃げ立ち止まった董筱清は予想通りに轢き殺されてしまった
周懐幸を助けた時の裴溯の血液恐怖症はどの程度のものなんだろ?制御できてたよね
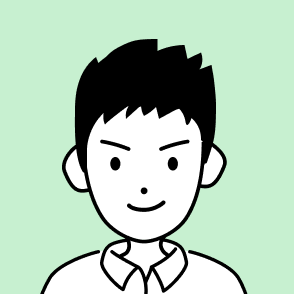
さめた
健常or無自覚グレーの親が、我が子に限ってそんなはずない!ってかんじ?
これから子どもと自身に降りかかるであろう苦労や子どもの能力の限界から目を逸らしたい?
私の母親もなかなか発達障害を直視しようとしないんだよな
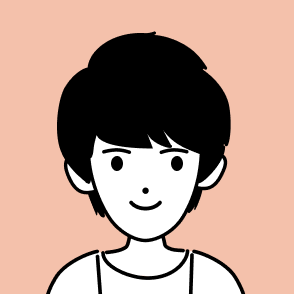
あーち
武器トークンは7週後だし、1層だけでは揃ってもアクセのみ
装備による緩和が望み薄な2層の難易度として考えると、適切だったとは言い難い

オルト
やっぱりな~・・・落ちなかったらいいねぇ・・・
ってチベスナ顔になってる。

スノウ

スノウ
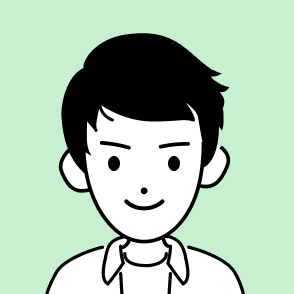
鰆
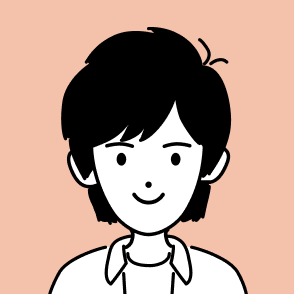
ぼのの
選び方とか就活エージェントのおすすめ書いたのあるから固定に貼っとくね
25卒NNTフリーターで既卒就活だと、1年以上就活してるわけだし本当に疲れるよね~…
ホワイト企業にいけることを願ってる…!

フグ
同じく箱積む予定の相互に待ってて欲しくて書いてるの?あわよくばDM打診来ないかなーとか?
そんな羨ましいなら潔くフライングすれば
もっとみる 
関連検索ワード
