投稿
empty
「どうして……一人、増えている!」
「誰だ……誰なんだ?」
声を上げた男の声は震えていた。
全員のスマホの画面が一斉に灯り、周囲の人間を恐怖に満ちた目で見渡す。目の前に見知らぬ顔が現れることを、心底恐れていた。
顔見知り同士が必死に寄り添い合い、びくびくと周囲を窺う。
その時、全員が確信した。確かに一人、増えている。遠くない角のほうに、その人影は寄りかかっていた。
「お前……誰だ?」
「人間か、それとも……鬼か?」
神秘の青銅巨棺のなか、何が起こっても不思議はない。場にいた全員の心は極度の不安に苛まれていた。
漆黒の闇の奥から、ごほん、ごほん、と重い咳払いが聞こえてきた。その黒い影が身じろぎし、低く、そして嗄れた声を発した。
「鬼……鬼……」
嗄れた声が青銅の棺内に響き渡る。その瞬間、全員の頭から足の先までが凍りつき、鳥肌が立ち、背筋にぞくぞくと寒気が走った。
皆は氷室に投げ込まれたかのようだった。心胆を寒からしめ、女子学生たちのなかには耳を劈く悲鳴を上げ、大声で泣き叫び、その場にへたり込みそうになる者もいた。
「鬼……の場所……」
その声は少しだけ虚ろで、黒い影が非常に疲弊しているのが感じ取れた。彼はよろめくように体を起こそうとしている。
「なんて……酷い場所だ。俺たちは……まさか、銅棺のなかにいるのか?」
角の黒い影がゆっくりと立ち上がると、困惑したような疑問を口にした。声は次第に力強くなっていった。
その高さのある黒い影が立ち上がったのを見て、多くの人間が思わず後ずさりした。
黒い影はこちらに向かって歩み寄りながら、さらに口を開いた。
「俺だよ、龐博(ほうはく)だ。」
「止まれ!近づくな!」
全員がスマホを掲げ、微かな光を頼りに前方を凝視した。
葉凡(ようぼん)が人垣を掻き分けてゆっくりと前に出ると、こう尋ねた。
「お前が本当に龐博なのか?」
「俺の声が分からないのか?」
闇の中、スマホの画面が灯り、前方に現れた見慣れた姿。濃い眉に大きな目、がっしりとした体格。
龐博は葉凡の大学時代の親友だった。彼は個人的な用事で同窓会に参加できず、今こうして突然現れたのだから、誰もが疑念を抱くのは当然だった。
「信じられない。龐博は同窓会に来るはずがない。お前……いったい誰なんだ?」
後方から、震える声が投げかけられた。
本来、ここにいるはずのない人間が、青銅巨棺の中に立っている。場にいた多くの人間が、頭皮がぞわぞわするのを感じた。
「俺は確かに龐博だ。誰か水を持ってないか?喉が乾いて死にそうだ。」
黒い影がさらに近づいてくる。
「止まれ!」
それでも、人々は信じられなかった。
龐博は仕方なく足を止め、自分の身元を証明しようと、大学時代の思い出を次々と語り始めた。
「俺は彼が龐博だと信じる。」
葉凡が確信に満ちた口調でそう言い、大きく歩み寄って龐博のそばに来ると、二人はしばらく会っていなかったこともあり、このような状況下ながら力強く抱擁した。
「最初は家の用事で、同窓会に参加できなかったんだ。その後、みんなが泰山に来ると聞いたから、家の用事を片付けてすぐに駆け付けたんだ……」
龐博は葉凡から渡されたミネラルウォーターのボトルを受け取ると、「ごくごく」と連続して何口も飲み、それから青銅巨棺に入った経緯を話し始めた。
彼が駆け付けた時には、全員がすでに山頂に上がっていた。彼はケーブルカーで索道を登ってきたのだ。
総じて言えば、彼は幸運だった。九匹の龍屍と青銅巨棺が泰山に衝突する前に、ケーブルカーで玉皇頂に無事に到着していたのだ。彼は逃げる人波に紛れず、一本の木を死ぬほど抱きしめていた。そして、泰山が静穏を取り戻すまで耐え、怪我を負わずに済んだ。
その後、彼は遠くから葉凡たちが巨坑に墜落する光景を目撃した。彼が駆け付けた時には、ちょうど古代文字が空中に輝き、彼は巨坑の外で足を踏み出せなくなっていた。青銅巨棺が揺れ、蓋がずれた瞬間、彼は全員の後ろに続いて棺の中に吸い込まれたのだ。
五色の祭壇の外にいたためか、龐博は青銅巨棺に墜落した衝撃で気を失っていた。
ようやく、人々は疑念を解き、緊張していた心が少しずつ緩んでいった。
「俺たちは自力で脱出を考えなければならない。この銅棺の中にいるのは、落ち着かない。俺には悪い予感がする……」
李小曼(りしょうまん)の顔は少し青ざめていた。彼女は美しい瞳で銅棺の奥深く、闇に包まれた場所を凝視した。他の女子学生たちと比べて、彼女と林佳(りんか)は冷静さを保っていた。
その言葉を聞き、多くの人間が体を冷たく感じた。
「全員、バラバラにならずに集まっていよう。」
周毅(しゅうき)がそう提案した。
皆が寄り集まり、スマホの微かな光を頼りに周囲の様子を窺った。彼らは銅棺の内壁に身を寄せ、ぼんやりとした青銅の刻図を見ることができた。凶暴な九頭の神鳥が飛び立つ姿、体中に一尺もの硬い剛毛を生やした巨大な凶獣が天を仰いで咆哮する姿……。
錆びた青銅の刻図には、『山海経』に記された荒古の凶獣、例えば饕餮(とうてつ)、窮奇(きゅうき)、檮杌(とうおつ)などがいた。その巨体と凶悪な面相は生き生きと描かれ、見る者を畏怖させた。
銅棺の内壁に沿って少し歩くと、上古の先民や遠古の神々と思しき人物の刻図も見つかった。その後、彼らは大きな奇妙な模様の群れを発見した。びっしりと星がちりばめられたようで、まるで星空図のようだった。
青銅巨棺は長さ二十メートル、幅も八メートル以上ある。彼らが見た刻図はほんの一部に過ぎなかった。しかし、その観察を続けなかったのは、この時、銅棺の奥深くに何か別の器物があることを察知したからだった。
全員がスマホを一か所に集めた。皆は勇気を振り絞って数歩前に進むと、闇に包まれた銅棺の中央に、ぼんやりとした長方形の物体があるのが見えてきた。
明らかにそれは屍骸ではなく、生きた物体でもない。それを見て、皆は少しだけ安心したが、さらに数歩前に進んだ。
「棺の中に棺がある!まさか、もう一口の銅棺なのか!」
前方の物体をしっかりと見た瞬間、多くの人間が思わず冷気を吸い込んだ。
最も中央の位置に、もう一口の銅棺が安置されていた。長さ四メートル足らず、幅も二メートル足らず。古めかしく、そして地味で、古図が刻印され、錆が覆い、刻まれた時を物語っていた。見る者に寒気を覚えさせ、畏怖の念を抱かせた。
「棺の中に棺があるのではない。こっちが本当の棺で、遺体を納める器具だ。外側の青銅巨棺は椁(かく)と呼ばれる外棺で、両者を合わせて棺椁(かんかく)というんだ。」
龐博が、棺椁の意味をよく理解していない少数の人間に説明した。
前方の棺が本当に遺体を納める器具だと聞いて、多くの人間が「どたばた」と後退した。内心は極度の恐怖に陥っていた。
このような神秘の青銅古棺には、いったいどのような人物が葬られているのか?皆の心には驚きと疑念、そして恐怖が入り混じっていた。
これまでに聞いたことのある考古学的秘密や、皇陵古墓の話などは、この青銅棺と比べれば、全く話にならない。比べ物にならないのだ。
二十メートルもある青銅棺椁を見たことがあるだろうか?天から降ってきた神秘の巨棺を見たことがあるだろうか?九匹の龍屍が棺を引くのを見たことがあるだろうか?中に入っているのが人間の遺体なのかすら疑わしく、棺内に一体何が葬られているのか、想像もつかなかった。
関連する投稿をみつける
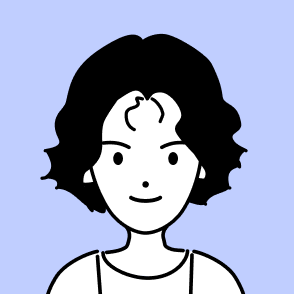
秋
ブチャリティ
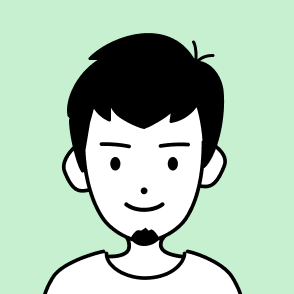
yu
全力の👹やるぞ、がおー
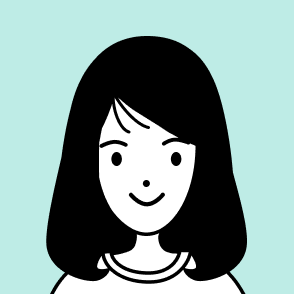
lll
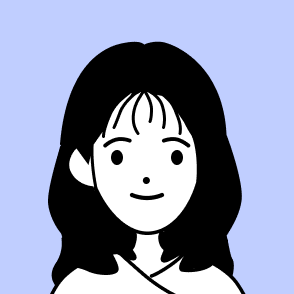
笑
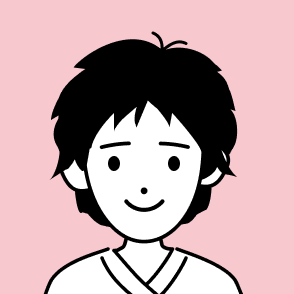
もんてい
回答数 949>>
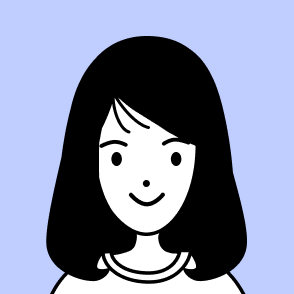
💞
カワサキ
もっとみる 
話題の投稿をみつける
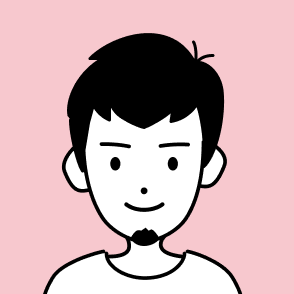
センザ
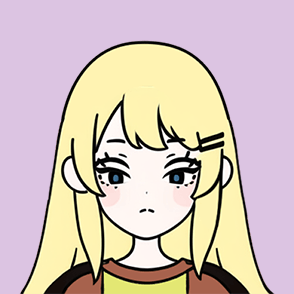
なすの
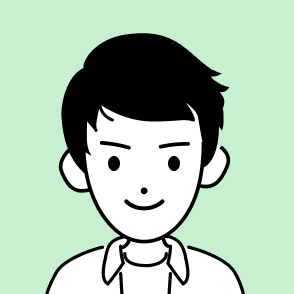
キノガ
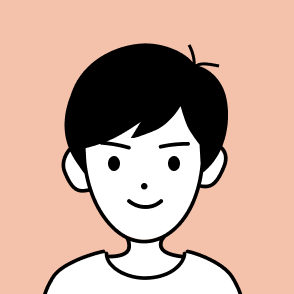
栗まぜ
制服のん……
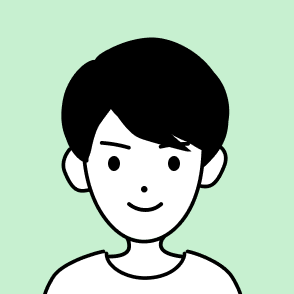
ねむ
#ネプリーグ
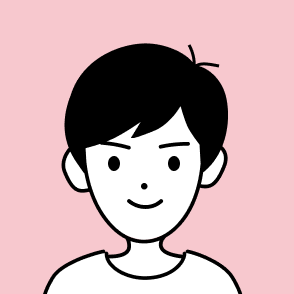
ュ‐リ
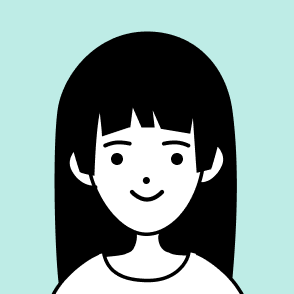
柚々
女子供のひとりすら逃すな
全て殺せ!赤子もだ!
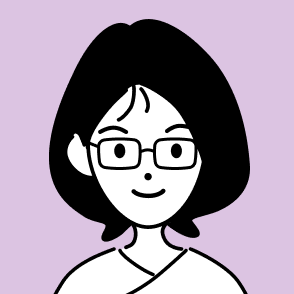
ちか
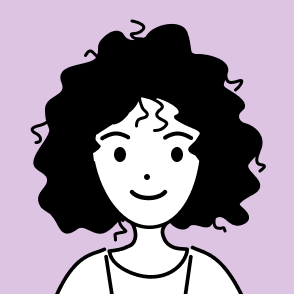
ネネ
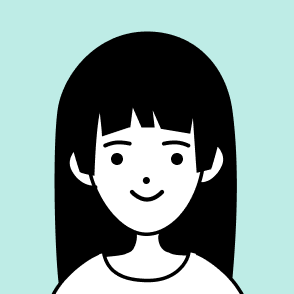
柚々
もっとみる 
関連検索ワード
