投稿

みみ
夢の始まりは、村ではなかった。
それは、どこにでもあるような、ありふれた都市の風景から始まった。
鉄製の外階段が壁に沿って伸びる、二階建てのアパート。
外廊下には、同じ形の玄関ドアが、まるで記号のように無機質に並んでいた。
その中の一室、手狭な1LDKの部屋で、かつて彼女と私は暮らしていた。
今となっては、その頃の記憶はひどく曖昧だ。まるで、古びた映画のフィルムのように、所々が白く焼け落ちてしまっている。
ただ、断片的に思い出せるのは——
窓から差し込む西日が、部屋の埃を金色に照らし出す中で、私はいつも仕事に没頭していたこと。
そして、その背後で、鈴が転がるような彼女の笑い声が響いていたこと。
いつからだろうか。
私が彼女の言葉に相てを打つ回数が減り、彼女が私に話しかける声の温度が、少しずつ下がっていったのは。
やがて、あの鈴の音は聞こえなくなり、些細な口論がその空白を埋め、最後には、まるで最初から何もなかったかのような、冷たい沈黙だけが部屋を支配するようになった
それから私は、日本の海辺にある一軒の民宿へと流れ着いた。
宿の夫婦が温かく迎えてくれ、私たちは波の音だけを肴に、夕食を囲んだ。
翌日、彼らが仕事に出かけた後、静寂だけが残された家で、私は棚に並ぶ古びた品々を眺めていた。
その中で、一本のゲームカセットだけが、まるで私を待っていたかのように目に留まった。
それを埃をかぶったゲーム機に差し込むと、世界は色を失い、私は調査員としての物語に吸い込まれていった。
目を覚ますと、私は木造の廃屋の中にいた。
鼻腔を刺すのは、新しい木の香りではなく、湿った埃と、忘れ去られた時間そのものが腐敗したような匂い。
深い褐色の闇が、部屋の隅々までを支配していた。
使命だけが与えられ、目的は知らされぬまま、私はただ手がかりを求めて、軋む床の上を彷徨う。
屋敷の中には、めぼしいものは何もなかった。
私は外へ出て、周囲の地質調査——という名目で、ただやみくもに地面を掘り返し始めた。
鬱蒼とした緑に囲まれ、一台の車が、すべてを見ているかのようにぽつんと停まっている。
そして、道路の真ん中あたりをシャベルで掘った時だった。
浅い土の下で、カツン、と硬い何かに突き当たった。
石かと思い、その周りをさらに掘り進めていく。
すると、それはただの石ではないことが分かってきた。
それは滑らかな曲面を描いており、まるで、巨大な卵の殻の先端が、地表近くに埋まっているかのようだった。
私はその曲面に沿って、夢中で土を掻き分けた。
掘れば掘るほど、その巨大な輪郭が明らかになり、私の背筋を冷たいものが走った。
一人では無理だと判断し、同僚に協力を仰いだ。
屋敷に戻ると、正面の机に装飾品がいくつか置かれていたが、もはや私の注意を引くことはなかった。
間もなく、同僚が知らせを持ってきた。この村の村長の娘が失踪したという。
私たちが調査しているこの場所にも、その痕跡があるかもしれない。
私はあの卵のような巨大な構造物を思い出し、初めてこのゲームの目的が「娘を見つけること」だと理解した。
外に出ると、同僚たちは既にその巨大な卵の周囲を、完全に掘り起こしていた。
全貌を現したそれは、石というより、巨大な墓石の蓋だった。
一人では持ち上げられなかったが、同僚たちと力を合わせ、息を殺してそれを持ち上げると、冷たい空気が吹き上げる、暗い階段が現れた。
そして、その闇の底に、ぽつんと、ひとりの人影があった。
彼女は、白いワンピースを着て、折りたたみ椅子に静かに腰掛けていた。
その顔には、怒りも悲しみもなく、自ら選んだ永い眠りにつくかのような、湖の底の静けさだけが広がっていた。
湿った土の匂いが立ち込める地下室。血の跡はない。
だが、私の目には、どこか鮮烈な赤が見えた。
面識のないはずの彼女を前に、心臓が冷たい手で掴まれたような痛みに襲われた。
地下室の冷たい空気の中で、私は上司に支援を要請した。
だが、いくら待っても応援は来ない。
まるで、この村が世界から切り離されてしまったかのようだった。
痺れを切らした私は、何が起きているのかを確かめるべく、一人であの主幹道を村の外へと向かった。
道の先から、村長が村人たちを率いて現れた。
彼らの手には農具が握られ、その目は、秘密を暴かれたことへの警戒心で鋭く光っていた。
その笑みは、私の目にはどこか不穏に映った。
私は本能的に踵を返し、廃屋へと駆け戻った。
ちょうどその時、同僚たちが彼女の亡骸を運び出し、私と合流した。
私たちは、この閉ざされた村からどう脱出するかを話し合ったが、すでに村人たちの壁に完全に取り囲まれていた。
万策尽きた私たちの前に、村長が静かに歩み寄ってきた。
彼は運び出された娘の姿を一瞥すると、すべてを諦めたかのように、深く長いため息をついた。
「ついて来なさい」とだけ言うと、彼は私たちをある場所へと案内し始めた。
彼に導かれて歩き出すと、奇妙なことが起こった。
昼間だったはずの世界が、急速に夕闇に包まれ、やがて深い夜の闇に沈んでいったのだ。
古びた村の風景は消え、道には不釣り合いなほど近未来的なデザインの車が、音もなく行き交っていた。
混乱する私の前方に、やがて簡素な青いテントが見えてきた。
そこが、彼が娘のために建てたという霊堂だった。
霊堂へと続く小道には、赤い頭巾を被った幽霊たちが、嘆くように漂っていた。
彼らは冷たい視線で私を見つめ、その無言の眼差しが、私自身の心の奥底にある罪悪感を突き刺すようだった。
いくつかの受付用のテントを通り過ぎ、古びた木の扉を開けて霊堂の中へ入る。
村長は、扉の前で立ち止まり、まるで中に入ることを躊躇うかのように、一瞬だけ苦しげな表情を浮かべた。
薄暗い蝋燭の光の中に、彼女の遺影だけが、静かに浮かび上がっていた。
私は三本の線香を立て、震える手で、そっと合わせた。
遺影の中の彼女は、この悲劇を知らないかのように、ただ晴れやかに笑っていた。
その瞬間、私は彼女の世界に吸い込まれる。
そこは、現実とは異なる法則で動く空間だった。
空は晴れているわけではないが、創造の黎明を思わせる、深い桃色の光に満たされていた。
空気は静かで、乾いた温度が心に沁み込む。
足元には一本の主幹道が延びていた。
村の泥にまみれた道ではない、滑らかで整った、光の粒子で舗装された道だ。
道の両脇には、設計図のまま立ち上がったような、半透明のモダンな建物が並んでいる。
人影はない。だが、ここには確かな創造の意志が息づいていた。
主幹道の突き当たりには、空中に浮かぶ島——浮島があった。
そして私は悟った。
この道、この島の構造は、あの村の、古びた廃屋へと続く一本道と、驚くほど似通っているのだ。
だが、こちらの道の起点は、まるで彼女自身の手によって断ち切られたかのように、虚空に溶けていた。
彼女は、自ら外界との橋を焼き、この聖域を創り上げたのだ。
島の中は、華やかではない。むしろ、巨大な「創世の工房」と呼ぶべき場所だった。
地面には、星々の配置を示す設計図や、未完成の詩の断片が、青白い光のインクで描かれては消えていく。
空には、まだ名前のない星座たちが、半分だけ線を結び、残りの半分を星屑として漂わせていた。
島の中心には、色とりどりの液体の光が湧き出る泉があり、それが小川となって島全体を巡り、奇妙な形をした水晶の植物を育てている。
それら全てが、「夢」「幻想」「憧れ」「未来」——彼女が育み続けた、感性の原材料たちだった。
そして、島の最も奥まった場所、あの廃屋があったはずの位置に、一軒のガラス張りのアトリエが静かに佇んでいた。
私はその中を覗き込むことしかできなかった。
イーゼルには描きかけのキャンバスが置かれ、机にはインクの乾いていない楽譜が広げられている。
だが、主の姿はどこにもない。
部屋のすべてが、薄い光の塵をかぶり、まるで持ち主がほんの少し前に席を立ったかのような、静かな不在を物語っていた。
そして、そのアトリエの窓辺に、一つの風鈴が吊るされていた。
風もないのに、ちりん、と涼やかな音を立てる。
それはまるで、帰りを待つ者の、孤独で、しかし希望に満ちた、小さな信号のようだった。
やがて、私は夢の現実へと引き戻される。
冷たい鎖が手足に絡みつき、見知らぬ囚人たちと共に、一つのテーブルに縛り付けられていた。
向かいに座る少女の瞳に、私と同じ諦めと、まだ消えぬ微かな光が映る。
私たちは、逃れる術を囁き合った。
村長は、私たちを娘の復活のための生贄にしようとしていた。
彼自身の手で、その命を葬ったにもかかわらず。
それは狂気か、それとも歪んだ贖罪の儀式なのか。
祭壇の蝋燭が燃え尽きては、また新しいものに替えられた。
時間の感覚はとうに失われ、私たちはただ、鎖の冷たさを分かち合いながら、語り続けた。
彼女は、あの浮島の星々の話をした。
私は、失われた笑い声の話をした。
私たちは互いの記憶の断片を拾い集め、一つの物語を紡いでいるかのようだった。
絶望の中で、私たちはかつてないほど近くにいた。
そして、その時が来た。
鎖が肌に食い込む鋭い感覚がふっと消え、代わりに、夕焼けよりも優しい光が意識を包み込んでいく。
私たちは、あの暗い部屋から逃げ出したのだろうか。
それとも、長い対話の果てに、あの祭壇の上で、すでに供物として溶け合い、分かちがたい一つの存在へと還ったのかもしれない。
次に目を開けた時、私は村長が営む食堂の、小さなテーブルの前に座っていた。
店内は温かい光に満ちている。向かいには、あの少女が座っていた。
いや、彼女はもう囚人ではない。
ただ、そこにいる。
そして、静かに微笑んでいた。
その笑みは、もはや囚人のものではなく、遺影の中で見た、あの太陽のような笑顔そのものだった。
村長は、ただ黙って私たちを見つめていたが、やがて、すべてを悟ったかのように深く頷いた。
彼は私たちの関係を受け入れ、そして、ただ一言、「彼女を、守ってやってくれ」と言い残し、光の中へと静かに姿を消した。
再び海辺の民宿へ。
波音が窓辺に響く中、私は数本のビデオテープを見つけた。
そのラベルには、この村での出来事が暗示されていた。
私はそのテープを手に取り、海を背景にシャッターを切った。
すべては私自身だった。
村長は、極端な理性を生きる私。
調査員は、違和感に気づいた私。
石は、理性によって封印された論理の防壁。
同僚たちは、感性の死を望まなかった私の断片。
娘は、かつての感性の極点。
彼女は殺されたのではない。あまりに純粋なその世界が、現実を乱すことを恐れ、自ら道を閉ざしたのだ。
幽霊たちは、感性を無くしてしまった私への嘆き。
浮かぶ島は、感性が守り抜いた心の聖域。
囚われた少女は、もう一人の彼女、あるいはもう一つの私。
あのアパートで一緒に暮らしていた彼女は、かつて共に世界を探検した、いつしか私が置き忘れてきてしまった私自身だった。
そして最後にカメラを構えた私は——
このバラバラになった物語を拾い集め、現実へと帰港させる、唯一の船乗りだった。
話題の投稿をみつける

翠
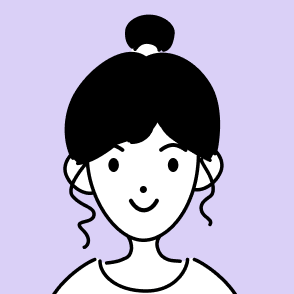
マオ
かみしげ多めで幸☺️
#WESTube
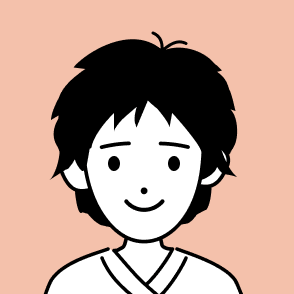
大根太
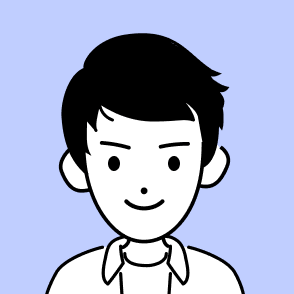
まこと
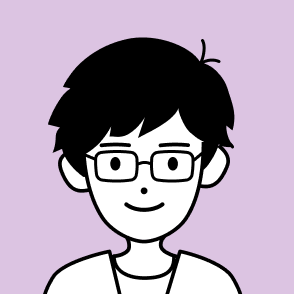
中山 環
裕太くんも六花がそういうならと従ってくれる
…でもたまにポロっと惚気こぼすのは六花さん、というユニバース
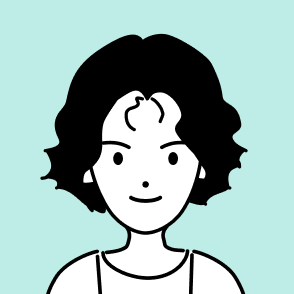
嘉男た
首位以外勝率5割未満て
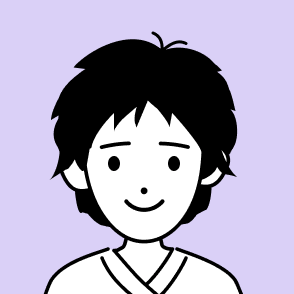
mo0513(も
皆に認知してもらう為だけど
本当の理由は
ネーミングセンスないので考える時間が欲しいからですたすけて
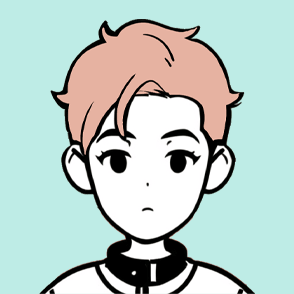
◎
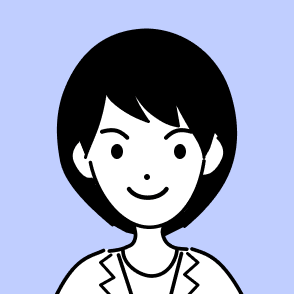
こひめ
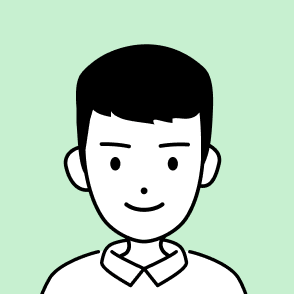
かる
もっとみる 
関連検索ワード
