投稿
サザエ
子どもの頃、時々おばあちゃんと一緒に北京へ行き、ひいおじいちゃんに会いに行っていた。
ひいおじいちゃんの家は小さな庭付きの一戸建てで、初めて行った時からすごく気に入った。いわゆる「フルシチョフカ」(縦長の古い集合住宅)みたいな団地ではなかったので、見た瞬間にもう屋根に登るルートを3、4本も頭の中で思い描いてしまって(笑)、こんなに登りやすそうな家は初めてで、心の中で花が咲いたように楽しかったのを覚えている。
庭には鶏小屋があって、小さな畑が2〜3区画あり、家と家の境は木の柵で仕切られていた。今ではもうあまり見かけない光景かもしれない。
家の中は、外屋と内屋をつなぐ部分に、ちょっとした室内の小さなサンルームのようなスペースがあって、そこでは、当時はまだ珍しかった独身主義を貫いていた小姨(祖母の弟の娘)が、大きなチンチラ(龍猫)を飼っていた。彼女はもともと野良猫をたくさん引き取って飼っていたのだが、ある時1匹の猫が死んでしまってからはもう飼わなくなったそうだ。おばあちゃんによると、兄や弟に殺されたのではと疑っていたみたいで…。それ以来、ただ野良猫にキャットフードをあげるだけになったらしい。
その住民区ではよく年上の子どもたちが走り回っていて、私も混ざろうとしたが、遊び方があまりに激しくて、耳や頭を叩かれた記憶がある(わざとではなかったと思う)。それを見ていた家政婦のおばさんが、「猫にエサをあげてみたら」と言ってくれた。
当時の私は背が低く、中国の家によくあるラジエーター(暖房器具)の上に置かれたキャットフードの袋にやっと手が届くくらいだった。おばさんが袋に切れ目を入れて、手に5〜6粒入れてくれた。それを持ってサンルームの外に手を伸ばすと、猫たちは最初逃げてしまった。仕方なく地面に置いて食べさせ、その隙に背中をなでると逃げずにいてくれた。敏感で触ろうとするとすぐ逃げる子もいたが、他の猫が食べているのを見て羨ましくなり、時間が経つとそっと近づいてきた。
彼らが少し食べるたびにまた袋から取り出して与える、という繰り返しだった。中には、足りないと感じたのか、食べたあと私の手のひらをペロッとなめる子もいた。背中をなでたい時は、左手にたくさんキャットフードを準備しておかないと、すぐ食べ終えて逃げてしまうので大変だった。
一度だけ小姨が餌をあげているのを見たことがあって、その時は地面にザザーッと大量にまいていて、私は「こんなにあげるの?」と驚いた。すると彼女は「もちろん!この子たちはこれだけ食べるんだよ。あなたはいつも少なすぎる」と笑っていた。そして話が止まらなくなった彼女は、昔ある猫がドアを開けると堂々と家の中に入ってきて、我が物顔でキャットフードを食べていたことを話してくれた。でもその猫はもういなかった。「ゴミをあさっていて、病気になって死んでしまった」と彼女は言っていたが、それは“毒殺されたのでは”と疑われていた猫かもしれない。彼女はそのことを深く悲しんでいたが、それ以上は語らなかった。
また、小姨は「大きな黒猫が他の子をいじめて、特に白くて臆病な子猫を追い払う」とも話していた。だからその白猫に少しでも多く食べさせたい時は、大きな黒猫を追い払ってから白猫にご飯をあげたそうだ。白猫は怯えながら黒猫をチラチラ見つつ、やっとの思いでご飯を食べていたとのこと。黒猫も仕方なく、白猫が食べ終わるまで待たなければ自分も食べられない、という状況だった。
ひいおじいちゃんの家に行くたびに、胸が重くなるような気分になった。みんな優しいのに、そこには愛を少しも感じられなかった。ある時、ひいおばあちゃんが突然ベッドに座ったまま子どものように大声で泣き出し、昔、飢饉の時に嫁いだ妹が帰ってきて家の価値ある物を全部奪って行き、自分には何も残さなかった話を繰り返していた。家族は「もうその人は死んでるんだから、大丈夫だよ、大丈夫!」と必死に慰めていた。7歳の私には、彼らが若い頃どれほど威勢があったのかを知らず、ただ気の毒に思っていただけだった。
ひいおじいちゃんが亡くなり、その葬式で祖母の世代が最後に集まった。その場でみんなで楽しく記念写真を撮ろうとした。黒と灰色の群影の中から、真っ赤な服を着た舅姥姥(祖母と同世代の親戚)がひときわ目立っていた。
時はこの世のあらゆる情念を洗い流すと言われるが、彼女は本当にすべてを手放したのだろうな。
話題の投稿をみつける

もや
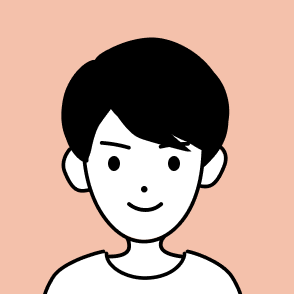
ふにゅ
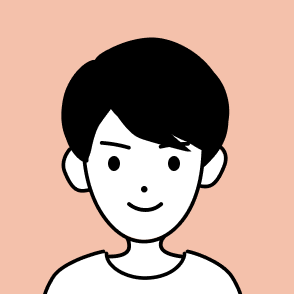
はる

櫻 雪
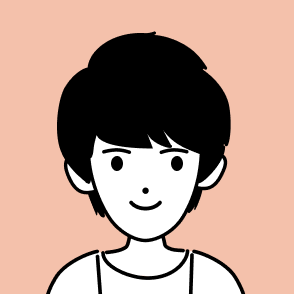
大零音

羽々
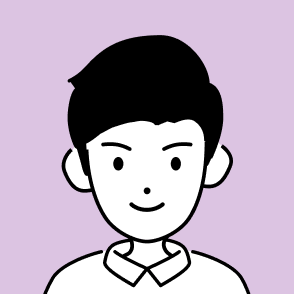
なっき
痛い
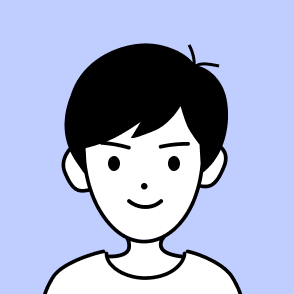
えーず
同一ラップは5台だけやし、突然遅く走り始めるやつもいるし、2回フリーピットが発生するし
高額なお金払ってこれは、、ねぇ笑
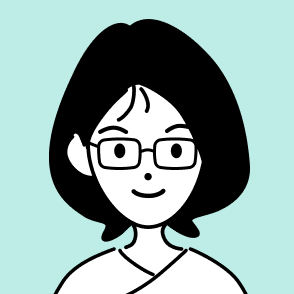
みろ@フ

うけり
もっとみる 
関連検索ワード
