投稿
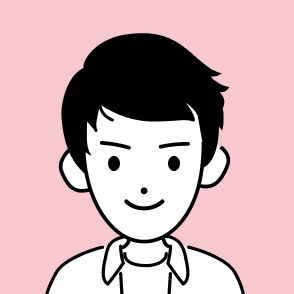
ハサン
広い公園。真ん中には静かな湖。そこにはたくさんの鯉が飼われていた。魚たちが一斉に水面に浮かび上がると、それはまるで不思議な祭りのように見えて、なんとも美しい。けれども悲しいことに、こんなに広い公園なのに人影はほとんどない。まるで無人の場所のようだった。私はここに何度も来たことがあるが、人を見かけることはほとんどなかった。たまに、犬を連れて散歩している二、三人を見かけるくらいだ。
私は本のページに没頭していた。すると、突然、中年の男の人が私の横にどさりと座った。男の人は片手に犬を、もう片手に本を持っていた。私は犬を見るや否や立ち上がろうとした。犬に対してはひどいアレルギーがあり、見るだけで怖くなるのだ。男の人はおそらく、私の恐れを察したのだろう。だから安心させるように言った。
"トニーは何もしないよ。大丈夫、安心して座っていい。"
そうそう、言っておくが、トニーというのはその男の人の犬の名前だ。
"君が本を読んでいる姿を見て、嬉しくなったんだ。一人で静かに本を読んでいるね。俺も本を持ってきている。時々こうして公園で一人本を読むんだ。君の読書への熱心さを見て、少し話してみたいと思ったんだ。俺ははしもと。君の名前は?何を読んでいるの?"
男の人は自分の名前を告げ、私の名前を尋ねた。さらに私が読んでいる本の題名まで聞いてきた。
私は心の中で少し嬉しくなった。この静かな公園に来るたびに、いつも一人で少し時間を過ごしては帰っていた。けれども、今回は話し相手ができた。大人と話すのは特別な味わいがある。彼らの話を聞くことで、経験から多くのことを学べるのだ。
"私はハサンです。本はちゃんと読めていません。漢字が多すぎて。でも、本の題名は"今、会いにゆきます"です。"
そう言って、本をはしもとさんに差し出した。彼はそれを手に取り、大きなため息をついて言った。
"人の人生がもし小説のようだったら。自分の思うままにペンのインクで書けるのなら、どんなにいいだろうな。"
私は微笑みながら彼を見つめた。彼の瞳の奥には、まだ語られていない物語が沈んでいるようだった。静かでありながら、強く。
"もし本当に人生が小説のようだったら……はしもとさん、あなたは最初の章に何を書きますか?そして最後の章は、どんなふうに終わらせたいですか?"
私の言葉を聞いて、彼は少し黙り込んだ。苦しみを隠すように、わずかに笑い、遠い空を見つめて言った。
"人はみんな、言葉通りに約束を守るわけじゃない。彼女は本好きだった。たくさん本を読んでいた。でも、昔の俺は本にあまり興味がなかった。けれど今は、本を読むことが習慣になった。おそらく彼女の記憶をつなぎとめるために。"
彼女との出会いは図書館だった。私は本を読むのがあまり好きではなかったが、暇つぶしに図書館に行くことがあった。時々少し読んだりもした。ある日、"白い光の午後"という本を読んでいたら、一人の女性が来て、ぜひその本を譲ってほしいと頼んできた。ずっと探していた本だと言う。俺の読書が終わったら渡してほしいと。
それが彼女との出会いだった。本をきっかけに話をするようになり、自然と知り合いになった。少しずつ関係は深まり、やがて愛情へと変わった。なぜかはわからないが、私は彼女を強く愛してしまった。彼女と話すのが楽しかった。彼女と過ごす時間が幸せだった。つまり、彼女がすることすべてが好きになった。
そうして二人の関係は二年続いた。その後、私たちは結婚を決意した。永遠に一緒にいると誓い、結婚したのだ。結婚してからの一年間は幸せに過ごせていた。だがその後、彼女は変わり始めた。
そう言ってはしもとさんはもう一度ため息をついた。肩にかけていたバッグのファスナーを開け、酒の瓶を取り出して飲んだ。そして私に差し出し、"君も飲むか?"と尋ねた。私は酒を飲まないので断った。彼は次にタバコを取り出し火をつけた。煙を空に投げるように吐き出す。その姿は、まるで自分の苦しみを煙と一緒に吹き飛ばそうとしているよう。
酒もタバコも私は嫌いだ。タバコの匂いは特に我慢できない。息が詰まるようで、呼吸が苦しくなる。それでも、なぜか私はその場を立ち去りたくなかった。むしろ、彼のバッグからもう一本の酒を取り出して差し出したい気持ちにさえなった。何かを得たいのなら、時に嫌なことでもしなければならないのだ。私は彼の"最後の章"を知りたかった。彼の話を聞いて、好奇心がどんどん膨らんでいた。たぶん私は人の話を聞くのが好きなのだろう。おそらく、それが理由だ。
彼はしばらく黙っていたが、再び語り始めた。
"彼女は俺の最初で最後の好きな人であり、愛する人だった。本好きの人間がそんなふうになるなんて、思ってもみなかった。俺は彼女が本のように透明で、柔らかく、優しい心を持っていると思っていた。でも、あんなに冷たくなれるなんて想像もしなかった。俺が彼女を好きだっただけではない。彼女も俺をとても好きでいてくれた。最初のころは、俺が何を言っても何をしても彼女は喜んでくれた。だが、結婚して一年経つと、彼女は変わってしまった。俺のすることすべてが嫌になり、話す言葉さえもきつくなった。あまりにも変わってしまった彼女を見て、調べたらわかった。彼女は職場で別の男と関係を持っていたんだ。だから、もう俺を耐えられなくなった。"
"それでどうしたんですか?"と私は尋ねた。
"それでどうしたかって?……離れたんだ。"
彼は答えた。
"一番つらいことが何かわかるか、ハサン?"
私は首を横に振った。
"愛する人に無視されることだ。人はなんだって耐えられるけど、愛する人からの無視だけは耐えられない。"
"じゃあ、一番美しい犠牲は何だと思う?"
また首を横に振った。
"その人がもう自分を望んでいないと知ったとき、怒りも、わがままも、不満も、責める気持ちも持たず、静かにその人の人生から去っていくことだ。俺もそうした。彼女は今、誰かと幸せに暮らしているのかもしれない。でも、俺はまだ忘れられない。たぶん一生忘れられない。彼女が去って以来、誰のことも愛する目で見られなくなった。ただ、目の前に彼女の姿が浮かぶだけだ。彼女の記憶をつなぎとめるために、俺は今や本の虫になった。本とトニー、それが今の俺の唯一の仲間だ。"
私は彼を見つめた。彼の頬を涙が伝っていた。その涙には、得られなかった痛み、裏切りの炎、そして愛する人を失った空白が混じっていた。私はただ黙って彼を見つめていた。煙と共に彼の苦しみは宙に消えていくように見えたが、胸の奥にはどうしても埋められない虚無が残っていた。
日本に来てから何度も聞いた――浮気も、不倫も、離婚もここでは珍しくないと。だが、私は初めてこういう愛の物語を聞いた。裏切りの中に隠された一途さ。失う中に隠された無限の愛。
そのとき思った――はしもとさん自身が一つの歩く小説なのだ。各章には、悲しみと愛、そして静かな犠牲が詰まっている。
"最後の章の涙"
---ハサン

話題の投稿をみつける
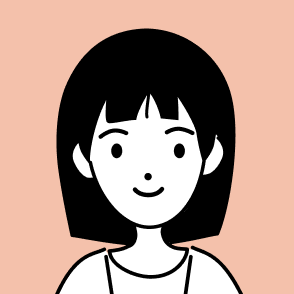
꒰ঌ く

ゆう🦅
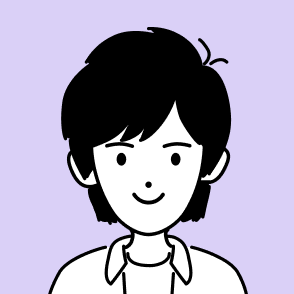
なるる
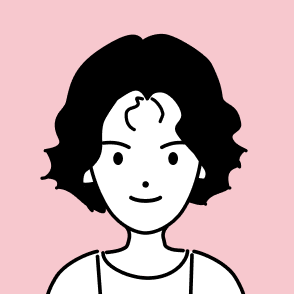
ルチ
是非聞きたい…
俺もイメソン探すか…
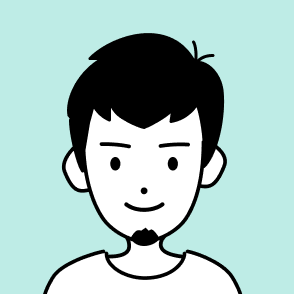
東京
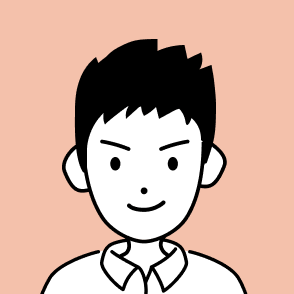
モバニ
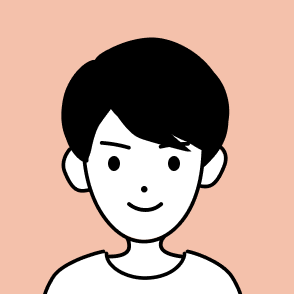
じょう
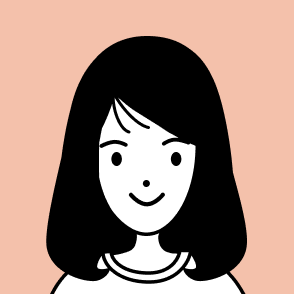
まき

🐟鯖缶
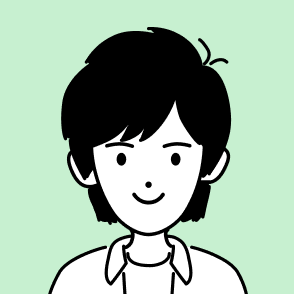
こば🕊
もっとみる 
関連検索ワード
