投稿
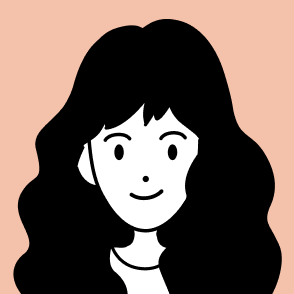
眠/おむ
話題の投稿をみつける
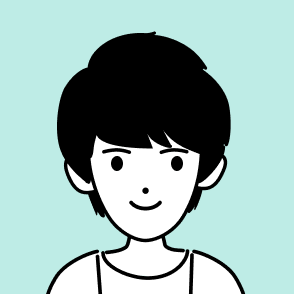
お豆倶
すげーおもろいね めちゃポップ。
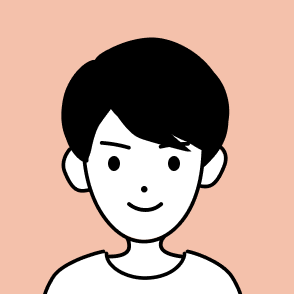
じょう
今でもなりきりアカウントで下半身画像送ってるんかな

ゆづか
案件の荷物2重に届く事件2回目
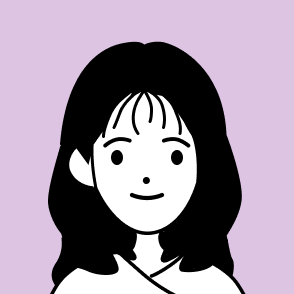
じゅら
ステージでやればいいのに
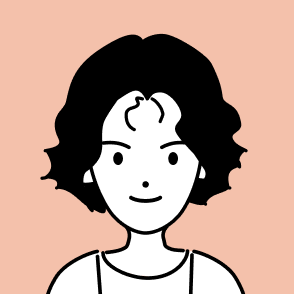
ゆめう

イチチ
NTLSYVJとは何ですか?
NTLSYVJは、特定のコンテキストや情報が不足しているため、詳細な説明が難しいですが、一般的には特定のプロジェクトや製品、またはアート作品の略称やコード名である可能性があります。もしこの用語が特定の分野や作品に関連している場合、その背景や文脈を教えてもらえると、より具体的な情報を提供できるかもしれません。
何か他に知りたいことがあれば、気軽に聞いてくださいね!
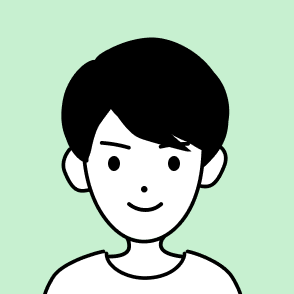
おしゃ

きど

あああ
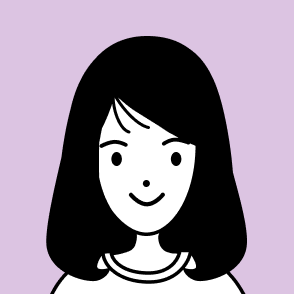
なーん
NTLSYVJの意味は?
NTLSYVJは、特定の意味を持つ略語やコードではなく、一般的には特定の文脈やコミュニティで使われることが多い言葉です。具体的な意味は、その使用される場面によって異なることがあります。
可能性のある解釈:
特定のプロジェクト名や製品名
ソーシャルメディアやオンラインゲームでのユーザー名
特定のグループやコミュニティ内での内部用語
もしこの言葉が特定の文脈で使われている場合、その文脈を教えてもらえると、より具体的な情報を提供できるかもしれません。
もっとみる 
関連検索ワード
