投稿
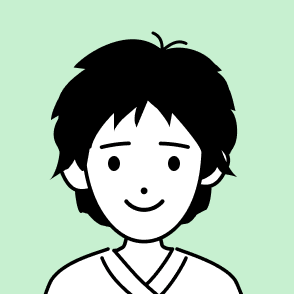
誤条悟
蛇に巻かれる
第一章:蛇に巻かれる
テレビの画面には、男が映っていた。
ぬらりとした光沢のある黒い蛇が、男の上半身に巻きついている。肩から胸、腹部へと、その長くしなやかな胴体が密着し、肌を這っていた。男はそれを恐れる様子もなく、むしろ恍惚とした笑みすら浮かべていた。
アナウンサーが解説する。
——「この蛇は全身の筋肉を使って相手に圧をかけ、心拍数を上げさせることで興奮状態を引き出す効果があるとも言われています」
俺はその番組を、深夜の休憩室でぼんやりと見ていた。
そして今でも、日量翠のことを思い出すとき、俺の脳裏にはあの映像がよみがえるのだ。
蛇に巻かれながら微笑む男。その笑みの奥にある、理屈ではない何か。
逃れようとすればするほど、より深く巻きついてくるもの。自分でも気づかないうちに、相手に自分の鼓動を委ねてしまっている状態。
翠は、俺にとって、まさにそういう女だった。
---
桐堂大(とうどう まさる)——役者の夢を捨てきれず、三十を過ぎても小劇団にしがみついていた。日の当たらない稽古場、少人数の観客、深夜のコンビニでのバイト。誰もが「お前には無理だ」と心の底で思っているのを、笑って受け流す日々。
演技の腕には自信があった。顔だって悪くない。だがどこかに決定的な「何か」が欠けていた。だからこそ燻り続け、いつの間にか“夢を追う者”という肩書きさえ、自分にとって免罪符になっていた。
翠(みどり)と出会ったのは、そんな夜勤のバイト先だった。
地方から出てきたばかりだというその女は、制服に着られているような華奢な体つきをしていて、化粧気もなく、顔立ちはどこか地味だった。だが一度歩く姿を見た瞬間、俺の目は彼女の長い手足に釘付けになった。華やかさはないのに、妙に視線を引く。それは、舞台の上で時折感じる“間”に似たものだった。
最初は、いつも通りだった。
話しかけ、距離を詰め、流れのままに体を重ねる。バイトの後輩に手を出すのはこれが初めてではない。感情を介さず、ただの慰めとして女を抱く——それが俺の癖だった。だが、翠は違った。
彼女は、こちらのリズムを拒否しない。だが、合わせるわけでもない。彼女には彼女の“間”があり、それがすべてを支配していた。
その独特の沈黙に、俺は少しずつ巻き取られていったのだ。
---
翠は、ある日ふいに俺の稽古を見に来たいと言い出した。
「興味があるんです、演劇に」
その目に浮かぶ無邪気な光と、わずかに覗く執着の影。演技でも、恋愛でも、俺が人を引き込むときには、まず相手の目を見た。けれどそのとき、俺は初めて、“見られる側”の恐れを感じたのだった。
劇団『句読点』の主宰、八嶋は一風変わった男だった。かつて新人戯曲賞を受賞した経歴がありながら、以降は売れ線を嫌い、難解な台詞と無音の演出を多用する偏屈な演出家だった。観客はどんどん離れ、今では身内に毛が生えた程度の舞台しか打てていない。
だが、翠が見学に来たあの日、空気は変わった。
休憩中に、ぽつりと彼女が言った。
「この台詞、なんか、難しくしようとして難しくなってる気がします。もっと普通に、伝えたいことだけにしたら、もっと響くかも」
八嶋は最初、黙って彼女を睨んでいた。けれどその目の奥に、微かに火が灯るのを俺は見逃さなかった。
それがすべての始まりだった。
翠は、舞台に引き込まれていった。
脚本は変わり、芝居も変わり、やがて彼女自身が主役になった。
気づけば、俺の居場所が、少しずつ奪われていった。
---
「蛇に巻かれる」という言葉がある。身動きが取れず、逃げられず、飲み込まれるように。
彼女の前では、俺のすべてが、無力だった。
なのに、俺は——そのことに、どこかで救われていたのかもしれない。
(続く)
話題の投稿をみつける
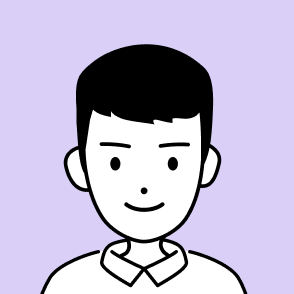
GO豪ラ

コヒノ
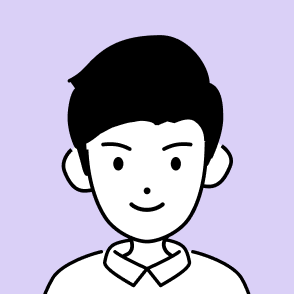
ケロッ
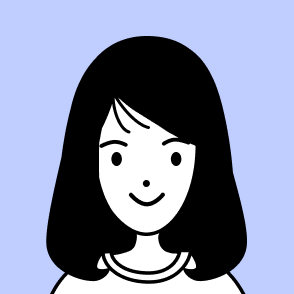
乾電池
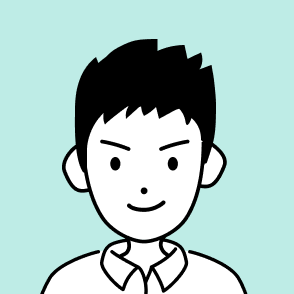
藤崎🌞
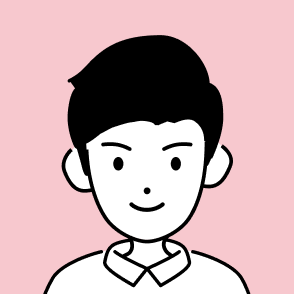
季節の

✨クレ
ちゃんと買いました☺️


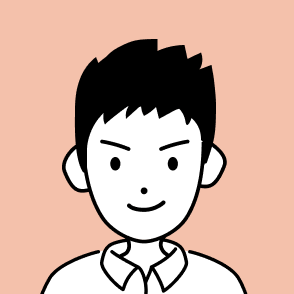
テサブ

羽々
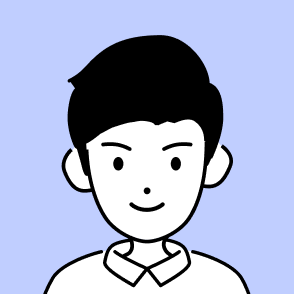
べんざ
大丈夫か…?
もっとみる 
関連検索ワード
